もし夜間に突然ペットが体調を崩したとき、飼い主として冷静に対処できるでしょうか。
ペットは大切な家族の一員であるため、体調が悪そうな様子を見たときには不安になったり気が動転したりしてしまうこともあるでしょう。特に夜間に発生すると、焦りや戸惑いが強くなることもあるかもしれません。
しかし、そんなときこそペットのためにも落ち着いて行動することが大切です。不安な気持ちに負けず、冷静に対処できるように心がけることがペットを守るために必要なことです。
本記事では、夜間診療を受診すべき症状、受診時の持参物や受診の流れについて解説します。
これらの情報を把握し、ペットが急な体調不良を起こした際も冷静に対処できるよう、しっかりと準備をしておきましょう。
動物病院の夜間診療で受診するべき症状

動物は言葉を発することができないため、日中は元気そうに見えても、夜になると急に症状が悪化することがあります。夜間にペットの体調が急変すると、不安を感じる飼い主も多いでしょう。
朝まで様子を見て、通常の診療時間にかかりつけの動物病院を受診すべきか迷うこともあるかもしれません。
しかし、病気によっては迅速な治療が必要になるケースも少なくありません。
そのため、夜間にペットが体調を崩した際は朝まで待つべきか、またはすぐに動物病院を受診すべきか症状を見極めることが大切です。
判断が難しい場合もありますが、以下のような症状が見られた場合は、できるだけ早く夜間診療を受診することを検討しましょう。
- 息が荒いなどの呼吸異常
- 吐きたそうにしているが吐けない
- 突然身体を硬直させたり痙攣を起こしたりする
- ぐったりして動かない
- 意識が朦朧としている
- 難産
- 高所からの落下
- 交通事故
- ほかの動物との喧嘩による重い怪我
- 異物および中毒性物質を食べた可能性がある
これらに該当しない場合でも、明らかに普段と異なるような症状がみられる場合には動物病院へ問い合わせ、受診の必要性を相談してみることもよいでしょう。
実際に夜間診療では、日中から調子が悪かったというケースが大変多いです。変化に気付いた時点で、できるだけ早めに相談・受診することがペットの健康を守るうえでとても大切です。
動物病院の夜間診療に持参するもの

スムーズに診察や治療を受けるために、動物病院の夜間診療時に持参すると役立つものを以下に記載します。
ただし、病院やペットの症状によって必要なものは少しずつは違うことがあります。受診前に病院のホームページを確認するか、必要に応じて電話で問い合わせておくと安心です。
また、夜間にペットの体調が急変すると、どうしても気が動転してしまうこともあるかもしれません。急いでいると忘れ物をしたり、思わぬ事故につながったりすることもあります。
急に病院へ連れて行くことになっても落ち着いて行動できるように、普段から持ち物の準備をしておいたり、夜間診療に対応している病院を確認しておいたりすると安心です。
飼い主の身分証明書
動物病院によっては、飼い主の身分証明書(運転免許証や健康保険証、マイナンバーカードなど)が必要な場合があります。
特に初めて利用する動物病院の場合は、カルテ作成のために提示を求められることがあるため、持参しておくとよいでしょう。
ペット保険の保険証
加入している保険にもよりますが、救急や夜間対応を受けた場合にもペット保険が利用可能です。
もし、ペット保険に加入している場合、ペット保険証を持参すると治療費の一部が補償される可能性があります。
ただし、動物病院が保険会社と提携していない場合はいったん診療費を立て替えて、後日領収書をもとに飼い主から保険会社に請求するといった流れになることもあります。
保険請求のために獣医師による診療録や診断書が必要になることもあり、その場合には別途費用がかかる点に注意が必要です。保険請求の流れについては、動物病院に確認しましょう。
かかりつけ医の診察券や診療記録
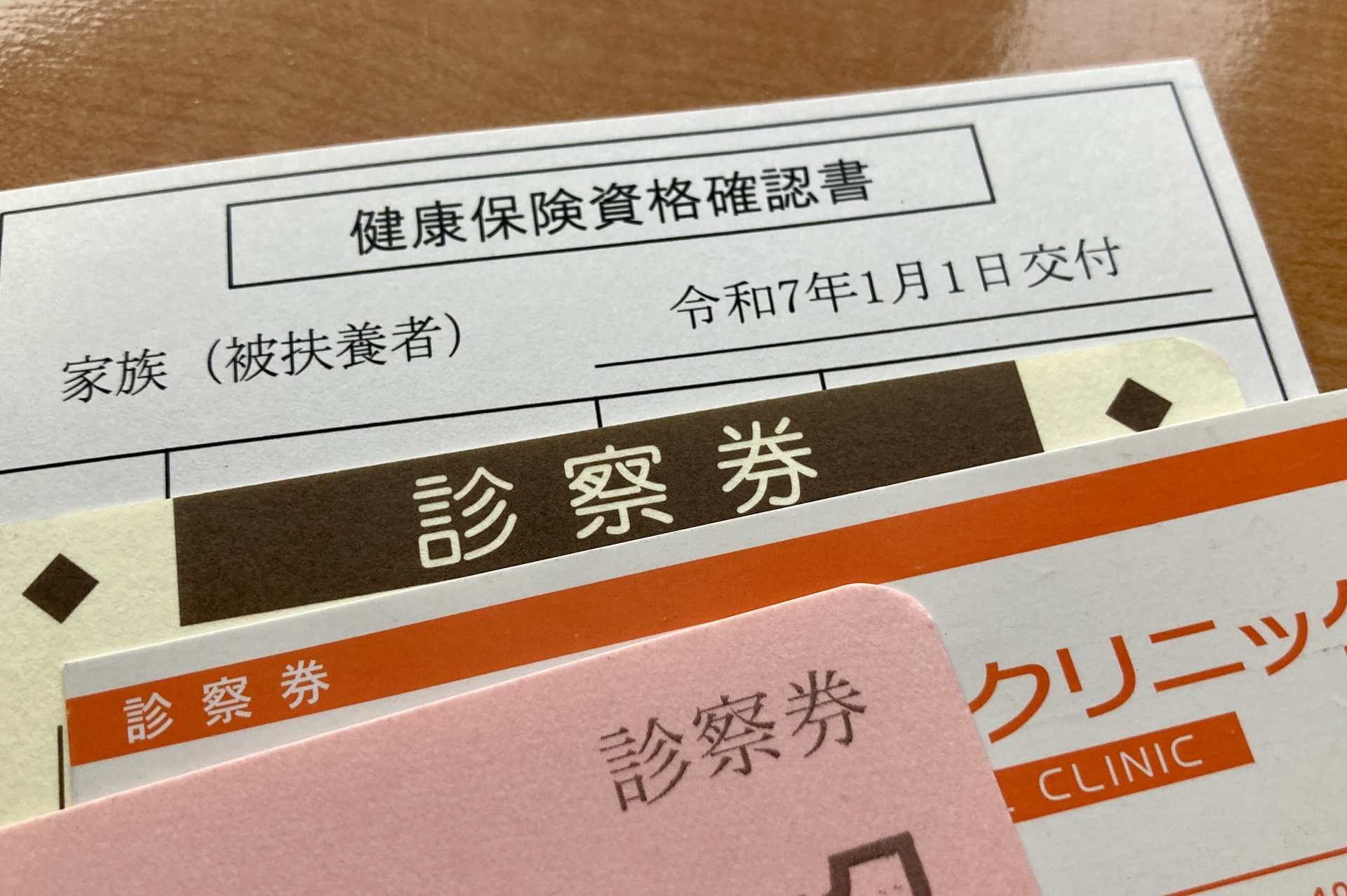
かかりつけ医の診察券や診療記録を持参しましょう。
夜間診療対応の動物病院は、通常診療時間帯(主に昼間)にかかりつけの病院に受診するまでの間の応急処置のみ行っている病院もあります。
その場合、夜間診療での診療内容をかかりつけの病院に適切に報告する必要があるため、かかりつけ医の診察券をもっていきましょう。
また、ペットに持病がある場合、過去の診療記録があると病気の診断の手助けになることがあります。
ペットがより迅速に適切な治療を受けられるようにするためにも、診療記録がある場合には持参しましょう。
血液検査などの検査結果
直近の血液検査やレントゲンの結果も獣医師が迅速に病状を判断するための重要な手がかりとなります。
特に、持病がある場合や定期的に検査を受けている場合は、直近の検査データを持参することで適切な治療を受けやすくなるでしょう。
ペットの症状によってはこれまでの検査結果を参考にしながら治療方針を決めることもあります。
紙の検査結果のほか、スマートフォンに保存したデータや写真でもよいので、できるだけ持っていくとよいでしょう。
普段使用している薬

ペットが服用している薬がある場合は、その薬を持参しましょう。
服薬中の薬の種類や用量によっては、使用できる薬が制限されたり、治療の方針が大きく変わったりすることがあります。そのため、現在使用している薬は必ず持参しましょう。
薬のパッケージや処方内容がわかるメモ、かかりつけ医での処方履歴があると、よりスムーズに診察が進みます。
特に、持病がある場合や長期間服用している薬がある場合は、過去の治療歴も含めて整理しておくと役立ちます。
便や尿など診察の参考になるもの
下痢の場合は便、血尿の場合は尿を清潔な容器に入れて、可能な限り持参しましょう。実際の便や尿を持参すると診断の精度が上がります。
採取の際は、清潔なビニール袋やタッパーなどに入れ、冷蔵保存(常温でも短時間なら可)しておくとよいでしょう。また、採取が難しい場合は、便や尿の写真を撮影しておくのも有効です。
誤飲の場合飲んだものの成分がわかるもの
ペットが誤飲や誤食をした場合、飲み込んだものの成分がわかると治療がスムーズになります。
可能であれば、誤食や誤飲したものの一部または成分がわかるもの(食品や薬品のパッケージなど)を持参すると適切な対処が受けやすくなります。
特にチョコレートや玉ねぎ、ブドウ、キシリトールや医薬品などはペットにとって毒性が強く緊急処置が必要になることもあるため注意が必要です。
誤飲の量や時間をできるだけ正確に把握し、病院に伝えましょう。
動物病院の夜間診療で伝えること

夜間診療では、獣医師が迅速に診断し適切な治療を行うために、飼い主が正確な情報を伝えることがとても重要です。
焦らずに必要な情報を整理し、スムーズに伝えられるようにしましょう。
犬種・年齢・体重
診察時にペットの基本情報を伝えましょう。犬種や年齢、体重は治療の方針を決定するうえでとても重要な情報です。
特に年齢や体重は、薬の投与量や治療法を選ぶ際に大きな影響を与えるため、しっかりと把握しておくことが大切です。
また、小型犬と大型犬などの体格差によって、考えられる病気のリスクや処置の方法が異なる場合もあります。
ペットの正確な体重がわからない場合は、おおよその目安でも構いませんが、最近の体重変化がわかれば獣医師がより的確な判断をしやすくなります。
ペットの健康管理のためにも、できるだけ定期的にペットの体重を測定してあげましょう。
症状が出始めた時間
症状がいつから出始めたのかを伝えることは、診断のうえでとても重要です。
- 急に発症したのか徐々に悪化したのか
- 発症のタイミングは何か特定の行動(食事後、散歩後など)と関連があるのか
- 直前に何か異変はなかったか(誤飲や怪我、ストレスなど)
獣医師が原因を特定しやすくなるように、できるだけ具体的な情報を伝えましょう。
例えば、「朝から元気がなかった」よりも「午後3時頃に急に嘔吐し、それ以降ぐったりしている」と具体的に伝えることで、より正確な診断につながることが期待できます。
また、症状の変化も重要な手がかりです。先ほどまで体調の変化はみられなかったのに突然苦しそうにし始めた場合は、誤飲や中毒の可能性が考えられます。
逆にゆっくりと症状が悪化している場合は感染症や持病の影響が疑われます。
症状の詳細
症状をできる限り詳しく説明することで、診断の精度が高まります。以下の点に注意して伝えるとよいでしょう。
- 具体的な症状:嘔吐・下痢・呼吸困難・けいれん・歩行困難など
- 症状の頻度や持続時間:1時間に3回嘔吐した、5分間けいれんが続いたなど
- 症状が悪化しているか、改善しているか
- 食欲や水分摂取の有無:ご飯は食べないが水は飲むなど
- 排泄の様子:下痢が続いている、血尿が出たなど
言葉だけで説明するのが難しい場合は、症状が出ているときの写真や動画を撮影しておくと、獣医師に伝えやすくなります。
夜間診療は事前に電話連絡が必要?

動物病院の夜間診療を受診する際は、事前に電話連絡をするとスムーズに受診できます。
病院によっては夜間診療が完全予約制となっているところもあり、事前連絡がないと診察を受けられない可能性があります。
また、電話連絡の際にペットの症状を事前に伝えることで、病院に到着するまでのペットに対する適切な処置について獣医師から指示を受けることが可能です。
ペットの症状の緩和や診察時のスムーズな処置につながるため、できるだけ事前に連絡するのがよいでしょう。
動物病院へ連絡する際には、以下の情報を事前に整理しておくとスムーズです。
- 品種、年齢、体重
- 症状の詳細
- 既往歴や持病の有無
- 服用中の薬の有無
- どのような状況で体調が悪化したか(誤飲や怪我など特定の原因があるか)
動物病院によって、対応できる診療内容に制限がある場合もあります。
例えば外科手術が必要な場合や特定の検査機器を要する場合、受診を希望する動物病院では対応可能な医師がいない、検査機器がないなどの理由で診察を受け付けられないことがあります。
その場合には、ほかの救急病院を紹介してもらえるか確認してみましょう。
動物病院の夜間診療の受診の流れ

夜間診療は通常診療時間帯(主に昼間)の診察とは異なり、救急対応が優先されるため、通常診療とは流れが異なることがあります。
前述のとおり、事前に動物病院へ電話し、受診の可否や指示を確認しましょう。動物病院が受け入れ可能であることを確認したら、ペットの病状を悪化させないように、落ち着いて病院へ向かいます。
また、病院までの移動中にペットが暴れたり吐いたりする可能性があるため、キャリーケースやタオルを利用して安全性を重視して運びましょう。
病院到着後の一般的な夜間診療の流れを以下に紹介します。
受付
病院に到着したら、受付を済ませます。なお、夜間は病院の入り口が施錠されているケースもありますので、電話連絡時や動物病院のホームページから夜間時の病院への入り方を確認しておきましょう。
受付で身分証明書、かかりつけ医の診察券、持参できる場合にはこれまでの診療記録などを提出します。
また、このときに電話で連絡した際に伝えたペットの症状や状態を再確認されることがありますので、落ち着いて情報を伝えましょう。
受付が完了した後、診察までの流れや待機場所について案内されるので、その指示に従いましょう。
夜間診療では、緊急性の高いペットの診察が優先されるため、診察の順番が前後することもあります。時間に余裕を持って到着することをおすすめします。
診察・処置
飼い主から確認した症状やかかりつけ医の診療記録などをもとに獣医師がペットの診察や処置を行います。
必要に応じて血液検査やレントゲン、超音波検査などの追加検査が実施されることもあります。
緊急性が高い場合には、そのまま手術を行い、入院することもありますので獣医師の指示に従いましょう。
診察結果説明・会計
獣医師より診察結果や今後の流れについて説明を受けます。
不明点や懸念点がある場合には、獣医師との面会時にしっかり質問をしましょう。ペットにとってより過ごしやすい環境をつくってあげるためにも、不明点や懸念点を解消することが重要です。
また、かかりつけの病院で再診を勧められることもあります。その場合、夜間診療の診察や治療内容に関する報告書が渡されることがありますので、かかりつけの病院に行く際には忘れずに持っていきましょう。
すべての検査や治療について獣医師の説明が終わり次第、会計の流れになります。入院が必要な場合には、入院手続きを行います。
夜間診療の支払いの注意点

多くの病院では現金やクレジットカードでの支払いが可能ですが、防犯上の理由からクレジットカードのみの対応となる病院もあります。
動物病院のホームページまたは事前の電話連絡時に、支払い方法についても確認しておきましょう。
また、夜間診療は通常の診療よりも高額になる傾向があるため、クレジットカードを持参するか現金は余裕をもって用意しましょう。
動物病院の夜間診療の費用

前述のとおり、夜間診療は時間外診療の料金が加算されることがあるため、通常の診療よりも高額になる傾向があります。
夜間診療にかかる費用としては、20,000~50,000円程度かかることが多いでしょう。もし、入院が必要な場合は、200,000円程度と高額になることもあります。
ペットの診療費用は自由診療であるため病院ごとに異なります。ホームページに診療費を記載している動物病院もあるので、緊急時に備え動物病院をリストアップしておくとよいでしょう。
まとめ

夜間にペットが体調を崩してしまうと、飼い主にとってはとても不安に思うことでしょう。しかし、緊急時こそ飼い主は冷静に対応することが求められます。
夜間診療を受けるべき症状を事前に把握し、必要な持ち物や診察の流れを理解しておくことで、緊急時にも落ち着いて対応できるようになります。
特に、事前に夜間診療を行っている動物病院を調べ、緊急時の連絡先をメモしておくことはとても重要です。
夜間診療は通常の診療に比べて費用がかかるため、ペット保険の活用や必要な治療のみを選択するなど、費用面の準備もしておきましょう。
ペットの健康と幸せな生活を守るために、飼い主として適切な対応ができるよう、日頃から準備をしておくことが大切です。
参考文献


