動物病院ではペットも人間と同じように治療や検査を受けることが可能です。
しかし、ペットにもCT検査は行えるといわれても、「CT検査は普通に行えるの?」「造影剤は使っても大丈夫なの?」といった不安や疑問があるでしょう。
この記事では動物病院でCT検査はどのように行われるのか、造影剤使用による効果や副作用からCT検査にかかる料金まで解説していきます。
動物病院でのCT検査について理解を深め、大切な家族の病状にあった治療が選択できるようにしましょう。
動物病院でCT検査を行うのはどのようなとき?

動物病院で行われるCT検査は、主に腫瘍の状態や骨の異常などの把握に役立ち、診断の一助となります。
人間のCT検査と同じように、動物もCT検査を受けることで体内の病変を診断できるのです。
では、具体的にどのような疾患の診断へつながるのか、身体の部位ごとに解説します。
頭部の疾患や外傷が疑われる場合
頭部の疾患や外傷が疑われる場合に見られる症状は、主に神経症状です。
脳や脊髄などの中枢神経系に異常をきたしている場合に見られる症状で、意識レベルの低下や歩行障害、視力障害や麻痺および痙攣などがあります。
確定診断のためにはCT検査だけでなく、採血や神経学的検査なども行われます。頭部CTでは、主に以下の疾患が発見可能です。
- 脳腫瘍
- 水頭症
- 頭蓋骨折
- 鼻腔・咽頭・眼窩の病変
脳腫瘍は高齢になるにつれ発症率が高くなり、水頭症は生後半年頃から見られます。水頭症での初期症状は、活気がなかったり、睡眠時間が長かったりします。
頭部外傷による頭蓋骨折の際には硬膜外血腫を形成することもあるため、神経症状の出現に注意が必要です。
また頭部CTは頭部全体を撮影できるため、鼻腔や咽頭、眼窩の病変の有無も観察できます。
胸部の疾患や外傷が疑われる場合
胸部の疾患や外傷が疑われる場合は、呼吸器症状が見られます。咳や息上がり、苦しそうにしているなどの症状です。
しかし、呼吸器だけでなく心臓が悪い場合でも似たような症状が見られます。ただ、心疾患を診断する場合、CT検査は静止画となるため常に動いている心臓を撮影するのは難しいです。
心疾患の診断には心電図検査や超音波検査の方が向いています。胸部CTで見つけることのできる疾患は、主に以下のものがあります。
- 肺腫瘍
- 気管支や肺の炎症
- 気胸
重度の呼吸器疾患では全身麻酔での負担が大きくなるため、麻酔ができる状態か確認するための検査も必要となるでしょう。
肺腫瘍は転移によるものも少なくありませんが、ペットで受動喫煙が要因で肺腫瘍を発症することがあります。ペットの前であっても分煙を心がけることをおすすめします。
腹部の疾患や外傷が疑われる場合
腹部の疾患や外傷が疑われる場合、主に見られる症状は食欲不振や嘔吐、下痢などの消化器症状です。
しかし肝臓疾患の場合、初期には症状があまり見られず、疾患が進行してから症状が現れ気付くことも少なくありません。腹部CTでよく見つかる疾患は主に以下のものです。
- 腹部の腫瘍
- 肝臓の病変
- 腎臓腫瘍
- 膀胱腫瘍
- 尿路結石
消化器官の病変だけでなく腎臓などの泌尿器系の病変も腹部CTで発見できます。泌尿器系の疾患がある際は血尿や頻尿が見られ、以下の疾患が見つかるでしょう。
脊椎の疾患や外傷が疑われる場合
脊椎の疾患や外傷が疑われる場合は神経症状が見られ、歩行時のふらつきや抱こうとすると嫌がる、段差を上れなくなるなどの症状が見られます。CT検査では主に以下の疾患が見つかるでしょう。
- 椎間板ヘルニア
- 脊椎腫瘍
- 骨折や脱臼による脊髄損傷
- 先天性の脊椎・脊髄疾患
ヘルニアでは、頸部や腰部など発症する部位により症状は変わってきます。頸部では四肢がふらつきますが、腰部では下半身のみ力が抜ける様子が見られるでしょう。脊椎腫瘍でも似た症状が見られます。
骨折や脱臼などの外傷では、脊髄を損傷することでほかの脊椎疾患と同じように立ち上がれなくなったりします。また、外傷による損傷部位の痛みも出るでしょう。
先天性の脊椎疾患は小型犬種でよく見られ、脊椎の奇形など状態により症状の進行は異なります。
CT検査でわかること

CT検査では全身の体内の状態を観察できます。筒状の機械により360度から放射線を当てることで、体内の断面図が得られるため、臓器や骨などの組織を立体的に把握することが可能です。
また、造影剤を使用することで病変部位をより精密に診察できます。造影剤により血管走行を明瞭化させることが可能で、通常のCT検査より立体的に臓器や骨の形を把握しやすくなります。
どのように見えるのか、骨や歯、腫瘍の状態や転移の有無を具体的に解説していきましょう。
骨や歯の異常の有無
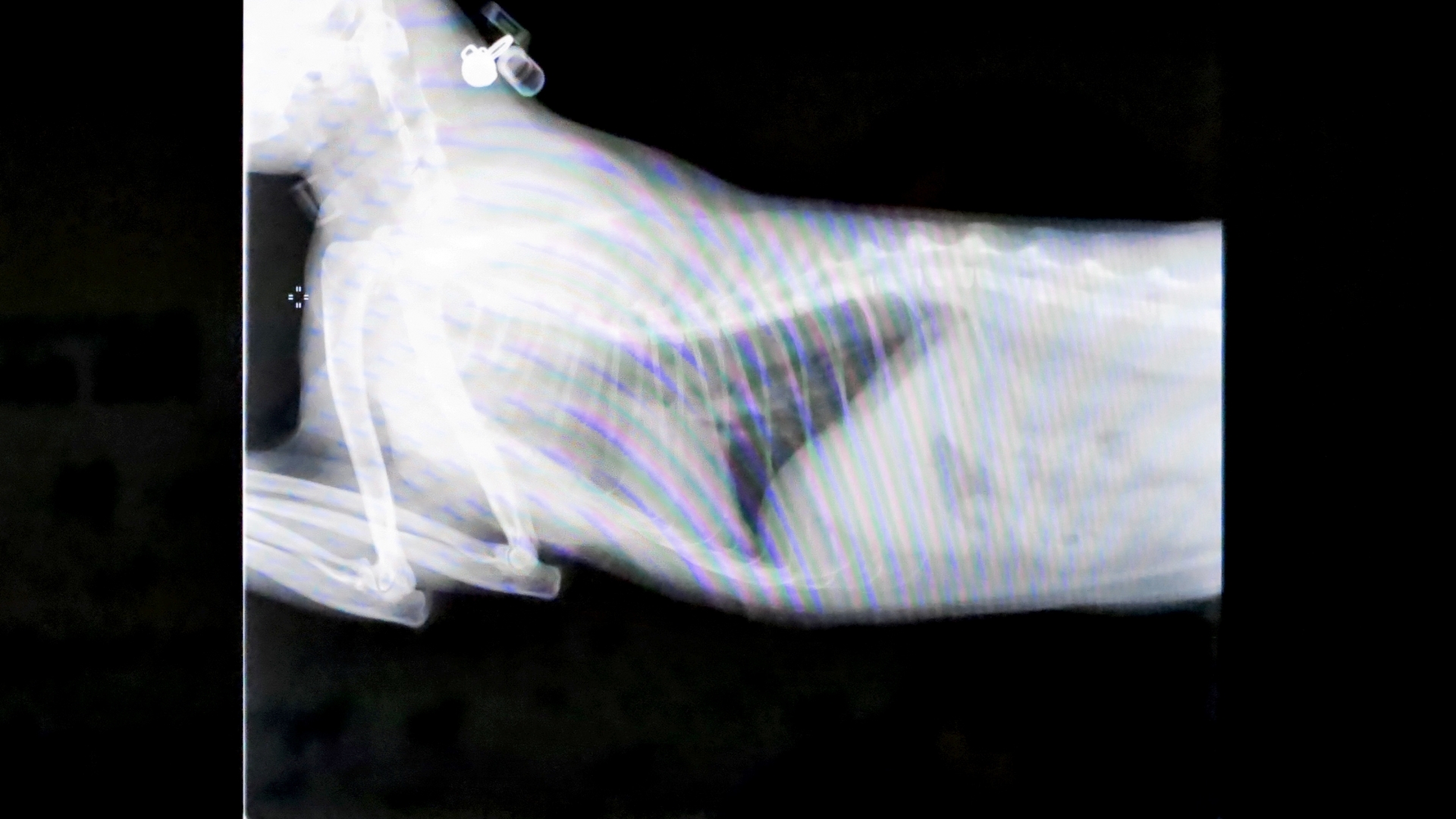
CT検査ではレントゲン検査よりも精密に骨折部位の観察が可能になります。骨は放射線が透過しにくく、レントゲン検査やCT検査では白くはっきりと写るのが特徴です。
CT検査は360度から放射線を当てるので、骨や歯の形がレントゲン写真よりも細かく把握できます。
特に頭部では頭蓋骨や顎骨など骨が重なる部分も多くあり、複雑な構造をしているためCTでの診察が有効となるでしょう。
さらに、3D像へ変換することで立体的に骨の形が把握できるので、骨折のタイプまで診断しやすくなります。
腫瘍の位置や大きさ
人間だけでなく、犬や猫も悪性腫瘍は死因の上位に入ります。ペットたちは話せない分、異常が出てきた時点で病状が進んでいることもあるでしょう。
病状が進んでいる場合は、予後の判断や今後の治療方針を決定するためにもCT検査は大事な役割を果たします。
CT検査をすることで、腫瘍の位置や大きさを可視化することが可能です。しかし、腫瘍はほかの臓器と同じような淡い色で写るため、小さいものなどは見つけづらいです。
造影剤を使用することで、コントラストが高くなり腫瘍がはっきり写るため腫瘍の位置や大きさがわかりやすくなります。
転移の有無
転移の有無もCT検査を行うことで発見できます。CT検査は全身の状態を確認できるので、浸潤具合や転移病変などの確認も可能です。
採血やレントゲン検査を定期的に行い、必要時にはCT検査を行うことで転移したがんを発見できます。
CT検査の流れ

CT検査は撮影時、静止していなければいけません。
動物では動きの制御が難しいことが多いため、全身麻酔下で眠っているうちに呼吸管理を行いながらCT検査を行わなければなりません。
どのような流れで検査が進むのか、以下で詳しく解説します。
検査
ペットが全身麻酔を受けられる状態かどうかの検査を行います。全身麻酔は負担の大きい処置となるため全身状態が良好であることが望ましいです。
採血やレントゲンなどからペットの全身状態を詳しく観察し、全身麻酔が行える状態かどうか獣医師が判断します。
検査の結果、全身麻酔が可能と判断された場合は全身麻酔下でCT検査を行います。全身状態が悪く全身麻酔の適応とならない場合は、病院によっては無麻酔でのCT検査も行うことも可能です。
ただし、CT撮影中は動かないように固定をしないといけません。撮影時間も短く済む機械が望ましいです。
麻酔

全身麻酔では深い眠りに入り、筋肉も弛緩します。食物が胃に残っていると嘔吐するリスクが高いです。嘔吐した際に嘔吐物が気管へ入れば窒息や誤嚥性肺炎などの危険があります。
嘔吐を予防するため、検査前日の夕食後から食事を抜くよう指示が出ることがあるでしょう。全身麻酔中は、自発呼吸もなくなるので呼吸を補助するために気管挿管を行います。
CT検査
CT検査中は全身麻酔下となるため、心電図や体内の動脈酸素濃度を測定するセンサーなどをつけて注意して全身長体を観察していきます。
撮影はまず、造影剤を使わず単純撮影を行い、次に造影剤を注入し撮影する順番です。必要時は腫瘍や組織の一部を少しだけ取り、病理や細胞診検査へ提出します。
検査終了後は、麻酔から覚めるまで待ちます。しっかり休んで問題がないことを確認したら帰宅が可能です。
CT検査自体は数分〜数十分で終了することが多いですが、麻酔の導入からしっかり目が覚めるまで時間を要するため、全体を通すと1日がかりとなる場合も多いでしょう。
検査結果報告
CT検査の結果説明をすぐ聞けるかどうかは動物病院によって異なるため、CT検査の流れは事前に確認が必要です。
病理や細胞診の検査を一緒に行った場合は、詳しい説明は後日になることがよくあります。
しかし、病理や細胞診を行なった場合も説明のタイミングは検査を行った施設により違うので、検査を行う施設で確認しましょう。
CT検査で使用する造影剤で起こりうる副作用

造影剤の副作用を含めて、CT検査をする場合は獣医師としっかり話し合いましょう。
もし検査後に以下のような症状が出たら、動物病院を受診しましょう。
かゆみ

イヌやネコも人間と同じようにアレルギーがあり、生体が造影剤に対しアレルギー反応を示し、かゆみが出ます。
造影剤に対するアレルギー反応をI型アレルギーといい、アレルゲンに反応したマスト細胞がヒスタミンを放出することで発症します。
I型アレルギーは即時型ともいわれ、かゆみなどの反応の出現が早いです。アレルゲンが体内へ侵入し、約15分ほどで症状が出るのが特徴です。
過敏症の場合、高浸透圧の造影剤が急速に体内へ入ってくることによりマスト細胞が刺激され、ヒスタミンを放出するためかゆみが出ます。
かゆみは軽い副作用として起こることが多く、ほとんどが経過観察で改善します。
吐き気
吐き気もかゆみと同様に、造影剤へのアレルギー反応や過敏症による反応です。血管に存在するヒスタミン受容体と結合することで血管の細胞の結合がゆるまってしまいます。
これにより血液の血漿成分が漏れやすくなり発生するのが、浮腫です。
消化管が浮腫することで、消化管内の内圧が高くなり吐き気を引き起こします。
吐き気もかゆみと同様に軽い副作用であり、ほとんど治療を必要としないことが多いです。ただし、稀に重症なアナフィラキシーショックを、起こすことがあるので何か症状がある時は獣医師へ相談しましょう。
無麻酔でもCT検査を行える?

無麻酔でも検査を行うことはできます。ただし、無麻酔で行うには条件があり、基本的には麻酔下で行う方が正確な画像診断が行えるでしょう。
無麻酔で行うにはまず、短い時間で撮影のできる多列式のCTが向いています。また、身体をポジショナーなどを用いて動かないようにポジショニングを行う必要があります。
検査中に動いてしまうと画像がブレてしまい、正しく撮影できません。撮影前にしっかり動かないようにポジショニングができていれば、頭部や胸部、腹部など身体全体の撮影が可能です。
無麻酔での検査が適応となるのは、麻酔のリスクが高い症例
や気管挿管が困難な症例です。
麻酔リスクの高い症例は全身状態がよくない状況であったり、呼吸器や腎機能が悪いなどがあげられます。気管挿管が困難な例は口腔内や咽頭に病変がある場合などが考えられます。
動物病院のCT検査の費用相場

動物病院でCT検査を行った際の費用は、単純CT撮影か造影CT検査か、全身麻酔を使用したかで値段は変わるでしょう。それぞれの平均費用は以下になります。
- CT検査:約20,000〜50,000円(税込)
- 造影剤:約2,000〜10,000円(税込)
- 全身麻酔:約2,000〜30,000(税込)
CT検査は撮影部位や枚数によって料金が変わってきます。造影剤は使う量により変動があり、麻酔は体重や使用時間により料金が異なります。
合計すると、少なくても24,000円(税込)以上の費用がかかるでしょう。料金は施設によるので、受診先で確認をしてみるとよいでしょう。
まとめ

この記事では動物病院でのCT検査について解説してきました。
ペットも人間と同じように治療や検査を受けることが可能です。CT検査の際は画像を正確に撮影するためにも全身麻酔をかける必要があります。
しかし、病状や全身状態を考慮して、麻酔をかけずにCT検査を行う施設も増えてきました。
大切な家族にCT検査が必要といわれ、不安に感じる方も少なくないでしょう。この記事を読んで少しでも不安を和らげてもらえれば幸いです。
参考文献
- X線CT、MRIを希望される飼い主さんへ
- 機器・設備について | 麻布大学付属動物病院
- CT検査室
- 犬の急性硬膜外血腫の1例
- 脊椎および脊髄の疾患 | 岐阜大学動物病院
- 最近における獣医核医学診療の内外の現状―わが国における法的整備の必要性―
- 循環器・呼吸器内科 | 北海道大学動物医療センター
- 第10回獣医さんが教えてくれる「心臓病」さん | 北里大学獣医学部
- 犬の膀胱腫瘍
- 伴侶動物運動器獣医療の現状
- X線CT検査とは? | 金沢大学付属病院放射線部
- CTリンパ管造影を用いた犬口腔内腫瘍におけるセンチネルリンパ節同定のための実験的検討
- 電子ビーム積層造形法による伴侶動物骨折治療用アナトミカルプレートの開発
- 犬の肝臓腫瘍
- 胆嚢壁の損傷を伴う犬の気腫性胆嚢炎の1例
- 犬の腎細胞癌の1症例
- ワンヘルスにおけるヒトと動物のアレルギー疾患
- 実験動物用汎用型X線CT
- 造影剤によるアナフィラキシーの病態とその対処方法を理解する
- 第1章 アレルギー総論
- 山口大学共同獣医学部附属動物医療センター診療規則|山口大学共同獣医学部附属動物医療センター
- 鳥取大学農学部附属動物医療センター諸料金規則|鳥取大学農学部附属動物医療センター
- 北海道大学大学院獣医学研究院附属動物病院規程|北海道大学大学院獣医学研究院附属動物病院
- 宮崎大学農学部附属動物病院診療規程
- 麻酔科 | 東北大学病院


