犬を屋内で飼う世帯が増加傾向にある昨今ですが、室内で留守番をする犬の問題行動も飼い主さんにとって、悩みの一つではないでしょうか。
犬は、群れになって行動する習性上、留守番で孤独や不安を感じる動物です。しつけ教室で留守番トレーニングをすれば、犬が感じるストレスを減らせるでしょう。
また、トレーニングなしに度重なる留守番は、孤独感や不安が増していくと分離不安という症状を発症する犬もいます。
本記事では、しつけ教室で行う留守番トレーニングの内容から、犬の分離不安の詳しい症状や対処法まで解説します。ぜひ、犬のストレス軽減に役立ててもらえると幸いです。
犬の留守番にはしつけが必要

犬はもともと群れで生活してきた動物で、人間でいう家族や仲間と一緒にいることで安心感を得ます。
誰もいない室内に長時間いると、不安や寂しさを感じてストレスになってしまうことがあります。
ストレスが溜まると、犬が吠えたり噛んだりするだけではなく、物を壊すような行動をとることも少なくありません。
犬が留守番に慣れるにはしつけが必要です。飼い主さんのしつけ次第で犬は、1匹でも問題なく留守番できるようになります。
犬と飼い主さんがしっかり信頼関係を築いてしつけをすることが、犬は「飼い主さんは帰って来る」と納得できるようになり、留守番も苦手になりにくくなるでしょう。
犬が留守番できる時間

犬が留守番できる時間は犬の年齢や性格、健康状態によっても留守番可能な時間は異なり、若い犬や活発な性格の犬は短時間でもストレスを感じてしまいます。
また、シニア犬や落ち着いた犬は長めの留守番ができる場合もあり、環境省のガイドラインでは犬のストレスや健康に配慮し、飼育環境を整えることが重要です。
長時間の放置は避けるべきで、留守番の際は快適な居場所の確保と定期的な排泄、食事と運動の機会の確保が必要になります。
留守番時間の平均の調査によると、3時間未満が37.9%で、3時間以上6時間未満が36%で6時間未満の2つで7割以上を占めていました。
10時間以上はわずか3.8%と低く、多くの飼い主さんが犬のことを考え、1匹での長時間の留守番を避けていることがわかります。
留守番可能とされる時間は最長12時間ほど
前述したとおり環境省の動物愛護管理のガイドラインでは明確な時間は記載されていませんが、長時間の放置は避けるべきと推奨しています。
国内の保険会社の調査、各都道府県の指針によると留守番トレーニングを十分にできた成犬であれば8〜12時間ほどが限界とされています。
平均的な時間として10時間程度が目安になるでしょう。しっかりと留守番トレーニングをうけている犬は、留守番の状況にも慣れていき、安心感をもって飼い主さんの帰りを待つことができる傾向にあります。
12時間を超える留守番は飼い主さんのほとんどがペットホテルやペットシッターの利用をしています。
年齢や生活習慣によっても左右される
犬の年齢や生活習慣によっても留守番時間は異なります。個体差はありますが、子犬や老犬の場合は、注意が必要です。
子犬は生後6ヶ月以上からが基準になり、1時間ぐらいから始め、長くても2〜3時間程度を目安にしましょう。
子犬はまだ心や身体が発達途中の時期なので、1匹で留守番をさせるようなストレスの強い経験は、できるだけ避けた方がよいでしょう。
シニア犬は健康状態を考えたうえで、4〜5時間が留守番時間の目安になります。トイレに行く回数も増えてくるので無理のない範囲で行いましょう。
しつけ教室で行う留守番トレーニング

留守番トレーニングも年齢や犬種によって違いがありますが、留守番トレーニングの目的は飼い主さんがいなくても不安にならず、犬が留守番の環境に慣れていくことが重要です。
少しずつ飼い主さんとの距離を離していき、姿が見えない時間を増やしていきます。少しずつひとりの時間に慣れていくことが大切です。
例えば1日1回でも、おもちゃなど犬が夢中になれるものを与えると、遊んでいる間は飼い主さんのことを思い出さずに過ごせるようになります。
誰もいない室内で遊ぶ時間を少しずつ増やしていき、さらにほかのトレーニングも同時に行っていきます。大切なほかのトレーニングをみていきましょう。
吠え防止のトレーニング
犬が留守番の時に吠える理由は、飼い主さんと離れる不安や恐怖心から吠え続けることがあります。
犬種の性格によっては吠える頻度も変わってくるため、自身が飼っている犬種の特性をしっかりと認識することが重要です。
犬によっては落ち着いてくるタイミングも異なり、吠えるのをやめたときにごほうびをあげると、少しずつ静かにできるようになる犬もいます。
また、クレートやケージのなかに入っていると、吠える回数が減る犬もいます。犬に合った方法で、少しずつ吠え防止トレーニングをすすめていきましょう。
ホームステイトレーニング
犬のトレーナーが自宅や専用施設で一定の期間預かり、生活全般を管理と指導を行い、集中的にトレーニングを行う方法です。
ホームステイトレーニングの特徴は犬にとっての日常生活のなかで実践的にトレーニングができるところです。長時間繰り返すことで習慣化しやすくなります。
犬のトレーナーが留守番の不安を解消できる基本的なしつけや、問題行動の改善をしてくれるので飼い主さんにとっては、安心感をもって対応できるでしょう。
トイレトレーニング

室内でのトイレトレーニングの目的は、犬が決められた場所で自発的に排泄することです。犬の習性上、巣穴を汚さないように就寝場所から離れたところで排泄する傾向があります。
トイレに適した設置場所候補は、以下のとおりです。
- ケージやサークルからでてよく遊んだりくつろいだりする場所
- すでによく排泄する場所
- 犬の就寝場所から離れた場所
- すでによく排泄する場所が不適切なら飼い主さんの希望場所
候補の場所に犬の体長や排泄前の行動に合わせてトイレシートを設置します。
希望の場所に排泄ができた場合は犬の好きなおやつやおもちゃを与えてほめてあげましょう。トイレ以外の場所で排泄した場合、やってはいけない行動は以下のとおりです。
- 目をあわせない
- 話しかけない
- 触らない
- 叱らない
- 叩かない
コミュニケーションを好む犬に興味を示さずに後始末をしましょう。飼い主さんの興味を常に引きたい犬にとっては、飼い主さんが望まない行為として受け止めることになります。
クレートトレーニング
犬が室内で落ち着ける場所を作ってあげることが重要です。クレートは屋根のついた箱型のハウスです。
犬のなかには、自分だけの落ち着ける場所があることで安心感をもって過ごせる犬も少なくありません。まずは、クレートに慣れさせておくことが基本の留守番トレーニングです。
留守番中の不安や苦手な音が聞こえたときでも、クレートを自分が過ごしやすい場所だと感じていれば、犬は気持ちが落ち着きやすくなります。
留守番が難しい犬の分離不安の問題点
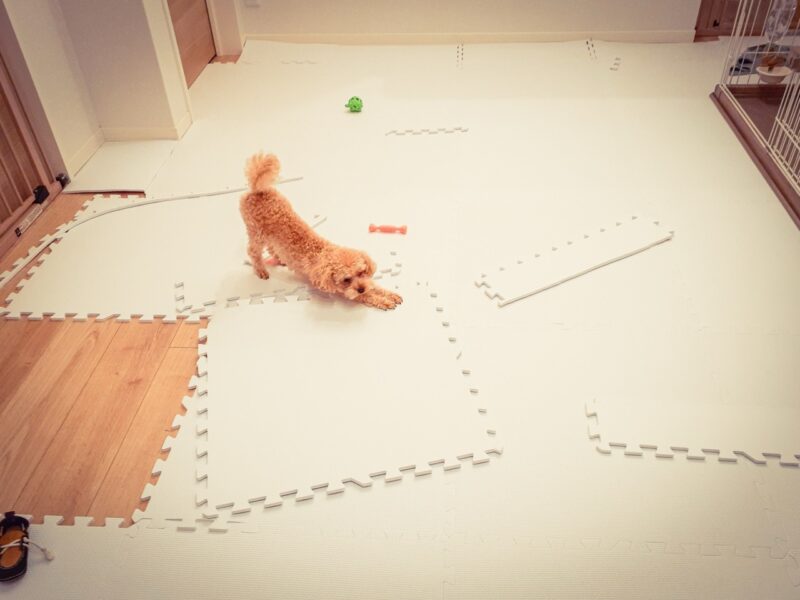
留守番をする犬が引き起こす問題行動の分離不安症は、飼い主さんを信頼して暮らしている犬にとって、飼い主さんの姿が見えないことにより不安と恐怖心を感じて起こる症状です。
分離不安を発症すると、犬と飼い主さん双方にさまざまな問題がでてきます。分離不安の問題点は以下のとおりです。
- 室内での犬の問題行動
- 犬の行動に対する犬と飼い主さんの精神的ストレス
- 吠える声の近所迷惑
- 犬の破壊行為に伴う自傷行為によるケガや神経障害
留守番をきっかけに発症するケースも珍しくありません。飼い主さんが犬の変化を見逃さず、早めの改善やトレーニングで分離不安の症状も軽減できます。
早めの対処を心がけましょう。
犬の分離不安の症状

飼い主さんの姿が見えない状態が分離不安の症状を発症し、精神的にも肉体的にも犬に悪影響を及ぼします。ある調査では、メスよりもオスの方が症状がでる傾向がみられます。
また犬が分離不安症を起こすと、飼い主さん自身も悩み、ストレスを感じるため注意が必要です。
場合によっては、問題が深刻になりすぎて、つらい決断をしなければならないことも少なくありません。
発症する原因として考えられるのは環境の変化や飼い主さんへの依存、加齢と病気といわれています。犬の性格も起因していますが、原因ごとの対策が効果的です。
飼い主の姿が見えないと吠える
とにかく大好きな飼い主さんの姿が見えないだけで不安になり、恐怖心が強くでると犬の本能の吠える行為が真っ先に現れます。
一概にすべてが分離不安症ではありませんが、飼い主さんが出かけた直後から吠え続けて落ち着く気配が見えない場合は、分離不安症の可能性が高いです。
犬は本来、うれしくても吠える動物です。吠える理由をしっかりと見極めましょう。
そわそわして落ち着かない

飼い主さんが出かける準備を始め、出かける気配を察知すると犬は不安からそわそわして落ち着かなくなります。
飼い主さんの気を引こうと、同じところをぐるぐるとまわったり、部屋中を歩きまわったり落ち着きのない行動をします。
また、飼い主さんと離れることの不安から、後をついてまわって不安を解消することも珍しくありません。
トイレ以外の場所で排泄する
トイレトレーニングも終わっている犬が、留守番中にトイレ以外の場所で排泄してしまうことは、分離不安症の一つです。
留守番中にいつもと違う場所で排泄してしまう行為は、不安やパニックが原因とされています。一説では、自分の匂いを残すことで不安を解消しようとしていると考えられています。
飼い主さんが帰ってきたときにうれしさでお漏らしする行為は、子犬の時期にはよく見られますが、成犬になってからも続く場合は対処が必要です。
嘔吐や下痢をする
飼い主さんが外出した後にでる症状として、室内に誰もいなくなるストレスから嘔吐や下痢をする犬もいます。
嘔吐や下痢は飼い主さんが外出後30分以内に症状がでる傾向にあり、繰り返す場合やひどい場合は速やかに医療機関を受診しましょう。
飼い主ができる分離不安への対処法

分離不安の症状のでている犬を飼い続けることは、飼い主さんにとってもストレスを感じ続けることです。犬と飼い主さん両方の生活がつらくなってしまいます。
分離不安の症状の原因を知り、早めの対処をするだけで犬との適切な主従関係を築く助けになるでしょう。
対処法は、飼い主さんがいなくても不安を解消できる環境作りと段階的な慣らしがポイントになります。
離れる練習を飼っている犬の性格にあわせて工夫をし、必要ならばしつけ教室やかかりつけの獣医師などの力を借りて対処しましょう。
短時間の留守番から始めて時間を少しずつ長くする
離れる練習から少しずつ始めることが大切です。隣の部屋に飼い主さんが移動して、犬を孤独にしてみることを1分単位から始めるのもよいでしょう。
徐々に時間を長くしていき、離れる距離ものばしていきます。気を付けるポイントは、いきなり長時間離れるのではなく、少しづつ時間を延ばすことで犬の許容範囲を見極めましょう。
犬には飼い主さんがドアから出て行っても、間違いなく飼い主さんは戻って来ることを学習させることが大切です。
ラジオやテレビをつけたまま外出する

分離不安症への対処には、犬が感じている不安や怖さをなくしてあげることが大切です。
不安をなくすためには、ストレスのない環境づくりを心がけ、普段の生活環境でリラックスできるようにしてあげることがポイントです。
いつもどおりの環境を変えないことで犬にとっては安心感がうまれます。ラジオやテレビをつけて音が流れている状態にしておくことで、急に静かになって不安を感じにくくなります。
音は犬にとって、とても敏感に感じるものです。特に繊細な犬は、ちょっとした音にも過剰に反応することがあります。犬の性格によって違うので、よく様子をみて判断しましょう。
しつけ教室やかかりつけの獣医師に相談する
犬のしつけは子犬期から行うことが推奨されており、飼い主さんと犬の信頼関係構築にはたいへん重要です。
これからも犬とよい関係を続けるためには、犬がストレスなく過ごせる生活リズムを整え、家族の一員として一緒に暮らすことが望まれます。
段階的に慣らしたり、ストレスの少ない環境を整えたりしても、うまくいかないこともあります。無理せず、しつけ教室の利用やかかりつけの獣医師に相談することがおすすめです。
まとめ

犬のしつけ教室での留守番トレーニングから、分離不安の症状の内容と対処法まで解説してきました。
犬は本来、集団のなかで生活してきた動物で、急に孤独になり不安や恐怖感を覚える犬が少なくありません。
考え方を変えると、犬の反応は生まれ持った本能でもあります。私たち人間の生活圏で生活していると異常行動としてとらえられますが、自然な反応です。
賢い犬は、きちんとしたしつけを受けることで、飼い主さんとの信頼関係や主従関係をしっかり築くことができます。
飼い主さんの知識や接し方は大きく関わりがあり、正しいしつけの方法や犬の気持ちを理解するだけで、犬は安心感をもって落ち着いた毎日を過ごせるようになるでしょう。
参考文献


