犬の鼠経ヘルニアは見た目の変化が目立つ場合もあれば、ほとんど症状が出ずに進行することもあります。気が付いたときには手術が必要な状態になっていることも少なくありません。この記事では、犬の鼠径ヘルニアの原因や症状、検査と治療法、予防のポイントを解説します。
犬の鼠径ヘルニアとは

鼠径ヘルニア(そけいヘルニア)とは、腹腔内の腸などの臓器や脂肪が、足の付け根にある鼠径部の筋肉のすき間から皮下に飛び出してしまう病気です。特に若齢のオス犬や中高齢のメス犬に多くみられます。
鼠径ヘルニアの原因は先天性と後天性に分類できます。先天性の鼠径ヘルニアは胎生期に性腺が下降する過程で鼠径管が閉じきらず、穴が残ることで発症します。後天性の鼠径ヘルニアは、加齢や妊娠、肥満、外傷などにより鼠径部の組織が弱くなり、臓器が脱出することで起こります。
犬の鼠径ヘルニアは初期には症状が出にくく、気付いたときには腸閉塞や壊死などの合併症を伴っていることもあります。
犬の鼠径ヘルニア|外見の特徴と症状

犬が鼠径ヘルニアを発症すると、以下のような外見の特徴や症状がみられる場合があります。
犬の鼠径ヘルニアでみられる外見の特徴
よく確認できる症状は、鼠径部にできるやわらかいふくらみです。このふくらみは、触るとやわらかく、押すと引っ込むような感触があり、痛みを伴わないこともあります。
進行した鼠径ヘルニアのふくらみは立ったときに目立ちやすく、歩き方に違和感が出ることもあります。左右の動きに差がある、歩くときにぎこちなさがあるといった場合は、ヘルニアが進行している可能性があります。
鼠径ヘルニアでよくある症状
見た目の変化に加えて、以下のような体調の異変が見られる場合は、ヘルニアの進行や合併症を疑いましょう。
- 食欲不振
鼠径ヘルニアによって腸が圧迫され消化機能に影響が出ると、食欲が落ちたり、元気がなくなったりすることがあります。 - 嘔吐
鼠径ヘルニアが原因で腸が締め付けられて腸閉塞や血流障害が起こると、嘔吐がみられることがあります。頻繁に吐く、苦しそうにしている場合は、嵌頓(かんとん)ヘルニアという合併症を発症している可能性があります。 - 排尿困難
膀胱の一部が鼠径部のヘルニアの隙間に入り込むことで、膀胱が圧迫され、排尿がうまくできなくなることがあります。トイレの回数が減る、排尿時に力んでいるといった様子がある場合は、すぐに受診しましょう。
犬の鼠径ヘルニアと間違えやすい病気
鼠径ヘルニアと見た目が似ている病気には、以下のようなものがあります。
| 病名 | 主な特徴 |
|---|---|
| リンパ節腫脹 | ・鼠径リンパ節が炎症や腫瘍で腫れる ・しこりは硬く、押しても引っ込まず、多くは左右対称に腫れる |
| 皮下腫瘍(脂肪腫、悪性腫瘍など) | ・良性腫瘍はやわらかく動くが、悪性腫瘍は硬く不規則で動きにくい |
これらは触診や超音波検査などの画像診断によって鑑別します。自己判断で放置せず、気になるふくらみやしこりがある場合は早めに動物病院を受診しましょう。
鼠径ヘルニアの合併症と緊急性

鼠径ヘルニアは初期には無症状のこともありますが、進行すると命に関わる合併症を引き起こすことがあります。
嵌頓(かんとん)ヘルニアの危険性とその症状
嵌頓ヘルニアとは、飛び出した腸などの臓器がヘルニアの出口(ヘルニア門)に挟まり、元の位置に戻らなくなった状態です。
この状態では血流が阻害され、うっ血や壊死を引き起こす可能性があり、緊急手術が必要になることもあります。
以下のような症状がみられた場合は、すぐに動物病院を受診してください。
- 鼠径部のふくらみが硬く、押しても引っ込まない
- 犬が患部を気にしたり、痛がったりなど
- 食欲が低下し、嘔吐を伴う
- 元気がなく、落ち着かない
内臓脱出による影響と注意点
鼠径ヘルニアでは、腸だけでなく膀胱や子宮などが脱出することもあります。脱出する臓器によって、以下のような症状が現れます。
- 腸:嘔吐、食欲不振、腹痛、腸閉塞、腹膜炎
- 膀胱:排尿困難、頻尿、失禁などの排尿障害
- 子宮:腹部膨満、子宮蓄膿症の悪化
外見だけでは、何が脱出しているかを判断することはできません。脂肪組織のように無害な場合もあれば、重要な臓器が関与していることもあります。
また、ふくらみを無理に押し戻そうとすると、臓器を傷つけたり、内部で破裂を引き起こしたりする危険があります。自己判断せずに必ず獣医師の診察を受けましょう。
犬が鼠径ヘルニアになる原因

犬の鼠径ヘルニアは、大きく分けて先天性と後天性のいずれかの原因で発症します。どちらも似たような症状を示しますが、発症の背景や年齢に違いがあるため、それぞれの特徴を理解しておきましょう。
先天性の原因
先天性鼠径ヘルニアは、胎生期の発達異常によって生まれつき発症するタイプで、オス犬によくみられるとされています。胎児期に性腺(精巣や卵巣)が腹腔内から鼠径管を通って下降する過程で、鼠径管が完全に閉じずに残ってしまうことが発症の原因とされています。
後天性の原因
後天性鼠径ヘルニアは、成長後に何らかの要因で鼠径部の筋肉や組織が弱くなり、臓器が脱出することで発症します。主な要因には以下があります。
- 事故や外傷
- 妊娠や出産
- 肥満による慢性的な腹圧の上昇
- 加齢による筋力低下や組織のゆるみ
これらは成犬以降によくみられ、生活習慣や体調の変化が関与していると考えられています。また、ホルモンバランスの変化によって組織がゆるみやすくなるため、高齢のメス犬は発症する可能性が高くなるという報告もあります。
鼠径ヘルニアになりやすい犬種

鼠径ヘルニアはどの犬種にも起こりうる疾患ですが、特定の犬種で発症する可能性が高いとされる報告があります。特に以下の犬種では、先天的な体質や解剖学的特徴から、鼠径部の筋肉や組織が弱くなりやすい傾向があると考えられています。
- ミニチュア・ダックスフンド
- ゴールデン・レトリバー
- コッカー・スパニエル
ただし、これらの犬種に該当していても、必ずしも発症するわけではありません。一方で、該当しない犬種でも、加齢や肥満、妊娠や出産などの後天的要因によって発症することがあります。犬種を問わず、普段から愛犬の様子を観察しておきましょう。
犬の鼠径ヘルニアの検査と治療

鼠径ヘルニアは、外見上のふくらみだけでは正確な診断が難しいことがあります。正しく鑑別するためには、獣医師による検査と状況に応じた治療判断が必要です。
鼠径ヘルニアが疑われるときの検査法
動物病院では、まず視診や触診によってふくらみの位置や大きさ、硬さ、圧痛の有無などを確認します。必要に応じて以下のような画像検査が行われます。
- 超音波検査(エコー):ふくらみの中身や合併症の有無を確認します。
- X線検査(レントゲン):腸閉塞や臓器の位置、ガスのたまりなどを評価します。
- CT検査、MRI検査:詳細な構造の把握や、ほかの疾患との鑑別を目的に行います。
これらの検査結果をもとに、ヘルニアの重症度や手術の必要性を判断します。
鼠径ヘルニアの治療法
鼠径ヘルニアの根本的な治療法は外科手術です。自然治癒は期待できず、放置すると嵌頓や臓器壊死などの合併症を引き起こす可能性が高まるため、早期の手術が推奨されます。
手術では、開腹して脱出した臓器を元の位置に戻し、ヘルニア孔(穴)を閉じます。嵌頓によって臓器が壊死している場合は、壊死部分を切除し、健康な部分をつなぎ合わせる吻合(ふんごう)手術が行われます。
ただし、すべてのケースで手術が必要というわけではありません。穴が小さく、症状がない軽度の場合では、経過観察や対症療法が選択されることもあります。特に子犬は、成長とともに自然に閉じることもあるため、年齢や全身状態を踏まえて判断されます。
犬の鼠径ヘルニアで手術が必要になったときの入院期間と治療費
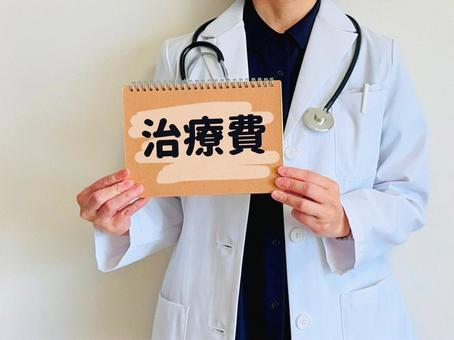
鼠径ヘルニアの手術は、緊急性の有無や全身状態によって、以下のように治療内容、入院期間、費用に差が出ることがあります。
鼠径ヘルニアの入院期間
通常、鼠径ヘルニアの手術による入院期間は経過観察を含めて1泊2日ないし2泊3日で行うことが多いです。
ただし、嵌頓(かんとん)ヘルニアなど緊急対応が必要な場合や、臓器の壊死がある場合は、術後の経過観察を含めて数日から1週間程度の入院となることもあります。
退院前には、傷口の状態、痛みの有無、排尿や排便の確認などが行われ、全身状態の安定が確認され次第、退院となります。
鼠径ヘルニアの手術、入院にかかる費用の目安
手術をふくむ入院費用は、病院の立地や設備、手術の難易度によって異なりますが、一般的な相場は通常50,000〜100,000円前後です。嵌頓ヘルニアなど重症度が高い場合には、100,000〜200,000円程度かかることもあります。また、避妊・去勢手術とヘルニアの手術を同時に行う場合は、追加費用として5,000〜10,000円程度かかることが多いです。
鼠径ヘルニアの予防と早期発見のポイント

鼠径ヘルニアは、一般的に発症してから治療を行う病気です。しかし、以下のような日常的なケアや観察を行うことで、ある程度の予防や早期発見が可能です。
早期避妊・去勢手術による予防効果(先天性の場合)
先天性の鼠径ヘルニアは、もともとの筋肉量や睾丸下降のタイミングなどによって起こるため完全に防ぐことはできません。しかし、ごく軽度のものなら、腹圧を上げない環境を整えることで目に見える形での発症や重症化を予防できる事があります。
吠えによる怒責や腹圧上昇を防ぐための避妊・去勢手術が予防策として推奨されます。特に高齢で未避妊のメス犬に多くみられるこの疾患は手術によってヘルニアの発症リスクを軽減できるといえます。
かかりつけの獣医師と相談しましょう。
体重管理と適度な運動(後天性の場合)
後天性の鼠径ヘルニアは、肥満や加齢による筋力低下、慢性的な腹圧の上昇などが原因とされています。以下のような日常管理が予防に役立ちます。
- 栄養バランスのとれた食事管理
- 日常的な散歩や軽い運動
- 便秘や咳など腹圧がかかる症状があれば早めに受診
また、出産経験のあるメス犬では、産後の筋肉や靭帯のゆるみにより鼠径部が弱くなりやすいため、特に注意が必要です。
定期的なボディチェックの方法
鼠径ヘルニアは、早期発見で重症化を防ぐことができます。日頃から、下記のポイントに沿って愛犬の様子をチェックしましょう。
- 散歩や歯磨き時などに鼠径部を軽く触ってみる
- 左右差のあるふくらみや、押すと引っ込むしこりがないか確認する
- 排尿や排便の様子や食欲、元気の有無に注意する
少しでも違和感があれば、早めに動物病院を受診することが大切です。
手術後のケアと再発防止

鼠径ヘルニアの手術は成功率が高く、術後に状態が悪化することはまれです。ただし、術後のケア次第で改善する期間や再発リスクが変わるため、飼い主さんのサポートが重要です。
退院後の自宅でのケア
退院後は、傷口の保護とストレスの少ない環境づくりを心がけましょう。まず、エリザベスカラーや術後服を着用して傷口を舐めたり引っ掻いたりしないようにすることで、感染や傷の悪化を防げます。
また、以下の内容を毎日確認しましょう。
- 傷口の赤みや腫れ、膿の有無
- 排尿や排便の回数と様子
- 食欲や元気の有無
異常が見られた場合は、すぐに動物病院へ連絡してください。手術の翌日から少しずつ元気を取り戻しますが、痛みや違和感が完全に落ち着くまでには時間がかかることもあります。
術後の運動制限と再開する方法
術後は、7〜14日程度の運動制限が設けられます。特に、ジャンプや走るなどの激しい動きは、傷口に負担をかけるため避けましょう。抜糸が終わるまでは、短時間の散歩にとどめ、段差や階段も避けるようにします。
ただし、運動再開のタイミングは状態によって異なるため、再診時に獣医師と相談して決めるようにしましょう。
再発の可能性と注意すべき症状
鼠径ヘルニアの再発率は低いとされていますが、以下のような条件が重なると再発する可能性が高まります。
- 術後に強い咳や便秘が続いたり、激しい運動をさせたりと手術後に腹圧が高い状況があった
- 傷口に感染や炎症が起こったなどの理由で、縫合部がなかなか閉じなかった
- 肥満・妊娠などで持続的に腹圧が高い状況が続いている
鼠径部に再びふくらみやしこりが確認された場合や、手術側とは反対側に膨らみが現れた場合は、再発や反対側の発症の可能性があるため早急に受診してください。
まとめ

鼠径ヘルニアは、見た目は小さなふくらみでも、放置すると深刻な病気に進行することがあります。特に嵌頓ヘルニアは命に関わるため、早期発見と迅速な対応が重要です。
大切なのは、少し気になる症状がみられた段階で迷わず獣医師に相談することです。愛犬の日々の観察やスキンシップを通じて、早めに受診できるような関係性の構築を心がけましょう。
参考文献
- Abdominal Hernias
- An evaluation of canine inguinal hernias containing the uterus: clinical experience of four cases (2017-2022) and literature review
- Retrospective Study on Clinical Features and Treatment Outcomes of Nontraumatic Inguinal Hernias in 41 Dogs
- Post-Operative Instructions in Dogs
- A Retrospective Study of Inguinal Hernia in 35 Dogs


