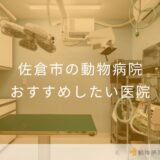犬を飼ったことがない方でも、犬には狂犬病予防注射が必要だと耳にしたことがあるでしょう。狂犬病は犬を含む動物が感染しやすい致命的なウイルスで、人間にも感染します。
致死率がほぼ100%という恐ろしいウイルス性の病気です。日本での発症例は確認されていませんが、海外旅行した方や日本に観光にきた外国人から狂犬病を発症したケースが何件か確認されています。
狂犬病ウイルスを防ぐには、狂犬病予防注射が効果的です。では、狂犬病予防注射は動物病院で受けられるのでしょうか。
本記事では、狂犬病予防注射を受けられる場所と必要なものや予防注射済票の交付手続きについて解説します。これから犬を飼育しようと考えている方は、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
狂犬病予防注射を受けるのは義務?

狂犬病予防注射について、まずは知っておいてほしい内容からみていきましょう。
犬の飼育をするうえで避けてはとおれない問題なので、狂犬病予防法で義務付けられている・受けていないと罰金の対象になる・狂犬病予防注射が猶予されるケースの3つにわけて詳しく解説していきます。
狂犬病予防法で義務付けられている
狂犬病予防法は、狂犬病の感染から人間・犬・その他の動物を守るために、毎年狂犬病予防注射を受けることを義務としている法律です。
狂犬病は一度発症してしまうと効果的な治療法がないため、ほぼ100%の確率で命を落とすことが現状です。現時点では、狂犬病予防注射を受ける以外に感染を予防する方法はありません。そのため、狂犬病予防法が制定されています。
定期予防注射は4月1日から6月30日までの春頃に実施されることがほとんどですが、地域によっては指定された期間内に行う必要があります。
また、子犬の場合は生後91日以降はなるべく早くに予防注射を受けさせましょう。その後は1年に1回の予防注射で免疫を補強することが大切です。
お住まいの市町村で指定されている期間があるか、調べておきましょう。
受けていないと罰金の対象になる
狂犬病予防注射は法律で制定されているため、受けていない場合には200,000円以下の罰金を科されることがあります。ほかにも飼い犬を登録していない飼い主さんや、飼い犬に鑑札や注射済票を装着していない飼い主さんも罰金の対象となります。
罰金は地域によって異なるため、注意が必要です。罰金以外にも、行政機関から注意や指導が入ることもあります。もし狂犬病予防注射を受けていない飼い犬が脱走した場合、捕獲・身柄の拘束(抑留:よくりゅう)の対象となる可能性があります。
もちろん、登録されていない犬や鑑札や注射済票を装着していない犬も捕獲・身柄の拘束の対象です。飼い犬が適切に健康管理されているかを確認するためでもありますが、罰金や捕獲されることを防ぐためにも狂犬病予防注射の打ち忘れには注意しましょう。
狂犬病予防注射が猶予されるケース
法律で制定されている狂犬病予防注射ですが、特別な理由がある場合には猶予されることがあります。
例えば、犬が病気やケガなどの健康状態によりワクチン接種が不可能な場合や、シニア犬で体調に負担をかける可能性がある場合です。
ただし、狂犬病予防注射の猶予を受けるには、動物病院で獣医師の診断と適切な猶予手続きを市役所で行う必要があります。どのような理由で狂犬病予防注射を猶予されたとしても、犬が狂犬病のまん延源になりやすいことは変わりません。
狂犬病予防注射を受けていない間は、飼い犬のよだれを口・鼻・眼などの粘膜に触れないようにしたり、傷口を舐められないよう防いだりする必要があります。
もしよだれがついたり、ひっかき傷や嚙まれたりした場合には速やかに石鹸と水で傷口をよく洗い流し、できるだけ早くに医療機関を受診しましょう。
狂犬病予防注射はどこで受けられる?

狂犬病予防注射は、動物病院もしくは市町村が毎年一定の期間に実施する集団接種で受けられます。基本的には動物病院で狂犬病予防注射を受けられます。
市町村の集団接種は、地区によって実施していない場合や期間が異なる場合もあるため注意が必要です。動物病院でワクチン接種する場合は、事前に予約を入れましょう。
狂犬病予防注射の予約日までに必要なものを揃えておくことも大切です。
狂犬病予防注射を受ける際に必要なもの

先述のとおり、狂犬病予防注射を受けるには必要なものがあります。
- 案内はがき
- 愛犬手帳
- 予防注射の手数料
それぞれ詳しく解説します。
案内はがき
狂犬病予防注射を受けるには、市町村から送られてくる案内はがきが必要です。案内はがきには予防注射を受けられる動物病院と市町村の集団接種場所の一覧・予防注射に必要なものの情報・注意点などが記載されています。
ほかにも、犬の認識番号やワクチン接種期間が記載されています。ただし、案内はがきが届くのは、過去に登録されている犬限定です。
まだ登録されていない犬の場合は、登録の手続きが必要となります。登録されている犬の場合は、3月中に案内はがきが届くことが一般的です。狂犬病予防注射の日まで、案内はがきを紛失しないよう注意しましょう。
愛犬手帳

愛犬手帳は、犬の健康状態や予防接種歴などを記録するための重要なアイテムです。
犬を飼うにあたってよくある困りごとや犬と生活するうえで知っておくべきマナーについても記載されています。健康状態や予防接種歴を効率的に獣医師に伝えるためにも、狂犬病予防注射を受ける際には、愛犬手帳を提出できるよう準備しておくことが大切です。
ただし、市町村によっては愛犬手帳を配布していない場合もあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
予防注射の手数料
狂犬病予防注射を受けるには、費用がかかります。ワクチン接種費用は地域や動物病院によって異なりますが、一般的には数千円程度です。
市区町村の集団接種でかかる費用も動物病院とほとんど変わりません。また、動物病院によっては登録していない犬でもその場で登録手続きができる場合もあります。
その際は犬の登録手数料として3,000円が別途かかります。クレジットカードが使用できる動物病院でも登録費用分は現金での支払いを求められることもあるため、事前に費用を確認して必要な金額を準備しておくとよいでしょう。
登録手続きに対応していない動物病院もあるため、狂犬病予防注射の予約をする際に確認することをおすすめします。
もし動物病院で登録手続きができない場合は、予防注射を受ける前に市町村窓口で犬の登録を済ましておきましょう。登録を動物病院または市町村窓口のいずれかで行うことができ、鑑札が交付されます。
鑑札には犬の登録番号が記載されており、もし飼い犬が脱走したり迷子になったりしても、鑑札が装着されていれば飼い主さんのもとに戻すことができる証明証です。
鑑札を受け取ったら、首輪・リード・ハーネスに装着するようにしましょう。
予防注射済票の交付手続き方法

ここからは、予防注射済票の交付手続き方法について解説します。予防注射済票の交付手続き方法は、動物病院での手続き・市町村窓口での手続き・引っ越しをした場合の手続きの3つがあります。
では、それぞれ予防注射済票の交付手続き方法を詳しくみていきましょう。
動物病院での手続き
一般的には狂犬病予防注射を受けた動物病院で、注射済票の交付とワクチン接種証明書の発行が行われます。注射済票の交付には、手数料として560円がかかります。
注射済票は小さいプレートになっていることがほとんどです。プレートには注射を実施した年度・予防注射を受けた市町村名が記載されており、1年間装着できるよう耐久性のある素材で作られているものです。
注射済票を交付された場合、愛犬の首輪・リード・ハーネスなどの外に出るときに身につけるものに取り付けることが求められます。鑑札と一緒に装着することをおすすめします。
市町村窓口での手続き

一部の地域では、狂犬病予防注射を受けた後に市町村窓口で注射済票を交付する場合もあります。
市町村窓口で注射済票を交付する場合には、ワクチン接種証明書と愛犬手帳の提出が求められます。市町村窓口で注射済票を交付する場合も手数料の560円は発生するため、準備しておくことが大切です。
引っ越しをした場合の手続き
狂犬病予防注射済票や鑑札には、犬の登録されている地区のものが交付されています。そのため、引っ越しをした場合には人間の住所変更手続きと同様に、犬の登録情報の変更が必要です。
犬の登録情報の変更は、引っ越し後から1ヶ月以内に行うことが推奨されています。その際には、ワクチン接種証明書と注射済票が必要となるため、忘れないよう注意しましょう。
鑑札や注射済票は市町村によってプレートの形・色・数字が異なるため、新しい市町村のものを装着することが大切です。
狂犬病予防注射で出る可能性がある副反応

狂犬病予防注射を受けるにあたって、飼い主さんからよく聞かれる不安の声はワクチン接種による副反応があるかについてです。
もちろん、ワクチン接種をすることで、副反応が出る可能性があります。どのような副反応があるのかについて、詳しく解説します。
疼痛
狂犬病予防注射後に発生する可能性がある副反応の一つは、注射部位の疼痛(とうつう)です。注射を受けた部位に軽い痛みや腫れを感じることがあります。
人間でも副反応が出にくい方と出やすい方がいるように、犬にも副反応の出方に個体差があります。疼痛の場合は一時的なものがほとんどです。
通常は注射後から数日以内に治まります。もし痛みや腫れが3日以上長引く場合には、動物病院に相談しましょう。
食欲不振

狂犬病予防注射後から、食欲不振が副反応として出る犬もいます。食欲不振も通常は注射後から1時間、もしくは1日以内に改善する一時的なものであることがほとんどです。
1日以上、食欲不振が続く場合にはほかの病気や異常の可能性が考えられるため、獣医師に相談することが大切です。
元気がなくなる
こちらも一時的な副反応ですが、犬の元気がなくなる場合もあります。ワクチン接種後は1日様子を見るために安静にするよう求められます。
しかし、長時間元気がない状態が続いたりほかの副反応が出たりするようであれば、すぐに動物病院を受診するようにしましょう。
下痢・嘔吐
狂犬病予防注射後に下痢や嘔吐を引き起こすこともあります。下痢や嘔吐も副反応の一つとしてみられる症状ですが、数時間程度で治まることがほとんどです。
下痢や嘔吐が長時間続くと、脱水症状を引き起こし致命的な状態につながるため注意が必要です。下痢や嘔吐の症状がひどくなる前に動物病院を受診するようにしましょう。
アレルギー反応

まれに狂犬病予防注射後にアレルギー反応が出ることがあります。アレルギー反応は、皮膚の発疹・かゆみ・呼吸困難などの症状です。
ほかにもムーンフェイスといって顔面が腫脹して丸くなることもあります。過敏体質・免疫力の低い子犬・免疫力が低下しているシニア犬に起こりやすいため、注意が必要です。
アナフィラキシー反応
アレルギー反応よりもまれなケースですが、アナフィラキシー反応が現れる場合があります。アナフィラキシー反応でみられる症状は以下のとおりです。
- 虚脱
- 貧血
- 血圧低下
- 呼吸速拍
- 呼吸困難
- 体温低下
- よだれが垂れる(流涎:りゅうぜん)
- ふるえ
- けいれん
- 尿失禁
上記のように、狂犬病予防注射後に意識を失ったり呼吸困難になったりなどのアナフィラキシー反応が起こった場合は、早急に動物病院で処置を受けなければなりません。
獣医師も狂犬病予防注射で起こった副反応は、農林水産省に報告することが義務付けられています。2015年に日本国内で狂犬病予防注射を受けた犬の数は4,688,240頭で、そのうち副反応が報告されたのは18件でした。
年々、副反応の発現率は減少傾向にありますが、免疫力の低い子犬やシニア犬は副反応が出やすい傾向にあるため注意が必要です。
まとめ

今回は動物病院で狂犬病予防注射を受けられるのか・必要なものや予防注射済票の交付手続きについて解説しました。
狂犬病はその名のとおり、犬が感染して影響を受けやすいウイルス性の疾患です。しかし、ウイルス感染した動物の唾液や血液を介して人間やほかの動物にも伝染します。
狂犬病に感染すると神経疾患を引き起こし、けいれんや麻痺を経て死亡に至ることがほとんどです。狂犬病は一度発症すると、ほぼ100%の致死率であるとされています。
日本での発症例は近年確認されていませんが、狂犬病が流行している国や地域ではいまだに発症が確認されており、人間への感染が大きな問題となっています。海外旅行や外国人からウイルス感染する恐れがあるため、国内であっても狂犬病予防注射を受けることは必須です。
狂犬病予防注射の必要性・ワクチン接種を受ける際に必要なもの・注射後の副反応などを把握したうえで、愛犬と飼い主さんの健康を守っていくようにしましょう。
参考文献