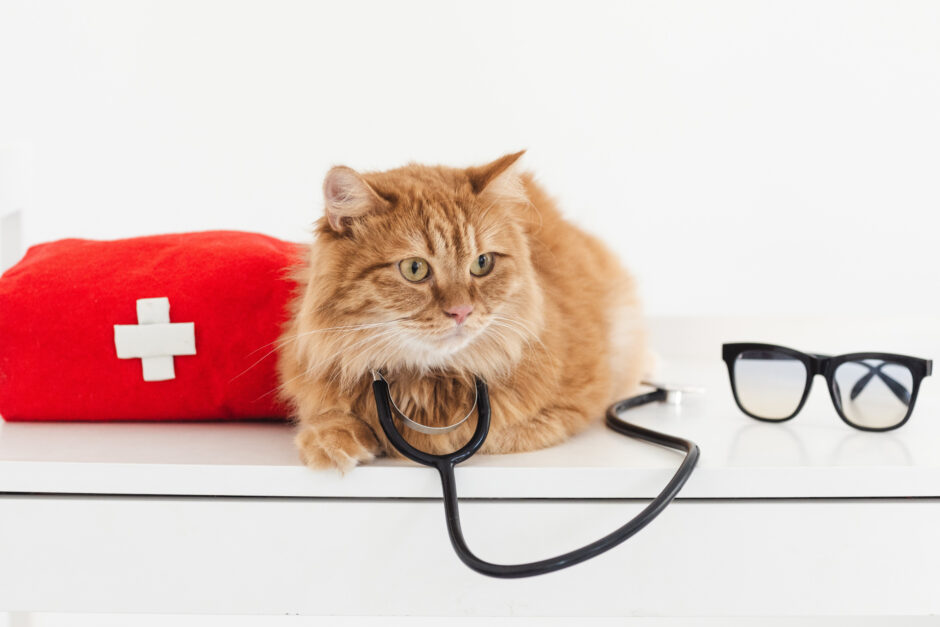猫にもさまざまな肝臓の疾患があります。
ただし肝臓は沈黙の臓器とよばれるほど、異常があってもなかなか症状が現れないため、肝臓の疾患は気付きにくい病気といわれています。
猫の肝臓の疾患のなかでも年齢に関わらず罹患率が高い肝臓の疾患が、肝炎や胆管肝炎です。
今回は、気付きにくい猫の肝炎について、種類・原因・症状・治療法などについて解説します。
以下の内容を参考に、何かしらの症状が現れた際には、早めに動物病院を受診するようにしましょう。
猫の肝炎の種類・原因

- 猫の肝炎の種類を教えてください。
- 肝炎はさまざまな原因によって引き起こされ、肝臓の細胞に炎症が起こることにより肝機能が低下する病気です。
肝炎は、急性肝炎と慢性肝炎の2つに分類されます。
また、猫でよくみられる肝臓の病気の一つとして、胆管肝炎もあります。胆管肝炎は、胆汁が流れる通り道である胆管で起きた炎症(胆管炎)が肝臓にまで広がった状態のことです。
猫の解剖学的特徴により胆管の出口と膵管の出口が同じであるため、胆管炎・胆管肝炎を発症しやすいと考えられています。
胆管肝炎は、化膿性(細菌性)と非化膿性(非細菌性)に分類されます。
- 猫が肝炎にかかる原因を教えてください。
- まず急性肝炎の原因として考えられるのは、細菌感染・ウイルス感染・中毒などさまざまです。
ウイルス感染では、猫伝染性腹膜炎ウイルスや猫白血病ウイルスなどに感染した場合に、肝臓にまで炎症が広がることがあります。
そして胆管肝炎は、感染が原因のもの(好中球性)と過剰な自己免疫が原因のもの(リンパ球性)があります。
さらに、膵炎や糖尿病、肝臓腫瘍に起因して肝炎を併発する場合も少なくありません。
また慢性肝炎の原因は、肝臓の炎症が繰り返し起こることにより慢性化する場合や肝臓に銅が蓄積することにより慢性化する場合、肝吸虫の寄生により慢性化する場合などです。
猫の肝炎の症状・治療法

- 猫の肝炎の症状を教えてください。
- 肝炎になると現れる主な症状は以下の5つです。
- 活動性の低下
- 食欲不振
- 嘔吐
- 下痢
- 発熱
さらに重度になると、黄疸や腹水、神経症状などの症状が現れます。
ただし、初期の場合はほとんど症状が現れないため、何かしらの症状が現れたときは病状は進行している場合がほとんどでしょう。
慢性肝炎になると、急性肝炎の症状に加えて、多飲多尿・体重の減少・肝機能低下による体温の低下などの症状の出現も考えられます。さらに、長期に渡って肝炎が続くと、肝臓が線維化し肝臓が硬くなる肝硬変に移行する場合もあります。
いずれの場合も、無処置の場合は命の危険があるため、症状が現れたら早めに動物病院で検査・治療をしましょう。
- 猫の肝炎の診断にはどのような検査を行いますか?
- 肝炎の主な症状である活動性の低下や食欲低下・嘔吐・下痢は、肝炎以外の疾患でも現れるような症状です。
肝炎の診断に必要な検査は、血液検査・腹部のエコー検査・レントゲン検査です。
血液検査では、感染症や炎症などの有無を調べる全血球検査(CBC)と肝臓・腎臓などの機能を調べる血液生化学検査を測定し、全身の血液成分の状態をチェックします。肝炎になると、肝機能の評価となる肝酵素(ALT・AST・ALP)や、肝臓や胆嚢の状態の評価となる総ビリルビン(T-Bil)などの数値の上昇が見られるでしょう。
腹部のエコー検査では、肝臓周囲の組織に炎症があるかどうかの確認が可能です。
レントゲン検査では、肝臓の大きさを確認できます。さらに詳しく肝炎の種類や原因を診断する場合は、CT検査や試験開腹・肝生検をする場合もあります。
試験開腹や肝生検は、肝臓の組織の一部または細胞組織を採取し、病理組織検査で肝臓の組織の構造を確認する方法です。
- 猫の肝炎の治療法を教えてください。
- 肝炎の原因や症状によって治療方法は異なりますが、一般的には輸液や投薬治療などの内科治療が行われます。
輸液は水分やミネラル補充など体内の水分バランスの調整のために行われ、投薬治療は症状や原因によって使う薬が異なります。肝臓の保護作用のある薬や消炎剤を使いながら、嘔吐や下痢などの症状に応じた薬の投与を行う対症療法です。
細菌感染が疑われる場合には抗生物質の投与、中毒が疑われる場合には解毒剤の投与、自己免疫の関与が疑われるリンパ球性胆管肝炎では免疫抑制剤を追加投与します。
また、症状の程度や緊急度により入院下での治療か通院での治療となるでしょう。
- 治療期間はどのくらいかかりますか?
- 治療期間は肝炎の種類や症状の程度によって異なります。
急性肝炎や化膿性胆管肝炎の場合、適切な治療を行い、上昇していた肝酵素の数値の低下が認められたら治療を終了できるでしょう。
自己免疫によるリンパ球性胆管肝炎は、投薬により上昇していた肝酵素の数値の低下が認められるものの、休薬すると再び数値が上昇することもあります。その場合は、薬の再投与を行い定期的なモニタリングが行われます。
休薬すると肝酵素の数値の上昇が認められる場合は、投与量の調整を行いながら長期継続的な投薬が必要です。
- 症状はほかの病気と区別がつきますか?
- 肝炎の代表的な症状である、食欲低下・活動性の低下・嘔吐・下痢・発熱の症状だけではほかの病気と区別するのは難しいでしょう。
ただし、黄疸が現れたら肝臓や胆嚢に問題があることに気付くことができます。
黄疸の症状が現れると、通常より濃い黄色の尿が出たり、眼球の白目の部分や皮膚・粘膜が黄色っぽく見えたりします。皮膚・粘膜だと歯茎や耳の内側の色などがわかりやすい箇所です。
黄疸の症状に気付くためには、日頃から愛猫の正常時の歯茎・目・皮膚の色を確認しておくことが大事です。
猫の肝炎に対しての予防方法・注意したいこと

- 猫の肝炎に対しての予防方法はありますか?
- 中毒による肝炎にならないように、猫が毒物や薬物などの中毒性物質に近付かないようにしましょう。
残念ながらその他の種類の肝炎を予防する方法はありません。
肝炎になっていても初期段階では臨床症状が現れないことがほとんどです。しかし、臨床症状が出てからでは、病状が進行していて早急な治療が必要な場合がほとんどでしょう。
健康診断で肝酵素の数値の上昇がみられ肝炎を疑う所見が認められる事例もあります。肝炎の早期発見のためにも、定期的な血液検査を行うことが望ましいでしょう。
そして肝炎だけに限ったことではありませんが、普段から愛猫の体調や身体の状態を気にかけ、すぐに異変に気付けるようにしておくのも重要です。
- 治療前後で注意すべきことはありますか?
- 治療前はなるべく負担をかけず安静にさせておくのがよいでしょう。
治療の甲斐あって無事に肝炎の治療を終了することができても、治療後も油断は禁物です。肝炎の原因によっては投薬を中止すると、肝炎が再燃する可能性もあります。
また愛猫の体調を維持するために、肝臓への負担を少なくした食事に切り替えたり、肝臓を保護するサプリメントを服用したりする必要があるでしょう。
- ほかの猫がいる場合、隔離した方がよいですか?
- ウイルス感染が原因と考えられる肝炎の場合は、ほかの猫に7が感染しないように隔離した方がよいです。
それ以外のほとんどの肝炎の場合は、ほかの猫との隔離は必要はありません。
ただし、愛猫が病気のときは一匹で静かに過ごしたい性格・気質の猫の場合は、棲み分けが必要になるかもしれません。棲み分けが難しい場合は、落ち着ける場所を作ってあげるのがよいでしょう。
- 治療費用について教えてください。
- 肝炎の種類によって、検査すべき内容や使用する薬の種類・数、入院の有無・治療期間などで治療費用は大きく変わってきます。そして、動物病院によって診療費の料金設定が異なります。
例えば急性肝炎で受診し入院下で1週間の治療を行ったと想定して考えてみましょう。仮に診察料・検査代(血液検査・腹部エコー検査)で15,000円、入院料・入院中の処置代(点滴・注射など)・入院中の検査代(必要項目の血液検査)で20,000円/日とすると、単純計算で155,000円です。退院してもしばらくは投薬が必要になるため薬代も追加されます。
さらに肝炎の診断のために試験開腹や肝生検までするとなると、治療費はより高額になります。
治療費用に関しては、受診する動物病院に確認するのがよいでしょう。
編集部まとめ

今回は、猫の肝炎について解説しました。猫の肝炎は、進行して重症化すると命の危険のある病気です。
何かしらの症状が現れた際は、様子を見ずに早急に動物病院を受診するようにしましょう。
そして猫の肝炎は、年齢に関わらず若齢の猫でも発症することのある病気です。
猫が若いうちから動物病院で定期的に健康診断を行って身体の内側も確認することは、猫の肝炎の早期発見に役立つでしょう。
参考文献