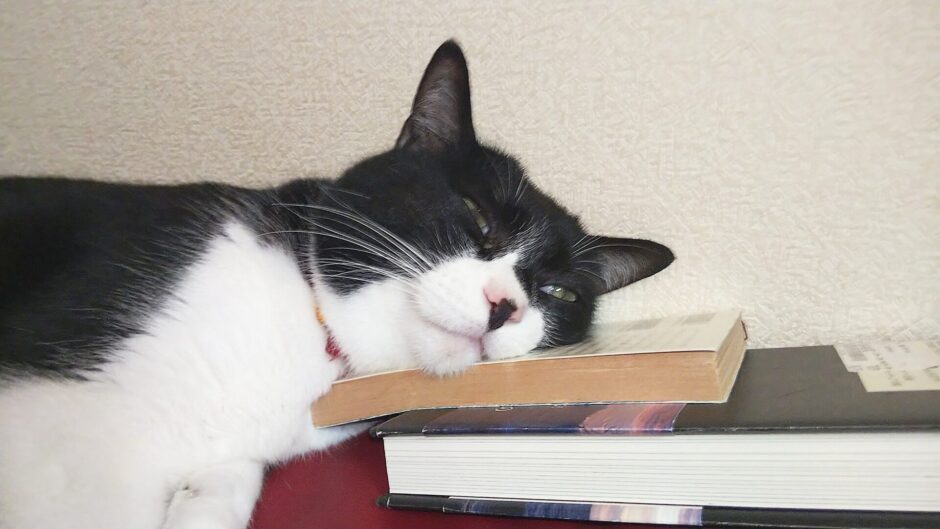鼻腔(びくう)内腫瘍とは、鼻のなかにできてしまう腫瘍のことです。人間と同じように、猫も鼻腔内腫瘍にかかることがあります。猫が鼻腔内腫瘍になってしまった場合にはどのような症状が出て、どのような治療が行われるのでしょうか。猫の鼻腔内腫瘍とはどのような病気なのか、その概要から、原因と症状、診断方法、治療方法などを解説します。大切な愛猫を守るためにも、鼻腔内腫瘍についての知識を備えておきましょう。
猫の鼻腔内腫瘍について

猫の鼻腔内腫瘍には良性腫瘍と悪性腫瘍の2種類があります。鼻腔内腫瘍とはどのような病気なのかを解説します。
鼻腔内腫瘍とは
猫の鼻腔内腫瘍は、空気が通る鼻腔や、骨の空洞である副鼻腔にできる腫瘍の総称です。鼻腔内腫瘍には良性の場合と悪性の場合があります。残念ながら、猫の鼻腔内腫瘍は悪性の場合がほとんどです。悪性でも治療により寛解するケースもありますが、症状が進行すると早い段階で死に至る恐ろしい病気です。
良性と悪性の違い
良性の場合は鼻腔内にできるポリープなどを指します。一方で、悪性はいわゆるがんのことを指しており、猫の鼻腔内腫瘍はリンパ腫が大半です。リンパ腫とは、血液由来の細胞のリンパ球が腫瘍になったことで起きます。猫のリンパ腫は消化管に生じることが一般的ですが、鼻腔内は消化管に次いで発生しやすい場所とされています。
猫のリンパ腫は、猫白血病ウイルス感染症と関係しているとされていますが、鼻腔内腫瘍ではあまり関係ないと考えられています。
リンパ腫以外にも、上皮細胞のがんであるケースも少なくありません。上皮細胞のがんには、鼻腔内にある腺細胞ががん化した腺がん、扁平上皮がん、未分化がんなどがあります。まれではありますが線維肉腫や骨肉腫である可能性もあります。
発生の可能性と統計
猫の鼻腔内腫瘍は、猫の腫瘍のうちでも1~8%程度であり、罹病率が高い病気ではありません。鼻腔内腫瘍のうち30〜50%程度は悪性のリンパ腫が占めています。また、猫の場合は犬よりも鼻腔内腫瘍の発生が少ないといわれています。
発症する年齢の平均は9歳前後ともいわれています。若い猫であっても罹患する可能性もありますので、初期症状が見られた際にはできるだけ早期に受診するようにしましょう。
悪性の鼻腔内腫瘍は予後が悪いのが特徴です。無治療や緩和ケアのみだと、余命は1ヵ月程度とされています。ただし、根治治療によって寛解するケースや年単位で生存するケースもあります。
猫の鼻腔内腫瘍の原因と症状

鼻腔内腫瘍が起きる原因や症状にはどのようなものがあるのでしょうか。愛猫の異変に早く気付き早期治療につなげるためにも、異変を見逃さないようにしましょう。
猫の鼻腔内腫瘍の原因
猫の鼻腔内腫瘍の原因ははっきりとはわかっていません。
タバコの煙、排気ガスが発症リスクを高める可能性があるといわれています。喫煙者の方は、愛猫が副流煙を吸ってしまう可能性がある場所での喫煙は控えましょう。
猫の鼻腔内腫瘍の初期症状
鼻腔内腫瘍の初期症状としては、鼻汁やくしゃみがあります。しかし、鼻汁やくしゃみは、感染症やアレルギーなどによる鼻炎、気管支炎などにかかっている場合でも見られる症状です。もし慢性的に鼻汁やくしゃみが続く場合や、治療を行ってもなかなか治らない場合は、鼻腔内腫瘍の可能性も否定できません。鼻汁やくしゃみの症状が続く場合は、動物病院での検査をおすすめします。
猫の鼻腔内腫瘍の進行と症状
鼻腔内腫瘍のリンパ腫は、侵襲性が強いことが特徴です。初期では鼻腔内のみに発生していますが、進行すると腎臓などのほかの臓器に転移することもあります。また、鼻の組織や骨を破壊して頭蓋骨にまで至る場合もあります。
進行は4段階のステージにわけられます。
- ステージ1:片側の鼻腔に限られており骨融解のない状態
- ステージ2:骨融解はありますが眼窩、皮下、結膜、鼻咽頭への浸潤なし
- ステージ3:目などのほかの臓器への浸潤
- ステージ4:鼻と脳の境目にある篩板という部分の破壊
進行すると鼻汁やくしゃみに膿や血液が混じることがあります。これは鼻腔内腫瘍の症状のなかでも高頻度に発症します。特に片側からのみ鼻血が出る場合は注意しましょう。
鼻腔内に腫瘍ができると空気のとおり道を塞ぎ、呼吸がしづらくなることがあります。いびきをかくようになったり、口呼吸や呼吸のしにくさから疲れやすくなったりする場合は、鼻腔内腫瘍の可能性があるといえるでしょう。また、口呼吸をすると空気を飲んで胃が膨らむため、食欲低下が見られる場合もあります。
行動の特徴としては、腫瘍が気になって物や地面などに顔を擦り付ける行動をすることがあります。顔を気にする動作が増えた場合は、体などに異変がないかよくチェックしましょう。
腫瘍が大きくなると、筋肉や骨を圧迫して、顔が変形することがあります。顔全体が腫れる、顔が左右非対称になる、鼻の形が変わるなどの変形が見られた場合は、かなり症状が進行している可能性が高いでしょう。
また、骨を溶かすまで進行すると、激しい痛みが生じます。さらに頭蓋骨まで浸潤した場合は、脳に影響が出るため、発作や異常な行動をすることもあります。
猫の鼻腔内腫瘍の診断方法

鼻腔内腫瘍が疑われる場合は、動物病院で検査を行いましょう。鼻腔内腫瘍は早期発見と早期治療が重要なポイントです。疑わしい点があれば早めの受診をおすすめします。
動物病院での診療の流れ
鼻腔内腫瘍が疑われる場合は、まず画像検査が行われます。レントゲン検査が一般的でしょう。鼻の部分を撮影して骨の内部の様子を検査します。レントゲンで異常が見られた場合は細胞の検査などが行われます。
レントゲン検査よりも精度の高い画像検査としては、CT検査やMRI検査があります。これらは特別な設備が必要なため、検査できる病院は限られます。また、CTやMRIの場合は麻酔が必要になります。
検査の内容は動物病院によっても異なりますので、事前に検査方法などを確認しておくとよいでしょう。
検査と診断
画像検査によって異常が発見された場合には、細胞を調べる病理組織検査が行われます。
病理組織検査は生検とも呼ばれ、問題の細胞の一部を採取して検査する方法です。鼻の孔からストローのような専用器具を挿入して、直接腫瘍の一部を切除します。採取後は鼻腔内の腫瘍が、どのような種類なのかを観察して診断が行われます。
鼻腔内腫瘍の種類がリンパ腫であった場合は、リンパ節転移や遠隔転移の有無や広がりを詳しく調べ、併発疾患があるかなどの検査も行われます。
鼻腔内腫瘍の種類がわかれば、その種類に応じた治療へと移行します。
鼻腔内腫瘍の治療法

鼻腔内腫瘍の治療では、腫瘍の種類によって選択される治療法が異なります。鼻腔内腫瘍と診断された際には、どのような治療が適しているのか、治療費、家庭でできることなど、しっかりと獣医師の話を聞いて治療に臨みましょう。
化学療法
化学療法とは薬物を使った治療法のことです。特に鼻腔内腫瘍の種類がリンパ腫であった場合に用いられます。具体的には、抗がん剤による治療が行われます。
抗がん剤治療は点滴によるものと飲み薬によるものがあり、基本的には抗がん剤治療は何クールか継続して行う必要があります。抗がん剤治療は、うまく効果が出れば全身状態が改善される可能性がある治療で、治療によってリンパ腫が寛解したケースも報告されています。なお、抗がん剤治療は副作用を起こしやすいのも特徴です。主な副作用としては、白血球の減少、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠(けんたい)感などがあります。
放射線療法
放射線治療は、がん細胞に放射線を照射することでがん細胞のDNAを壊す治療法です。がん細胞にのみ大きなダメージを与えられるのがメリットで、鼻腔内腫瘍のような局所的ながんには有効な治療法です。正常な細胞に対しての影響が少ないため、全身へのダメージを受けにくいのが特徴です。腫瘍のある場所が鼻腔内に留まっている場合にはよい効果が期待できます。
ただし、リンパ節やほかの臓器に転移している箇所には効果が得られません。照射できる放射線量には限度があるため、治療回数が限られている点にも注意が必要です。副作用としては、脱毛や皮膚炎が見られることがあります。また、晩発副作用として白内障や骨壊死のリスクがある点も留意したうえで治療を選択しましょう。
外科的切除
腫瘍が手術で除去できる場合は、外科的切除が行われます。鼻腔内腫瘍は完全な切除は困難なケースが少なくありません。しかし、一部を切除して腫瘍を小さくすることで、呼吸がしやすくなる場合もあります。症状を緩和するための治療として選択されることのある治療法です。なお、鼻腔内腫瘍がリンパ腫の場合は、基本的に手術による治療は行われません。
緩和ケア
緩和ケアとは、症状を和らげて苦痛を取り除くための治療です。化学療法や放射線療法が、猫の長期生存を目的にした根治治療であることに対し、緩和ケアでは少しの間であっても楽に生きられるように、生活の質を改善するためのものです。具体的には、抗炎症薬や止血治療など、症状を緩和するための治療が行われます。
鼻腔内腫瘍の予防法と健康管

鼻腔内治療を予防する方法はあるのでしょうか。日頃からできる愛猫の健康管理の方法と併せてチェックしましょう。
日常的な健康管理
あらゆる病気から愛猫を守るためにも日常的な健康管理は大切です。猫との暮らしにおいては、健康的な生活や快適な環境を整えるように心がけましょう。
食べ物は、年齢や体重に合ったものを選び、水分補給も十分にできるようにしておいてください。アレルギーがある場合は、アレルゲンを避けることも必要です。また、ストレスを溜めるような環境では体調を崩す可能性があります。くつろげるスペースがあるか、同居している動物との関係は良好か、トイレや部屋は清潔かといったことに日頃から気を付けてあげましょう。感染症や気管支炎などの予防のためには、カビや虫よけなどの対策も必要です。
日頃から猫がどのような生活を送っているのかをしっかりチェックしておくことも大切です。どのフードをどれくらい食べるのか、排便の様子、普段の行動などを知っておけば、異変が生じたときに早く気付くこともできるでしょう。スキンシップを取る際に、体に変わったところがないかボディーチェックをすることも大切です。見た目や行動にいつもと様子が違う点が見られたら、早めの検査をおすすめします。
リスク軽減のための予防法
猫の鼻腔内腫瘍には予防法がありません。発症の原因がはっきりしていないため、予防法もわかっていないのが現状です。
ただし、タバコの副流煙や排気ガスなどが鼻腔内腫瘍の発症リスクになるともいわれています。猫がいる場所でタバコを吸わない、排気ガスなど有害な物質には近づけないなど、猫が健康に暮らせる環境を整えることを意識しましょう。殺虫剤、除草剤、直射日光、石油ストーブ、アスベストなども避けてください。
愛猫の健康を守るために
愛猫の健康を守るためには、定期的な検査をおすすめします。見た目ではわからない病気でも、検査で発見できることも少なくありません。人間ドックと同じように、総合的にチェックできるキャットドックでは、触診、尿や便、血液の検査、超音波、レントゲンなど、多角的に検査ができます。
鼻腔内腫瘍は早期発見が重要ですが、気付いたときには症状が進行していることも少なくありません。特に異変を感じていなくても、定期的に動物病院を受診して検査をしてもらいましょう。
まとめ
猫の鼻のなかにできる鼻腔内腫瘍は、ほとんどの場合が悪性のがんです。鼻汁やくしゃみといった症状から始まり、鼻血や顔の変形などが現れます。進行すると鼻の組織や骨を溶かしていき、死に至る怖い病気です。鼻腔内腫瘍は発症の原因や予防策が確立されていません。しかし、治療を行うことで症状の緩和や寛解の可能性もあります。早期発見のためにも、日頃から愛猫の健康には気を配ることが大切です。気になる点がないかを日常的にチェックするのに加え、定期的に動物病院でも検査を受けましょう。