人間でも椎間板ヘルニアという病気を耳にしたことがあるかもしれませんが、実は猫にも椎間板ヘルニアが起こることがあります。椎間板ヘルニアとは背骨の骨と骨の間にあるクッション(椎間板)が本来の位置から飛び出し、神経を圧迫してしまう状態を指します。猫では犬ほど多くはないものの、発症すると痛みや歩行障害など深刻な症状が現れ、適切な治療が必要となります。本記事では、まれな疾患である猫の椎間板ヘルニアについて、原因や症状から予防法までを解説します。
猫の椎間板ヘルニアとは

椎間板ヘルニアとは、背骨(脊椎)を構成する椎骨と椎骨の間にある椎間板という軟骨のクッションが何らかの損傷や変性を受けて突出し、背骨の中を通っている脊髄や神経の根元を圧迫する病気です。椎間板は本来、背骨にかかる衝撃を吸収し柔軟性を保つ役割を果たしています。しかし、椎間板が変形して飛び出してしまうと脊髄の神経を圧迫し、痛みや運動機能の障害を引き起こします。
猫の場合、椎間板ヘルニアは犬ほど一般的ではなく、発症はまれです。ある研究報告では有病率は0.23%、犬の3.5%と比べると10分の1の頻度です。文献上は近年50年間でも200例ほどの症例の報告しかありません。しかし、発症することのある病気ではあり、日本各地でも発症例の治療が各動物病院で行われています。
猫の椎間板ヘルニアのおもな原因

猫の椎間板ヘルニアが起こる背景にはさまざまな要因があります。代表的な原因としては、肥満による背骨への負担、激しい運動や外傷による背骨への衝撃、そして加齢に伴う椎間板の変性が挙げられます。これらの要因が単独または複合的に作用し、椎間板が劣化・損傷することでヘルニアが発生すると考えられています。以下に考えられる主な原因を説明します。
外傷
高い所からの落下や遊びをふくむ激しい運動、交通事故などによる強い衝撃は、猫の背骨に深刻なダメージを与える可能性があります。このような外傷によって椎間板が急激に損傷を受けると、その一部が飛び出してしまい、突然椎間板ヘルニアを発症することがあります。特に高所へのジャンプや着地を好む猫では、着地の衝撃が積み重なって椎間板に負担をかけている場合もあります。激しい運動中に発症する症例も少なくないようです。
加齢
猫も高齢になると身体のさまざまな組織が老化し、椎間板も例外ではありません。加齢に伴って椎間板の水分量や弾力性は減少し、少しの衝撃であってもヘルニアを起こすリスクは高まります。これまでに報告のあった症例の平均年齢は8.3-8.7歳です。
肥満
これまでの研究報告は数が少なく、肥満は原因であるとは言い切れません。しかし、肥満そのものは猫の健康にさまざまな悪影響を及ぼします。犬では肥満が椎間板ヘルニアの発症に影響を与える因子の一つでもあります。猫でもその可能性が指摘されています。肥満では、日常的に背骨に過度な負荷がかかりやすくなります。重い体重を支えるため背骨や椎間板に大きなストレスがかかり、椎間板が変性しやすくなるのです。
椎間板ヘルニアを発症しやすい猫の特徴と猫種

前述の原因からもわかるように、椎間板ヘルニアの発症には体格や年齢、生活習慣などが関係しています。本章では、椎間板ヘルニアにかかりやすい猫の共通した特徴と、特に注意が必要とされる猫種を解説します。
椎間板ヘルニアにかかりやすい猫の特徴
一般的に、次のような特徴を持つ猫は椎間板ヘルニアを発症しやすい傾向があります。
- 高齢の猫
- 太り気味・肥満の猫
- 運動不足や筋力低下傾向の猫
- 体型に特徴がある猫(胴長短足など)
これらの特徴を持つ猫では、日常のなかで椎間板ヘルニアを疑わせるようなサインがないか注意深く観察することが重要です。
椎間板ヘルニアにかかりやすい猫の種類
犬では特定の犬種(ダックスフンドなど)が椎間板ヘルニアになりやすいことが知られていますが、猫でもこれまで椎間板ヘルニアの発症リスクが高いと指摘されている猫種があります。具体的にはブリティッシュショートヘアーとペルシャが挙げられます。また、エキゾチックショートヘアに特に多かったとする報告もあります。これらペルシャ科と呼ばれるような特定の猫種を飼っている場合は、特に椎間板ヘルニアに注意が必要といえます。
猫の椎間板ヘルニアの症状

猫の椎間板ヘルニアの症状は、ヘルニアが発生した部位や神経の圧迫の程度によってさまざまです。初期の軽い段階では痛みや違和感による微妙な行動変化のみですが、進行すると歩けなくなる、排泄が自力でできなくなるといった重大な症状に至ることもあります。本章では、椎間板ヘルニアの初期症状と進行した場合の症状を段階に分けて解説します。
椎間板ヘルニアの初期症状
椎間板ヘルニアの初期には、一見するとわかりにくいささいな症状から始まることがあります。例えば、以下のようなサインが初期症状として現れることがあります。
- 痛みの兆候:猫が急に抱っこを嫌がったり、背中や腰に触れられるのを避けるようになります
- 活動性の低下:椎間板ヘルニアによる違和感や軽度の痛みから、猫があまり動きたがらなくなります
- 歩行の異常:初期段階では軽いふらつきやぎこちない歩き方が現れることがあります
- 元気・食欲の低下:痛みや不快感から元気がなくなり、食欲不振になる猫もいます
これら初期症状の段階では、猫自身がなんとか普通に過ごそうと頑張ってしまうため、飼い主さんも見逃しがちです。
進行した椎間板ヘルニアの症状
椎間板ヘルニアが進行すると、より明らかな異常が現れます。椎間板の突出が大きくなり脊髄神経を強く圧迫するため、神経障害による重い症状が引き起こされるのです。
- 激しい痛みと運動困難:ヘルニアが悪化すると猫は強い痛みを感じ、動くこと自体を嫌がります
- 感覚障害(知覚の低下):神経の圧迫が強まると、痛みを感じる感覚自体が鈍くなったり失われたりします
- 排泄障害:ヘルニアによる神経圧迫が腰の神経にまで及ぶと、尿や便をコントロールできなくなることがあります
- 筋肉の萎縮:麻痺した足など使えなくなった筋肉は、長期化すると徐々に痩せ細って萎縮していきます
猫の椎間板ヘルニアの検査と診断
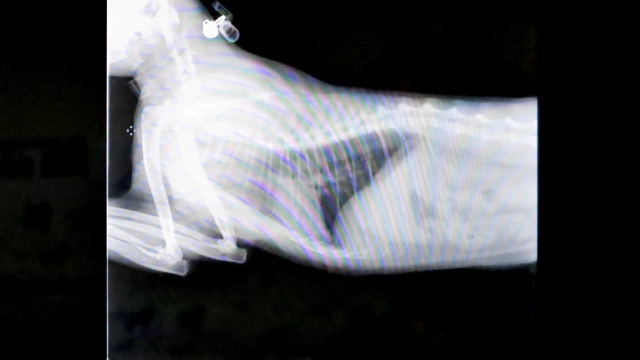
猫の椎間板ヘルニアが疑われる場合、獣医師はいくつかの段階を踏んで詳しく状態を調べ、診断を行います。本章では、診察時に行われる主な検査方法と、椎間板ヘルニアと診断するための基準を解説します。
椎間板ヘルニアの検査方法
椎間板ヘルニアの検査方法は、主に触診と画像検査に分けることができます。それぞれを詳しく解説します。
触診や神経学的検査
獣医師はまず猫の全身状態を把握するために触診や神経学的検査を行います。背骨に沿って優しく触れ、痛がる箇所や異常な反応がないか確かめることで、痛みの部位を特定します。首から尻尾の付け根まで順番に圧迫し、猫が敏感に反応する場所があれば、そこがヘルニアの起きている可能性の高い部位です。また足先をつねって反射や痛み反応を調べたり、ハンマーで腱反射を確認したりと、神経学的な反射検査も行います。さらに、診察室内を歩かせて歩行状態の観察をすることも重要です。歩き方にふらつきがないか、足の引きずりや麻痺が見られないかをチェックし、症状から脊椎のどの部分に問題があるかを推測します。
画像検査
身体検査で椎間板ヘルニアが疑われた場合、確定診断のためには画像検査が欠かせません。一般的によく行われるのはレントゲン検査(X線検査)ですが、レントゲン写真では骨は写っても軟骨である椎間板そのものは写りません。より詳細な検査としてはCT検査やMRI検査があります。CTはX線を使って身体の断面を撮影する検査で、骨や石灰化した椎間板片の位置を立体的に把握できます。一方、MRIは脊髄や椎間板の軟部組織まで鮮明に写し出すことができるため、ヘルニアによる脊髄神経の圧迫具合を確認する最適な方法です。MRI検査では椎間板から飛び出した髄核が神経を押し潰している様子や、脊髄の炎症・浮腫まで評価できます。これらの高度な画像検査は全身麻酔が必要ですが、椎間板ヘルニアの確定診断や重症度の判断にはとても有用です。
猫の椎間板ヘルニアの診断基準
最終的な診断は、臨床症状と検査結果を総合して行われます。一般的に、以下のポイントが椎間板ヘルニア診断の判断材料となります。
- 典型的な神経症状の存在
- 他疾患の除外
- 画像所見による裏付け
以上の条件が満たされた場合、猫の椎間板ヘルニアと診断されます。診断が確定したら、次はいよいよ具体的な治療に移ります。
猫の椎間板ヘルニアの治療法

猫の椎間板ヘルニアの治療法は、確立されたものはありません。発症例が少ないためです。しかし、頻度の多い犬の治療のガイドラインを参考に実際的には治療が行われます。本章では、主な治療方法である手術療法、内科的治療、その他の治療を順に解説します。
手術療法
手術療法は、椎間板ヘルニアによって強い神経圧迫が生じている場合に選択される治療法です。一般的な術式としては、背骨の一部を切開して圧迫部分まで到達し、飛び出した椎間板物質を除去する椎間板摘出術や片側椎弓切除術(ヘミラミネクトミー)などがあります。手術は全身麻酔下で行われ、専門的な設備を持つ動物病院で実施されます。手術の適応となるのは、重度の麻痺がすでに出ている場合や、内科的治療では改善しなかった場合、あるいは症状が徐々に悪化している場合です。早期に手術を行い神経の圧迫を取り除けば、麻痺が回復して再び歩けるようになる可能性があります。
内科的治療
内科的治療(保存的療法)は、症状が軽度な椎間板ヘルニアや、脊髄を圧迫しないタイプのヘルニアである急性非圧迫性髄核逸脱(Acute Non-compressive Nucleus Pulposus Extrusion:ANNPE)に対してまず試みられる治療法です。具体的には以下のような治療を組み合わせて行います。
少なくとも2週間以上、できれば症状が落ち着くまでの期間、猫を安静に保つことが特に重要です。走ったりジャンプしたりすると椎間板への圧が高まり症状が悪化する恐れがあるため、ケージや狭い部屋で運動を制限します。
痛みを和らげ炎症を抑えるために消炎鎮痛剤(NSAIDs)やステロイド剤などが用いられます。また、必要に応じて筋肉の緊張を取る筋弛緩剤やビタミン剤が処方されることもあります。
内科的治療は身体への負担が少ない反面、ヘルニアの原因を取り除けるわけではないため、再発が起こることもあります。
その他の治療
椎間板ヘルニアの治療では、手術や薬だけでなく補助的な療法も取り入れることで回復を助けます。以下に代表的なものを紹介します。
- リハビリテーション:手術後や内科治療で痛みが改善した後、失われた筋力や機能を回復させるためにリハビリ運動を行います
- 鍼療法:痛みの軽減や組織の治癒促進を目的に用いられることがあります
その他の治療はあくまで補助的な位置づけですが、組み合わせることで猫の負担を減らし、全身の回復を早める効果が期待できます。
猫の椎間板ヘルニアの予防法

猫の椎間板ヘルニアの発症はそもそも頻度が低いため、予防法などもわかってはいません。しかし、犬と同じような機序で起きていることも多く、それを参考に、日頃の生活の中で飼い主さんが実践できる主な予防策を紹介します。
適切な体重管理と食事管理を徹底する
重要な予防策は、猫の体重を適正に保つことです。肥満は椎間板ヘルニアのみならずさまざまな病気の原因となるため、日頃から愛猫の体重チェックを習慣づけましょう。適切な体重管理のためには、まず食事の量と質を管理します。年齢や活動量に見合ったカロリーのフードを与え、間食やおやつの与えすぎに注意します。
足腰への負担が少ない室内環境を整備する
猫が暮らす環境を見直し、背骨や関節に負担をかけにくい工夫をしましょう。例えば、キャットタワーや棚に登る際にはステップ台やスロープを設置して、飛び降りや高所からのジャンプによる衝撃を和らげます。フローリングなど滑りやすい床には滑り止めマットを敷き、走ったときに踏ん張りがきくようにしてあげると足腰の負担軽減につながります。好奇心旺盛な猫は思わぬ高い場所に登ってしまうこともあるため、危険な場所には登れないよう対策することも必要です。こうした生活環境の工夫によって、日常的に背骨にかかるストレスや転落リスクを減らし、椎間板ヘルニアの発症を未然に防ぐことに努めます。
定期的に健康診断を受ける
症状が出ていなくても、定期健診を受けて健康状態をチェックする習慣をつけましょう。特にシニア期に入った猫や上述したリスク要因を抱える猫では、年に1~2回のペースで動物病院で健康診断を受けるのがおすすめです。健康診断では体重管理のアドバイスが受けられるほか、歩行のふらつきや神経症状など、何か異常が見つかれば早めに対処できます。
まとめ

猫の椎間板ヘルニアは決して頻繁に起こる病気ではありませんが、いざ発症すると痛みや麻痺など猫の生活に大きな支障を来す怖い病気です。肥満あるいは特定の猫種を飼育している方は特に注意して、少しでも「おかしいな」と思う症状があれば早めに獣医師に相談しましょう。大切な愛猫が快適に長生きできるよう、飼い主さんも知識を持って備えておきましょう。
参考文献


