犬や猫とは違いエキゾチックアニマルに該当するハリネズミは、すべての動物病院で診察を受けられるとは限りません。特にハリネズミは特殊な動物ですので、適切な検査や治療をしてもらうためには、専門知識や設備の揃っている動物病院を選ぶことが重要です。
普通の動物病院ではなくエキゾチックアニマル専門の動物病院を受診することで、ペットのハリネズミの緊急事態にも対処してもらえるでしょう。こちらの記事では、ハリネズミが罹りやすい病気についてお伝えしたうえで、動物病院に行く前の注意点と流れなどについて解説します。
ハリネズミはどこの動物病院でも診察を受けられる?

結論からお伝えすると、ハリネズミはエキゾチックアニマルに分類される動物であり、どこの動物病院でも診察を受けられるとは限りません。エキゾチックアニマルとは、犬猫や産業動物(豚、鶏、牛など)以外の動物の総称です。
エキゾチックアニマルは、犬や猫とは身体の構造が異なることから検査や治療方法が変わってきます。そのため、ハリネズミを診療対象としていない動物病院に連れて行っても、知識がないことや検査キット、治療器具が揃っていないことなどを理由に断られる可能性が高いです。
ハリネズミをペットとして家族に迎え入れるのであれば、どこにハリネズミを診察できる動物病院があるか確認しておきましょう。エキゾチックアニマル専門病院で探すのではなく、ハリネズミが診察対象に含まれている動物病院を探すのがポイントです。
ハリネズミが罹りやすい主な病気

ハリネズミは、犬や猫と比べて痛みや不調を飼い主に伝えることがむずかしいです。手遅れになる前に動物病院でみてもらうためにも、どのような病気や不調になる可能性がある動物なのかを把握しておきましょう。
ここでは、ハリネズミが罹りやすい主な病気について解説します。
ダニ感染、真菌症などの皮膚病
ハリネズミは、針のように鋭いトゲトゲとした毛を持ち合わせているため屈強そうに見えますが、実は皮膚が敏感な動物です。そのため、フケや抜け針の数が急激に増えたり、痒そうな仕草を見せるようになったときは、皮膚病の疑いがあります。
ハリネズミの皮膚病は、ダニと真菌の2種類に区分されます。いずれにしても生活環境の衛生面が悪いと発症するリスクがあるため、どちらの原因かによって検査や治療が異なります。
| 検査 | 治療 | |
| ダニ症 | セロハンテープで皮膚の表面の組織を採取して顕微鏡でノミやダニの有無を確認する | エボリューションと呼ばれる治療薬を2週間おきに2〜3回塗り、ノミやダニを駆除する |
| 真菌症 | 針や毛を採取して溶媒液につけて陽性反応の有無を確認する | 毎日飲み薬を与える |
ダニ症は1ヶ月〜1ヶ月半、真菌症は1ヶ月程で回復する見込みで、再検査をしてノミやダニが確認されなかったり、陰性反応がでたら完治です。なお、真菌症は、ハリネズミから人に感染する症例も報告されているため、治療期間中はこまめな手洗いが欠かせません。
下痢、便秘などの消化器系トラブル
ハリネズミは、自然のなかでもじっとしている時間が長いため、運動不足になりやすい動物として知られています。家のなかでもほとんど動かずに生活していると下痢や便秘などの消化器系トラブルを引き起こします。
見た目はふっくらとしていますが、食欲不振になると徐々に痩せ細った見た目に変わってしまうため、食事量はこまめに確認しましょう。また、水分が足りていないと、体内の便が硬くなり排泄ができずに腸内バランスの乱れや免疫力の低下を引き起こします。
食べる量が少ないからといって、いつまでも同じフードと水を置いていると腐敗して下痢の原因になります。ハリネズミには、常に新鮮なフードと水を用意してあげてください。そして、便の状態をよくみて回数や硬さなどに違和感を感じたら、動物病院の受診を推奨します。
呼吸器系の病気
ハリネズミは、歯周病による細菌感染や抗酸菌の悪化などをきっかけに鼻炎や肺炎、気胸などの呼吸器系の病気になるリスクが高まります。初期症状として、くしゃみや軽めの食欲不振や、じっとして動かなくなるなどの特徴があります。さらに悪化すると、鼻腔への影響も懸念されるため、早い段階での治療が必要です。
動物病院では、肺の透過性を見るためにX線検査を行いますが、丸まってしまうハリネズミは肺の状態が見えないためCT検査で状態を確認します。原因がわかれば内服薬や注射など適切な対症療法で回復を目指します。
ハリネズミは気温の変化に敏感で、24〜29度より寒かったり暑かったりすると体調を崩しやすいです。自宅の飼育環境を見直すことで、呼吸器系の病気の予防が可能です。
口腔内トラブル
ハリネズミは、歯が弱い動物として知られており、人と同じく歯周病を発病しやすいです。ハリネズミの口腔内には常在菌が多数あり、健康バランスを整えるために大事な役割を担っています。しかし、フードの食べかすが残り続けていると、歯周病や歯肉炎の原因となります。顎の力が弱いためウエットフードを好みますが、ウエットフードは歯にくっつきやすいため要注意です。
定期的に口臭、歯の変色、歯茎の腫れがないかをチェックすることで早期発見できます。放置すると歯がぐらついて抜けてしまいます。ペットのハリネズミが口元を気にしているようであれば、一度動物病院でみてもらいましょう。
また、ドライフルーツややわらかいフードなどハリネズミが好むフード以外にも、噛むおもちゃや硬めのフードをあげるだけでも歯周病予防ができます。
ハリネズミを動物病院に連れて行く前に確認すべきポイント
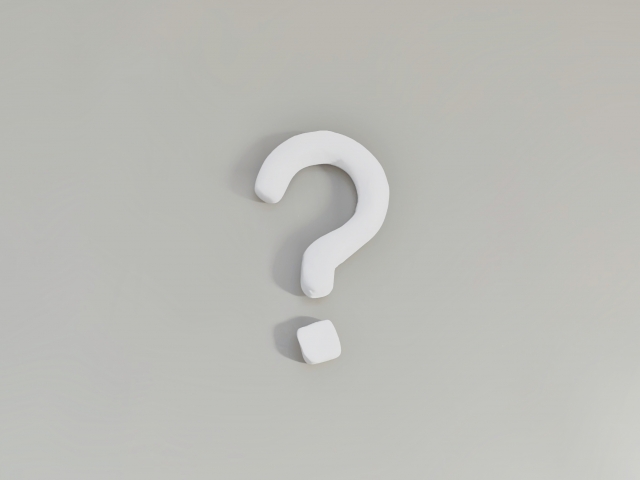
ハリネズミを診察対象にしている動物病院は限られており、住んでいる場所によっては時間をかけて通院しなければならないこともあるでしょう。適切な検査や治療を実施してもらうためにも、飼い主が獣医に状態を説明できるような準備を進めるようにしてください。
ここでは、ハリネズミを動物病院に連れて行く前に確認するべきポイントについて解説します。
飼育環境や食事内容を整理しておく
動物病院では、ハリネズミの病気や不調の原因を特定するために、飼い主からもヒアリングを行います。普段どのような環境で生活しているか、どのようなものをどれくらい食べているのかなどを聞かれるでしょう。
飼育環境については温度や湿度、ゲージの大きさ、食事内容についてはフードやおやつの種類とハリネズミが普段食べている量などを整理しておくことがポイントです。温度や湿度まで細かく管理していない場合、冷暖房の有無を伝えるだけでも、獣医は飼育環境をイメージしやすくなります。
さらに、ハリネズミ以外の動物をペットとして飼っている場合は、その動物についても必ず伝えるようにしてください。ハリネズミが感染症にかかっているのであれば、ほかの動物にも感染するリスクがあるからです。
体重変化や食欲・排泄の状態をチェックする
飼育環境や食事の内容の整理にくわえて、いつからハリネズミの調子が良くないのかについてもヒアリングが行われます。体重や食欲、排泄の状態について、いつ頃から変化があるのか、どれ程の変化があるのかを的確に伝えましょう。
例えば、何日も食事をとっていなかったり排泄をできていなかったりする場合は、危険性が高いため即効性の高い対症療法が必要です。一方で、病気や不調の症状が現れてすぐに動物病院を受診しているのであれば、ハリネズミに負担がかからないような形で治療できます。
新鮮な状態の嘔吐物や排泄物があれば、プラスチックの容器や袋に入れて持参すると、実物を見てウイルスや寄生虫などの可能性を判断してもらえます。
皮膚の状態や歩き方を観察しておく
ハリネズミの体調の変化は目立ちにくいため、常日頃から皮膚の状態や歩き方を観察し、些細な変化を見逃さないようにするのが大切です。抜け針やフケが増えたり、ほとんど動かなくなったりしたときは病気や不調のサインの可能性があります。
また、ハリネズミは口腔系トラブルも起こしやすいため、普段からスキンシップを取りつつ、口臭や口周りの異常がないかを確認しましょう。このように常に観察する習慣をつけておくことで、動物病院を受診する際にも、変化や違和感に関する説明がしやすくなります。
診察・検査の流れ

ペットのハリネズミを動物病院に連れて行くと、どのような流れで診察や検査が行われるのでしょうか。診察と検査ではどのようなことが実施されるのか把握しておくと、はじめてのエキゾチックアニマル専門の動物病院でも安心です。
ここでは、ハリネズミの診察と検査の流れについて解説します。
問診と視診・触診
まず、動物病院に来院後は問診票の記入をしながら待合室で待ちます。事前予約できる動物病院を受診すれば、待ち時間をできる限り減らすことができ、ペットの負担も軽減できます。
順番が回ってきたら、言葉の話せないハリネズミの代わりに飼い主が「なぜ動物病院を受診したのか」「どういった状態なのか」を説明します。はじめての動物病院では、うまく話せないこともあるかもしれませんが、そのときは獣医に聞かれた質問に答えるようにしましょう。
問診と同時に、ハリネズミを見たり触ったりして身体検査をし、病気や不調の原因を特定するために必要な検査へと進みます。
血液検査、便検査、レントゲン検査
検査方法には、血液検査や便検査、レントゲン検査などさまざまあります。ハリネズミは、体が小さいため、検査をするだけでも身体的な負担がかかります。そのため、問診や視診、触診の結果によって必要な検査を厳選します。
なお、ウイルスや寄生虫に感染した疑いがある場合は、便検査が有効です。ただ、古い便は正確な検査結果が出ない可能性が高く、便を持参するのであれば当日もしくは前日の夜までのものが好ましいです。便を持っていくべきか悩んだ際には、動物病院に通院する前に電話で確認してみてもよいでしょう。
投薬治療
検査が終わり病気や不調の原因が特定されたら、必要に応じて投薬治療を行います。例えば、ダニやノミに対しては、駆虫薬の注射やスポット剤、スプレー剤など、真菌に対しては、抗真菌薬が有効です。
ハリネズミにはたくさんのトゲトゲした毛があるため、獣医から怪我をしないように塗り薬の使用方法を確認しておきましょう。また飲み薬に関しては苦味が強いこともありますが、専用のシロップに混ぜて与えると、おいしそうに飲んでくれるようです。
手術や特殊な処置
検査結果によっては、投薬治療ではなく手術や特殊な処置が必要になることもあるでしょう。例えば、悪性腫瘍が見つかれば、転移する前に摘出手術が必要です。
なお、悪性腫瘍に対しては必ずしも手術が必要とは限らず、まずは投薬治療で様子を見る場合もあります。腫瘍の大きさや病気の進行によって、投薬をするのか摘出手術が必要なのか判断されるため、獣医の説明をよく聞きましょう。
また、摘出手術のように大がかりな治療を避けるためには、早期発見が欠かせません。小さな違和感を感じたら、早めに動物病院を受診することが重要です。
ハリネズミの診療をスムーズに進めるために

ハリネズミは、皮膚や歯、気温の変化などに敏感な動物であり、些細な体調不良から重症化する症例も報告されています。大切な家族として健康を守るためにも、万が一の体調不良に備えていつでも動物病院を受診できる準備が必要です。
ここでは、ハリネズミの診療をスムーズに進めるためのポイントについて解説します。
エキゾチックアニマルに対応できる動物病院を探しておく
ハリネズミは、エキゾチックアニマルに該当する動物であり、犬や猫を診察している動物病院ではみてもらえない可能性が高いです。住んでいる地域によっては、遠方まで足を運ばなければハリネズミをみてもらえないこともあります。ペットのハリネズミが体調を崩してから受診する病院を探し始めると、時間がかかってしまうため、事前リサーチが重要です。
動物病院ごとに診療時間や休診日が異なるため、いつ発病しても通院できるように複数の候補を用意しておくことを推奨します。また、動物病院によっては完全予約制をとっている場合があるため、通院前に電話で確認しましょう。
移動用のキャリーケースなどを用意しておく
動物病院では、ハリネズミ以外にも犬や猫、ウサギや鳥などさまざまな動物が集まるため、キャリーケースやゲージなどが必要です。暴れないからといって手で持って連れて行くことは認められていないため、すぐに動物病院に行けるようにキャリーケースはあらかじめ用意しておきましょう。
ハリネズミが入るサイズであれば指定はありませんが、寒さに弱いハリネズミのためにカイロを入れて保温調整できるタイプのキャリーケースなどもあります。動物病院のほかにも、震災時や何かしらの移動でも活用できるため、一つ持っておくと安心です。
日頃から様子をチェックしておく
ハリネズミの様子を日頃からチェックしておくことで、些細な変化を見落とさずに動物病院を受診できます。
例えば、フードや水を毎日取り替える習慣をつけることで、食欲不振に気付きやすくなるでしょう。また、こまめな掃除で抜け針やフケの増加の有無、スキンシップをとりながら口臭、口周りの腫れや変色の有無を確認できます。
ハリネズミが罹りやすい病気の初期症状を覚えておき、それらに該当する症状がみられれば早急に動物病院を受診しましょう。また、衛生面や気温などを配慮することで病気の予防にも効果的です。
まとめ

ハリネズミは、皮膚病から消化器系や呼吸器系までさまざまな病気のリスクがあるため、小さなサインを見逃さずに動物病院を受診することが大切です。
犬や猫向けの動物病院では診療してもらえないことがあるため、最寄りのエキゾチックアニマルに対応している動物病院を探しておきましょう。同時にキャリーケースを用意したり、ハリネズミが罹りやすい病気を知り予防できる環境を作ることで、ペットの健康を守ることにつながります。


