猫がもし病気になったら、不安に感じるのではないでしょうか。どのような病気なのか、重症化することはないか、治療費はどのくらいかかるのかなど不安に感じるでしょう。
猫の寿命も長くなってきたため、飼い主として猫の病気に関して調べておくことは大事なことです。猫に違和感があればすぐに動物病院に連れて行く必要があります。
猫は体調が悪いと隠れてしまうため、姿が見えないときは注意しましょう。この記事では、猫がかかりやすい病気や医療費とペット保険について解説します。
猫がかかりやすい病気について

- 猫がかかりやすい病気を教えてください。
- 猫がかかりやすい病気の上位3つは、消化器疾患や泌尿器疾患、皮膚疾患です。その他、感染症も猫によく見られる病気です。
具体的な病名を以下で紹介します。- 消化器疾患:胃腸炎・肝炎・膵炎
- 泌尿器疾患:慢性腎臓病・尿結石症・膀胱炎
- 皮膚疾患:アレルギー性皮膚炎・アトピー性皮膚炎・脱毛
- 感染症:猫上部気道感染症(猫カゼ)
次に、それぞれの疾患と関連する症状について解説します。
消化器疾患では、嘔吐や下痢がよく見られます。ただし、原因が必ずしも消化器疾患とは限りません。猫は毛玉を吐くので、それほど嘔吐について問題視しない方もいるかもしれません。
注意しなければならないケースは一日に何度も嘔吐し、体力を消耗することで、脱水症状が起こることです。
下痢も嘔吐と同様に、長期間続く場合は脱水症状を引き起こす場合があります。
また、血便の場合もすぐに受診が必要です。
泌尿器疾患では、尿が出ない場合や排尿困難が見られる場合は、尿路結石が疑われます。また、血尿や頻尿の症状が現れたときは膀胱炎や腎不全を疑います。
これら尿道や膀胱の疾患をまとめた総称が下部尿路疾患です。このうち特発性膀胱炎の原因ははっきりしていません。
皮膚疾患に見られる症状は、かゆみや皮膚の赤み、脱毛などです。皮膚炎の症状は、食物アレルギーやカビ、ノミやダニによるアトピー性皮膚炎が原因として考えられています。脱毛は、精神的なストレスが原因の場合もあるため、診断には検査が必要です。
感染症では、鼻水やくしゃみなどの症状がよく見られます。ウイルスや細菌が原因で発症する疾患は猫上部気道感染症とよばれるもので、猫カゼとして知られており、多頭飼いの場合はグルーミングによって感染が広がることも少なくありません。
- 病気以外で動物病院での受診が必要なのはどのようなときですか?
- 病気以外に、ケガや誤飲したときも受診が必要です。
留守番をさせていたり、ほかの部屋にいたりして眼を離した後に急に嘔吐し、遊んでいたおもちゃの一部がなくなっていることがあれば誤飲したと考えられます。
特にひも状のおもちゃで遊んでいた場合で、身体のなかで異物が引っかかっている場合は、レントゲン検査でも異物が写らない場合があり注意が必要です。
場合によっては、緊急処置として開腹手術が必要になることもあります。
猫が病気になったら治療費はどのくらいかかる?

- 猫が病気になったら治療費はどのくらいかかりますか?
- 日本獣医師会が実施した、家庭飼育動物(犬や猫)の診療料金実態調査結果の資料をもとに説明します。
一般的な猫カゼ症状で、くしゃみや鼻水程度の場合は、初診料と内服薬が獣医師より日数分処方されます。
この場合の初診料は1,000~2,000円未満で、調剤料は内服薬で1回あたり500円未満です。
例として内服薬を1日朝夕の2回で5日分処方された場合、総額でおよそ6,000~7,000円かかります。調剤の場合、処方箋が必要になりますが、動物病院ではほとんどが院内処方です。
次に、膀胱結石になった場合の治療費について解説します。頻尿や血尿、残尿感などの症状がある場合は検査を行います。膀胱結石の場合に行われる検査は以下です。- 血液検査(採血料):1,000~2,000円未満
- カテーテル留置(血管確保):1,000~2,000円未満
- 血液検査(生化学検査):5,000~7,500円未満
- 尿検査採取料(圧迫採取料):無料
- 尿検査採取料(カテーテル採尿):1,000~2,000円未満
- 尿検査採取料(膀胱穿刺):1,000~2,000円未満
- 尿検査検査料(尿比重・試験紙・沈査):1,000~2,000円未満
- X線検査(単純撮影):3,000~5,000円未満
- X線検査(尿路造影):5,000~7,500円未満
- 超音波検査(腹部エコー):3,000~5,000円未満
- CT検査(造影なし):30,000~40,000円未満
- CT検査(造影あり):30,000~40,000円未満
- 内視鏡検査:20,000~25,000円未満
- 麻酔料(内視鏡検査のための全身麻酔):10,000~12,500円未満
以上が膀胱結石の検査項目と費用です。上記すべてが費用としてかかるわけではなく、行った検査項目分の費用が発生します。
平均すると検査料はおよそ110,000円で、医療費としては150,000円以上になります。なぜなら、診察料や内服薬なども加算され、外科的治療が必要になると手術費用や入院費もかかる可能性があるためです。
結論として、治療費の目安は検査料およそ110,000円、手術費用が30,000円以上です。さらに入院料のほか、看護料や食事代などが加算され、高額になる可能性があります。
また、治療によっては長期間の通院が必要となる場合があることも考慮しておきましょう。
- 猫が手術を受ける場合の費用の目安を教えてください。
- 膀胱結石の手術では、尿路閉塞解除や、必要に応じて膀胱洗浄が行われます。
この場合の費用の目安は、尿道閉塞解除が3,000~5,000円未満で、膀胱洗浄は3,000~5,000円未満です。また、手術には全身麻酔10,000~12,500円も必要になります。
カテーテル留置(尿道)の費用は3,000~5,000円未満です。このことから、手術費用は目安として30,000円以上かかるでしょう。
- 入院が必要になった場合の費用の目安を教えてください。
- 一般的な猫の入院費は2,000~3,000円未満ですが、ICUに入ると3,000~5,000円未満の入院費がかかります。
さらに、入院していれば動物病院のスタッフが看護にあたるため、看護料もかかる場合があるでしょう。
日本獣医師会が実施した資料によると看護料は無料としていますが、一部では500~1,000円未満と料金を設定しているところもあり、費用の差が生じます。
一日1,000円の看護料がかかる場合、一週間入院すれば、さらに費用がかさむことになります。
- 動物病院によって治療費が違うのはなぜですか?
- 日本獣医師会では独占禁止法により、獣医師同士が協定して料金を設定することを禁止されています。そのため、動物病院によって治療費に差が生じます。
このような制度により、治療費等を獣医師が自由に料金を設定できるようになっているため、動物病院ごとに治療費用に差が生じているのです。
ペット保険の必要性
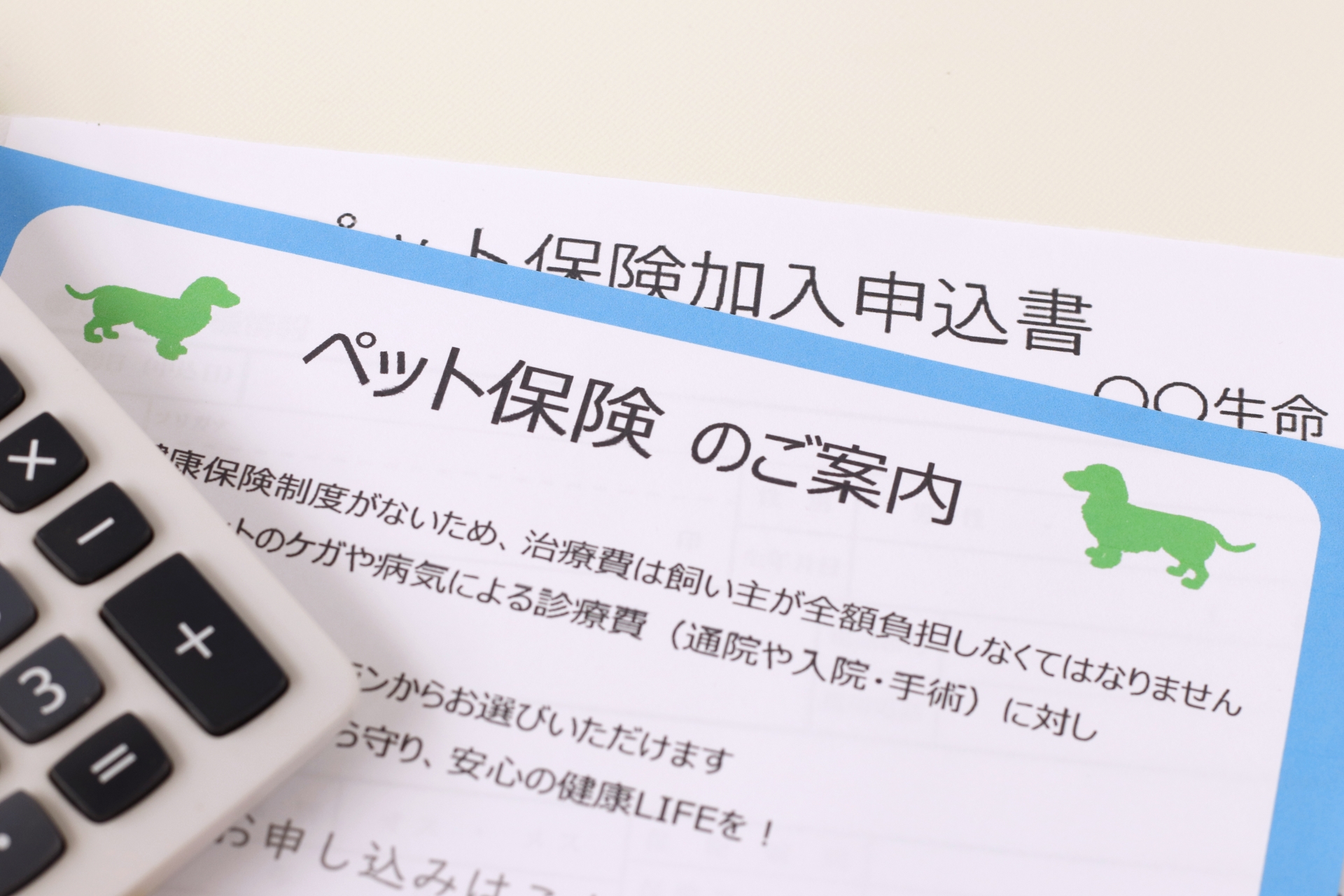
- 猫などのペットには公的な医療保険はありますか?
- ペットには公的な医療保険はありません。そのため、病気やケガで動物病院を受診した場合は全額自己負担になり、高額な医療費を支払わなければなりません。
ただし、保険会社が提供するペット保険はあります。ペット保険は保険会社によって補償内容や保険料が異なり、複数のプランが用意されています。
- ペット保険の必要性を教えてください。
- ペットの寿命は延びており、猫でも20歳まで生きることは珍しくありません。猫は7歳になるとシニア期に入り、病気やケガのリスクが高まります。
公的医療保険がないペットの医療費は、全額自己負担になるため、その負担を少しでも軽減できるのがペット保険です。
万が一、病気やケガで医療費が高額になった場合でも、加入している保険の補償で自己負担は減らすことができます。
- ペット保険の補償対象外となるのはどのようなケースですか?
- 病気の予防として受ける診察や健康診断、ワクチンの予防接種、去勢や避妊手術などが補償の対象外となるケースがあります。
保険によっては、先天性や遺伝性の疾患も補償対象外となる場合があるため、保険の補償内容をしっかり確認してから加入しましょう。
また、ワクチン接種で防げる病気や飼い主による故意のケガは、補償の対象外です。
- ペット保険を利用する場合の注意点を教えてください。
- 保険は新規で加入するときに年齢制限や、今まで罹患したことのある病気によっては加入できない場合があるため注意が必要です。
年齢制限により、猫は7歳からシニアとみなされ、加入できない場合があります。そのため、なるべく若い年齢でまだ病気に罹患したことのない、健康な状態のうちに加入しましょう。
また、保険に加入するときは、告知義務が必要です。告知義務とは、ペットがこれまで罹患したことのある傷病や、現在の健康状態を正確に申告することです。
編集部まとめ

ここまで猫がかかりやすい病気や、もし病気になったときの治療費、手術費や入院費についてとペット保険について解説してきました。
猫は痛みを隠す習性があるため、病気になっても飼い主が気が付かないこともあります。そのため毎日一緒に暮らす家族として、猫の食事やトイレ、行動をチェックし異変に気付けるようにしましょう。
猫が病気になった場合、症状によっては命に関わる可能性もあります。その際も、落ち着いて対処しましょう。
また、ペットには公的保険がないため、医療費はどれだけ高額でも全額自己負担となります。そのため、日頃からワクチン接種や健康診断を受け、予防に努めることが重要です。
ペット保険も猫が若いうちに検討し、加入しておくことで、医療費の負担を軽減できます。この記事がお役に立ちましたら幸いです。
参考文献


