ペットの目に異常が見られると心配になりますが、適切な目薬で早めに治療することが大切です。動物病院で処方される目薬と市販の目薬にはどのような違いがあるのでしょうか。また、目薬の正しい点眼方法や、ペットが点眼を嫌がるときの対処法、目薬の使用期限や保管方法についても解説します。大切なペットの目の健康を守るため、獣医師の指導のもと正しい方法で目薬を使いましょう。
動物病院で処方される目薬の種類

動物病院で処方される眼科用の薬剤には、大きく分けて液体の目薬と眼軟膏(ぬり薬)の2種類があります。それぞれ特徴が異なり、症状やペットの状態に応じて使い分けられます。
点眼薬(目薬)
点眼薬(目薬)は液体状の目薬で、角膜や結膜など目の表面に直接滴下して使用します。水のようにさらっとした液体なので目に行き渡りやすく、扱いやすいのが利点です。動物病院では、細菌感染に対する抗生物質の目薬や、炎症を抑える抗炎症目薬、乾燥を潤すヒアルロン酸などの人工涙液、緑内障に対する眼圧を下げる目薬など、ペットの症状に合わせたさまざまな目薬が処方されます。
軟膏
眼軟膏は半固形状の軟膏タイプの目薬です。軟膏は油分が主成分のため目に留まる時間が長く、薬効が持続しやすい利点があります。例えば、感染症や角膜潰瘍の治療で長く薬を留めたいときや、眼瞼炎などで目の周りの皮膚に薬を留まらせたいときなどに用いられます。一方で軟膏は塗った直後に視界がぼやける欠点があり、ペットによっては嫌がることもあります。また、液体の目薬に比べてやや塗布が難しく感じるかもしれません。
動物病院で処方される目薬と市販目薬の違いとリスク

市販でもペット用の目薬が販売されていますが、動物病院で処方される目薬とは成分や目的が大きく異なります。自己判断で市販薬を使う前に、その違いとリスクを正しく理解しておきましょう。
動物病院の目薬と市販薬の違い
動物病院で処方される目薬は、獣医師が診察してペットの症状に合わせて選んだ医薬品です。細菌感染には抗生物質の入った目薬、炎症には抗炎症の目薬といったように、原因に応じて適切な有効成分・濃度の薬が処方されます。
一方、市販のペット用目薬や人用目薬は誰でも購入できますが、基本的には症状を一時的に和らげる対症療法的な成分が中心で、感染症など根本的な原因を治療するものではありません。
なお、動物病院では場合によって人間用の目薬が処方されることもあります。これは、獣医師が成分と安全性を確認したうえで、動物にも使用可能と判断したものだからです。決して素人判断で人間用の目薬を流用せず、使用してよいかは獣医師の指示にしたがってください。
市販の目薬を使用するリスク
市販の目薬を自己判断で使うことには大きなリスクがあります。まず、人間用目薬には動物には有害となりうる成分が含まれる場合があります。例えば、充血を取る目的で含まれるテトラヒドロゾリン塩酸塩などの血管収縮剤で、動物がこれを点眼すると目から体内に吸収され、心拍数や血圧の変化、神経症状など副作用を起こすおそれがあります。ごく少量であっても犬や猫には危険です。
動物病院で処方される目薬の正しい点眼方法

ここからは、処方された目薬を正しく点眼する方法をペットの種類ごとに解説します。基本的な手順は共通していますが、動物の種類によって保定のコツが少し異なります。
犬用目薬の点眼方法
飼い主が犬の頭をしっかり支え、白目部分に向けて目薬を1滴落としています。正面からではなく少し後方上方から点眼することで、犬が驚かずスムーズに薬を受け入れられます。そして、下記の手順で目薬を使いましょう。
- 姿勢を整える
- まぶたを開ける
- 目薬を1滴さす
- 薬をいきわたらせる
- 褒めてご褒美
猫用目薬の点眼方法
猫をタオルで包んで動かないよう優しく保定し、後ろから頭を支えて点眼しています。猫の正面からではなく後方から白目に向けて1滴垂らすことで、猫が恐怖を感じにくくなります。そして、下記の手順で目薬を使いましょう。
- 保定(身体を包む)
- 頭とまぶたの固定
- 目薬を1滴さす
- 褒めて解放
小動物用目薬の点眼方法
小動物(ウサギ、フェレット、モルモット、ハムスターなど)に点眼するときも、基本の手順は猫と似ています。ただし、小動物は身体が小さく骨も華奢なため、過度な力をかけない保定が重要です。
鳥類用目薬の点眼方法
鳥(インコやオウムなど)の場合も点眼は可能ですが、飛んで逃げたり咬んだりする子もいるため慎重に行います。鳥は気道がデリケートで強く握ると呼吸困難になるので、優しく保定することが重要です。鳥は目薬を入れられると嫌がって足で目を擦ったり、止まり木やケージに顔をこすり付けたりすることがあります。必要に応じてエリザベスカラー(保護用カラー)を装着して目を触れないようにすることも検討してください。
爬虫類用目薬の点眼方法
爬虫類(カメ、トカゲ、ヘビなど)の目薬は、対象の種類によって方法がかなり異なりますが、基本はほかの動物と同様に目を洗浄・治療するために点眼や眼軟膏を行います。爬虫類は種類によってまぶたの構造が違い、点眼のしやすさも異なります。
動物病院で処方される目薬をペットが嫌がるときの対処法

いざ目薬を点そうとしても、ペットがどうしても嫌がって暴れてしまうことがあります。ここではペット別に目薬を嫌がるときの対処法を紹介します。大切なのは決して無理強いしないことと、少しでもポジティブな体験にすることです。
犬が目薬を嫌がるとき
犬が点眼を嫌がる場合、まず無理に押さえつけたり怒ったりしないでください。力ずくで押さえると犬は余計に恐怖を感じ、次回以降ますます抵抗するようになります。点眼が終わった直後に大好きなおやつを与えたり、思い切り遊んであげたりしてください。また、犬がリラックスしているときを狙います。散歩や遊びで十分発散した後や、夜寝る前で眠そうなときなどは抵抗が少ないでしょう。このような工夫をして、目薬が楽しいものであると思ってもらうことが重要です。
猫が目薬を嫌がるとき
猫は犬以上に目薬嫌いが多いかもしれません。嫌がる猫には、基本的に無理強いせず工夫で乗り切る姿勢が大切です。猫はタオルで包むとおとなしくなる子が多く、それだけで目薬をさせる場合があります。また、猫は見慣れない目薬の容器を見るだけで警戒することもあります。その場合、点眼の前に容器を猫に嗅がせて馴染ませるのも有効です。
小動物が目薬を嫌がるとき
ウサギやフェレットなど小動物は臆病な子が多く、目薬を嫌がるときもパニックになりがちです。対処の基本は短時間で済ませることとストレスを最小限にすることです。小動物は視界に迫るものに驚きます。点眼時は可能なら顔にやわらかい布をかけて視界を遮り、点眼の瞬間だけ目の部分をめくってさっと薬を落とすと恐怖を和らげられます。また、犬猫と同じく、タオルで身体を包んで優しく固定すると安全に処置できます。ウサギなど大型の小動物では特に有効です。布で包むと本人も落ち着くことがあります。
鳥類が目薬を嫌がるとき
鳥の場合、嫌がると自ら飛んで逃げるため、まず逃げられない環境を整えることが重要です。鳥は暗いとおとなしくなる傾向があります。点眼前に部屋を暗めにし、そっと近づいて捕まえると興奮を抑えられます。捕まえたらすぐ明るくして手早く点眼しましょう。そして、タオルで身体を包んで翼を使えなくすることが何より効果的です。顔だけ出してしまえば、後は多少バタついても安全に点眼できます。
爬虫類が目薬を嫌がるとき
爬虫類は種類によってリアクションがさまざまですが、嫌がるときの対処法として共通するのは安全確保とストレス軽減です。無理に押さえつけると尻尾が切れたり噛まれたりするので、基本二人がかりで保定してください。そして、爬虫類は変温動物なので、身体が冷えているときは動きが鈍くなります。温浴後や日光浴直後は活発ですが、逆に涼しい朝方などはおとなしいこともあります。個体の行動パターンを観察し、扱いやすい時間帯を狙うのも手です。
目薬の点眼に失敗したときはどうする?

頑張って点眼しても、ペットが動いて目薬が目に入らずこぼれてしまうこともあります。そんな点眼の失敗に気付いたときの対処法を説明します。まず、落ち着くことが一番大事です。ペットが動いたり飼い主の手元が狂ったりして点眼に失敗するのは珍しくありません。失敗したからといって大声を出したりペットを叱ったりすると、ペットはさらに怯えて次の点眼が難しくなります。深呼吸して、自分もペットもリラックスしましょう。
そして、目に入らなかった薬液はすぐ優しく拭き取ります。清潔なティッシュやガーゼで、目の周囲にこぼれた液体を押さえるように取り除きましょう。薬液が皮膚に残ったままにすると、かぶれや黒ずみの原因になる場合がありますので、必ず拭き取ってください。その後、落ち着いてもう一度トライします。
薬がまったく入らなかった場合は、少し時間を置いてから再度点眼して構いません。ペットが暴れている場合は、まずしっかり落ち着かせてからにしましょう。焦ってすぐ追いかけ回すとさらに嫌がります。いったんその場を離れてペットが安心できる環境に戻し、数分~数十分後にあらためて挑戦すると成功しやすくなります。
半分入ったか判断が難しい場合は、獣医師の指示にもよりますが、基本的に追加で点眼しない方が安全です。角膜上には涙で覆われたごく少量のスペースしかなく、1滴の半量でもある程度効果は出ますし、それ以上入れてもあふれて無駄になります。強い薬の場合は重複投与になるおそれもあるため、「入ったかも」程度であれば次の定時点眼まで待つ方が安心です。どうしても心配ならかかりつけ医に相談しましょう。
点眼を完全に嫌がってできない場合は、前述の対処法をいろいろ試してもダメなら点眼治療自体を一時中止する選択もあります。無理に続けてペットと飼い主の信頼関係が壊れては本末転倒です。そうなったら一度獣医師に相談し、内服薬や注射で代用できないか、入院して治療できないか検討してもらいましょう。
動物病院で処方される目薬の使用期限と保管方法

最後に、目薬の使用期限(特に開封後)と適切な保管方法について説明します。これらを守らないと、せっかくの薬の効果が弱まったり安全性が損なわれたりする可能性があります。
目薬の使用期限
未開封の目薬は基本的に製造元が設定した使用期限まで使用できます。しかし、一度でも開封すると、容器内に外気や雑菌が入り込み、時間とともに薬効成分が劣化したり細菌が繁殖したりします。そのため、一般的には開封後は約1ヶ月を目安に使い切るよう指導されます。
もし開封後1ヶ月以上経過した点眼薬が残っていた場合、たとえ濁りがなくとも使用を中止して廃棄し、新しいものを用意してください。「もったいないから」と古い目薬を使い続けるのは危険です。特に治療用の抗生剤点眼などは劣化すると十分な効果が得られないだけでなく、容器内で増殖した細菌を目に入れてしまい二次感染を起こすおそれすらあります。
なお、なかには開封後数日~1週間など極めて短い使用期限が設定されている目薬もあります。例えば、防腐剤無添加のものや特殊な調剤点眼薬などが該当します。これらは処方時に獣医師や薬剤師から説明がありますので、指示にしたがって期限内に使い切るようにしてください。うっかり期限を過ぎてしまった場合は、自己判断で使わず新しいものを処方してもらいましょう。
目薬の保管方法
処方された目薬は、表示された方法に従って適切に保管する必要があります。温度や光の管理に気を付けないと、薬の効果が低下したり変質する可能性があります。
- 室温保管
多くの点眼薬は室温(1~30度程度)で保存となっています。直射日光が当たらず、高温にならない場所で保管しましょう。特に夏は室温が上がりすぎないよう注意が必要です。 - 冷所・冷蔵保管
一部の目薬は冷所保存(15度以下)や要冷蔵(2~8度)指定があります。その場合は指示どおり冷蔵庫内で保管してください。ただし、冷蔵庫でも冷凍庫付近は温度が0度近くになり凍結のおそれがあるため、極端に冷えすぎない場所に置きます。また、冷蔵庫から出した直後の冷たい点眼はしみて嫌がる原因になるので、使用前に少し室温に戻してから点眼するようにしましょう。 - 遮光
光に弱い成分を含む目薬は茶色や白色の遮光容器に入っていますが、さらに念を入れて処方時についてきた遮光袋に入れて保管すると安心です。使うとき以外は袋に入れ、日光や蛍光灯の光が直接当たらない場所にしまってください。 - 子どもやペットの手の届かない所に
目薬は子どもやペットが誤飲・誤用しない場所に保管します。犬や猫が容器を噛んで穴を開け、中身を飲んでしまうこともあります。高い棚の中やフタ付きの容器に入れるなどして、安全管理も忘れずに行いましょう。
以上の点に留意して目薬を保管すれば、処方された薬の効果をしっかり維持できます。
まとめ
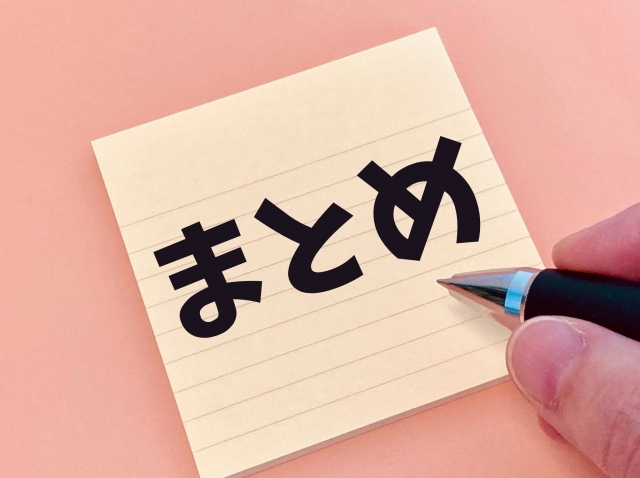
ペットの目のトラブルには、獣医師の診断に基づいた適切な目薬での治療が不可欠です。動物病院で処方される目薬は、市販のものとは成分も目的も異なり、ペットの症状に合わせて選ばれています。自己判断で市販の目薬を使うことは避け、必ず獣医師に相談しましょう。
正しい点眼方法で薬を目に行き渡らせることも治療効果に直結します。ペットが目薬を嫌がるときは、決して力ずくで抑えつけず、ご褒美を使ったり環境を工夫したりして少しでも嫌がらない方法を探すことが大切です。どうしても点眼できない場合は無理せず獣医師に相談し、別の対処法を検討してください。また、目薬は開封後の使用期限や保管方法を守り、清潔に扱うことで安全かつ効果的に使えます。
大切なペットの目を守るため、飼い主として正しい知識を持ち、適切なケアを行いましょう。少しでも異変を感じたら早めに動物病院を受診し、判断を仰ぐことが何よりの近道です。日頃から目を観察し、異常の早期発見・早期治療に努めてください。
参考文献


