近年は犬を飼いたいと考えたときに、保護犬を迎えることを選択する方が増えてきています。しかし、いざ保護犬に寄り添おうとしても、どのようにしつけたらよいのかわからない場合も多いのではないでしょうか。今回は保護犬の特徴をまとめたうえで、しつけ教室に通わせる重要性や、しつけを行う際の注意点について解説を加えました。飼い主が押さえておくべきポイントをわかりやすく掘り下げるので、ぜひ参考にしてください。
保護犬の特徴
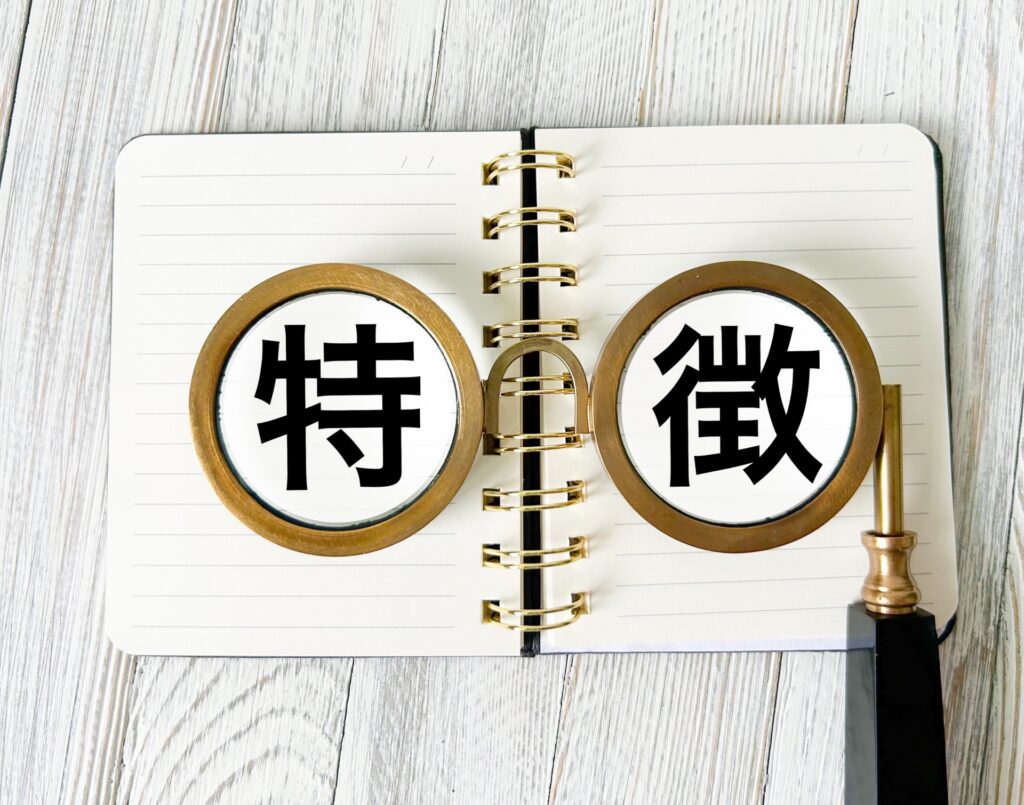
まずは、保護犬の特徴をまとめます。保護犬にはさまざまなバックグラウンドがあり、より繊細なケアが求められるケースも少なくないため、しっかりと理解を深めたうえでしつけを行うことが大切です。
- 保護犬とは、どのような犬のことを指しますか?
- 保護犬とは、動物愛護相談センターといった施設や保護団体に保護されている、飼い主がいない犬のことを指します。その背景はさまざまで、一般家庭において飼育放棄された犬や、ブリーダー崩壊、多頭飼育崩壊の家庭からレスキューされた犬などがいます。幼齢の犬だけでなく、高齢の犬も見られます。サイズも小型犬から大型犬までまちまちなので、保護犬を迎えたいと考えたら、飼い主のライフスタイルに合った犬を選ぶ必要があります。
- 保護犬は人に慣れにくいですか?
- 保護犬にはそれまでどのような体験をしてきたかによって、苦手なものがあるケースが見られます。人が苦手で慣れにくい場合もあれば、犬が苦手、散歩が苦手ということも珍しくありません。迎え入れる段階では何が苦手かよくわからず、ともに生活していくなかで判明していくこともあります。ペットショップなどから迎えた犬に比べると、新しい環境に馴染みづらい繊細さを感じることも少なくないでしょうが、その一方でとても大人しい、穏やかな性格の保護犬がたくさんいることも事実です。保護犬だから人に慣れにくいと単純に決めつけることはできないので、それぞれの個性に目を向けてあげましょう。
- 保護犬には、どのような行動や癖などの特性がみられやすいですか?
- 適切なしつけを受けてこなかった保護犬の場合、うまくトイレができなかったり、吠え癖があったりします。落ち着きなく動き回って、おすわりができないケースもあるでしょう。こうした問題行動は、警戒心や恐怖、不安感によって引き起こされているのかもしれません。改善するためには、保護犬の心を落ち着かせるような声かけや、根気強いしつけが必要です。とはいえ、前述のとおり、すべての保護犬に同じような特性があるとはいえません。新しい環境に馴染むための時間などにも、個体差があると念頭に置いてください。
保護犬をしつけ教室に通わせる重要性
ここでは、保護犬をしつけ教室に通わせることの重要性について説明します。保護犬に限らず、ペットのしつけは想像以上に難しいものです。飼い主が自宅でしつけを行うことに限界を感じたら、プロのサポートを受けることを検討してみるとよいでしょう。
- 保護犬のトレーニングはしつけ教室に任せるべきですか?
- 保護犬に必要なトレーニングは、その背景によって異なります。一般家庭で普通に暮らしていた犬や、良好な環境に身を置いていた犬であれば、成犬の場合でもあまりしつけに苦労しません。一方で人間との関わりが薄かった犬や、虐待を受けた経験がある犬、野犬の経歴がある犬などについては、トレーニングの難易度が上がります。ブリーダー崩壊からレスキューされた犬などの場合、人の存在は知っていても、外の環境に順応していないことも考えられるでしょう。幼齢の犬であれば、警戒心が強くてもしつけに順応できるケースが見られるものの、いずれにしろ時間をかけてトレーニングする必要があります。また、誤った方法でしつけを行う、逆効果になる可能性があるため、十分注意しなければなりません。自力でのしつけが難しいようであれば、早い段階で適切なしつけを受けさせるためにも、しつけ教室の利用を視野に入れてください。
- 保護犬を対象とした、しつけ教室はありますか?
- それぞれの事情に寄り添ってくれる、保護犬を対象とした出張トレーニングクラスなどがあります。また、譲渡会を実施した保護団体がしつけ教室を開いている場合もあるので、関連の情報をチェックしてみるとよいでしょう。
- 迎え入れたのが成犬であっても、しつけ教室の効果があるのか教えてください
- しつけ教室は成犬でも通うことが可能であり、トレーニングの効果が期待できます。ただし、成犬は習慣や癖が固まっているため、子犬に比べてしつけに時間がかかることも多いと覚えておきましょう。一方で、忙しい家庭などの場合、子犬よりもむしろ落ち着いた成犬の方が迎え入れやすかったというケースもあります。繰り返しになりますが、それぞれの犬だけでなく、迎え入れる家庭の事情もさまざまなので、保護犬と暮らすときは、多角的な視点を持つことが大切です。
保護犬をしつける際の注意点

終わりに、保護犬をしつけるにあたって飼い主が押さえておきたい注意点をまとめます。適切なしつけを行わないと、よかれと思っての行動が逆効果になる恐れもあるため、正しい知識を確認しましょう。
- 保護犬をしつけるときは、どのような点に気を付けるとよいですか?
- さまざまな背景を持つ保護犬の場合、新しい環境に馴染むことが難しいケースもあります。飼い主としては早くしつけの効果を実感したくなりますが、焦ることがないよう気を付けて、根気強くしつけを行いましょう。まずは、保護犬がどのようなことに不安を感じるのか理解して、リラックスできる環境を整えてあげてください。同時に、保護犬が心地よく感じられる距離感を見極めつつ、徐々にスキンシップを増やしていき、しつけがうまくいったときには優しく褒める言葉をかけましょう。
- いつも構ってあげるように意識すれば、早く人に慣れますか?
- 人間を怖がって逃げ回る犬や、部屋の隅から動こうとしない犬の場合、過干渉は逆効果になることもあります。いつも優しくしていれば早く人に慣れると考えてしまいがちですが、犬を思っての行動が恐怖心をあおる可能性もあるため、まずは不用意に触れたりせず、一緒の空間で穏やかに過ごせる状態を目指してください。保護犬が飼い主と適度な距離を保ちながらリラックスできる、パーソナルスペースを確保してあげることもポイントです。少しずつ信頼関係が築かれていけば、やがて保護犬の方から近付いてきてくれるでしょう。
- 保護犬をしつけ教室に通わせたいので、教室選びのポイントを教えてください
- 保護犬をしつけ教室に通わせる場合には、それぞれの背景を汲み取ったうえで、その犬に配慮したケアを実施してくれる施設を選びましょう。保護犬のしつけに理解があり、通常よりも安い料金設定でトレーニングを行ってくれる教室もあるようなので、関連の情報を調べてみてください。動物病院や自治体、保護団体などが
教室を開いているケースもあります。
編集部まとめ
保護犬のしつけは簡単ではないケースも少なくありませんが、適切なしつけを行って信頼関係が築かれたら、ともに歩む大切なパートナーになってくれます。保護犬だからといって性格を決め付けるようなことはせず、その犬の背景や個性と丁寧に向き合って、根気強くしつけを行ってください。うまくいかないようであれば、早めにしつけ教室に通わせるのがおすすめです。一人で悩まず、一度教室の見学やカウンセリングに行ってみるとよいでしょう。


