猫と暮らしていると、「なんだか普段より元気がない」と感じることがあるかもしれません。本記事では、元気のない猫にみられる特徴や、考えられる原因を解説します。疑われる具体的な病気や、すぐに病院に連れて行くべき症状、元気がない猫に対する対処法なども解説します。猫の飼い主さんや、これから猫をお迎えする予定のある方はぜひ最後までお読みください。
元気がない猫の特徴

この章では、元気がないと判断すべき猫の様子を解説します。判断材料として、食欲や活動量、寝ている時間のほか、くしゃみなどの症状も確認しましょう。
食べる量、飲む量が少ない
食事を用意しても食べに来ない、食べ残しが多い、食事の催促がないなどの場合は、元気がないと判断します。また、水を一口飲んだだけで離れる、水を飲む姿をまったくみないような日も元気がないといえるでしょう。
普段よりも活動量が減っている
普段は飼い主さんとの遊びの時間が大好きな猫が、飼い主さんが遊びに誘っても無関心でケージやベッドなどで丸まっている場合、元気がないといえます。キャットタワーなど高いところに寝そべって下りてこない場合や、反対に、階段やタワーなどの垂直運動を嫌がる場合も元気がないといえます。
寝ていることが多い
いつもは朝早くに飼い主さんを起こすはずなのに、飼い主さんが起きても起きない場合や、普段なら活発に遊んでいる時間に寝ている、飼い主さんが呼びかけても起きないなどは元気がない状態です。寝ていることが多いと感じた場合は、徐々に寝ている時間が増えているのか、寝ているときの様子に普段と違うところがないかもチェックしましょう。
くしゃみや鼻水、下痢や嘔吐などの症状がある
食欲や活動量が普段と変わらなくても、くしゃみや鼻水、下痢や嘔吐などの症状がみられる場合は、これから元気がなくなる可能性を示唆しています。鼻水などの症状がなくても、目やにの量や顔回りの毛がべとついていないかなどもチェックしましょう。
猫に元気がないときに考えられる原因

猫に元気がないときに考えられる原因はさまざまです。ストレスや機嫌など、動物病院の受診が必要ない要因もありますが、ケガや病気などの可能性もあります。
ストレスを感じている
猫にとっては、来客、部屋の模様替えなどの飼い主さんにとっては意外なことがストレスになります。ストレスの原因は猫によってさまざまですが、環境が変わった後で猫の元気がなくなった場合、ストレスが要因の可能性があります。
機嫌が悪い
猫の機嫌は、耳やヒゲ、尻尾の動きなどを観察するとわかりやすいといえます。耳が横に寝るイカ耳になっていたり、ヒゲが後ろ向きになっていたり、飼い主さんが呼んでもそっぽを向いて尻尾をさかんにパタパタしていたりする場合は機嫌が悪い状態です。
ケガをしている
爪をカーペットに引っかける、高所から落ちる、多頭飼いや外飼いの場合はほかの猫との喧嘩など、ケガの原因はさまざまです。動物病院を訪れる飼い主さんからは、しばしば「子どもと遊んでいた猫が突然元気をなくした」という話を聞きます。こうした場合、子どもが猫との遊びに夢中になり過ぎて、いつのまにか猫の足などを踏んでケガをさせていることもあります。
加齢により活動量が減っている
子猫のときはいつも走り回っている猫も、成長とともに行動は落ち着き、年齢とともに活動量は減る傾向があります。年齢とともに徐々に活動量が減る場合は加齢の影響による活動量の減少だと判断します。
病気を発症している
なんらかの病気を発症している場合、猫の元気がなくなります。疑われる代表的な病気については、次の章でお伝えします。
猫の元気がないときに疑われる病気

本章では、消化器、呼吸器、泌尿器、感染症に分けて、猫がかかりやすい病気を解説します。
消化器の病気
消化器の病気では、主に腹痛により元気が消失したり、嘔吐や下痢によって衰弱したりすることがあります。代表的な消化器の病気は下記です。
- 毛球症
- 胃炎・腸炎
- 腸閉塞
- 肝リピドーシス(脂肪肝)
- 膵炎
毛球症は、長毛種の猫でよくみられる病気で、毛づくろいの際に飲み込んだ自分の毛をうまく吐き出せず、胃や腸に残って蓄積されることで嘔吐などの消化器症状が出る病気です。
胃炎や腸炎は、なんらかの原因で胃や腸に炎症がおこる病気です。猫の場合、ウイルス、細菌、寄生虫などの感染によるものや、不適切な食事、猫にとって有毒な植物の誤飲などが原因となります。
腸閉塞は、物理的、または機能的に腸の通過障害が起こる病気です。物理的な閉塞の原因として、異物の誤飲のほかに、腫瘍や重度の便秘なども挙げられます。機能的な閉塞とは、腸が正常に動かなくなって通過障害がおこる状況です。神経麻痺などが原因として挙げられます。
肝リピドーシス(脂肪肝)は、特に肥満気味の猫に発症しやすい病気で、なんらかの原因で絶食状態になると、肝臓への脂肪沈着と肝臓からの脂肪動員のバランスが崩れ、肝臓内に中性脂肪が過剰に蓄積して発症します。
膵炎は、膵臓の消化酵素が自らの膵臓を消化し、膵臓に炎症を生じる病気です。猫の場合、原因が明確でないことも多いですが、猫伝染性腹膜炎(FIP)などの感染症、トキソプラズマなどの寄生虫などが原因となることがあります。
呼吸器の病気
呼吸器の病気では、呼吸困難などによって猫は元気を消失します。代表的な呼吸器の病気は下記です。
- 猫風邪
- 喘息(猫喘息)
- 肺炎
- 肺水腫
- 猫糸状虫症(猫フィラリア症)
猫風邪は、くしゃみ、鼻水などいわゆる風邪の症状を引き起こす病気の総称です。原因は主に猫ヘルペスウイルスや、猫カリシウイルスなどのウイルスです。
喘息(猫喘息)は、花粉やハウスダストなどのアレルギーを起こす物質に対する過剰なアレルギー反応が原因で、気管支が狭くなり、呼吸困難がおこる病気です。
肺炎は、ウイルス、細菌、真菌や異物の誤飲が原因となり、肺に炎症がおこる病気です。特に、猫白血病(FeLV)や猫免疫不全ウイルス感染症(FIV)などに感染している猫で、免疫が低下するとかかりやすく重症化しやすい傾向です。
肺水腫は、肺に多量の水が溜まり、水に溺れたときのような状況になる病気です。猫の肺水腫の原因の多くは、心臓病です。
猫糸状虫症(猫フィラリア症)は、犬で有名な犬糸状虫症(フィラリア症)の原因である糸状虫(フィラリア)という寄生虫の感染による病気で、咳や呼吸困難などを引き起こします。予防薬で予防ができるので、気になる場合はかかりつけの動物病院で相談しましょう。
泌尿器の病気
泌尿器の病気では、体に毒素が溜まったり、結石による痛みがでたりすることで元気を失います。代表的な泌尿器の病気は下記です。
- 慢性腎臓病(慢性腎不全)
- 尿結石
- 下部尿路疾患
慢性腎臓病(慢性腎不全)は、なんらかの原因で腎臓の機能が徐々に低下した状態で、猫に多くみられます。原因として、さまざまな腎臓の病気が挙げられますが、特に、ペルシャ猫では腎臓に小さな袋(嚢胞)がたくさんできる多発性嚢胞腎という病気による慢性腎不全が報告されています。
尿結石は、腎臓、尿管、膀胱、尿道のどの部分においても形成されます。猫では特にストルバイト結石と呼ばれるリン酸アンモニウムマグネシウムの結石が多く、食事や腎臓の病気、水分摂取不足などが原因で発症します。
下部尿路疾患は、膀胱や尿道など尿が排泄されるまでの通り道の疾患の総称で、猫に多いといえます。特に、猫では特発性膀胱炎と呼ばれる原因不明の膀胱炎が半数以上を占めます。
参照:『猫の特発性膀胱炎の尿中バイオマーカー候補を発見 | 東京大学大学院農学生命科学研究科・農学』』(岩手大学付属動物病)
感染症
感染症にかかった猫は、非特異的なさまざまな症状を呈します。元気消失、食欲不振などはいずれの感染症でも現れることのある症状です。
- 猫白血病(FeLV)
- 猫免疫不全ウイルス感染症(FIV)
- 猫伝染性腹膜炎(FIP)
猫白血病(FeLV)は、感染した猫の唾液や血液から感染します。感染初期には、リンパ節の腫れなどが出ますが、その後は無症状での持続感染期に入ります。持続感染による影響で、徐々にリンパ腫、再生不良性貧血、免疫介在性溶血性貧血、糸球体腎炎などさまざまな疾患が発症します。トキソプラズマ症などほかの感染症にかかりやすくなる傾向もあります。
猫免疫不全ウイルス感染症(FIV)は、猫エイズと呼ばれることもあります。猫白血病と同様、感染した猫の唾液や血液から感染し、一過性の発熱などの後は潜伏期となり無症状になります。しかし、免疫が低下するため、徐々にさまざまな疾患をひきおこし、最終的には猫後天性免疫不全症候群(猫エイズ)を発症します。
猫伝染性腹膜炎(FIP)は、感染した猫の糞や口腔、鼻腔分泌物などによって感染します。感染の影響で体内の臓器が障害を受け、元気消失や食欲不振など、さまざまな症状が出ます。最終的に腹膜炎が発症すると、予後が悪い病気です。
猫をすぐに病院に連れて行った方がよい症状
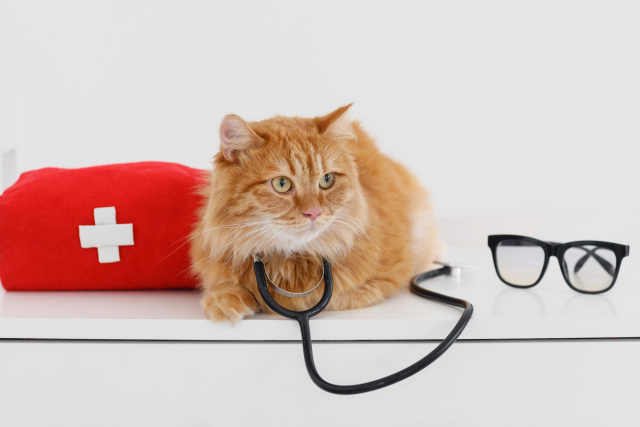
下記のような場合は、自宅での様子見は行わず、すぐに動物病院を受診しましょう。
ぐったりして動かない
横たわり、呼びかけに反応がない場合、様子をみていても回復する可能性は低いといえます。動かすと危険な可能性もあるため、まずは動物病院に電話して指示を仰ぎましょう。
嘔吐や下痢が続いている
猫は一過性のストレスなどでも嘔吐や下痢をしますが、何日も続く場合、頻度が増える場合は動物病院を受診しましょう。
発熱している
猫の体温は、肛門から体温計を差し込んで測ります。平熱は人間よりも高く、38度~39度前後ですが、これよりも高い場合は動物病院を受診しましょう。自宅で熱を測れない場合、猫の元気がなく、触って普段より熱く感じる場合は発熱しています。
意識がない
猫に触っても体のどこも動かさないときは、緊急で動物病院を受診する必要があります。動物病院に電話して、そのような状況になる直前の様子がわかれば伝え、指示を仰ぎましょう。
尿や便が出ない
猫がトイレで排尿や排便の姿勢を取っているのに出ない場合はすぐに動物病院を受診しましょう。普段よりも尿や便の回数や量が少ない場合も受診が必要です。
触ると痛がる部位がある
体を撫ででいて突然猫が怒ったり逃げたりする場合、その部分が痛い可能性があります。病院を受診して、どのような状況で猫が痛がったのかを説明しましょう。
普段よりも呼吸が荒い
元気な猫は、安静にしているときの呼吸は目で見てわからないほど静かです。体全体で呼吸をしていたり、お口を開けて呼吸をしていたりするときはすぐに動物病院を受診しましょう。
病気ではないのに猫に元気がないときの対処法

動物病院を受診して、何も病気がないと判断されても、猫の元気がないと心配になることもあるでしょう。そのような場合、下記を参考に対処してみてください。
食欲があり排泄が通常どおりであれば自宅で様子を見る
いつものように遊びや運動に積極的でなくても、普段と同じ量の食事を同じスピードで食べきり、尿や便の回数や量にも変化がない場合は病気の可能性は低いでしょう。心配のあまり普段より猫を構いすぎると余計にストレスになるため、そっと様子をみましょう。
ストレスを減らす環境づくりを心がける
暑さ、寒さ、湿度が合っていない、トイレやベッド、水飲み用の容器が汚いなどはストレスの原因になるため環境の改善をしましょう。環境が変化した直後は、慣れるまで無理に遊んだり食べさせたりせず、静かに見守るとよいでしょう。
判断に迷う場合は早めに受診する
猫の元気のなさが病気によるものなのか、ストレスなどが原因なのかを飼い主さん自身で判断するのは簡単ではありません。少しでも迷った場合は早めの受診をおすすめします。
まとめ

本記事では、猫の元気がない状態に着目し、どのような猫を元気がないと判断するのか、猫の元気がなくなる原因、対処法などをお伝えしました。猫は繊細なため、少しのストレスでも元気がなくなることがあります。一方で、機嫌が悪いだけだと思っていたら深刻な病気だという可能性もゼロではありません。「いつもより元気がないな」と感じたら早めに動物病院で相談してみましょう。
参考文献
- 『イヌネコ家庭動物の医学大百科 改訂版』(公益財団法人 動物臨床医学研究所)


