ペットが体調を崩したとき、「病院に連れて行きたいけれど移動が大変」と悩んだ経験はありませんか?近年、獣医師が自宅まで来て診療を行う訪問診療(往診)サービスが注目されています。動物病院への通院が難しい飼い主さんにとって、訪問診療はペットの負担を減らし、飼い主さんの生活にも寄り添った便利なサービスです。本記事では、動物病院による訪問診療を詳しく解説します。
動物病院の訪問診療とは

動物の訪問診療はいったいどのような診療なのでしょうか。本章ではその概要と利用できるペットの種類を解説します。
動物病院による訪問診療の概要
動物病院の訪問診療(往診)とは、獣医師がペットのいるご自宅や施設に出張して診察・治療を行うサービスです。高齢や病気で移動が難しいペット、あるいは動物病院での診察に強いストレスを感じてしまうペットに特におすすめの診療形態です。獣医師が必要な診療器具やお薬を持参し、ペットが普段過ごしている慣れた環境で診察を行います。そのため、病院までの移動によるストレスや負担を軽減できる点が大きなメリットです。さらに、往診では獣医師が直接ペットの生活環境を見ることができます。住環境や日頃の様子を把握したうえでアドバイスや治療方針を立てられるため、より適切な診断・治療につながります。
訪問診療の対象となるペットの種類
訪問診療は主に犬や猫を対象とすることが一般的です。多くの往診専門動物病院では、犬と猫であればほぼ対応可能で、犬種や猫種を問わず診療してもらえます。また、クリニックによってはウサギ、フェレット、ハムスター、小鳥といった小動物にも応相談で対応している場合があります。事前に問い合わせれば、これら小動物の診察に対応可能か教えてもらえるでしょう。
動物病院の訪問診療が役立つ状況

訪問診療はあらゆるケースで利用できますが、特に以下のような状況で大きなメリットを発揮します。それぞれ具体的に見てみましょう。
大型犬や多頭飼育で通院が難しい
大型犬を飼っている場合、その体重やサイズゆえに動物病院まで連れて行くこと自体が困難です。筋力の低下した高齢の大型犬ではなおさらで、車に乗せるのも一苦労というケースもあります。30kgを超える犬では自力で立てなくなると2人がかりでも抱えるのが難しいため、こうしたケースで往診がとても助けになります。
また、多頭飼育の場合、全員を一度に病院へ連れて行くのは大変です。複数のキャリーや移動用ケージを準備し、順番に診察を受ける負担は飼い主さんにもペットたちにも大きいでしょう。往診であれば自宅でまとめて診察が受けられるので、多頭飼育のご家庭にも便利な選択肢となります。
ペットが病院を嫌がる
ペット自身が車での移動や病院での診察を極端に怖がったりストレスを感じたりする場合、往診は大きな助けになります。ペットにとって安心できる自宅で診療を受けられる往診は、病院嫌いの子にとって大きなメリットがあります。ペットのストレス軽減は飼い主さんの精神的負担の軽減にもつながります。
生活環境のアドバイスが必要
往診では獣医師が実際にペットの生活環境を見たうえで診察できるため、生活面のアドバイスを直接受けられる利点があります。また、トイレやケージの配置、床の滑り止め対策など、住環境の工夫についても自宅で直接アドバイスを受けられます。
往診ではペットが普段過ごす環境をそのまま獣医師が見られるため、「どこに段差があるか」「滑りやすいフローリングか」などを確認し、ペットが快適に暮らせる環境整備のアドバイスがしやすいです。このような細やかな指導も、往診を利用する大きなメリットといえるでしょう。
自宅での緩和ケアを希望している
末期の病気を抱えたペットについては、「できるだけ病院ではなく自宅で家族と一緒に穏やかに最期を迎えさせてあげたい」と願う飼い主さんも多いでしょう。在宅での緩和ケアを希望する場合、往診サービスは大変心強い存在です。寝たきり状態の子や末期がんの子では、病院への通院自体が体力を消耗させてしまうおそれがあります。往診であれば移動の負担がないため、ペットは残された時間をできるだけ苦痛少なく過ごすことができます。
子育てや介護などで飼い主さんの外出が難しい
飼い主さん側の事情で動物病院に行けないケースでも、往診が役立ちます。例えば、小さなお子さんがいて長時間家を空けられない、高齢のご家族を介護中でなかなか外出できない、といった状況です。このような場合でも往診なら自宅に来てもらえるので安心です。
また、飼い主さん自身がご高齢だったり、ケガや病気で移動が困難だったりする場合にも往診は有効です。このように、飼い主さんの事情で通院が難しいときにも、往診を活用すればペットの医療ケアを継続できます。
動物病院の訪問診療での診療内容と処置

訪問診療では、動物病院に行かなくても自宅でさまざまな診療や処置を受けることが可能です。本章では往診で対応できる主な診療内容を項目ごとに紹介します。
病気や怪我の診察と検査、治療
ペットが病気にかかったり怪我をしたりした場合でも、往診で診察・検査・治療を受けられます。獣医師は聴診器や簡易検査キットなど必要な器具を携えて訪問し、視診(見た目のチェック)や触診、聴診といった一般的な身体検査を行います。症状に応じて、血液検査・尿検査・便検査などの基本的な検査も往診時に実施できます。診察の結果、怪我が見つかった場合は傷の手当てをしてもらえますし、必要に応じて点滴や注射による治療もその場で受けられます。往診の獣医師は鎮痛剤や抗生物質など基本的な医薬品を持参していますので、診断に基づきお薬の処方もしてもらえます。
健康診断
特に具合は悪くないけれど健康チェックをしてほしいという場合も、往診で対応可能です。また、自宅でリラックスした状態のペットなら、本来の状態に近い形で健康評価ができるという利点もあります。定期的な健康診断はペットの病気の早期発見・予防に重要ですが、忙しくて病院に行けないときなど往診を利用すれば自宅で完結するので便利です。
点滴や注射などの処置
往診では点滴や各種注射などの処置も受けられます。注射についても、ワクチン注射はもちろん、鎮痛剤や制吐剤、抗生剤などの治療用注射がその場で可能です。点滴や注射などは治療法が限られることはありますが、基本的な点滴や注射などはその場で行うことが可能です。
ワクチン接種
各種ワクチンも往診で実施することができます。犬であれば混合ワクチンや狂犬病予防接種、猫であれば混合ワクチンなどを、自宅で受けることができます。複数のペットを飼っている場合、往診で全員まとめてワクチン接種してもらえると通院の手間が省けて便利です。特に子犬・子猫の初年度は接種回数が多いため、往診を上手に活用するとよいでしょう。
爪切りや耳掃除などの処置
病気ではないけれどケアをお願いしたい場合にも、往診を利用できます。爪切りや耳掃除、肛門腺しぼりといった日常のお手入れも、往診で対応可能なことをご存知でしょうか。自宅で飼い主さんがやろうとすると嫌がって難しい犬猫の爪切りや耳掃除も、獣医師や愛玩動物看護師に来てもらえば安全に行うことができます。
緩和ケア
緩和ケアも、往診で提供される重要なサービスの一つです。末期の病気や慢性疾患で痛み・苦痛を抱えるペットに対し、疼痛管理や介護ケアを自宅で受けられます。例えば、がんの痛みに対する鎮痛剤の調整や、食欲が落ちた子への補液、床ずれ防止の体位変換のアドバイスなど、ペットが少しでも楽に過ごせるようサポートしてもらえます。往診ではペットと飼い主さんがリラックスできる雰囲気のなかで診療が行われるため、獣医師と相談しながらケアを進められるのも利点です。自宅なので飼い主さんも遠慮なく不安や悩みを話しやすく、ペットにとって適切なケアについて一緒に考えてもらえます。
動物病院の訪問診療では処置が難しい検査や処置

便利な訪問診療ですが、自宅では対応が難しく動物病院での診療が必要になることもあります。本章では往診では対応できない主な検査や処置を解説します。
レントゲン検査
レントゲン検査(X線検査)は往診では対応できない代表例です。レントゲン撮影には大型の撮影装置と放射線防護設備が必要であり、自宅にそれらを持ち込むのは現実的ではありません。したがって、骨折の疑いがある場合や胸部・腹部の詳細な評価が必要な場合には、動物病院でレントゲン検査を受ける必要があります
外科手術
外科手術も往診では基本的に行えません。開腹手術や骨折の整復手術などは、無菌的な手術室と全身麻酔設備、複数のスタッフによるモニタリング体制が不可欠です。自宅はどうしても清潔度や設備面で限界があり、万全な手術環境を整えることが難しいのです。したがって、腫瘍の摘出手術や避妊・去勢手術、緊急の開胸処置などは動物病院で行う必要があります。
抗がん剤治療
抗がん剤治療(化学療法)についても、往診で対応するのは難しい場合が多いです。抗がん剤の点滴投与などは、投与中の厳重なモニタリングや副作用管理が必要であり、動物病院で行うのが安全です。特に、強い抗がん剤は投与後の急変リスクもあるため、入院施設のある病院で経過を見ながら処置されることが一般的です。
訪問診療の前に準備しておくこと
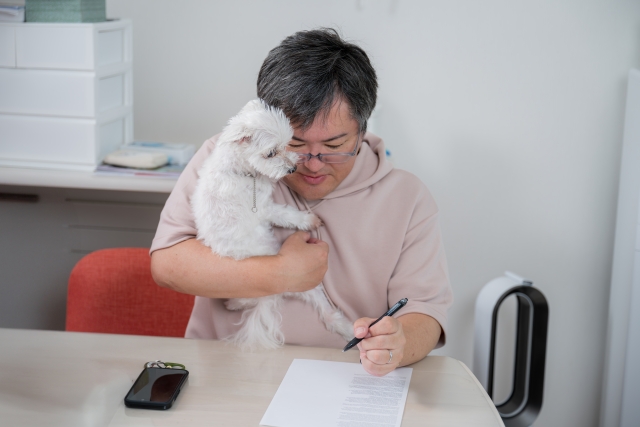
訪問診療を受ける際は、病院へ通院するときとはまた違った事前準備や配慮が必要です。スムーズに往診診療を受けるために、以下の点をしっかり準備しておきましょう。
ペットが落ち着ける環境を整える
まず、獣医師が来る当日はペットが落ち着いて診察を受けられるスペースを用意しましょう。普段くつろいでいる部屋やお気に入りのマットの上など、ペットにとって安心できる場所が理想的です。診察台の代わりになるような安定したテーブルや床のスペースがあると診察しやすくなります。興奮しやすい子の場合はリードを付けたりケージに一時的に入れたりしておくと、安全に診察を始められるでしょう。
ペットの状態をメモする
往診に来てもらう前に、ペットの健康状態や気になる症状を整理してメモしておくと診察がスムーズです。具体的には、以下のような情報を事前に書き出しておくとよいでしょう。
- 基本情報:ペットの年齢、品種(犬種・猫種)、性別、体重
- 現在の症状や経過:いつからどのような症状が出ているか、食欲や元気はどうか、排泄の様子は普段どおりか
- 過去の病歴:これまでにかかった病気やケガ、受けた手術
- 投薬状況:現在飲んでいる薬やサプリメントがあれば種類と量
- アレルギーの有無
- ワクチン接種歴
これらの情報を整理して獣医師に伝えることで、より的確な診断・治療につなげることができます。
獣医師に伝えたい質問や相談内容をまとめる
往診の診察時間は時間にゆとりがありますが、それでも当日聞きたいことを事前に整理しておくことが大切です。いざ獣医師を目の前にすると緊張して聞き忘れてしまった、というのはよくある話です。そこで、事前に質問リストを作っておくとよいでしょう。ちょっとした疑問でもかまいません。メモに書いておけば、診察時に一つ一つ確認できます。
動物病院の訪問診療にかかる費用の目安

気になる費用面ですが、往診では診察料(初診料・再診料)と往診料、そして行った診療や検査ごとの処置料が基本となります。本では一般的な費用の目安を項目別に紹介します。
初診料、再診料
往診でも通常の動物病院と同様に初診料・再診料がかかります。初めて診てもらう場合の初診料は、1,000~2,000円程度、再診の場合も1,000円前後が相場です。これはクリニックによって多少異なりますが、通院時の診察料と大きく変わらないか、やや高い程度です。ただし、往診の場合は診察料とは別に後述の往診料(出張費)が追加される点に注意してください。
往診料
往診料は、獣医師が自宅まで来るための費用です。多くの動物病院では距離に応じて段階的に設定されています。例えば、病院から半径2km以内は1,000円、5km以内は2,000円、10km以内は4,000円といった具合です。遠方になるほど交通費・時間がかかるため料金も高くなります。夜間や休日の往診ではさらに割増料金(夜間加算)が発生する場合もあります。
診療や検査にかかる費用
往診時の診療・検査費用は、内容自体は基本的に病院での料金と同様ですが、いくつか代表的な項目の目安を挙げます。
- 血液検査:10,000円前後(項目数によって増減)
- 超音波検査:3,000~8,000円(部位や時間による)
- ワクチン接種:1回あたり3,000~8,000円(ワクチンの種類による)
- 点滴・注射:5,000~15,000円(使用する薬剤や量による)
- 爪切り・耳掃除:500~2,000円程度(病院の設定による)
これらは一例ですが、検査や処置の内容次第で費用が加算されていきます。重症例で血液検査やレントゲン紹介、複数の処置を行った場合などは、合計額が増えます。特に夜間の緊急往診では通常より費用が高くなりがちです。
費用について不安がある場合は、依頼前に大まかな見積もりを問い合わせることをおすすめします。往診専門の動物病院では、電話予約の段階で症状を聞いたうえで概算費用を教えてくれるところもあります。
まとめ
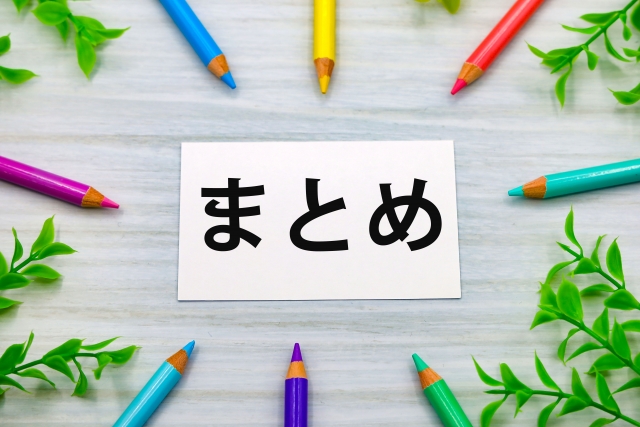
訪問診療(往診)は、獣医師がペットの自宅まで訪問し診察や治療を行ってくれるサービスです。通院が難しいペットや飼い主さんにとって、移動や待ち時間の負担を軽減できる便利な選択肢となっています。ペットは慣れた環境でリラックスした状態で診療を受けられるため、ストレスが少なく適切なケアにつながります。一方で、往診には設備面の制約や費用面で追加負担があることも事前に理解しておく必要があります。レントゲンや外科手術など高度な処置は往診では対応できず、必要に応じて病院での診療に切り替えるケースもあります。費用についても、往診料が加算される点を踏まえ、事前確認を怠らないようにしましょう。信頼できる往診可能な動物病院を見つけて、いざというときに備えておくと安心です。ペットの健康管理に訪問診療を上手に活用し、飼い主さんとペット双方にとって快適な療養環境を整えていきましょう。
参考文献


