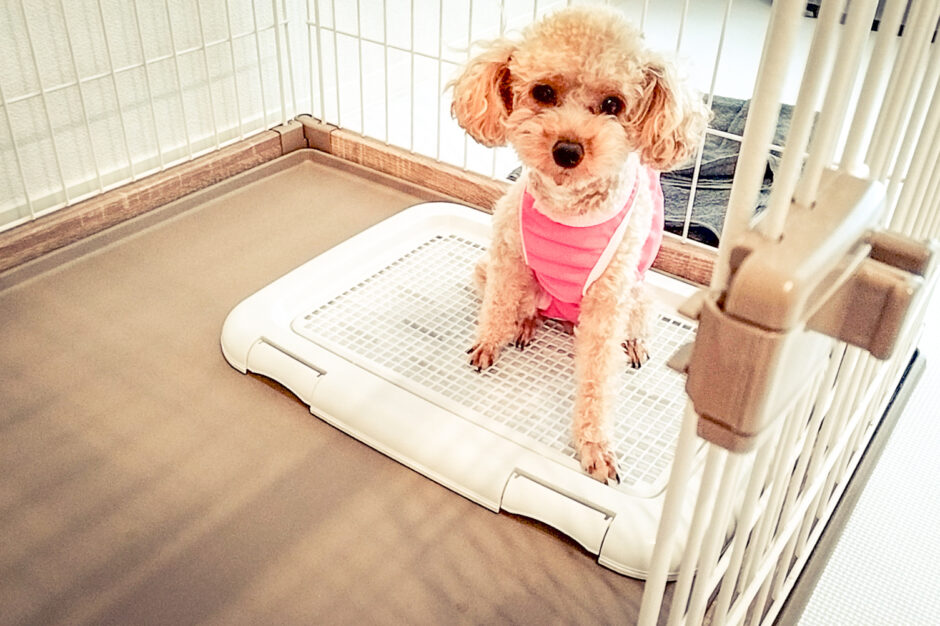動物病院を受診するときに、便を持参するよう指示を受けることがあります。便はペットの健康状態を知る重要な手がかりとなるためですが、実際に便を用意するとなると、どのような手順を踏むべきかわからず、困惑してしまう方もいるのではないでしょうか。今回は動物病院への便の持って行き方をテーマに、採取方法や持参する際のポイントをまとめました。便検査の目的についても解説を加えるので、その必要性を理解したうえで正しく対応できるように準備を整えましょう。
動物病院への便の持って行き方

まずは、動物病院へ便を持参する際の基本的な流れをチェックしましょう。どうしても気になってしまう移動時のにおいなどについても対策を立てておくと、いざというときに慌てることがありません。
- 便を動物病院に持って行く際の基本的な流れを教えてください
- 自宅でペットが排便したら、少量を採取しましょう。採取できたら、水分を吸収しないラップやビニールなどに包んで動物病院へ向かいます。トイレットペーパーやティッシュを使用すると検査の邪魔になるため、注意が必要です。慣れない作業に戸惑ってしまいそうですが、採取後はできるだけ早く動物病院へ持参してください。時間が経つと原虫などの検出が難しくなります。
- 漏れやにおい対策に適した容器はありますか?
- 漏れやにおいの発生を防ぐためには、密封容器を活用するとよいでしょう。便が入った袋を二重にするのも有効です。
- 採取後は何時間以内に持って行くべきですか?
- ジアルジアやトリコモナスといった運動性の原虫は時間が経つと動かなくなってしまい、検出が難しくなります。そのため、採取後2時間から3時間以内に冷やしていない新鮮便を持参するのが理想です。しかし、どうしても採取後受診に時間がかかるようなら冷蔵保存してください。冷蔵保存をするとジアルジアやトリコモナス、一部の線虫は死滅します。新鮮便でない場合、原虫などの疑いがあれば動物病院で採便棒で新鮮便を採取してもらいましょう。
- 夏場や長距離移動のときに気を付けることがあれば教えてください
- 夏場は便のにおいがより強くなるため、受診するまで涼しい場所に置くことを心がけてください。長距離移動の際には、便が入った袋を二重にするなどの対策を立てるとよいでしょう。
便の採取方法と必要な量
このパートでは、実際に便を持参するときの採取方法などをより具体的に確認します。ポイントを押さえて便を採取すると、正確な診断の助けになるため、飼い主として理解を深めておきましょう。
- 正しい便の採取方法を教えてください
- 便を採取する際に血や粘膜が付着している部分が見受けられたら、重点的に採取するよう意識してください。さまざまな病気や異常を発見するための重要な手がかりとなります。トイレ砂は多少付いてしまっても問題ありませんが、便が乾燥すると検査結果に支障が出る可能性もあることから、できれば取り除く方が望ましいです。どうしても自宅での採取が難しい場合は、動物病院で採取してもらうことも可能なので、一度獣医師に相談してみるとよいでしょう。
- 下痢で便がやわらかいときはどうすればよいですか?
- 下痢便や水下痢はすべてを採取するのが難しいことがあるため、できる範囲で拾うようにしてください。ペットシーツに排便した場合は、シーツごとビニールに入れて持参するというのも一案です。下痢や軟便、血便などの普段とは明らかに異なる状態が見られたら、早急な検査が必要となります。便が真っ黒でドロドロしているときなども特に注意して、速やかに獣医師の判断を仰ぐよう意識しましょう。
- 検便に必要な便の量はどのくらいですか?
- 便は親指の先程度の量を目安に採取しましょう。便を丸ごと持って行くこともマナー違反ではありませんが、少量でも便検査は可能です。
動物病院で行われる便検査の内容と目的

終わりに、動物病院で行われる便検査の詳細と、検査の目的についてまとめます。便検査の意義を理解することで、飼い主の取るべき行動を知り、大切なペットの健康管理に役立てていきましょう。
- 動物病院の便検査では何がわかりますか?
- 動物病院で実施される便検査は、ペットの病気を早期発見するための重要な手段です。便の色や形、においなどをチェックすることで、異常がないか詳しく確認していきます。顕微鏡を用いた検査では、採取した便のなかに存在する寄生虫や細菌、炎症細胞、出血の有無などを調べます。寄生虫感染に関しては、少量の便を飽和食塩水で溶かして浮遊した成分を観察する浮遊法などにより、寄生虫卵を確認し、犬回虫や鉤虫、コクシジウム、条虫類などがいないか判断します。細菌検査では、腸炎の原因となるクロストリジウムやカンピロバクターの異常増殖について調査します。抗原検査やPCR(ポリメラーゼ連鎖反応)検査では、ジアルジアやパルボウイルス、腸コロナウイルスといった特定の病原体の感染を精密に確認することが可能です。染色試験では、消化不良の程度や脂肪、炭水化物の消化異常などを判定します。なお、便に異物が混入している場合は誤食の可能性があるため、便に混ざった異物の確認が重要なポイントになります。
- 便検査は定期的に受けるべきですか?
- 便検査はペットの健康状態に異常が見られたときだけでなく、健康管理の一環として定期的に受けることが推奨されます。便検査によって異常が発見された場合、早期治療が可能となり、ペットの健康を守ることができるため、普段から愛犬や愛猫の便をよくチェックして、何らかの変化があればすぐ気付けるよう心がけておくことも大切です。また、排便の回数や量、色や形などを観察してメモを取る習慣を付けておくと、万が一のときに役立ちます。なお、気になる変化があって便検査を受ける場合には、症状が出た時期や生活環境の変化などを記録しておくと、診断の手がかりになるでしょう。嘔吐物があれば、便と併せて持参することも有効です。便以外の症状が出ているときの動画や過去の医療記録なども準備しておくことをおすすめします。便検査はさまざまな病気の早期発見につながる重要な手段ですが、飼い主がその他の準備も整えておくと、さらに的確な診断や治療を受けることが可能になります。動物病院を受診する際には、必要な情報を正確に伝えることも意識しましょう。
- 便検査で見つかりやすい病気を教えてください
- 便検査を受けることで、消化器系の健康状態や潜在的な異常を把握しやすくなります。顕微鏡や特殊な検査機器を使用するため、病原体の有無といった肉眼ではわからない要素についても詳しく調べられる点は、便検査の大きなメリットといえるでしょう。腸内細菌のバランスや便中の赤血球、脂肪分、消化不良の痕跡や異物、出血などについても確認できるので、特に便の異常が続く状態であれば、早めの検査実施が望まれます。また、新たにペットを迎える場合にも、寄生虫や母動物からの感染リスクを確認するために、便検査を受けてください。いずれにしても、ペットの便について気にかかる点があれば、まずは獣医師に相談してみるとよいでしょう。
編集部まとめ
動物病院の便検査というと、手間に感じる場合もあるかもしれませんが、検査を受けることにより、ペットの健康状態を把握しやすくなります。検査を実施するとき以外でも、ペットの便はその健康状態をチェックするための重要なバロメーターになるため、普段から異常が見られないか、よく観察しておきましょう。便の状態について不安に思うことがあれば、できるだけ早く獣医師の判断を仰ぐことも大切です。