猫にワクチン接種は必要なのか、室内飼いでも必要なのか、気になる方は多いのではないでしょうか。
本記事では、動物病院での猫のワクチン接種は必要ないのかについて、以下の点を中心に解説します。
- 猫にワクチンは必要なのか
- 動物病院で受けられるワクチンの効果や回数、種類、費用
- 動物病院で猫のワクチンを受ける前後の注意点
動物病院での猫のワクチン接種は必要ないのかについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
猫にワクチン接種は必要ない?

「室内飼いの猫にワクチンは必要なの?」と疑問に思う飼い主の方も多いのではないでしょうか。
結論は、室内飼いであってもワクチン接種は感染症予防のために必要です。
猫のワクチン接種は感染症の予防を目的としており、たとえ外に出る機会が少なくても、リスクをゼロにはできません。
例えば、飼い主の方が外出時にウイルスを衣服や靴に付着させて持ち帰ったり、通院時にほかの動物から病原体がうつったりする可能性が挙げられます。
また、万が一猫が脱走したり、ベランダに出たりした際も感染リスクは高まります。
ウイルスへの感染は、特に子猫や免疫力の低い猫にとって、猫汎白血球減少症など命に関わる可能性があります。
しかし、こうした感染症の多くはワクチン接種によって予防できるとされています。
愛猫の健康を守るためにも、動物病院で定期的なワクチン接種を欠かさず行い、万全な感染症対策を心がけましょう。
猫がワクチン接種を受けない場合のデメリット

猫にワクチン接種を行わない場合、いくつかのデメリットがあります。
まず、感染症にかかりやすくなることです。
猫ウイルス性鼻気管炎や猫カリシウイルス感染症など、風邪のような症状を引き起こす病気から、命に関わる猫汎白血球減少症(猫パルボウイルス)まで、さまざまな感染症の脅威があります。
免疫力の低い子猫や高齢猫が感染すると、重症化する可能性が高くなります。
また、治療費の負担も挙げられます。
日本では動物の医療費に公的保険が適用されないため、重症化すればする程、高額な費用がかかり、経済的な負担となり得ます。
さらに、ペットホテルや動物病院での預かりを断られる可能性もあります。これらの施設ではワクチン接種証明書の提示が必要なことがあるため、未接種だと利用できないことがあります。
加えて、災害時などでほかの動物と一緒に避難する際も、ワクチン未接種の猫は感染リスクが高まり、危険です。
こうしたリスクを回避するためにも、ワクチン接種は大切です。
動物病院で受けられる猫のワクチン接種について

ここでは、猫のワクチン接種によって期待できる効果や、接種する時期、回数について解説します。
効果
- 猫ウイルス性鼻気管炎(FVR)
通称「猫風邪」と呼ばれるこの病気は、猫ヘルペスウイルスが原因です。くしゃみ、鼻水、結膜炎など風邪に似た症状を引き起こし、一度感染するとウイルスが体内に潜伏して再発することもあります。
ワクチン接種によって感染前の予防につながり、発症しても症状の重症化を防ぐことが可能とされています。
- 猫カリシウイルス感染症(FCV)
猫風邪と似た症状のほか、口内炎や潰瘍、重症の場合は肺炎を引き起こすウイルス性の感染症です。発症率と重症化のリスクを下げ、感染拡大の抑制にもつながります。
- 猫汎白血球減少症(猫パルボウイルス感染症)
警戒すべき感染症のひとつで、発症すると激しい嘔吐や下痢、白血球の減少により急激に状態が悪化します。子猫では致死率が高く、迅速な対応が求められます。
屋内飼育の猫でも、ヒトの靴や手からウイルスが運ばれる可能性があるため、ワクチン接種が推奨されます。
- 猫白血病ウイルス感染症(FeLV)
貧血や免疫力の低下、腫瘍などを引き起こし、数年以内に命を落とすこともある深刻な病気です。特に子猫や高齢猫は発症しやすいため注意が必要です。
ワクチンは感染リスクのある猫(外猫との接触がある、同居猫が感染しているなど)にとって、発症を未然に防ぐ手段として有効とされています。
- 猫クラミジア感染症
目に炎症を起こす細菌感染症で、重症化すると肺炎などの合併症を引き起こす可能性があります。主に接触感染で広がるとされています。
ワクチンは目の炎症や肺炎の予防に役立ち、多頭飼育や保護猫を迎える場合にも重要な予防策となります。
- 猫免疫不全ウイルス感染症(FIV・猫エイズ)
長い潜伏期間を経て、免疫力が低下し、さまざまな感染症にかかりやすくなる病気です。発症すると、体調の管理が重要になります。
ワクチンで一定の感染抑制効果が期待でき、感染リスクのある環境下では接種が勧められます。
猫のワクチンには、すべての猫に必要な「コアワクチン」(FVR・FCV・猫パルボ)と、猫の生活環境に応じて接種を検討する「ノンコアワクチン」(FeLV・クラミジア・FIV)があります。
室内飼育であっても、飼い主の衣類や手を通じて感染するケースもあるため、動物病院で獣医師と相談しながら、ワクチンプランを立てましょう。
時期や推奨回数
子猫の場合、生まれてしばらくは母猫の初乳によって得られる免疫(移行抗体)に守られていますが、その効果は生後8週齢頃には消失します。そのため、最初のワクチン接種は生後8週頃、2回目は12週頃に実施が推奨されています。
そして、生後12ヶ月時点で3回目(ブースター)の接種を行い、以降は年に1回の追加接種が推奨されます。
一方、成猫の場合は健康状態に問題がなければいつでも接種が可能とされていてますが、初回接種の1ヶ月後に2回目を行うのがよいでしょう。
近年では、猫の生活環境やワクチンの種類によっては3年に1回の接種でよいとする獣医師も増えており、抗体価検査で確認するケースもあります。
猫の年齢や体調に合わせ、獣医師と相談することが大切です。
動物病院で受けられる猫のワクチンの種類と費用目安

猫のワクチンはさまざまな種類があり、飼育環境と周囲の環境によって推奨されるものが異なります。以下で詳しく解説します。
3種混合ワクチン
3種混合ワクチンは、猫にとって命に関わる重大な感染症3種、猫ウイルス性鼻気管炎(ヘルペス)、猫カリシウイルス感染症、猫汎白血球減少症(パルボウイルス)を予防できる基本的なワクチンです。
3種混合ワクチンは、すべての猫に接種が推奨されている「コアワクチン」とされています。室内飼いの猫でも、ウイルスが人を介して持ち込まれる可能性があるため、予防は不可欠です。
費用は1回あたり約3,000〜7,000円が目安です。
4種混合ワクチン
4種混合ワクチンは、猫の命を守るために重要な感染症4種を予防するワクチンです。基本の3種混合ワクチン(ヘルペスウイルス・カリシウイルス・パルボウイルス)に加え、猫白血病ウイルス感染症(FeLV)の予防が可能とされています。
猫白血病は免疫力を著しく低下させ、さまざまな病気を引き起こす恐れがあります。
外に出る猫や、多頭飼いの家庭では感染リスクがあるため、4種混合ワクチンが推奨されています。
費用は5,000円〜8,000円前後が目安です。
5種混合ワクチン
5種混合ワクチンは、3種混合ワクチンに加え、猫白血病ウイルス感染症と猫クラミジア感染症の予防につながる「ノンコアワクチン」を加えたものです。
ノンコアワクチンは、生活環境や感染リスクに応じて接種を検討するものです。
外出の多い猫や多頭飼いの家庭では感染リスクがあるため、5種混合ワクチンの接種が推奨されます。
クラミジアにかかると目の炎症やくしゃみを引き起こし、猫白血病は免疫低下など深刻な症状を伴います。
費用目安は、5,000〜8,000円程度です。
7種混合ワクチン
7種混合ワクチンは、5種混合ワクチンに加え、カリシウイルスの3種の型に対応したワクチンが加えられたものです。
3種・4種混合ワクチンでは1つのタイプのカリシウイルスの予防に役立ちますが、7種混合ワクチンでは3タイプのカリシウイルスの予防につながります。
猫カリシウイルス感染症は、通称「猫風邪」と呼ばれる上部気道感染症です。
猫カリシウイルスは型が多く、通常のワクチンでは防ぎきれないケースもあるため、より広い型に対応した7種混合ワクチンが推奨されます。外出の多い猫や、多頭飼いの環境での感染リスクを軽減するのにおすすめです。
費用は7,500円〜8,000円程度が目安です。
どのワクチンが必要なのかは、猫の健康状態や生活環境に応じて異なります。獣医師と相談しながら接種を検討しましょう。
動物病院で猫のワクチンを受ける前の注意点

猫にワクチンを接種する際は、体調が万全であることが重要なポイントです。免疫力が落ちている状態で接種すると、ワクチンによって体に負担がかかり、逆に感染症を引き起こしてしまう恐れがあります。
例えば、食欲がない、元気がない、下痢や嘔吐をしているといった症状が見られる場合は、無理に接種せず日を改めて、体調回復を優先しましょう。
また、すでに病気の治療中である場合や、持病がある猫の場合は、必ず事前に動物病院に相談し、接種の可否や時期を判断してもらうことが大切です。
さらに、接種後に副反応が出る可能性もあるため、ワクチンは午前中に受けるのが理想的です。
また、万が一体調不良が起きた場合も、動物病院の診療時間内であれば迅速に対応してもらえるでしょう。
安全性を重視してワクチン接種を行うためには、猫の健康状態をしっかり確認し、無理のないスケジュールでの接種が基本です。
動物病院で猫のワクチンを受けた後の注意点
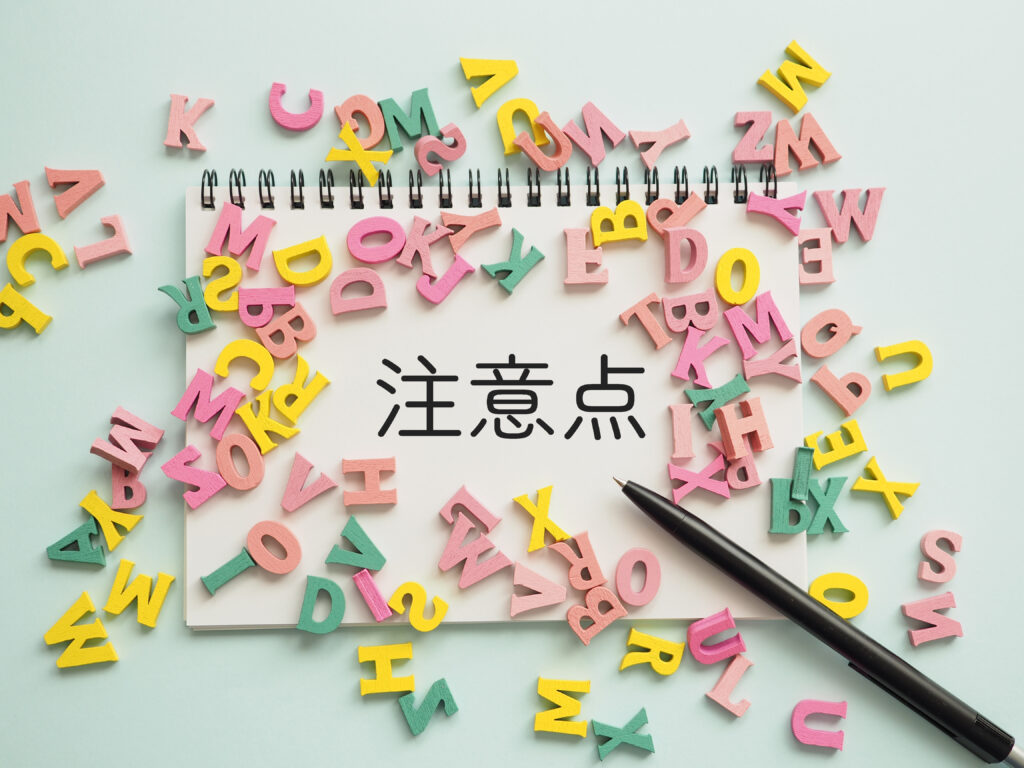
様子をよく観察する
猫がワクチン接種を受けた後は、副反応の有無を確認するためにしっかりと様子を観察しましょう。体調がよく見えても、接種後に発熱あるいは体温低下、食欲不振、ぐったりするといった反応が起こることがあります。
激しいものでなければ一過性の症状であり、病院での治療は必要ない場合が多いようですが、心配な場合は、動物病院に連絡をして相談しましょう。
ワクチンの副反応は、接種後すぐから数時間以内に現れることがあるため、接種は午前中に行い、午後は自宅で安静に過ごさせるのが理想的です。
また、夜間に体調が急変する可能性もあるため、夜間対応の動物病院を事前に調べておくといいでしょう。
ワクチン接種当日は猫を興奮させないよう、なるべく静かに過ごさせることも重要です。
アナフィラキシーショック
猫のワクチン接種後、ごくまれとされていますが、アナフィラキシーショックと呼ばれる重篤なアレルギー反応が起こることがあります。
接種後約15分〜1時間以内に、ショック状態や痙攣発作を起こした場合は注意が必要です。
また、ワクチン接種後約2~3時間以内に顔の腫れ(ムーンフェイス)、じんましん、よだれ、嘔吐、呼吸困難、意識低下などの症状が見られる場合は要注意です。速やかに動物病院へ連絡し、指示に従いましょう。
アナフィラキシーショックは命に関わる可能性もあるため、接種後30分程は愛猫から目を離さず、異変があればすぐに動物病院へ連れて行きましょう。
しこりがある
猫の予防接種後、まれに接種部位に「しこり」ができることがあります。これは肉腫と呼ばれる悪性腫瘍の可能性があり、発症率は約0.01%とされ低いものの、注意が必要です。
ワクチン接種後4週間〜10年と、発生までの期間に幅があります。
ワクチンによるしこりの原因はまだ解明されていませんが、注射に含まれる補助剤が作用するのではと考えられています。
通常は一時的なしこりで自然に消えることが多いとされていますが、1ヶ月以上経過しても2cmを超えて大きくなり続ける、3ヶ月経っても消えない、急速に大きくなる場合などは手術が必要となることもあります。
早期発見が大切なため、異変があればすぐに獣医師へ相談しましょう。
その他
ワクチンの接種部位は2〜3日程シャンプーなどで濡らさないように注意しましょう。
また、免疫がしっかりと定着するまでは約2週間かかるため、その間は外出やほかの猫との接触も控えるようにしてください。
その他何か異常を感じた場合や、軽い症状であっても24時間以上続く場合は、すぐに動物病院へ連絡をしましょう。
事前に獣医師から注意点を聞いておくのもよいでしょう。
まとめ

ここまで動物病院で猫のワクチン接種は必要ないのかについてお伝えしてきました。
動物病院で猫のワクチン接種は必要ないのかの要点をまとめると以下のとおりです。
- 猫のワクチン接種はは感染症のリスクを防ぐために必要
- 猫のワクチンはコアワクチンである3種に加え、4種・5種・7種などの種類があり、猫ウイルス性鼻気管炎や猫カリシウイルス感染症などの猫によく見られる感染症の予防に役立つ
- 猫のワクチン接種の前は体調が万全であるときに臨み、接種後は様子をよく観察することが大切
猫は「室内飼いだから大丈夫」と思われる方が多いかも知れませんが、思わぬ形で病原体に触れてしまう可能性があります。ワクチンは、猫自身を病気から守るだけでなく、周囲の猫たちへの感染拡大を防ぐためにも重要です。
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。


