がん治療の選択肢として挙げられる「免疫細胞療法」は、動物の体に本来備わっている免疫の力を活用し、がん細胞と闘う治療法を指します。
本記事では動物病院での免疫療法でがんが治療できるのかについて以下の点を中心にご紹介します。
- 免疫とは
- 動物病院で受けられる免疫療法の種類とは
- ペットの免疫力を高めるには
動物病院での免疫療法でがんが治療できるのかについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。
動物の免疫について

まずは、動物の免疫について以下で詳しく解説します。
免疫とは
免疫とは、体内に侵入したウイルスや細菌、寄生虫、さらにはがん細胞などの異物を排除し、体を守る防御システムのことです。これは、体が持つ自然な抵抗力の一つであり、健康を維持するために欠かせない機能です。
免疫の仕組みでは「体の細胞」と「異物」を識別し、異物と判断したものを攻撃・排除する働きがあります。例えば、細菌やウイルスは代表的な異物であり、体はそれらの侵入を防いだり、侵入してしまった場合には排除したりすることで健康を守っています。
もし免疫が正常に機能しなければ、ちょっとした風邪でも命に関わる程の影響を受ける可能性があります。
また、免疫のバランスが崩れると、感染症やアレルギー、さらにはがんなどの病気にかかりやすくなるため、適切なケアが必要です。ペットの体も人間と同じように免疫系のバランスによって健康が保たれており、このバランスが崩れると病気のリスクが高まります。
そのため、愛犬や愛猫の健康を守るためには、免疫力を維持し、適切にサポートすることが大切です。
免疫の中心的な役割を担うのは血液中に存在する白血球であり、そのなかでも異物の情報を伝える樹状細胞とともに「免疫細胞」と呼ばれます。免疫の働きは常に一定ではなく、異物に対抗するために強まることもあれば、逆に過剰な反応を抑えるために弱まることもあります。この絶妙なバランスを保つことが、健康を維持するカギとなるのです。
免疫力が低下するとどうなる?
免疫は、健康を維持するために重要な役割を果たしますが、低下すると体の抵抗力が弱まり、さまざまな病気にかかりやすくなります。高齢の犬や子犬は免疫機能が不安定になりやすく、アレルギーや感染症、ウイルス性疾患にかかるリスクが高まるため、注意が必要です。
また、免疫力の低下は、がんや自己免疫疾患の発症リスクも高めるといわれています。例えば、関節リウマチは、本来は体を守るはずの免疫が誤作動を起こし、自身の関節を攻撃してしまう病気です。
このように、免疫が正常に機能しないと、健康を損なう原因となることがあります。免疫低下によって起こる代表的な病気を以下でご紹介します。
1.感染症
免疫が低下すると、ウイルスや細菌、真菌(カビ)による感染症にかかりやすくなります。人間でいうインフルエンザや新型コロナウイルスのように、ペットにもそれぞれ特有の感染症が存在し、なかには人に感染するものもあるため注意が必要です。
2.敗血症(はいけつしょう)
敗血症は、細菌が血液中に入り込み、その毒素や体の防御反応によって全身に重篤な影響を及ぼす病気です。通常であれば免疫が働いて細菌を排除しますが、免疫力が低下していると、細菌が増殖しやすくなり、敗血症を引き起こす危険性が高まります。
3.がん
がん細胞は、健康な体内でも日常的に発生していますが、いつもは免疫機能が働き、それらを排除しています。しかし、免疫力が低下すると、がん細胞を抑え込む力が弱まり、腫瘍として成長してしまう可能性があるようです。そのため、免疫力を維持することが、がんの予防にもつながるのです。
4.歯周病・口内炎
犬や猫は、3歳以上になると約8割が歯周病を抱えているといわれています。免疫力が低下すると、お口のなかのバリア機能も弱まり、歯周病菌が繁殖しやすくなります。
最近では、免疫物質である「インターフェロンα」を歯茎に塗布することで、歯周病の原因菌の増殖を抑えられる可能性があることが研究によって明らかになっています。
このように、免疫力の低下はさまざまな病気を引き起こす原因となるため、日頃から免疫バランスを整え、適切なケアを行うことが大切です。
ペットのがんについて

ここでは、ペットのがんについて詳しく解説します。
がんは犬と猫の死因上位
犬や猫における死亡原因のなかで「がん(悪性腫瘍)」は高い割合を占めています。犬の場合、約3割が悪性腫瘍によって命を落としており、高齢になる程発症リスクが高まる傾向があるようです。
一方で、猫の死亡原因としてもがんは上位に挙げられ、約3分の1の猫が悪性腫瘍で亡くなっています。
犬の主な死因の内訳をみると、腫瘍によるものが約18.4%と多く、次いで循環器疾患(17.4%)、泌尿器疾患(15.2%)となっています。一方、猫では泌尿器疾患が多く(29.4%)、その次に腫瘍(20.3%)、循環器疾患(11.8%)が続きます。
このように、犬と猫のどちらにとってもがんは深刻な健康リスクとなっており、シニア期に入ると発症率が高まります。そのため、定期的な健康診断や早期発見・早期治療を意識したケアが大切です。
がんの治療法
がんの治療法には以下のような種類があります。
外科療法
がん治療のなかでも、外科的に腫瘍を摘出する方法はおすすめな治療法のひとつとされています。外科手術が可能なケースでは、腫瘍の種類に関わらず、迅速かつよりしっかりと切除し、根治を目指すことができます。
ただし、この治療法は局所的な腫瘍の除去に限られるため、全身に広がるがんには効果が限定的です。また、全身麻酔のリスクや手術による体への負担、さらには外見や体の形状の変化などの影響が生じる可能性もあるため、手術の適応を慎重に判断することが重要です。
化学療法
獣医療におけるがん治療には「三大療法」と呼ばれる外科療法、放射線療法、化学療法があります。これらの治療は、がんの状態や治療の目的に応じて「根治治療」と「緩和治療」に分類されます。
がん治療を行う際には、まず詳しい検査を行い、腫瘍の種類や進行度、行動特性(悪性度)、さらには基礎疾患の有無を把握することが重要です。そのうえで、治療の目的を明確にし、各治療法のメリット・デメリットを考慮しながら、よい治療法を選択していく必要があります。
放射線療法
局所的な腫瘍の治療においては、外科療法に次いで効果が期待できます。外科手術とは異なり、組織の機能や形状を維持しながら腫瘍を抑制できる点がメリットです。
しかしこの治療法も、局所的な対応に限られるため、全身に広がるがんには期待できる効果が限定的です。また一度の治療では、十分な効果をえることが難しく、複数回の施術が必要になるケースが多いとされていることが特徴です。
さらに、治療時には全身麻酔が必要となること、放射線による副作用(放射線障害)が発生する可能性があること、そして治療を行える施設が限られていることなど、いくつかのデメリットも伴います。
免疫療法
これまで、がん治療は主に外科手術、抗がん剤治療、放射線療法の3つを軸に進められてきました。しかし、免疫の働きががん治療において重要な役割を果たすことが明らかになり、「免疫細胞療法」という新たな治療法もあります。
現在、人の医療では、さまざまな病院がこの療法を取り入れ、有効性の向上に向けた研究が進められています。その流れを受け、獣医療の分野でも免疫療法を導入する動物病院が少しずつ増え始めています。
免疫細胞療法は、動物の持つ免疫力を強化し、がんの進行を抑えることを目的とした治療法です。具体的には、血液中からがん細胞を攻撃する役割を持つ免疫細胞を採取し、体外で増殖・活性化させた後、再び体内に戻します。自己の細胞を利用するため、副作用のリスクが低く、通常の治療に比べて麻酔を必要としない治療とされています。
この治療法は、進行がんや末期がんを治癒させることは難しいとされていますが、がんの進行を遅らせたり、再発を防いだりすることで、動物のQOL(生活の質)の向上に貢献する可能性があります。そのため、「がんの完治を目指す」のではなく、「がんと共存しながら生活の質を向上させる」ことを目的とした治療法といえるでしょう。
動物病院で受けられる免疫療法とは
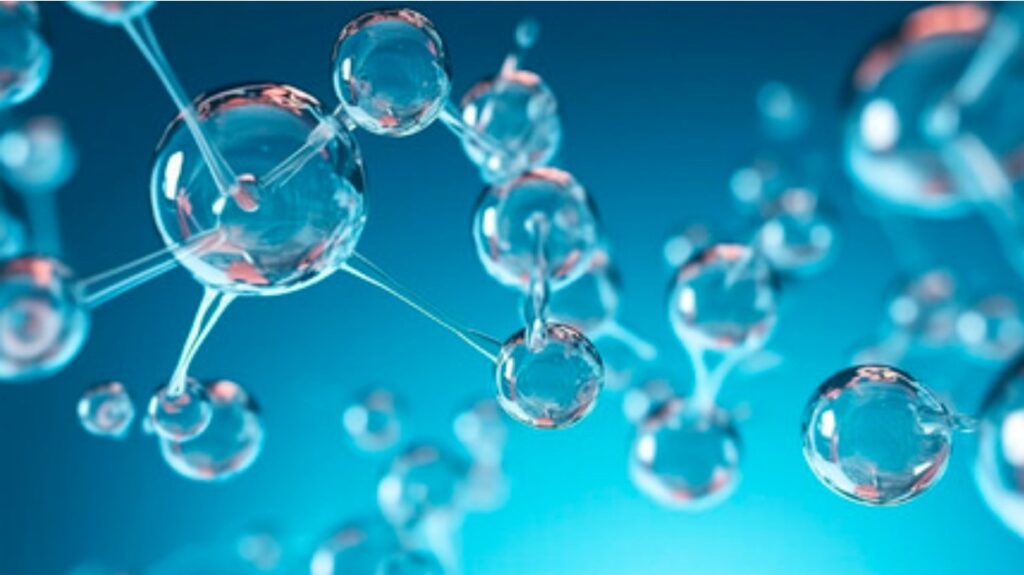
体内で発生するがん細胞は、免疫の働きによって異物として識別され排除されます。しかし免疫が低下している場合や、がん細胞自体が免疫の攻撃を回避する仕組みを持つことで、正常な免疫機能が十分に働かなくなり、がん細胞が体内に残ってしまうことがあります。
免疫療法は、体が本来持つ免疫力を回復・強化し、がん細胞を排除する力を高める治療法です。動物病院で行われる免疫療法のメリットとして、以下のような点が挙げられます。
- 副作用が少ない
抗がん剤治療とは異なり、食欲不振や嘔吐などの副作用がほとんどなく、体へ負担がかかりにくい治療法です。 - がんの進行を抑える
がん細胞の増殖を抑え、病状の進行を遅らせることで、延命効果が期待できます。 - 症状の改善
免疫機能の回復により、がんによる痛みや体調不良などの自覚症状が軽減され、QOL(生活の質)の向上が見込まれます。 - ほかの治療との併用が可能
抗がん剤や放射線治療と組み合わせることで、より高い治療効果を期待することができます。
動物病院で受けられる免疫療法は、がんの根治を目指すものではなく、がんと共存しながら動物の生活の質を維持・向上させることを目的としています。
現在、免疫療法を導入する動物病院は徐々に増えていますが、治療を検討する際は、獣医師と相談しながら愛犬・愛猫に合った治療法を選ぶことが大切です。
動物病院で受けられる免疫療法の種類

動物病院で受けられる免疫療法の種類は以下のとおりです。
活性化リンパ球(CAT)療法
活性化リンパ球(CAT)療法は、犬や猫の血液からリンパ球を採取し、体外で増殖・活性化させた後に再び体内へ戻すことで、がん細胞の抑制を目指す免疫療法のひとつです。
この治療ではまず、10〜12ml程度の血液を採取し、そのなかに含まれるリンパ球を回収します。リンパ球は、がん細胞に対する免疫機能を担う重要な細胞のひとつです。採取したリンパ球には特別な薬剤を加え、2週間程かけて活性化・増殖を行います。
その後、増えたリンパ球を洗浄・回収し、点滴によって再び体内に戻します。活性化・増殖されたリンパ球は元の約1,000倍にもなり、がん細胞に対する免疫反応を強化する効果が期待できます。
この療法は、がんの進行を抑えることを目的としており、副作用が少なく、体への負担が少ないのが特徴です。ほかのがん治療と組み合わせることで、相乗効果を発揮する可能性もあるようです。
樹状細胞・活性化リンパ球(DC・CAT)療法
樹状細胞ワクチン療法は、がん細胞を特異的に攻撃する免疫細胞を強化する治療法です。犬や猫の血液(約10〜15ml)と、すりつぶした腫瘍組織を組み合わせ、樹状細胞とともに培養します。
樹状細胞は、リンパ球にがん細胞を攻撃するための目印を提示する重要な細胞です。この培養過程によって、がんに特異的な免疫応答を引き出すことができます。さらに、活性化され約1,000倍に増えたリンパ球とともに体内へ投与することで、がん細胞に対してより精度が期待でき、攻撃を行うことが可能となるようです。
この治療法は、免疫の力を利用してがんを抑えることを目的としており、がん細胞の増殖を抑制しながら、副作用を抑えられる点が特徴です。ほかの治療法と併用することで、さらなる効果が期待されています。
キラーセル(KC)療法
がんに対する免疫機能を担うリンパ球のなかでも、特に強力ながん細胞攻撃能力を持つキラー細胞を選択的に増殖させ、体内に投与する治療法です。がん細胞を標的とし効果的に攻撃できることが期待されます。
ペットの免疫力を高めるには

ペットの免疫力を高めるために必要なことは以下のとおりです。
栄養面のサポート
腸は食べ物を消化・吸収するだけでなく、食事とともに体内に侵入する病原菌や有害物質とも常に接しています。腸管免疫は、これらの有害な微生物や物質が体内で悪影響を及ぼさないように防御する重要な役割を担っています。がんと戦う免疫細胞も、腸に存在しているといわれています。
また、腸内に生息する細菌のバランスが、腸の免疫機能に大きな影響を与えることがわかっています。腸内細菌には、体によい影響を与える「善玉菌」と、悪影響を及ぼす「悪玉菌」があり、善玉菌を増やすことで腸内環境を整え、免疫力を高めることができると考えられています。
ストレス対策
悩み事や不安、ストレスを抱えていると、副交感神経の働きが鈍くなります。よって、リンパ球の数が減少し、がんと闘うための免疫力が低下してしまいます。がんを患っている動物たちは、痛みや体の不自由さ、通院や治療に伴うストレスなど、さまざまな負担を抱えています。
そのため、できるだけストレスを軽減し、快適に過ごせるようサポートしてあげることが大切です。痛みを和らげることや、日常生活での不便を手助けすることは、免疫力を維持するうえでも重要な役割を果たします。
適度な運動
犬の場合、毎日2回の散歩を習慣にしましょう。犬種や体格によっておすすめな運動量は異なりますが、1回30分程度の散歩を行うことが理想的です。また、猫は基本的に室内で過ごすため、遊びを通じてしっかりと運動させることが大切です。
運動不足になると、代謝が低下し、血液の循環が悪くなることで免疫力の低下を招く可能性があります。適度な運動を取り入れることで、健康を維持し、体の防御機能を高めることにつながります。
まとめ

ここまで動物病院での免疫療法でがんが治療できるのかについてお伝えしてきました。動物病院での免疫療法でがんが治療できるのかについての要点をまとめると以下のとおりです。
- 免疫とは、体内に侵入したウイルスや細菌、寄生虫、さらにはがん細胞などの異物を排除し、体を守る防御システムのことを指す
- 動物病院では、がん治療の一環として免疫療法が実施されている。代表的なものに、活性化リンパ球(CAT)療法、樹状細胞・活性化リンパ球(DC・CAT)療法、キラーセル(KC)療法があり、免疫細胞を増強・活性化し、がん細胞を攻撃する効果が期待されている
- ペットの免疫力向上には、栄養面のサポート(腸内環境を整え善玉菌を増やす)、ストレス対策(快適な環境づくりで免疫低下を防ぐ)、適度な運動(代謝や血流を促進)が重要
免疫細胞療法は、動物本来の免疫力を活用し、がんと向き合う新たな治療法です。従来の治療と併用すると相乗効果が期待できるため、副作用の少ない選択肢としてさまざまな動物病院で導入が進んでいるようです。
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。


