動物病院では、ペットの健康状態を正確に把握するために内視鏡検査を実施することがあります。特に嘔吐や食欲不振などで消化器系のトラブルが想定されるケースに利用されますが、飼い主として知っておくべきデメリットも潜んでいるため注意が必要です。
こちらの記事では、動物病院の内視鏡検査でわかることをお伝えしたうえで、メリットとデメリット、検査を受ける流れと注意点について解説します。大切なペットの体調不良で、内視鏡検査が必要といわれた際には、参考にしてみてください。
内視鏡検査でわかること

人間の検査や治療において内視鏡が使われることはごく一般的ですが、動物病院ではあまり主流ではありません。ただ、内視鏡を使えば動物の体の中を直接確認できるため、ほかの検査方法よりも精度が高くなる場合があります。
ここでは、動物病院の内視鏡検査でわかることについて解説します。
消化器官の状態
内視鏡検査では、食道や胃、十二指腸を直接確認できるため消化器官の状態を把握できます。人と暮らす動物は、飼い主がみていないところで食べ慣れていないものを口に入れたり、ストレスを感じたりして嘔吐や下痢などの症状を見せることがあります。消化器系の病気は、何が原因で不調を引き起こしているのか突き止めなければなりません。
一般的には、血液検査やエコー検査で症状を判断しますが、これらの検査では症状の原因がわからないこともあります。その点において、内視鏡検査はスコープが届く範囲内で直接獣医が確認し、異常や疾患の有無を判断するため消化器官の状態を細かく確認できます。
腫瘍の位置や大きさ
内視鏡検査では、食道〜十二指腸にかけて検査をおこない、腫瘍がある場所と大きさを直接確認して、状態によっては直接処置をします。
犬や猫などの動物に腫瘍ができる原因は、明確に解明されていません。猫のリンパ腫にはウイルス感染との因果関係が疑われています。
血液検査やレントゲン検査、超音波検査で数値の異常や腫瘍の有無を判断できたとしても原因までは特定できません。もし、悪性腫瘍の場合、腫瘍と場所、進行浸潤転移度合いにより対応が変わってきます。正確な判断をするため、CTや他の画像診断をもちいて総合的に判断されます。
粘膜の炎症や出血の程度
内視鏡検査では、食道や胃、十二指腸までスコープを通せるため、動物の体内にある粘膜面の炎症や出血の状態を把握できます。粘膜トラブルの代表例として、大腸性下痢、リンパ管拡張症、炎症性腸疾患(IBD)などが挙げられます。
血液検査や尿検査などでも数値の異常や出血の可能性を判断することは可能ですが、粘膜の状態を正確に判断することは困難です。実際に内視鏡を使うことで、変色や異常の有無を確認できるほか、組織の一部を採取すれば原因の特定まで可能です。
粘膜トラブルでは、ステロイド剤や抗生物質、免疫抑制剤など投薬が必要なケースがあり、間違った治療はペットの負担や状態悪化につながります。そのため、検査精度の高い内視鏡を使った方が安心です。
内視鏡検査のメリット
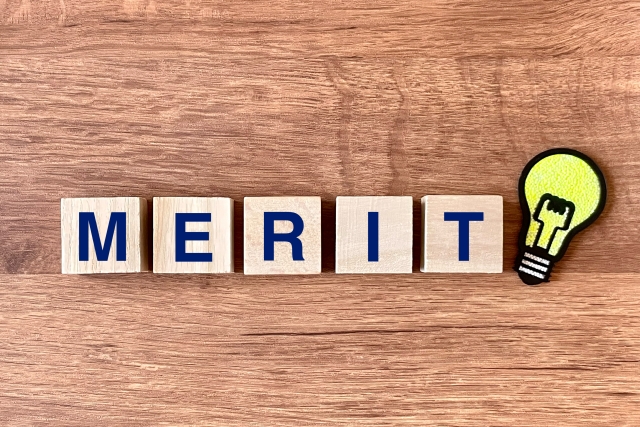
内視鏡では、消化器官の異常、腫瘍の状態や粘膜の炎症状態などを確認できるため、より正確な検査が可能です。また、それ以外にほかの検査方法よりも優れている点があります。
ここでは、内視鏡検査のメリットについて解説します。
リアルタイムでの診断が可能
まず内視鏡検査では、スコープをお口から通して身体の中の状態を確認するため、検査中に病気や不調の原因をリアルタイムで診断できます。血液検査やレントゲン検査、尿検査などでは、検査結果をもとに解析や原因の追求をしなければなりません。場合によっては、その日のうちに診断と治療方法の説明が受けられないこともあります。
その点内視鏡検査では、その場で粘膜の炎症や変色、腫瘍の場所や大きさが判明するため、すぐに診断と治療方法の説明が受けられます。動物は、自分で痛みや不調を飼い主に伝えられないこともあり、悪性腫瘍や病気が見過ごされてしまいがちです。検査結果によっては、いち早く投薬や手術が必要なケースもあるため、手遅れにならないためにも内視鏡検査は重要視されています。
治療と検査を同時に行える
内視鏡検査では、検査の結果次第で、そのまま治療に進むことがあります。よくある事例として、おもちゃや竹串などの異物誤飲です。この場合、内視鏡検査で異物の場所と大きさを把握したら、把持鉗子やバスケット把持鉗子などの器具を使って内視鏡検査中に取り除けます。
また、検査で病気や不調の原因が判明すれば、その日のうちに抗生物質や抗ステロイド剤などの薬を処方してもらえたり、食事療法のアドバイスをしてもらえたりします。動物の不調は急変する恐れもあるため、治療と同時に行える内視鏡検査は、命に関わるリスク回避にも効果的です。
開腹手術のリスクを回避できる可能性
ペットが誤飲したとき、催吐処置で異物を吐き出せなければ、開腹手術になるケースが見られます。しかし、開腹手術は切開になるためペットの負担が大きく、手術ミスによる死亡リスクも懸念されます。また、術後は感染症にも気をつけなければならないため、完治するまでに一定期間が必要でした。
その点、内視鏡を使っている動物病院を受診すれば、異物の場所と大きさによって開腹手術を避けられる可能性があります。内視鏡検査をして、お口から異物を取り出せると判断されれば、専用器具を使ってその場で摘出治療へと進みます。開腹手術の負担やリスクを回避できるため、飼い主としても安心でしょう。
なお、異物の大きさや形状によっては、体内を傷つけてしまうため開腹手術の方がよいケースもあります。異物を取り出す方法には、それぞれ一長一短の側面があるため、担当医の説明を聞きながら判断しましょう。
内視鏡検査のデメリット

内視鏡検査は精度の高さやリスクの低さがメリットとしてありますが、一方で飼い主として知っておくべきデメリットも持ち合わせています。後から「思っていたのと違った」と不満や後悔を抱かないためにも、内視鏡検査のリスクについて確認しましょう。
ここでは、内視鏡検査のデメリットについて解説します。
費用が高額になる場合がある
内視鏡はとても精度の高い設備であるゆえに導入費用が高く、さらに内視鏡を使えるだけのスキルと知識を持っている獣医が在籍していなければなりません。そのような背景から、内視鏡検査は、ほかの検査方法よりも費用が高くなる可能性があります。
内視鏡検査の費用は、基本料金と追加料金があります。基本料金は、内視鏡の使用料、獣医師・技術者の人件費、バルーンやスリーブなどの諸費用です。追加料金は、検査結果から治療や生検が必要になった場合に発生します。腫瘍摘出や異物除去などが対象です。
動物病院を受診した時点では、追加料金がどれ程かかるのか予測がむずかしいため、症例ごとに費用が変動してしまいます。費用面の不安があれば、あらかじめペット保険に加入するなどの対策をしておきましょう。
全身麻酔が必要なため負担がかかる
内視鏡検査ではお口から専用の管を通して身体の中を見る検査のため、ペットの不安や痛みを軽減するために全身麻酔を行います。暴れて事故の原因になるため、全身麻酔をせずに内視鏡を使うことはできません。そのため、ペットに全身麻酔の身体的な負担がかかります。
麻酔の種類や量は、ペットの年齢や大きさ、健康状態、基礎疾患の有無などに応じて獣医が判断します。リスクは低いとされていますが、ごく稀に後遺症が報告されています。
全身麻酔を使わない血液検査やエコー検査などと比べると麻酔による負担がある点は、理解しておく必要があります。特に過去の去勢・避妊手術などで全身麻酔をした際に、麻酔トラブルがあった場合、そのできごとを必ず伝えて対策をしてもらいましょう。
検査範囲が限定される
内視鏡検査では、小腸や大腸まで管を通すことができないため、検査範囲が限られます。これは開腹手術と比較した際のデメリットです。
「大切なペットのお腹にメスを入れたくないから…」との理由で内視鏡を取り扱っている動物病院を受診したものの、結局は開腹手術になったとの事例もあります。これは、内視鏡では病気や異物の原因を追求できなかった可能性が高いです。なお、開腹手術であれば、身体の臓器をすべて外から確認できるため、検査や治療の対応範囲が広がります。
開腹手術は内視鏡検査と比べてペットのへの負担は大きいですが、状態にあわせて使いわけが必要です。飼い主としては、内視鏡検査だけにこだわる必要はなく、獣医の説明をよく聞いて、大切なペットに適切な判断をしてもらいましょう。
検査の過程で臓器が傷つく可能性がある
内視鏡検査で使われる管はとても細いため、基本的には臓器を傷つけることはありません。ただし、粘膜が激しく炎症を起こして腫れていたり、異物や腫瘍があったりすると、内視鏡が触れて臓器を傷つける恐れがあります。
内視鏡を取り扱うためには高度な技術と豊富な知識が必要です。身体への負担を軽減するために内視鏡検査をしてもらっているはずが、かえって傷つけてしまう原因にならないためにも、経験のある獣医のもとを受診しましょう。
また、内視鏡を使った検査や治療をする予定でいても、状態によっては獣医の判断で別の検査方法や治療方法に切り替わることがあります。飼い主としても、ペットの健康と安全を優先にして、獣医の説明を聞くようにしてください。
内視鏡検査を受ける際の流れ

実際に動物病院で内視鏡検査を受ける際には、事前に準備するべき工程があります。自宅でもやるべきことがあるため、必ず確認しておきましょう。
ここでは、内視鏡検査を受ける際の流れについて解説します。
絶食
内視鏡検査では全身麻酔をするため、絶食が必要です。麻酔をすると一時的に消化機能が低下するため、身体のなかに食べ物が残っていると誤嚥性肺炎を引き起こす可能性があります。
絶食は、内視鏡検査をする前日の夜からはじめます。何も知らされていないペットにとっては辛い時間になりますが、コミュニケーションをとって空腹を和らげてあげてください。
血液検査
動物病院に着いたら、全身麻酔や内視鏡検査をしても異常が発生するリスクがないかを判断するための血液検査をします。同時に、レントゲン検査をする動物病院もあります。これらの事前検査は、ペットが安全な状態で検査と治療を受けるために欠かせません。
血液検査で問題がないと判断されれば、麻酔をします。基本的には、注射タイプの静脈麻酔が使われますが、ごく稀に吸引麻酔が使われることもあります。これらは、すべて動物の年齢や大きさ、健康状態に合わせて獣医が選択します。麻酔中は、常に体温と心拍数、血圧の状態をモニタリングしながら、同時進行で検査や治療を行います。
検査・処置
完全に麻酔が効いたら、内視鏡を患部に挿入して身体の内側の状態を確認します。異常や病変、異物、腫瘍のある場所と大きさから病気や不調の原因を特定します。その場で除去できるような異物が見つかれば、内視鏡と専門器具を使って処置が可能です。
また、病気や不調の原因が特定できれば、それぞれの原因にあわせて治療します。内視鏡で治療がむずかしいと判断されれば、その場で開腹手術になる症例もあります。この場合は、飼い主に連絡が入るため、獣医の説明をよく聞いたうえで納得できれば、そのまま手術をしてもらいましょう。
病理検査
内視鏡のカメラだけで病気や不調を特定できない症例もあります。その場合、粘膜の一部を採取して病理検査を実施します。病理検査をすると、目に見えないウイルスやアレルギー物質から病気の種類や進行度を調べられるため、的確な治療法を導き出せます。
採取した粘膜組織を外部に提出して解析してもらう場合、その日のうちには診断が受けられません。後日、あらためて動物病院への受診が必要です。
安静・診察
検査と処置が終了したら、徐々に全身麻酔が切れてきますが、最初のうちはふらふらしたり不安定な状態が続いたりします。麻酔から完全に目を覚ますまでは、激しく動かさずに静かな場所で安静にさせることが大切です。
目を覚ました後の食事量や水分量には、制限がかかっている場合があります。体調不良を引き起こさないためにも、獣医の指示にしたがってペットの回復を待ちましょう。
内視鏡検査を受ける際の注意点

内視鏡検査を受ける際の注意点は、獣医の技術力と全身麻酔の必要性です。
すべての動物病院に内視鏡が設置されているわけではないため、ほかの検査方法や開腹手術ではなく内視鏡がよいと希望する場合は、内視鏡検査を実施しているかどうかの確認が必要です。同時に、内視鏡検査をするには高い技術力が求められます。在籍している獣医の経験を確認しておくと、安心して大切なペットを預けられるでしょう。
続いて、内視鏡検査をするためには全身麻酔が必須です。動物病院で使われる麻酔は安全性に考慮されていますが、体質や健康状態によってはごく稀に麻酔の拒絶反応や後遺症が起こります。過去に麻酔で不調になったことがあれば、安全に検査と処置を済ませるためにも、必ず獣医に伝えてください。
まとめ

内視鏡を使って検査・治療をする動物病院は限られていますが、ほかの検査方法よりも精度や安全性が優れているとして注目されています。
ただし、導入費や人件費の側面から検査費用が高くなったり、全身麻酔が必要だったりする面はデメリットとして懸念されています。ペット保険の活用や事前検査などを徹底すれば解消できる可能性もあるため、ペットの安全を第一に内視鏡検査を検討してみてください。


