動物病院で行われる再生医療は、今までは治療を諦めるしかなかった病気や怪我を抱えていたり、終末期を迎えたりしたペットにとって希望の光です。自己治癒能力を高める点に特化しているため、治療中の負担も負担も小さいと考えられます。ただし、治療の選択肢が増える反面、実施できる動物病院はまだ少なく、費用も全額自己負担になる点は要注意です。
こちらの記事では、動物病院で受けられる再生医療とは何か、治療法の種類や流れ、費用相場を解説します。
動物病院の再生医療とは

動物病院で行われる再生医療とは細胞治療とも呼ばれ、ペットの病気や怪我を治療する1つの手段です。慢性的な病気や怪我に悩んでいるペットに対して治療が可能になります。とくにがんの場合、治療の段階で将来的な再発や転移を抑止する作用も期待できるため、画期的な治療法であると称えられ注目されています。
再生医療の基本知識
ペットの再生医療が注目され始めたのは2007年頃といわれており、活性化自己リンパ球移入療法と呼ばれる治療法が臨床応用された頃だと確認されています。2013年には旧薬事法である薬機法が改正され、再生医療等製品と呼ばれるジャンルが確立されました。
再生医療には、自家(じか)移植と他家(たか)移植の2つがあります。自家移植はペット自身の細胞を使うやり方で、他家移植ではほかのペットから細胞の提供を受けるやり方です。従来の治療法では効果が得られにくくなってきた場合や、薬の副作用を防ぎたい場合にも重宝するといわれています。
なお、動物領域の再生医療は、獣医療法や動物用医薬品等取締法の管理下にあり、ヒト医療で適用される薬機法とは審査枠組みが異なります。臨床研究段階の治療も多く、十分な有効性データは蓄積途上である点を理解しておきましょう。
犬・猫と人間の再生医療の違い
再生医療における犬・猫と人間との違いは、安全性の確保に対する法規制の有無です。そもそも再生医療の法規制を定めているのは薬機法であり、これは人間にもペットにも共通して同じ法律が適用されます。
ところが、人間に対して行われる再生医療は、安全性を定める再生医療等安全性確保法がありますが、動物の分野に同じような法律は存在しません。そのため、再生医療を治療法として採用するか否かの方針は、現場で実際に治療にあたる獣医師の裁量により実施されていました。
そこから、日本獣医再生医療学会と日本獣医再生・細胞療法学会が共同でガイドラインを作成しています。さらに、2018年には、犬および猫における再生医療および細胞療法における安全性確保に関する指針が農林水産省と日本獣医師会のアドバイスを受けて完成しました。
動物病院で再生医療が検討される疾患

動物病院で実施される再生医療は、病気や怪我、加齢によって引き起こされる症状に対する治療法として検討されています。
ここでは、具体例として4つの疾患における再生医療の詳細を解説します。
慢性関節炎・変形性関節症
慢性関節炎と変形性関節症はいずれも、身体の動きをサポートするはずの関節が、何らかの原因によって動かすと痛み、歩行機能に支障をきたす病気です。怪我や感染症による関節の損傷や、免疫力の低下などが要因として考えられます。
関節炎や関節症における再生医療では、軟骨や滑膜の形成を目指し、関節の柔軟な動きを実現するのが目的です。これにより炎症を鎮め、痛みを和らげる効果が期待できるでしょう。
椎間板ヘルニア、脊椎損傷
椎間板ヘルニアは、何らかの原因によって飛び出した椎間板が神経を圧迫する病気です。脊椎損傷はその名のとおり、脊椎が外傷によって傷ついてしまった状態を指します。いずれの症状においてもペットは痛みを感じ、歩行障害が出たり、散歩や抱っこを嫌がったりなどして日常生活に支障をきたすでしょう。
再生医療ではこれらの症状に対し、傷ついた椎間板の再生や修復を目指します。痛みが緩和され、神経の圧迫も解消できれば、ペットは痛みから解放されるでしょう。足を引きずったり歩けなくなっていたりしたペットについては、再び歩けるようになる可能性があります。
皮膚の難治性潰瘍
ペットにおける皮膚の難治性潰瘍といえば、何らかの理由により傷の治りが遅かったり、傷が大きすぎる状態を意味します。再生医療は皮膚そのものの再生を助けるため、皮膚の凹みを縮小させ傷の治りを促進するでしょう。ペットが本来持っている治癒能力を高めるやり方なので、投薬が難しいケースにも対応できます。
アトピー性皮膚炎で投薬を継続しているケースにおいては、再生医療による治療で薬を絶てるため、薬によるペットの身体への負担が気になる場合にも重宝するでしょう。
腎臓病などの内科疾患
腎臓病は、体内のろ過機能を担う腎臓が正常に機能しなくなる病気です。体内の毒素をうまく排出できずにあらゆる悪影響を及ぼしますが、腎臓病の厄介な点は病気の初期段階では無症状であるケースが散見されます。
症状が悪化し、具体的な不調が見て取れるような段階では病気がかなり進行しているケースも少なくありません。再生医療は、機能低下した腎臓の働きをサポートしたり、病気の進行を遅らせる効果が期待されています。
動物病院で受けられる主な再生医療の種類

動物病院でペットが受けられる再生医療には、主に次の3種類があります。それぞれの再生医療における概要と、特徴を解説します。
幹細胞治療
幹細胞治療とは、もともと体内に存在し、器官や臓器などに分化する間葉系幹細胞と呼ばれる細胞を使って行われます。幹細胞治療ではこの細胞を体外で培養したものをペットたちの体内に戻し、損傷部分の修復や再生、身体機能の維持などにあてがうのです。
幹細胞には、損傷を受けたり炎症を起こしたりしている部分に自然と集まる特長が認められています。詳細な方法は2つあり、1つはペット自身の細胞を培養する自家移植と、もう1つはほかのドナーから細胞の提供を受けて行う他家移植の2つです。自家移植の場合は自分の細胞を使うため、移植後の拒絶反応も起こりづらいとされています。
免疫細胞治療
免疫細胞治療とは、本来持っている自己治癒力を促進するがんの治療方法です。ペットの体内には本来、がん細胞を異物と認識して排除する免疫機能の働きがあります。ところが、がんを発症してしまうと免疫細胞の機能は抑制され、有害な細胞を体外に排出できなくなってしまうのです。
再生医療の免疫細胞治療では、この免疫力が高い状態の細胞をペットに投与し、がん細胞を自分の免疫の力で排除していくのを目指します。処置は細胞の注入だけになるので、入院せずに実施できる点も魅力です。
多血小板血漿(PRP)治療
多血小板血漿(PRP)治療とは、血液中に含まれる傷の修復を促す成長因子を使った自己治癒能力を促進するタイプの再生医療です。細胞を培養するのではなく、血液中に含まれる血小板を培養します。
採血した血液を遠心分離器にかけて血小板だけを取り出して培養し、ペットの身体に注入するもので、細胞を培養するよりも処置できるまでが早いのが特長です。
動物病院での再生医療の治療フローと通院スケジュール

動物病院で再生医療を受ける場合、おおよその流れは決まっています。
とくに再生医療を用いた治療は、動物病院への複数回の通院が前提で、一般的なスケジュールとして、治療は数週間〜数ヶ月におよぶでしょう。また、経過観察とその結果に対して再治療を検討するため、費用はもちろん時間にも余裕を持っておくのがおすすめです。
カウンセリング
再生治療をはじめる前には必ず、獣医師によるカウンセリングが行われます。ペットの普段の健康状態について飼い主さんにヒアリングを行い、過去に治療歴がある場合は再生医療の実施が問題がないか判断されるでしょう。
このとき、飼い主さんは再生医療による治療によってもたらされるメリットはもちろん、デメリットについても内容を確認します。最終的には飼い主さんの判断によって治療をするかどうかが決まるでしょう。
投与の流れ
再生医療では、注射器ないし点滴を使って投与=幹細胞をペットの体内に注入します。投与は静脈への点滴か、局所注射にて実施され、所要時間は点滴で1〜2時間、局所注射ならその場で治療が終わるでしょう。投与する幹細胞は、採取する脂肪の種類や量にもよりますが1回でおよそ3回分が確保できます。この一連の流れを症状が緩和、改善がみられるまで継続してくのです。
術後の経過観察と再治療のタイミング
再生医療による治療法は、細胞を注入した後も経過観察が必須です。通常、この経過観察は数週間〜数ヶ月に渡って行われます。この期間中に、症状の改善が見られないようであれば、再治療を行うか別の治療法に着手するかを検討します。
状態の変化を見極めるには、獣医師による定期的なチェックと判断が欠かせません。つまり、再生医療での治療期間中は経過観察のために動物病院への通院が必須です。また、再治療のタイミングについても見極める必要があります。治療の効き目がどのくらい出ているかや進行度合いにより、治療回数も変動するため注意してください。
動物病院での再生医療の費用相場

動物病院で行われる再生医療の費用相場は、治療を行う病院によって異なります。何より自由診療となるため、高額になるのは否めません。ここでは、再生医療にかかる費用について、おおよその費用相場をみていきましょう。
幹細胞治療の費用相場
幹細胞治療の費用相場は、細胞1回の投与で約7万円程です。また、幹細胞治療の費用については動物病院によって差が出るものの、継続した投与を前提とする病院が多く、セット回数は4回で設定されています。
つまり、治療の1クール(4回)で考えれば、幹細胞治療の費用相場は約28万円です。ただし、この費用には検査費などの諸費用が含まれないため、実際はこれよりも費用がかかると想定できます。
免疫細胞治療の費用相場
免疫細胞治療の費用相場は、1回の治療につき約6万5,000円程です。手術や放射線治療が1回あたり数十万円かかる治療法であり、およそ抗がん剤治療と似たような費用で実施できます。
身体への負担も少なく済む治療法ですが、お住いの近くにこれらの治療をやっている病院がさほどないと仮定すると、通院のための交通費などは費用に含めてもいいでしょう。
多血小板血漿(PRP)治療の費用相場
多血小板血漿(PRP)治療の費用相場は、1回の治療につき約4万5,000円程です。本記事で紹介した幹細胞治療と免疫細胞治療に比べると安価ですが、それでも自由診療となるため1回あたりの料金がかさみます。
また、ペット向けの再生医療のなかでも実施している動物病院が限られるため、免疫細胞治療と同様、治療のための交通費なども考慮しておかなければなりません。
動物病院で再生医療を受ける際の注意点

動物病院で行われる再生医療には、治療法特有の注意点があります。ペットの再生医療を検討する際は、以下に記す2つの注意点に留意してください。
まれに拒絶反応を起こすことがある
再生医療は、薬の力に頼らずペットの自己治癒能力を高める治療方法です。ところが、体外で培養した細胞や血小板を体内に注入するため、リスクとして一定の拒絶反応が予想されます。
特に、ほかのドナーから提供を受けて行われる他家移植においては、注入した幹細胞がペット自身の細胞ではありません。治療に際しては、ごくまれにアレルギー症状が出る可能性もあるため留意してください。
特定の動物病院でしか受けられない
ペットの再生医療については、画期的な治療法ではあるものの、実施している動物病院がまだまだ少ないため、治療可能な動物病院が限られています。つまり、豊富な選択肢から選べるわけではありません。治療の実績はもちろん、自宅から通院可能な病院を探し出す必要があります。
まとめ
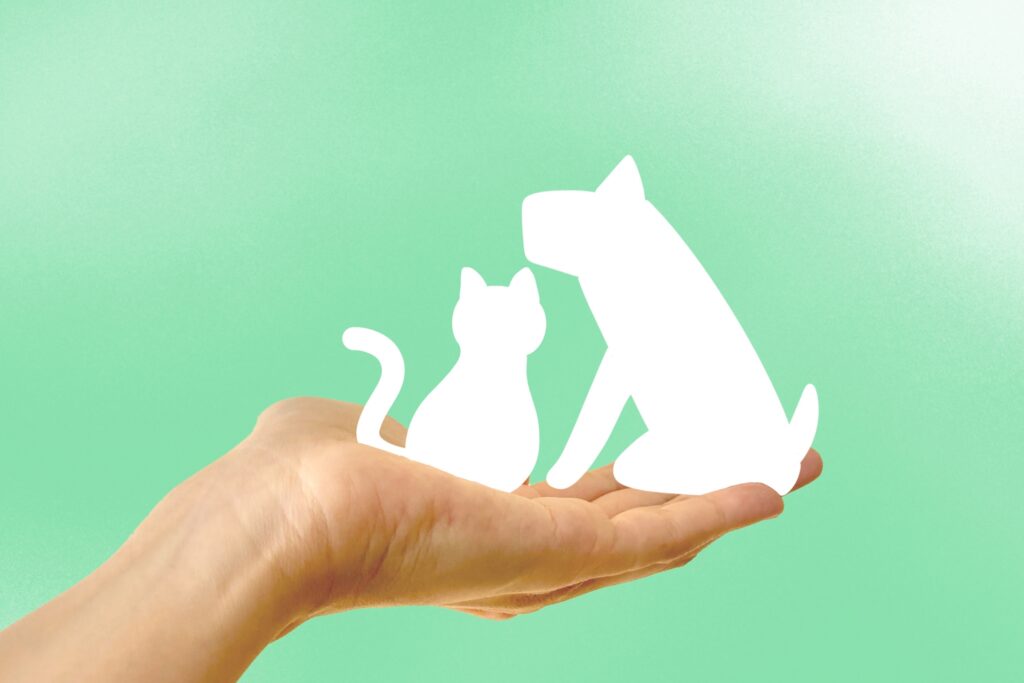
動物病院で行われる再生医療は、今まで治療を諦めざるを得なかった病気や怪我による損傷に対して、投薬とはまったく異なったアプローチができる治療法です。
基本は体外で培養した細胞や血液をペットの体内に注入して行いますが、ペット自身の細胞を使うか、ドナーからの提供を受けるかといった移植方法も選べます。培養した細胞や血液を注入するだけなので、治療による負担がさほど大きくないのも魅力です。また、再生医療における治療期間や内容は動物病院によって異なります。
治療中は定期的な通院が必須で、再治療の判断についても常に獣医師によるカウンセリングが必要となるため、治療の継続にあたっては根気強く付き添う必要があるでしょう。


