動物病院で接種できるワクチンは、愛犬や愛猫の健康を守るために欠かせないものです。感染症からペットを守り、ほかの動物や人への感染を防ぐためにも、適切なワクチン接種が重要です。
本記事では動物病院で受けられるワクチンについて以下の点を中心にご紹介します。
- ワクチンで予防できる犬の病気とは
- ワクチンで予防できる猫の病気とは
- ワクチン接種にかかる費用とは
動物病院で受けられるワクチンについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。
動物病院で受けられるワクチンとは

ワクチンは、感染症からペットを守るためにも重要な予防方法です。動物病院で提供されるワクチンは効果が期待でき、感染力が強く命に関わる病気に対して使用されます。ワクチンを接種することで、病気に対する免疫力を高め、重症化を防ぐことが目的です。
- ワクチンの仕組みと種類
ペットに接種されるワクチンは、病原体を無毒化または弱毒化したものを体に導入することで、感染症に対する免疫をつける仕組みになっています。
- 接種証明書の必要性
ワクチン接種は健康管理だけでなく、ペット保険やペットホテルの利用時にも関係します。多くの保険では、ワクチンで予防できる病気に未接種の状態で罹患した場合、補償の対象外となることがあるため、契約内容を確認しておきましょう。
また、ペットホテルを利用する際には、ワクチン接種証明書の提示を求められる場合があり、接種の記録をしっかり保管することが大切です。
ワクチンで予防できる犬の病気

ワクチンで予防できる犬の病気は以下のとおりです。
犬ジステンパー
犬ジステンパーは、ジステンパーウイルスが原因で引き起こされる、犬にとって深刻な感染症です。この病気は感染力が強く、致死率も高いため、犬の健康を脅かす代表的な疾患のひとつです。特に免疫力が低下しやすい子犬や高齢犬によく発生します。
- 感染経路
ジステンパーウイルスは、感染した犬との接触や、咳やくしゃみなどによる飛沫を通じて空気感染することがあります。また、ウイルスが付着した物に触れた後、口や鼻を介して感染することもあります。
このように、ジステンパーは重篤な病気でありながら、適切な予防で防ぐことができる疾患です。愛犬の健康管理の一環として、ワクチン接種を計画的に行うことが大切です。
犬パルボウイルス感染症
犬パルボウイルスによる急性の伝染病で、1979年にアメリカで初めて確認され、その後世界中に広がった病気です。このウイルスは強い耐久性を持ち、チリやホコリのなかで長期間生存することができます。
- 感染経路
感染した犬の嘔吐物や糞便を介して広がります。ウイルスは長く生存するため、間接的な接触でも感染することがあります。
犬パラインフルエンザウイルス感染症
犬パラインフルエンザウイルスは、単独で発症することは少なく、犬アデノウイルス2型や1型、ボルデテラ、マイコプラズマなどのほかのウイルスや細菌と一緒に感染することで、気管支炎や肺炎、通称:ケンネルコフと呼ばれる呼吸器疾患を引き起こします。
- 感染経路
このウイルスは感染力が強く、感染した犬との直接的な接触や、咳やくしゃみによる飛沫を介して空気感染することがあります。
また子犬の頃からスケジュールにしたがってワクチンを接種することで、感染リスクを大幅に減らすことができます。
犬アデノウイルス2型感染症
犬アデノウイルス2型が原因となる感染症です。このウイルスは単独でも、ほかのウイルスや細菌と複合して感染することがあります。
- 感染経路
感染した犬との接触や、咳やくしゃみなどの飛沫を通じて伝染します。密集した環境で感染が広がりやすい傾向があります。
犬伝染性肝炎
犬伝染性肝炎は、アデノウイルス1型によって引き起こされる感染症で、1歳未満の子犬では致死率が高い病気です。感染すると、腹痛や血が混じる下痢、嘔吐などの重い症状を引き起こし、急性の経過をたどることがあります。
さらに、食欲不振や体の浮腫、角膜が白く濁るブルーアイと呼ばれる目の異常など、さまざまな症状を示す場合があります。一部の犬では無症状のまま感染が進行することもあります。
- 感染経路
このウイルスは、感染した動物の便や唾液を介して伝播し、とても感染力が強いため、周囲の環境を汚染するリスクがあります。
犬コロナウイルス感染症
犬コロナウイルス感染症は、犬コロナウイルスが原因で発症する伝染病です。主な症状には食欲不振、下痢、嘔吐がありますが単独で感染すると1週間程度で回復が見られる疾患で、症状が出ないこともあります。パルボウイルスと同時に感染すると、症状が重篤化し、死亡率が増加します。
- 感染経路
このウイルスは、感染した犬の便や尿を介して環境中に広がり、経口感染することで犬の体内に入り込みます。特に衛生管理が不十分な環境では感染リスクが高まります。
また、定期的なワクチン接種を行うことで、発症リスクを減らすことができます。なかでも子犬は免疫力が弱いため、早めのワクチンプログラムに従うことが推奨されます。さらに、外出先での感染を防ぐために、ほかの犬との接触にも注意を払いましょう。
犬レプトスピラ感染症
レプトスピラ症は、細長いらせん状の細菌スピロヘータが原因で発症する伝染病です。この病気は犬だけでなく、人やほかの動物にも感染する可能性があります。症状には発熱、嘔吐、黄疸、出血傾向があり、重症化すると数日内に死亡することもあります。特定の地域では感染リスクが高く、治療には抗生物質が用いられますが、治療により病原菌が急死し体内に毒素が放出されることで、ショック症状が引き起こされることもあります。
- 感染経路
レプトスピラ菌は主に感染した動物の尿を介して広がります。感染した犬の尿と直接接触することで感染するほか、ネズミの尿も感染源となるため、注意が必要です。特に湿った環境や衛生管理が不十分な場所では感染リスクが高まります。
ワクチンで予防できる猫の病気

ワクチンで予防できる猫の病気について以下で解説します。
猫ウイルス性鼻気管炎
猫ヘルペスウイルスによる感染症は、鼻水、くしゃみ、発熱などの症状を引き起こします。この病気は、人間の風邪に似た症状が現れるため、猫風邪とも呼ばれることがあります。
- 感染経路
感染した猫が使った食器、トイレ、ベッド、タオルなどの物品に触れることで感染する可能性があるようです。また、くしゃみなどによる飛沫を吸い込むことで感染する場合もあります。
猫カリシウイルス感染症
猫カリシウイルス(FCV)による感染症は、鼻水、くしゃみ、発熱などの症状を引き起こします。この病気は猫風邪の一種で、症状が進行すると口内炎や口腔内の潰瘍が見られることがあります。
- 感染経路
猫カリシウイルス感染症は感染力がとても高いようです。感染した猫との直接的な接触が主な感染経路で、感染猫の唾液、鼻水、涙などの分泌物を介してウイルスが広がります。
猫汎白血球減少症
パルボウイルスによる感染症は、激しい嘔吐や下痢などの腸炎症状を引き起こします。この病気では白血球が減少し、免疫力が著しく低下するため、感染した猫は体力を大きく奪われます。なかでも子猫は免疫力や体力が未発達であり、脱水症状を起こしやすいため、命に関わる危険性が高いとされている病気です。
- 感染経路
このウイルスは、排泄物を介して環境中に広がり、自然環境でも長期間生存するという特徴があります。そのため、人間の衣服や靴などに付着して室内に持ち込まれる可能性があり、屋内飼育の猫でも感染リスクがゼロではありません。
猫白血病ウイルス感染症
猫白血病ウイルスによる感染症は、激しい嘔吐や下痢、高熱などの胃腸炎の症状を引き起こします。感染後、ウイルスを体内から排除できた場合は、初期症状のみで回復することがあります。しかし、ウイルスが体内に残った場合、リンパ腫や白血病といった重篤な疾患を引き起こす可能性があるようです。そのため、早期の対策と予防が重要です。
- 感染経路
主に唾液などの分泌物に含まれており、感染した猫とのケンカによる咬傷や、グルーミング、食器の共有を通じて伝播します。
猫免疫不全ウイルス(FIV)感染症
猫免疫不全ウイルス(FIV)感染症、いわゆる猫エイズは、人間のHIVに似た性質を持つウイルスによる病気ですが、猫同士でしか感染しません。
猫免疫不全ウイルス(FIV)感染症は、感染した猫に免疫不全を引き起こし、さまざまな症状を発症させる可能性があります。主な症状としては、発熱、口内炎、下痢、貧血、歯肉炎、リンパ節の腫れ、腫瘍の発生などが挙げられます。ただし、感染していても発症しない猫も多く、必ずしも即座に命に関わるわけではありません。
猫免疫不全ウイルス(FIV)感染症に対する特効薬はありませんが、発症した場合には、症状に応じた対症療法を行います。例えば、感染症を併発した場合は抗生物質で対応し、口内炎や歯肉炎がある場合は口腔ケアが行われることがあります。
また、このウイルスはストレスや免疫力の低下をきっかけに症状を引き起こすことがあるため、日常的にストレスの少ない環境を整えることが重要です。猫がリラックスして過ごせる環境や、バランスの取れた食事、適切な運動の機会を提供することが、健康維持に役立ちます。
- 感染経路
感染経路の多くは、猫同士のけんかによる咬傷が原因となる直接的な伝播です。空気感染の心配はなく、感染力も弱いとされています。
ワクチン接種の副作用
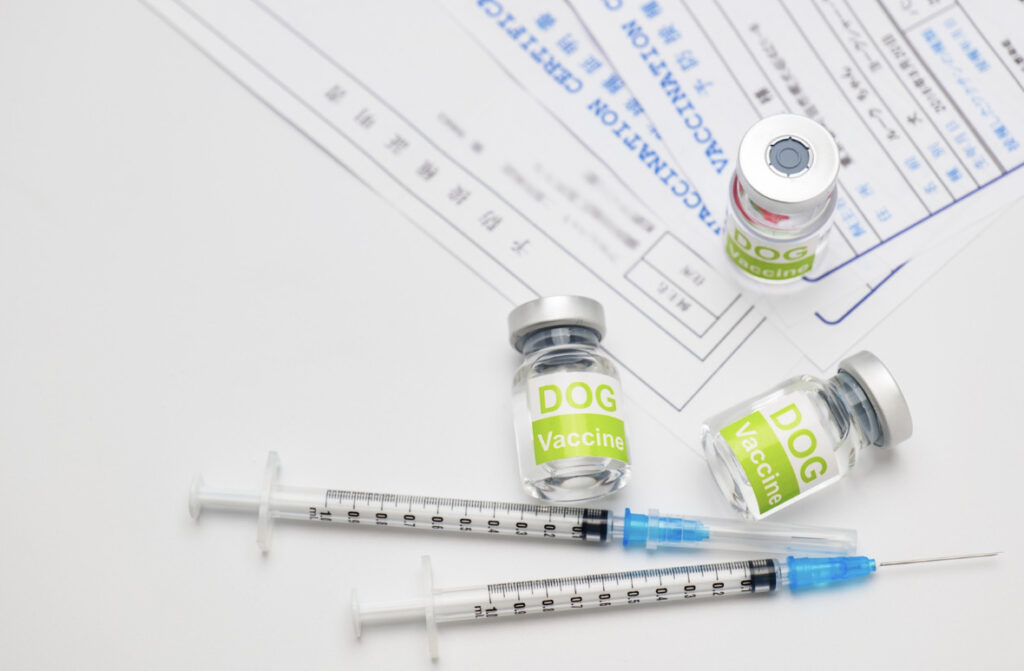
ワクチン接種後には、一時的に副作用が見られることがありますが、ほとんどの場合は軽度で、数日以内に自然に改善を目指します。代表的な症状としては、接種部位の腫れや痛み、発熱、食欲の低下、元気がないなどがあります。これらは通常、特別な治療を必要としないケースが多いようです。
- 軽度な副作用
副作用のなかには、1~2回程度の嘔吐や軽い下痢など、経過観察で問題ないものも含まれます。これらの症状が見られる場合は、落ち着いて愛犬の様子を見守りましょう。
- 注意が必要な症状
より深刻な症状が現れる場合、例えば嘔吐後にぐったりしている、食欲がまったくない、元気が極端に低下しているなどの症状が見られる際は、速やかに動物病院へ連絡してください。放置すると時に命に関わることもあるため、早急に対応することが重要です。
- アレルギー反応
稀にワクチン接種によってアレルギー反応が出ることがあります。その代表例がムーンフェイスと呼ばれる顔の腫れで、特に口や目の周りに腫れが見られることがあります。この症状は多くの場合命に関わるものではありませんが、不安を感じる場合は早めに獣医師に相談しましょう。
ワクチン接種の重要性

ワクチン接種は、犬や猫を感染症から守り、健康を維持するために欠かせない予防策の一つです。ワクチンを接種することで、免疫システムが特定の病原体に対する抵抗力を強化し、病気にかかるリスクを減らすことができます。さらに、病気の重症化を防ぐ効果も期待でき、場合によっては命を救うことにもつながります。
免疫力が未熟な子犬や子猫は感染症に対して脆弱であるため、早期のワクチン接種が重要です。一方、成犬や成猫も免疫力を維持するために定期的な追加接種が推奨されます。
感染症にかかってしまった場合、治療には多大な時間と費用がかかるうえ、動物自身にも大きな負担がかかります。そのため、予防を優先することで、病気のリスクを事前に軽減することが重要です。
また、ワクチン接種は、動物同士の感染を防ぐだけでなく、人間にも感染する狂犬病やレプトスピラ症などの人獣共通感染症の予防にも役立ちます。公衆衛生の維持にも貢献し、人と動物の健康な共生を支える重要な役割を果たすでしょう。
大切な家族であるペットの健康を守るためにも、ワクチン接種のスケジュールを守り、定期的に動物病院で相談することが重要です。予防に力を入れることで、ペットとの幸せな生活を長く続けることができます。
ワクチン接種にかかる費用

ワクチン接種にかかる費用は以下のとおりです。
犬のワクチン接種にかかる費用
犬の健康を守るために必要なワクチン接種は、費用が動物病院や接種するワクチンの種類によって異なります。初年度は免疫力を十分に高めるために3回程度の接種が推奨されており、その後は年に一度の追加接種が一般的です。
【ワクチンの費用目安】
- 2種混合ワクチン:3,000円~5,000円程度
- 7種混合ワクチン以上:7,000円~1万円程度
1回の接種費用はワクチンの種類や病院によって異なりますが、1万円程度が目安となります。多種混合ワクチン程対応できる病気が増えるため、ペットのライフスタイルや感染リスクを考慮し、かかりつけの獣医師と相談のうえ適切なワクチンを選ぶことが大切です。
ワクチン接種は、愛犬の健康を守るだけでなく、感染症の拡大を防ぐ社会的な役割も果たします。そのため、費用を含めた定期的な接種計画を立てて、安心して愛犬と過ごせる環境を整えましょう。
猫のワクチン接種にかかる費用
猫のワクチン接種費用は、動物病院や選ぶワクチンの種類によって異なります。
猫のワクチンは、大きく2種類に分けられます。一つは、すべての猫に接種が推奨されるコアワクチン、もう一つは猫の生活環境やライフスタイルに応じて必要に応じて接種するノンコアワクチンです。
それぞれのワクチンの選択は、かかりつけの獣医師と相談しながら適切に進めることが重要です。
【ワクチンの費用目安】
- 3種混合ワクチン:3,000~5,000円程度
- 5種混合ワクチンは5,000~8,000円程度
病院によっては診察料が追加される場合もあるため、事前に確認するとよいでしょう。
犬の鑑札と注射済票とは

犬を飼う際には、鑑札と注射済票を装着することが法律で義務付けられています。これらは狂犬病予防法に基づいた重要な標識であり、犬の安全と公衆衛生を守るために必要なものです。
また、以下のような役割があります。
- 登録された犬であることの証明
- 狂犬病予防注射の証明
- 迷子犬の身元確認
これらの標識は、犬の安全を守り、地域社会での適切な飼育を助けるために大切です。必ず鑑札と注射済票を装着するようにしましょう。
まとめ

ここまで動物病院で接種できるワクチンについてお伝えしてきました。動物病院で接種できるワクチンの要点をまとめると以下のとおりです。
- ワクチンは、感染症からペットを守るために開発された重要な予防手段である
- ワクチン接種を接種した後は、一時的に副作用が見られることがある。ほとんどの場合、軽度で数日以内に自然に改善される
- 犬ジステンパーは、ジステンパーウイルスが原因で引き起こされる、犬にとって深刻な感染症である。また、猫白血病ウイルスによる感染症は、激しい嘔吐や下痢、高熱などの胃腸炎の症状を引き起す可能性がある
ワクチン接種は、大切なペットの健康を守り、感染症を予防するために欠かせない取り組みです。
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


