蓄膿症は人間だけでなく猫にも起こりうる病気です。猫がくしゃみや鼻水を長引かせていると、「ただの風邪かな?」と様子を見てしまいがちですが、放置すると副鼻腔に膿がたまる蓄膿症に進行するケースもあります。蓄膿症になると鼻づまりがひどくなり、呼吸や食事にも支障をきたすため、早期発見と適切な対処が重要です。この記事では猫の蓄膿症とはどのような病気か、具体的な症状や原因、検査・治療方法、自宅ケアのポイントを詳しく解説します。
猫の蓄膿症とは?

猫の蓄膿症とは、副鼻腔炎(副鼻腔の粘膜の炎症)が悪化して副鼻腔内に膿がたまった状態を指します。猫の鼻腔は鼻の奥で骨に囲まれた副鼻腔という空洞とつながっており、通常は空気の通り道です。しかし、風邪などで鼻炎(鼻粘膜の炎症)が長引いて慢性化すると炎症が副鼻腔まで広がり、副鼻腔炎を起こすことがあります。この副鼻腔炎が重症化して膿性の鼻汁が蓄積した状態が蓄膿症です。人間の蓄膿症と同様、猫にとっても鼻が詰まって息苦しく、食べ物の匂いも感じにくくなる辛い病気です。
猫の蓄膿症でみられる症状と行動の特徴

蓄膿症に陥った猫には、鼻や呼吸に関するさまざまな症状が現れます。愛猫に以下のような症状や普段と違う様子がみられたら要注意です。それぞれの症状や特徴を詳しく見てみましょう。
鼻水やくしゃみが続く
蓄膿症の初期には粘り気のある鼻水や頻繁なくしゃみがみられます。鼻水は透明な水様から始まり、感染が進むと白〜黄色く濁った膿混じりの粘液性になります。くしゃみがひどく、何度も続くこともあります。膿や血が混じる鼻汁が出る場合もあり、特に膿性の鼻汁が長期間続くようなら蓄膿症の可能性があるため注意が必要です。
鼻詰まりや呼吸音の異常がある
膿や粘液で鼻が詰まるのも蓄膿症の典型的な症状です。鼻腔が塞がれることで空気の通り道が狭くなり、呼吸が苦しそうに見えたり「ズビズビ」「フガフガ」といった異常な呼吸音が聞こえたりすることもあります。特に、睡眠時にぐーぐーといびきをかいたり、起きているときも鼻息が荒かったりする場合は、鼻の通りが悪くなっているサインです。
口呼吸やいびきがみられる
鼻づまりが重度になると、猫は口で呼吸をし始めます。通常、猫は暑いとき以外口呼吸をしないため、口を開けてハアハアしているのは重い鼻づまりや呼吸困難のサインです。また、睡眠中にも鼻で息ができず口呼吸になり、いびきや鼻を鳴らすような音を立てることがあります。
顔や目の周りが腫れている
蓄膿症が進行し炎症が強くなると、鼻筋から目の下あたりの顔面が腫れる場合があります。副鼻腔内に膿が溜まり圧力が高まったり、炎症が周囲組織に波及したりすることで鼻すじから額にかけて熱感を伴う腫れが生じることがあるのです。見た目にも左右どちらかの鼻梁部が膨らんだり、目の周囲が腫れて涙や目ヤニが増えたりすることがあります。
食欲や元気がない
鼻の病気は猫の食欲や活力の低下にも直結します。猫は嗅覚で食べ物のおいしさを感じる動物なので、鼻が詰まって匂いを感じられないと食欲が落ちてしまいます。蓄膿症では鼻炎よりも強い鼻づまりと全身炎症が起こるため、ご飯に見向きもしなくなったり、水もあまり飲まなくなったりすることが少なくありません。
猫が蓄膿症になる原因
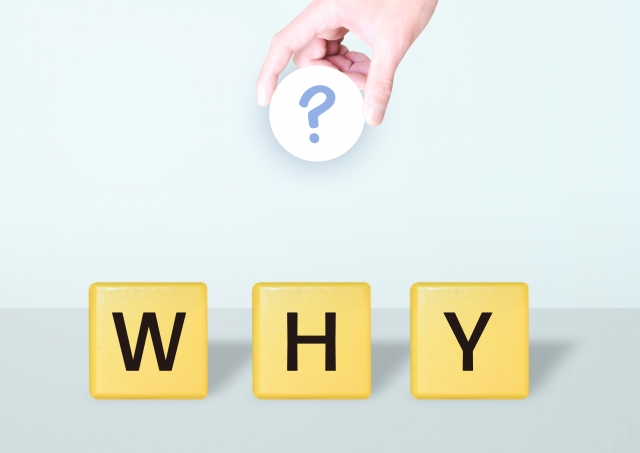
猫の蓄膿症は、さまざまな要因で起こる鼻炎が引き金となり、その炎症が長引いて副鼻腔に波及することで発症します。本章では、主な要因を解説します。
感染症
ウイルス、細菌、真菌(カビ)といった感染症は猫の鼻炎・副鼻腔炎の原因となります。ウイルス感染後、傷ついた粘膜に二次感染した細菌が慢性炎症を悪化させ、膿を伴う副鼻腔炎へ進行しやすくなります。真菌ではクリプトコッカス症(Cryptococcus neoformans)が猫の慢性鼻炎の原因として知られ、重度の場合に蓄膿症を起こすことがあります。また、喧嘩による顔面創傷が契機となり、副鼻腔炎を発症することもあります。
鼻咽頭狭窄
鼻咽頭狭窄は、鼻の奥の喉につながる部分(鼻咽頭)が狭くなる病気です。先天性と後天性があり、いずれの場合も鼻汁やくしゃみはあまりみられず、呼吸時に音がすることが主な症状です。そして、鼻咽頭狭窄があると、蓄膿症を起こすことが知られています。
慢性鼻炎
慢性鼻炎そのものも蓄膿症の直接の原因になります。上述のとおり、ウイルス性鼻炎などが長引いて慢性化すると副鼻腔まで炎症が広がりやすく、蓄膿症へ移行します。慢性鼻炎がある猫は、寒暖差やちょっとした刺激ですぐ鼻水・くしゃみがぶり返し、副鼻腔炎を併発することがあります。
アレルギー
アレルギーによって鼻炎・副鼻腔炎が起こることもあります。人と同じく猫も花粉、ハウスダスト、カビ、香料などにアレルギー反応を示すことがあります。季節的に花粉の多い時期だけ症状が出る猫もいれば、一年中室内アレルゲンに反応して慢性的な鼻炎になる猫もいます。
歯科疾患
意外かもしれませんが、歯の病気が原因で鼻炎・蓄膿症が起こるケースもあります。特に上顎の犬歯(牙)や前臼歯の歯根部が感染を起こすと、その炎症が鼻腔や副鼻腔に波及することがあります。猫は上顎の歯の根が鼻腔と近接しているため、歯周病や歯根膿瘍(歯の根元の化膿)が副鼻腔炎を引き起こすことがあるのです。
猫の蓄膿症の検査と治療

猫が蓄膿症と疑われる場合、動物病院では原因の特定と症状緩和のためのさまざまな検査・治療が行われます。ここでは一般的な検査方法と治療の流れについて説明します。
猫の蓄膿症の検査方法
鼻水や鼻づまりなどから、蓄膿症と疑われた場合の検査方法は下記のとおりです。
- 問診と身体検査
まず獣医師は飼い主さんから猫の症状の経過(いつから鼻水が出ているか、くしゃみの頻度、食欲の変化、猫免疫不全ウイルス、猫白血病ウイルスといった基礎疾患があるかなど)を詳しく聞き取ります。併せて猫の顔や鼻周りを触診し、顔面の腫れや痛み、左右の鼻の通り具合を確認します。 - 画像検査(レントゲン・CT/MRI)
次に頭部のレントゲン撮影を行い、鼻腔や副鼻腔、歯の根に異常がないかを調べます。レントゲンでは副鼻腔内の膿や腫瘍の有無、鼻甲介(鼻腔内のヒダ状構造)の破壊状況などをある程度把握できます。ただし、細かな変化は映らないことも多いため、必要に応じてCTやMRI検査が実施されることもあります。 - 鼻汁の検査・培養
鼻水が大量に出ている場合は、鼻汁を採取しての検査も行われます。顕微鏡で細胞を調べて感染か腫瘍かの判断材料にしたり、細菌培養検査と薬剤感受性試験を実施したりして原因菌と有効な抗生剤を特定することもあります。 - 血液検査とウイルス検査
全身状態の評価やほかの病気の有無を確認するために血液検査も行われます。感染症の場合、白血球の増加や炎症反応(CRP)の上昇が見られることがあります。また必要に応じて原因となりうるウイルスの検査をします。 - 内視鏡検査
鼻腔内の内視鏡検査(リノスコープ)が行われることもあります。小さなカメラを鼻孔から挿入し、鼻腔や副鼻腔内部を直接観察します。これによりポリープや腫瘍、異物の有無を確認でき、必要に応じて生検(組織の一部を採取して検査)も可能です。
猫の蓄膿症の治療方法
蓄膿症の治療は原因に応じた根本治療と症状を和らげる対症療法を組み合わせて行います。基本的には内科的な薬物療法から始め、必要に応じて副鼻腔の洗浄や外科手術も検討されます。本章では主な治療方法について解説します。
- 薬物療法
蓄膿症に対する第一の治療は薬物療法です。原因が感染症の場合、適切な抗生剤や抗真菌薬、抗ウイルス薬が選択されます。また、炎症と粘膜腫脹を抑えるための抗炎症剤(非ステロイドやステロイド)も症状に応じて併用されます。アレルギー性の場合は抗ヒスタミン薬やステロイドでアレルギー反応を鎮めます。 - 副鼻腔の洗浄
膿が溜まりきった蓄膿症では、薬だけではなかなか排膿できず改善が遅れる場合があります。その際に有効なのが副鼻腔あるいは鼻腔内の洗浄です。具体的には、鼻孔から生理食塩水を大量に流し込み、副鼻腔内の膿や粘液を物理的に洗い流す処置を行います。この処置により鼻腔・副鼻腔内に詰まった膿を可能な限り除去することで、呼吸が通りやすくなります。直接、腔内に投与するなどの方法も併用すると薬剤が患部に届きやすくなります。 - 歯科治療
歯の病気が原因で蓄膿症を起こしている場合、根本的な治療には原因歯の処置が欠かせません。具体的には、感染した歯の抜歯や歯周ポケットの徹底洗浄、膿瘍のドレナージなどを行います。歯を治療してしまえば、鼻への炎症刺激がなくなるため鼻水やくしゃみの症状も徐々に改善します。 - 手術療法
蓄膿症の治療で外科手術が検討されるのは、主に内科治療で改善しない場合や腫瘍やポリープ、鼻咽頭狭窄など外科的異常が原因の場合です。例えば、鼻腔内や副鼻腔内に腫瘍やポリープが見つかった場合、それを摘出する手術が必要になります。鼻咽頭狭窄であれば内視鏡を使い拡張術を行うことや、良性の鼻ポリープであれば内視鏡下や外科的に除去することで鼻づまり症状が改善します。
蓄膿症の猫を自宅でケアするときのポイント

蓄膿症と診断された猫の治療は動物病院で行いますが、自宅でのケアも回復を早めるうえでとても重要です。以下に、蓄膿症の猫をお世話する際に飼い主さんが気をつけたいポイントを挙げます。
室温と湿度を管理する
適切な温度と湿度の環境作りは、鼻づまりの猫にとって重要です。部屋の空気が乾燥していると鼻粘膜がさらに乾いて鼻汁が固まりやすくなるため、加湿器などで湿度を40〜60%程度に保つようにしましょう。湿度を上げることで鼻汁がやわらかくなり、膿性の鼻汁も排出されやすくなります。また冬場など気温が低いときは室温をやや高めに保ち、猫の身体を冷やさないことも大切です。
鼻を清潔に保ち、乾燥を防ぐ
鼻から膿や鼻水が出ている場合、こまめに拭いて清潔に保つことも重要です。湿らせたやわらかいガーゼやコットンで鼻の周りについた鼻汁や汚れを優しく拭き取りましょう。こうすることで鼻孔が塞がるのを防ぎ、呼吸を助けます。乾いて固まった鼻くそや膿は、ぬるま湯で湿らせたタオルを鼻先に当ててふやかしてから拭うと取りやすくなります。
小まめに水分補給を促す
蓄膿症で鼻水が大量に出ている猫は、気付かないうちに脱水気味になっていることがあります。鼻汁として水分が失われるうえ、食欲低下で水をあまり飲まなくなるためです。そこで意識的に水分補給を促す工夫をしましょう。まず新鮮な水をいつでも飲めるよう数カ所に用意し、猫が好む器で与えます。加えて、ウェットフードやスープ仕立ての食事を与えて食事から水分を取らせる方法もあります。このように、水分を十分に取ることで粘膜の潤いが保たれ、鼻汁も出やすくなります。
環境によるストレスを減らす
ストレスの軽減も蓄膿症からの回復を助けます。治療中は猫が静かで安心できる環境で過ごせるよう配慮しましょう。例えば、療養部屋は人やほかのペットの出入りが少ない静かな場所にします。トイレや水も近くに置き、すぐ利用できるようにします。小さな子どもがいるご家庭ではなるべく干渉させないようにし、猫が休んでいるときはそっとしておいてあげましょう。猫は繊細で環境の変化に敏感な動物です。療養中はスキンシップもほどほどに、愛猫のペースで休ませてあげてください。
猫が蓄膿症で食欲がないときの対処法

蓄膿症になると嗅覚の低下から食欲不振に陥る猫が多いです。しかし、長期間食べないと命に関わるため、食欲減退時のケアは極めて重要です。猫ちゃんが蓄膿症でご飯を食べないとき、以下のような対処法を試してみましょう。
食事の出し方を工夫する
まずは食欲を刺激するような工夫で食べてもらう努力をします。猫の食欲は匂いで引き出されるため、嗅覚が鈍っていても感じやすい強い香りの食べ物を用意すると効果的です。例えば、温めたウェットフードや出汁の効いたスープ状のフードは香りが立ち、鼻づまりの猫でも興味を示すことがあります。鼻が完全に詰まっている子には、口元にご飯を持っていって匂いを嗅がせる、あるいは指に載せて舐めさせるといった工夫も有効でしょう。それでも食が進まない場合、一度にたくさん食べさせようとせず少量を頻回に与えてみましょう。食欲が戻るまで忍耐強くいろいろと試して、猫が「これなら食べたい」と思う形態・温度の食事を探してみてください。
水分補給を促す
食事が摂れないときは水分から栄養とエネルギーを補うことも考えましょう。前述のようにウェットフードやスープ状のものを与えるのは水分補給にも役立ちます。加えて、ペースト状や液体の栄養補助食を活用するのもよい方法です。
困ったら獣医師へ相談する
自宅でさまざまな工夫をしてもまったく食べない・飲まない状態が24時間以上続く場合は、迷わず獣医師に相談してください。動物病院では、食欲増進剤の注射や点滴による栄養補給、必要ならチューブフィーディング(経鼻カテーテルや食道チューブで流動食を入れる)といった栄養管理を行ってくれます。また、鼻づまりそのものを解消するための処置を追加で実施し、猫が自力で食べられる状態に戻すサポートもしてくれるでしょう。
まとめ
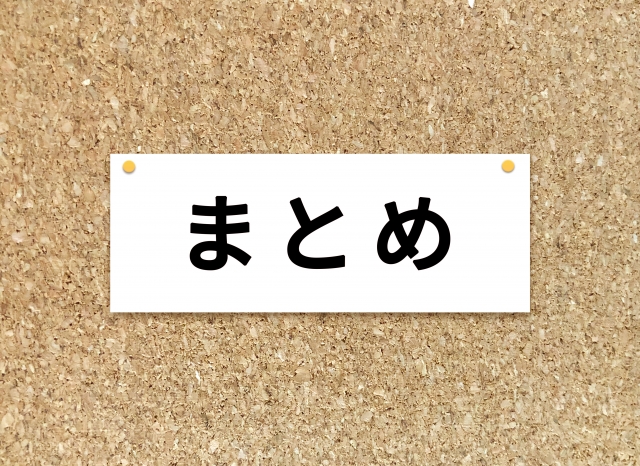
猫の蓄膿症は、鼻炎が悪化して副鼻腔に膿が溜まった状態であり、くしゃみや鼻水、鼻づまり、口呼吸、顔面の腫れ、食欲不振などさまざまな症状を引き起こします。主な原因はウイルス・細菌・真菌感染を中心に、鼻咽頭狭窄、慢性的な炎症、アレルギー、歯の疾患など多岐にわたります。
診断には身体検査や画像検査、培養検査などが用いられ、適切な治療方針決定のため原因の特定が重要です。治療は抗生剤・抗ウイルス薬・抗真菌薬などによる内科療法が基本で、必要に応じて副鼻腔洗浄や外科手術、原因歯の抜歯なども行われます。
自宅では室温湿度の管理や鼻腔ケア、水分摂取の工夫、ストレス軽減など飼い主さんによるサポートが回復を促します。特に、食欲が落ちた際は匂いの強い食事を与えるなど工夫し、それでも食べないときは早めに獣医師に相談しましょう。猫の蓄膿症は完治に時間がかかることもありますが、早期発見・治療と適切なケアによって症状をコントロールし、猫の生活の質(QOL)を維持することが可能です。日頃から愛猫の鼻の状態や元気・食欲の変化をよく観察し、少しでも異常を感じたら早めに受診してあげてください。
参考文献


