人間にとっても辛いといわれている膀胱炎は、猫にも起こる病気の一つです。膀胱炎を発病する原因はいくつかありますが、おもに生活環境や飼い主との関係性からのストレスが強く影響するといわれています。放置すると、重症化するため早期治療が必要です。
こちらの記事では、猫の膀胱炎につながるストレス要因についてお伝えしたうえで、症状、治療の流れ、飼い主ができる部分について解説します。大切なペットが健康に過ごせるよう、ぜひ参考にしてみてください。
猫の膀胱炎につながるストレス要因

猫は、とても繊細な性格をしています。日常のストレスが膀胱に負担を与えて病気につながる場合もあるため、飼い主は、猫にとって安心できる環境づくりを心がけなければなりません。ここでは、猫がストレスを感じやすい要因について解説します。
生活環境の変化
猫は、ほかの動物と比べて縄張り意識が強く、行動範囲が狭いといわれており、引っ越しや通院など環境の変化に強いストレスを感じやすいです。
自然界で生きる肉食動物は獲物を捕まえるために数十キロ移動、草食動物は植物を食べるために数百キロ移動するといわれています。一方の猫は、メスは生まれた場所から600m以内、オスは自分のテリトリーを見つけたら200m以内が拠点といわれています。例外的に、500m程度の移動もあるそうですが、ほかの動物と比較すると、いかに猫の活動範囲が狭いかがわかるでしょう。
さまざまな理由で引っ越しが必要になる場合は、猫にとって大きなストレスになるのを理解しておきましょう。自分の匂いがついた毛布やトイレ砂を持っていくと、ストレス緩和に効果的です。
運動不足
猫は、獲物を狩るために無駄な体力を消耗しないように寝ている時間が長いですが、狩猟本能があるので、動くのが大好きな動物です。
「いつも寝ているから大丈夫だろう」と狭い部屋やゲージの中で飼育すると、猫にはストレスになってしまいます。猫を飼っていると、突然家の中を猛スピードで走り回る様子を見かける機会はあるでしょう。若い猫によく見られる症状で、真空行動と呼ばれています。真空行動は、狩りのために蓄えたエネルギーを一気に発散できストレスを解消する行動です。
猫が自由に動き回れるような広い部屋を用意してあげるのが適切ですが、難しい場合は、キャットタワーなどで猫が遊べる遊具を設置してあげましょう。
愛情不足
家猫として生まれ育った猫は、飼い主への依存や愛情が深くなります。
一匹でたくましく生きている野良猫を見ていると、「猫は自立心が強くて、一匹でも寂しさを感じないのだろう」と考える方もいるでしょう。しかし、人間に育てられた猫は、いつまでも子猫のように甘えん坊な性格になりやすいです。その結果、飼い主から撫でてもらえなかったり、要求を無視されたりすると、不安からトイレに行く頻度が減って、膀胱炎につながります。
仕事が忙しくて家で過ごす時間が少なくなってしまう時期でも、一緒にいられる時間は撫でたりおもちゃで遊んだり積極的にコミュニケーションをとるようにしましょう。
多頭飼育や周囲の刺激
猫は、縄張り意識や警戒心が強い生き物なので、ほかの猫や動物との共同生活はストレスになる可能性があります。
「仕事の時間を一匹で過ごすのは寂しいだろう」と考える飼い主もいますが、必ずしもすべての猫が多頭飼いに向いているとは限りません。もしも相性の悪い猫と一緒に暮らさなければならない場合、狭いところに隠れたまま出てこなくなるでしょう。そうなると、自由にトイレにも行けなくなるので、膀胱炎につながりやすいです。また、電車や人どおりなど周囲の刺激を感じやすい物件も猫が隠れてしまう原因になりやすいです。
猫の膀胱炎でみられる主な症状
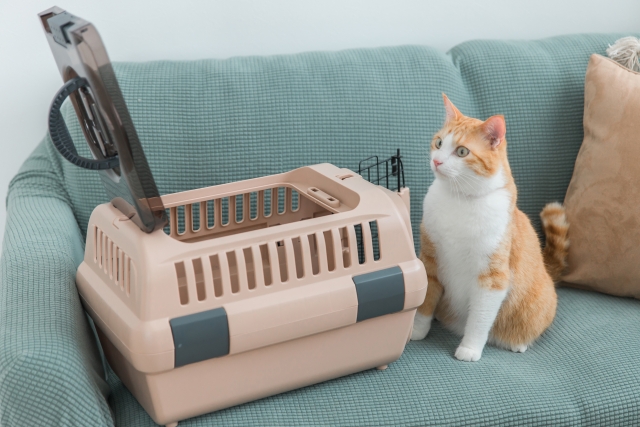
猫の膀胱炎は、再発しやすく、放置すると重症化して命に関わります。しかし、食欲不振やぐったりするなどわかりやすい症状が少ないため、発病している状態に気付くのが遅くなりがちです。ここでは、猫の膀胱炎でみられる主な症状について解説します。
排尿回数が増える、または少量頻回の排尿
まず、膀胱炎の症状として頻尿の状態が挙げられます。1回の尿の量が少なくなる代わりに、1日に何回もトイレに行く猫は、膀胱炎の可能性が高いです。しつけをしなくてもトイレで排尿できる猫がほとんどですが、膀胱炎になると、トイレ以外の場所で排泄したり、尿失禁(尿が垂れてしまう状態)になったりします。
一方で、半日以上トイレに行かない猫も要注意です。オス猫は、メス猫よりも尿道が細いため、結晶や結石が詰まると排尿できなくなります。排尿したくてもできない状態の猫は、陰部を舐めたりソワソワした様子になる傾向があるので、猫の様子が普段と違うときは、トイレの頻度を確認しましょう。
血尿や排尿時の痛み
また、膀胱炎になっている猫の尿をみると、匂いがキツかったり、白く濁る、ピンクや血の混じった色をしている場合があります。また、猫の結石は人間のように大きくなくて、細かい結晶のようになっているため、キラキラ光ってみえる場合もあります。
また、排尿時に痛みがあると大きな声で鳴く猫もいます。もともと猫は、体調不良を隠そうとする習性があるため、普段聞かないような声で鳴いているときは、痛みがでていると考えてよいでしょう。
猫の膀胱炎治療の流れ

特効薬や根本的な治療法がない猫の病気もありますが、猫の膀胱炎は治療可能です。ただし、再発しやすい特徴があるため、異常を感じたらすぐに動物病院を受診して、症状が軽いうちに治療を始められるようにしましょう。ここでは、猫の膀胱炎治療の流れについて解説します。
問診や尿・血液検査で原因を特定
猫の膀胱炎治療をするためには、膀胱炎の原因を特定します。猫の膀胱炎は、大きく二つに分けられます。
動物病院では、膀胱炎を発病した根本的な原因を特定するために、問診でストレスの可能性、触診と尿検査で、pH数、細菌や結晶の有無を調べます。検査結果によって、尿路結石の可能性があれば超音波検査やレントゲン検査、腎臓トラブルの可能性があれば血液検査をあわせて実施し、より具体的な原因特定を行ないます。
膀胱炎になったと思い診察を受けたところ、尿石症だったケースもあるため、猫の状態を適切に把握するためにも、動物病院の受診が重要です。
生活環境の見直し
特発性膀胱炎の場合、抗菌薬を投与しても症状が緩和するとは限りません。なぜなら、特発性膀胱炎の原因の大半は、原因不明なことが多いからです。
そのため、問診や検査で細菌が確認されずに特発性膀胱炎と診断されたら、医師の指導のもとで生活環境の見直しが必要です。具体的には、膀胱炎を改善する効果のあるフードを与える、水飲み場の数を増やす、トイレを清潔にする、飼い主と過ごす時間を増やすなどが挙げられます。問診の中で、猫がストレスを感じているであろう要因を洗い出して、膀胱炎の症状を改善するために対処します。
投薬治療・食事療法
細菌性膀胱炎の場合、抗菌薬の投与が効果的です。猫の膀胱は無菌状態のはずですが、何かしらの原因で菌が繁殖していると膀胱炎を発病します。そのため、検査によって細菌が発見されたら、薬を使った治療で細菌の増殖を抑えられます。
ここで重要なポイントは、途中で投薬をやめない点です。抗菌薬を飲み始めると、痛みや出血などの症状が改善されますが、完治したわけではありません。膀胱内の細菌が完全に死滅するまで投薬を続けなければ、再発の原因になりえます。もし、猫が投薬を強く拒絶する場合、注射でも治療可能ですので、担当医に相談してみましょう。
猫のストレスを軽減するためにできる工夫

猫は繊細でストレスを溜めると膀胱炎を発病する恐れもあるとわかったところで、飼い主が飼い猫のために今日からできる工夫は、なにがあるのでしょうか。ここでは、猫のストレスを軽減するためにできる工夫について解説します。
静かな環境を整えて刺激を減らす
狩猟動物である猫は、獲物を狙うために小さな音を聞き分けられるだけの繊細な聴力を持っているので、大きな音が苦手です。特に、野良猫を家族として迎え入れたのであれば、過去に聞いた身の危険を感じるような音、突然響く大きな音に不安を感じてストレスを感じてしまいます。
猫は、子猫の鳴き声のように高音域の音を好む一方で、男性の低い声、ドライヤーや掃除機などの大きな音、金属音、鈴、くしゃみ音などは、不安を感じやすいです。猫の首輪に鈴をつける家庭もいますが、動くたびに耳のそばで大きくチリンチリンと鳴っていると、ストレスを溜める猫もいるので音は控えめなものを選んであげましょう。
猫と過ごす家選びでは、できるだけ静かな地域を選び、大きな音が出ないような生活を心がけましょう。
高い場所を用意する
猫は、自分のテリトリーが見渡せて、外敵から狙われる恐れがない点から、高いところを好みます。そのため、ロフトのついている物件を選んだり、キャットタワーやキャットウォークなどを設置したりすると、猫にとってストレスの少ない環境になります。
本能的に高いところを猫は好み、家のなかでもタンスや机など高いところに行きたがる習性を目にする飼い主はいるでしょう。キャットタワーやキャットウォークの組み立て方が中途半端だと、猫が飛び乗った衝撃で壊れてしまう恐れがあります。安全性の高い製品を購入し、万が一に備えて床にはカーペットなどを引いておくとケガのリスクを防げます。
スキンシップを取る
人間に育てられた猫は、いつまでも子猫のように甘える性格になるケースがあります。猫は、人間と同様にスキンシップをとるとオキシトシンと呼ばれる安心感や愛情を感じられるホルモンが分泌されます。そのため、猫が鳴いたり擦り寄ったりしてきたときは、その要望にしっかりと応えてあげましょう。
猫が好む体の部分を撫でるほかにも、おもちゃで一緒に遊ぶ、ブラッシングや抱っこなどコミュニケーションの取り方はさまざまです。なお、身体を触られるのを極端に嫌がる猫もいるので、適切な距離感を保てると、猫のストレスを軽減させられます。
休憩できる場所を用意する
猫は、恐怖や不安を感じた際に、身を隠せる場所があると安心できます。実際、家族に懐いていても友人や近所の人が来ると、公然と姿を消す場合があります。
身を隠して休息できる場所は、暗く、狭く、静かであるのが理想的で、さらに高いところに隠れるスペースを用意できれば、猫にとって安心できる家になるでしょう。猫は、自分でスペースを見つけて隠れるのがうまいので、ベッドの下やタンスの裏などを自分だけの空間とする場面があります。ただし、ホコリが溜まっているとハウスダストによって病気になる恐れがあるので、猫の好みの場所が決まっているのであれば、定期的に掃除をして清潔に保つようにしてください。
膀胱炎を防ぐためにできる日常ケア

猫の膀胱炎を未然に防ぐため、そして再発しやすい膀胱炎を繰り返さないために、飼い主がしてあげられるなにかはあるのでしょうか。ここでは、膀胱炎を防ぐためにできる日常ケアについて解説します。
給水器などを設置して水分を摂取しやすくする
膀胱炎は、尿を一時的に溜める部分に細菌が増殖している状態のため、水分摂取の量を増やすと、尿が希釈され膀胱内の細菌が尿とともに排出されやすくなります。これにより、細菌が膀胱内で停滞・繁殖するリスクが低下します。
もしも、飼っている猫が水を飲みたがらない場合は、水が常に流れている状態の給水機がおすすめです。猫は、動いているものに興味関心を抱く傾向にあるので、水が流れているだけで水分摂取量が増える場合があります。また、給水機を工夫しても水を飲む量が増えない猫に対しては、ウェットフードを与えると最低限の水分を摂取させられます。
快適な排泄環境を整える
膀胱炎は、トイレに行きたがらない猫が発病しやすいです。トイレを苦手とする理由は、いくつか考えられますが、一番の理由は汚れによるものです。きれい好きな猫は、汚いトイレでは排泄を我慢する場面があるので、毎日きれいに掃除して、定期的にトイレシートと猫砂を変えましょう。また、多頭飼いしている家では、一匹に対して一つのトイレを用意するのが理想です。
寒い季節は、飲水量が減るため、トイレに行く回数が減りがちです。冬場にトイレの頻度が少ないと感じたら、飲水量が少ない可能性があるので、暖房の効いた部屋にお水やトイレを設置するなどの工夫をしましょう。
定期的な健康診断で早期発見を心がける
猫の膀胱炎は、定期的な健康診断で早期発見が可能です。猫の排尿の一部をスポイトで採取して、動物病院に持ち込むと、顕微鏡で細菌や結晶の有無、潜血、pH、尿糖、尿比重などを調べてもらえます。特発性膀胱炎のほか、尿路結石や腎臓病など命に関わる病気の可能性をチェックしてもらえるため、早期治療につながります。
尿検査の時点では、猫が動物病院に来院する必要がなく、通院ストレスもありません。すべての動物病院が膀胱炎の定期検査を受け付けているとは限らないので、気になる方はかかりつけの動物病院に相談してみましょう。
まとめ

こちらの記事では、猫が膀胱炎になるストレスの要因をお伝えしたうえで、症状や治療方法、予防策について解説しました。猫の膀胱炎は、生活習慣の変化や飼い主からの愛情不足でも発病する可能性があるので、トイレの頻度が増えたり、血尿などの症状が見られた際には、動物病院を受診すると同時に生活習慣の見直しが必要です。なお、猫の膀胱炎は治療すれば治りますが、再発しやすい特徴があるので、水飲み場やトイレ環境を整えてあげて、長く健康で過ごせるように工夫しましょう。


