猫の耳に触れるとひんやり冷たく感じることがあります。飼い主さんはそれを感じて「うちの子に何か異常があるのでは?」と心配になるかもしれません。しかし、猫の耳が冷たいことは必ずしも病気のサインではありません。この記事では、猫の耳が冷たく感じられる場合に考えられる健康上の異常や病気について詳しく解説します。
猫の耳を冷たく感じるのは異常のサイン?

ふと猫の耳に触ったときに冷たく感じると、「体調が悪いのではないか」と心配になりますよね。この章では、猫の耳の適正な温度や、普段猫の耳が冷たくない(むしろ温かい)と感じる場合の理由について説明します。猫の耳が冷たいことが正常なのか異常なのかを理解し、過度に心配しすぎないようにしましょう。
猫の耳の適正温度
まず知っておきたいのは、猫の平熱(体温)です。一般的に成猫の平熱は約38度といわれています。人より少し高めなので、抱っこすると暖かく感じるほどです。ただし身体の表面の温度はそれより低く、被毛で覆われた身体の部分では触っても温度がわかりにくいでしょう。
一方で、耳は被毛が薄く毛細血管が集まる部分なので、体内の熱を放散しやすい構造をしています。そのため、健康な猫でも耳を触るとひんやりと冷たく感じるのが正常です。猫は汗をかいて体温調節をするのが得意ではなく、人のように全身で汗をかけません。その代わりに耳や肉球から熱を逃がして体温を調整しています。
つまり、猫の耳が冷たいこと自体は、体内の余分な熱を逃がして快適に過ごせている証拠ともいえるのです。環境温度にもよりますが、リラックスしている猫の耳は適度に冷えているのが普通であり、耳が冷たいだけでただちに異常と考える必要はありません。
猫の耳が冷たくない理由
では反対に、猫の耳があまり冷たくなく、温かく感じる場合はどのような理由があるのでしょうか。先述のとおり、本来猫の耳は放熱のために冷えやすい部分ですが、状況によっては耳が熱く感じられることもあります。例えば、運動や遊びに夢中になって興奮しているとき、一時的に体温が上がって耳まで熱くなることがあります。また、ウトウトと眠いときや日向ぼっこをした後なども血行が良くなり耳が温かく感じられることがあります。
環境的に気温が高い夏場などは、体内の熱を逃がすため耳の血管が拡張し、耳が普段以上に熱く感じられるでしょう。
しかし注意が必要なのは、猫の耳が熱い場合です。耳が熱いということは耳に集まった毛細血管が拡張し、身体に余分な熱がこもっている状態を示します。この原因としては、発熱や熱中症などの可能性があります。もし猫の耳が明らかに熱く感じ、なおかつ元気や食欲がない、ぐったりしている、呼吸が荒いといった症状を伴う場合には注意しましょう。
平熱より高い発熱状態や暑さによる熱中症かもしれません。いずれにせよ、耳の温度だけで判断せず体温計で実際の体温を測って確認することが大切です。普段から愛猫の耳を触っていつもの温度を知っておくと、冷たすぎる・熱すぎると感じたときに異常に気付きやすくなります。
猫の両耳が冷たいときに考えられる病気

両方の耳を触ってみてどちらも冷たいと感じ、さらに体全体や足先まで冷たくなっている場合、猫の体温が低下している可能性があります。猫の平熱は約38度ですので、それより明らかに身体が冷えている場合は何らかの異常が起きているかもしれません。この章では、猫の両耳が冷たいときに考えられる代表的な病気について説明します。
低体温症
両耳だけでなく全身がひどく冷えているとき、まず疑われるのは低体温症です。低体温症とは体温が通常よりも大きく下回った状態のことで、猫ではおおむね体温が37度以下になった場合に低体温と判断されます。健康な猫が普通に生活するなかで低体温症になることは滅多にありませんが、極端に寒い環境に長くいた場合や、身体が濡れたまま長時間過ごした場合などには低体温症を起こす可能性があります。特に子猫や老猫は自力で体温を保つ力が弱いため、低体温症に陥りやすい傾向があります。
低体温症になると、猫は震えたり、元気がなくなり動かなくなります。さらには、徐々に呼吸や心拍数が遅くなり、意識がもうろうとしてしまうこともあります。耳や四肢など末端の部位から体温が失われ、触ると氷のように冷たく感じるでしょう。低体温の状態をそのまま放置すると、身体の働きがさらに弱まり命に関わる危険もあります。
腎臓系の病気
高齢の猫で両耳が冷たく感じられる場合、腎臓の病気も考えられます。腎臓は体内の老廃物を尿として排泄する重要な臓器ですが、その機能が低下する慢性腎臓病になると全身の状態にさまざまな影響が出ます。その一つに体温の低下があります。
実際、腎臓病の猫では体温が平熱より下がってしまうことがあるのです。腎臓の働きが悪くなると体内に有害な老廃物が蓄積し、それにより身体の細胞の働きが鈍って熱を産生しにくくなります。さらに腎臓病が進行すると食欲不振になり十分な栄養エネルギーが摂れなくなるため、身体を温めるためのエネルギーも不足しがちです。加えて、腎臓の機能低下に伴って尿が増え脱水が進むと血液の循環量が減り、身体の隅々まで熱を運べなくなります。こうした理由から慢性腎臓病の猫は身体が冷えやすく、耳や足先が冷たく感じられることがあります。
そのほかの病気
両耳を含め全身が冷えてしまう原因は、腎臓病以外にもいくつか考えられます。心臓の病気(循環器疾患)もその一つです。先天的な心臓病や肥大性心筋症などで心臓のポンプ機能が低下すると、全身に十分な血液を送れず体温が下がることがあります。心不全に陥った猫では四肢や耳先まで血液が行き渡らなくなり、触れると冷たく感じられます。特に末期の心臓病でショック状態に近づくと、著しい低体温と虚脱が見られることがあります。
また、重度の貧血も身体を冷やす原因になります。貧血になると血液が酸素を運搬できずエネルギー産生が低下するうえ、血液量自体が減って末端まで熱が届きにくくなります。上記の慢性腎臓病による貧血のほか、慢性感染症や自己免疫疾患、腫瘍などさまざまな病気で貧血は起こりえます。特に急激に貧血が進行した場合はショック状態となり体温が急低下することもあります。
猫の片耳だけ冷たいときに考えられる病気

両耳ではなく片方の耳だけが冷たく感じる場合はどうでしょうか。そのようなケースでは、深刻な病気が原因であることは多くありません。通常、全身的な体温低下であれば両耳とも冷たくなるはずなので、片耳だけ冷たい場合は局所的な要因を考えてみます。
まず、猫の姿勢や環境によって一時的に片耳の温度が変わることがあります。例えば片側の耳を床につけて寝ていた場合、その耳はもう片方に比べて冷たく感じるかもしれません。また、片耳だけ風に当たっていたり濡れていたりすると、その耳だけ温度が下がることもあります。こうした場合、猫が起きて身体を動かしたり温かい場所へ移動したりすれば、耳の温度もすぐにもとに戻るでしょう。
一方で、片耳の血流が悪くなっている可能性も考えられます。耳の血管に血栓(血のかたまり)が詰まったり、耳介の先端が凍傷になったりすると、片耳だけ極端に冷たくなることが考えられます。耳先が白く変色していたり黒ずんでいたりする場合は、凍傷や壊死の疑いもあります。特に冬場に外で過ごした猫では、耳先だけ凍傷になってしまうことがありますので注意してください。
猫の耳が冷たいときの対処法
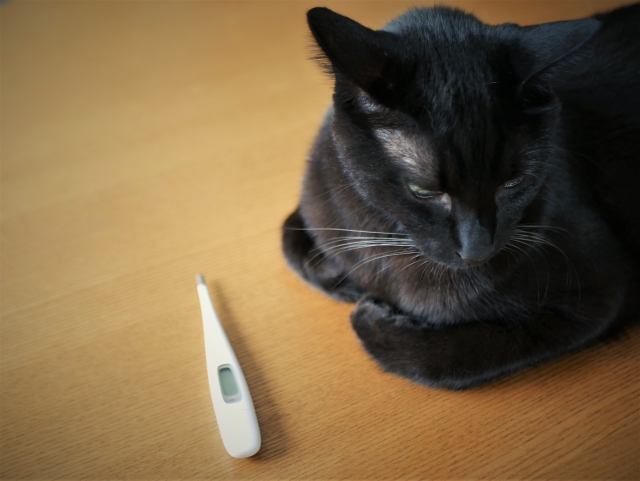
愛猫の耳が冷たく感じるとき、飼い主さんが家庭でできる対処法にはどのようなものがあるでしょうか。ここでは、猫の耳が冷たいと感じたときにまず行うべき体温の確認方法や、日頃からチェックしたい食欲・動き観察ポイントについて解説します。適切な対処と観察により、異常の早期発見につなげましょう。
体温を計る
猫の耳が明らかに冷たく感じたら、まず最初にするべきことは実際に体温を測定して確認することです。耳の温度は体温とおおむね比例しますが、正確な深部体温を知るには体温計を使う必要があります。猫専用あるいはペット用の体温計があれば、それを使って体温を測りましょう。平常時の猫の体温は約38度です。測ってみて37度台後半であればおおむね正常範囲といえます。37度を下回る体温だった場合は低体温の疑いがありますし、逆に39度を超えるようなら発熱している可能性があります。測定した体温が明らかに平熱から逸脱していた場合は、早めに動物病院に連絡して指示を仰いでください。
食欲や動きの変化を観察する
猫の耳が冷たく感じるとき、猫自身の様子にも注目しましょう。耳が多少冷たい程度でも、猫が普段どおり元気に動き回り、ご飯もモリモリ食べているようであれば過度に心配はいりません。寒いと感じれば猫は自分で暖かい場所に移動したり丸まったりして体温調節できますし、健康な猫であれば多少耳がひんやりすることはよくあるためです。
一方、耳だけでなく身体も冷え気味で猫の動きが鈍い、じっと丸まったまま動かない、震えているといった場合は体温低下のサインかもしれません。明らかに元気がなくぐったりしている、呼んでも反応が鈍い場合は注意が必要です。さらに、食欲がない、水もあまり飲まないといった変化も重要なポイントです。ご飯を半分以上残す日が続いたり、大好きなおやつにも興味を示さない場合は体調不良が疑われます。低体温になる原因の一つに病気がありますので、食欲不振や活動低下が見られたら早めに対処を考えましょう。
猫の耳が冷たいときの受診目安と病院での診療内容

耳が冷たいと感じるとき、どのタイミングで動物病院を受診すべきか悩む飼い主さんも多いでしょう。また、病院に連れて行った場合にどのような検査や治療が行われるのか不安に思うかもしれません。この章では、猫の耳が冷たいときの受診の目安と、動物病院で行われる主な検査方法・治療法について説明します。
猫の耳が冷たいときに受診する目安
猫の耳や身体が冷たく感じ、「体温が低いかも?」と思ったとき、次のような場合には動物病院への受診を検討してください。
- 体温を測って37度以下だったとき
- 猫の元気や食欲がないとき
- 震えが止まらないとき
- 呼吸や心拍に異常があるとき
- 子猫や老猫の場合
上記のような状況では、できるだけ早く動物病院に連絡・受診することをおすすめします。
動物病院での検査方法
実際に動物病院を受診すると、獣医師は問診と身体検査を通じて低体温の原因を探ります。具体的には以下のような検査・確認が行われます。
まず体温を再測定し、正確な数値を確認します。
耳の中や耳介の状態、四肢の冷え具合、お腹のハリ具合、外傷の有無などを隅々まで観察します。
飼い主さんへの質問も重要です。いつから耳が冷たいと感じたか、室温はどのくらいか、最近食欲や飲水量に変化はあったか、嘔吐や下痢はないか、持病はあるか、何か思い当たるストレス要因はあったかといったことを詳しく聞かれるでしょう。
必要に応じて血液を採取し、血球数や生化学検査を行います。血液検査では貧血の有無や炎症反応、腎臓・肝臓の数値、血糖値、電解質バランスなどを調べます。
必要に応じてレントゲン検査や超音波検査(エコー)を行います。
ショックや貧血が疑われる場合には血圧を測定することもあります。
以上のように、総合的な検査によって耳が冷たくなる原因を突き止めていきます。
動物病院での治療法
診察の結果、猫の耳が冷たくなっている原因が判明したら、その原因に対する治療と低下した体温を戻すための保温と支持療法が行われます。
まず低体温そのものへの対処としては、身体を温める処置が取られます。軽度の低体温で意識がはっきりしている場合は、毛布でくるんだり保温マットの上で安静にさせるなど、外部から徐々に温めます。重度の低体温で自力で体温を上げられない状態では、獣医師がより積極的な加温措置を行います。
低体温を引き起こした原因への治療も同時に行われます。原因が脱水や栄養低下であれば点滴による水分・栄養補給が行われます。感染症による発熱が背景にあるなら抗菌薬や抗ウイルス薬の投与が考えられますし、炎症を抑えるために消炎鎮痛剤やステロイドが使われる場合もあります。ただし低体温の場合、感染症よりもむしろ感染が全身に回った敗血症など末期状態のことが多く、その場合は輸液や強心剤など集中治療的な対応になります。
まとめ
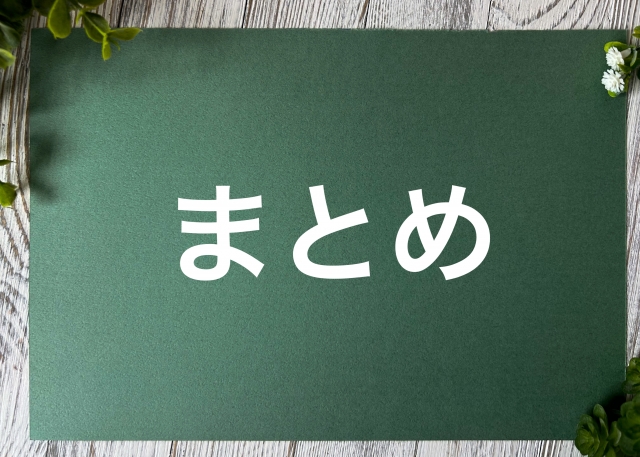
猫の耳が冷たく感じられるときについて、考えられる病気や対処法を解説しました。猫の耳が冷たくても正常な場合も多いですが、病気が原因で愛猫の耳が冷たくなっていることがあります。まず落ち着いて体温を測定し確認しましょう。平熱より低ければ保温を開始し、猫の様子を注意深く観察します。震えがある、ぐったりしている、食欲が明らかに低下している、といった異常が見られたら早めに動物病院に相談してください。飼い主さんの適切な判断と行動が、愛猫の健康と命を守ることにつながります。
参考文献


