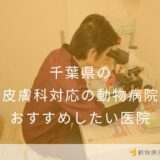子宮蓄膿症とは子宮内部に細菌感染が起こり、子宮内膜が炎症を起こして膿がたまる病気です。発症すると猫は重い全身症状を起こし、放置すれば命に関わる危険な状態になります。本記事では猫の子宮蓄膿症をその症状から治療法まで質問形式で解説します。
猫の子宮蓄膿症の基礎知識

- 猫の子宮蓄膿症とはどのような病気ですか?
- 子宮蓄膿症とは、子宮の内部で細菌が増殖して炎症(子宮内膜炎)が起こり、そこに膿が溜まってしまう病気です。子宮頸管が開いた状態で進行する開放型と、閉じた状態で進行する閉鎖型に分けられます。初期にははっきりした症状が出ないことが多いですが、病気が進行すると子宮が膨らんでくるほか、元気がなくなり、嘔吐や発熱など全身症状が現れます。特に内部に膿がたまった子宮が破裂すると腹膜炎やショック症状を引き起こし、短時間で命に関わる危険な状態になります。
- 猫の子宮蓄膿症の原因を教えてください
- 原因は、発情期間の黄体期に分泌される黄体ホルモン(プロゲステロン)の影響と細菌感染です。発情期間は子宮内膜が厚くなって子宮頸管(子宮の出口)が緩み、かつ免疫力も低下します。そのため外部から大腸菌やブドウ球菌、サルモネラ菌などの細菌が子宮内に侵入しやすくなり、子宮内膜炎を起こします。この子宮内膜炎が治らずに長引くと膿が次第に溜まり、子宮蓄膿症となります。
- 子宮蓄膿症になりやすい猫の特徴を教えてください
- 避妊手術をしていない雌猫は、基本的に誰でも子宮蓄膿症のリスクがあります。特に、若年の猫よりも、高齢の猫の方が発症しやすいとされています。ただし、猫の場合は若齢でも発症例があるため、避妊手術をしていなければどの年齢でも注意が必要です。また、発情を繰り返すごとに子宮内膜の変化が進むため、発情回数が多い猫ほど発症しやすい傾向があります。
猫の子宮蓄膿症の症状

- 猫の子宮蓄膿症の前兆や初期症状を教えてください
- 子宮蓄膿症は初期には症状がはっきりしないことが多いのですが、飼い主さんが注意すべきサインがあります。具体的には、飲水量や排尿量がいつもより増える、多飲多尿になることが見られることがあります。また、陰部を観察して血が付いていたり、膿(おりもののようなもの)が見られたりする場合もあります。食欲不振や活気の消失が続くようなら早めに受診を検討しましょう。初期に気付きにくい病気なので、日頃から猫の様子に細かく目を配ることが大切です。
- 猫の子宮蓄膿症が進行したらどのような症状が現れますか?
- 病気が進むと子宮内の膿が増え、猫は徐々に全身の症状を示すようになります。典型的には多飲多尿、腹部の膨満、食欲低下、嘔吐、下痢、発熱などが現れます。子宮頚管から膿が出てくる開放型では子宮頸管が開いているため陰部から悪臭を伴った膿や血液が排出されることがあります。そのため発見も早いです。これに対して子宮頸管から膿の出てこない閉鎖型では膿が外に出ず子宮内部にどんどん溜まり、腹部が大きくハリます。膿が大量になると子宮が破裂しやすくなり、腹膜炎や敗血症、急性腎不全などの重大な合併症を引き起こして急変し、命に関わることがあります。
- 猫の子宮蓄膿症のチェック方法を教えてください
- 飼い主さんが自宅でできるチェックとしては、まず飲水量や排尿回数、食欲に普段と違う変化がないか観察しましょう。子宮蓄膿症の初期には飲水量や排尿量が増えることがよくあります。また、陰部の周りが汚れていないか確認し、血や膿(おりもの)が付着していないかを見てください。お腹を優しく触ってみて、いつもより膨れている、痛がる様子があるといった変化も手がかりになります。体重の減少や嘔吐・下痢の有無なども日々チェックしておくとよいでしょう。
- 猫の子宮蓄膿症が疑われる場合の受診サインを教えてください
- 猫の子宮蓄膿症が疑われる場合はさまざまな症状が現れます。特に、以下のような症状が見られたら、早めに動物病院を受診してください。
・飲水量・排尿量の急増
・食欲不振や活気の低下
・陰部から膿や血液が出ている
・お腹が膨れてきている
これらに加えて、体温が高い、震えや下痢、嘔吐など全身症状が出ていると緊急性がさらに高まります。これらのサインがあれば早急に獣医師に相談し、診察を受けましょう。放置しておくと急激に悪化し危険な状態になる恐れがあります。
猫の子宮蓄膿症の検査と診断、治療法

- 猫の子宮蓄膿症の検査と診断方法を教えてください
- 獣医師は身体検査や各種検査を組み合わせて診断を行います。まず身体検査で発熱や脱水、腹部膨満の有無などを確認します。血液検査では白血球数やCRP(炎症マーカー)が上昇していることが多いです。腹部の超音波検査(エコー)では、腫大した子宮や子宮内の液体貯留を詳細に観察でき、診断の重要な手がかりになります。さらに、必要に応じて腹部X線(レントゲン)検査を行い、肥大した子宮の存在を確認したり、腹水の有無を調べたりします。ほかの病気(子宮内膜炎や子宮水腫など)を除外するために、細菌培養検査や腹水の検査を併用することもあります。これらの検査結果を総合して、子宮蓄膿症であるかどうかが判断されます。
- 猫の子宮蓄膿症の治療法にはどのようなものがありますか?
- 基本的な治療は外科手術で、病気の原因となっている子宮と卵巣を同時に摘出する卵巣子宮摘出術が第一選択となります。この手術により膿の原因となる病巣を根本から取り除けるため治療効果が高く、通常は術後2~3日で退院できるほど経過が良好です。診断後の手術はできるだけ早い段階で行うことが望まれます。一方で、すでに容体がかなり悪い場合や高齢などで手術が難しいケースもあります。そのような場合にはプロスタグランジン製剤などで子宮頸管を開かせて膿を排出させたり、抗生物質を用いて炎症を抑えたりする内科的治療を行うこともあります。ただし内科治療だけでは膿を完全に排出しきれないことが多く、再発の可能性も高いため、根本的な治療としては手術が望ましいです。
- 子宮蓄膿症の治療中に飼い主が気を付けるべきことを教えてください
- 手術後や治療中は、猫の全身状態をしっかり観察してケアすることが大切です。具体的には、退院後も傷口が清潔で化膿していないかを確認し、食事は少量ずつ与えて様子を見ながら徐々に通常量に戻します。外出や激しい運動は禁止し、ケージや安静な場所で十分に休ませましょう。また、避妊手術後はホルモンバランスの変化で体重が増えやすいため、食事管理と適度な遊びで肥満を防ぐことも大切です。獣医師の指示どおりに抗生物質や鎮痛薬を飲ませ、術後の経過観察や検診を忘れず行ってください。少しでもおかしいと思ったら早めに病院に相談し、再診を受けるようにしましょう。
編集部まとめ

猫の子宮蓄膿症は、初期にはわかりにくいものの、病状が進むと多飲多尿や陰部からの膿、腹部膨満などが見られ、放置すると腹膜炎や敗血症を引き起こして命に関わります。しかし、早期の症状に気付き、適切な治療を行えばほとんどの猫は大事に至らずに済みます。愛猫の様子に異変があれば速やかに獣医師に相談し、定期的な健康チェックと予防ケアを心がけてください。
参考文献