猫は泌尿器疾患にかかりやすいとされていますが、なかでも、尿石症や膀胱炎・尿路閉塞などの病気が見られます。適切な予防や早期発見が大切ですが、症状を見逃すと深刻な状態になることもあるため、注意が必要です。
本記事では猫は泌尿器疾患になりやすいのかについて以下の点を中心にご紹介します。
- 猫が泌尿器疾患になりやすい理由
- 腎不全腎臓病にかかりやすい猫
- 猫を泌尿器疾患から守るために
猫は泌尿器疾患になりやすいのかについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。
猫が泌尿器疾患になりやすい理由

なぜ猫は泌尿器疾患になりやすいといわれているのでしょうか?以下で詳しく解説します。
濃い尿を出す身体の仕組み
猫の祖先は、乾燥地帯で生き抜いたリビアヤマネコであり、その名残から現在の猫も水分を無駄なく利用する身体の仕組みを持っています。
なかでも、腎臓は尿を濃縮し少ない水分摂取でも生命を維持できるよう適応しているため、猫の尿は濃く特有の強い匂いがあります。
しかし、この仕組みは泌尿器系に負担をかける要因ともなります。腎臓が疲れると、慢性腎臓病などの疾患が発生しやすくなります。また、尿が濃縮されることでミネラルが結晶化し、尿石症や膀胱炎などの下部尿路疾患(F.L.U.T.D)を引き起こすリスクが高まります。
したがって、猫の健康を守るためには、適切な水分摂取を促し、泌尿器系の負担を軽減するケアが欠かせません。
飲水量が減る冬は要注意
寒い季節になると、猫の飲水量はさらに減少しやすくなります。猫はもともと水をあまり飲まない動物ですが、冬の寒さで活動量が減ると、飲水量も一層低下した結果、尿が濃縮されやすくなり、尿石症や膀胱炎といった泌尿器疾患のリスクが高まります。
また、慢性腎臓病の初期症状である「多飲多尿」は、冬の方が飼い主さんに気付かれやすく、病気の早期発見につながることがあります。
寒い季節には、猫の健康管理に注意が必要です。また、異常な飲水行動や排尿回数の変化が見られた場合は、早めに動物病院で相談することをおすすめします。
猫の代表的な泌尿器疾患

猫には、どのような代表的な泌尿器疾患があるのでしょうか?以下で詳しく解説します。
慢性腎臓病
猫の慢性腎臓病は、腎臓内のネフロン(尿を作る単位)が徐々に機能を失う病気で、高齢の猫に多く見られます。原因は不明ですが、1歳未満では先天的な要因が関与することがあります。
腎臓の75%以上のネフロンが損傷すると症状が現れ、主な初期症状には多飲多尿、体重減少、元気消失などがあります。また、エリスロポエチン分泌の低下により貧血が進行し、病気が悪化すると尿毒症が見られるようになります。
慢性腎臓病は治癒が難しい病気ですが、早期発見と適切な管理で進行を遅らせられ、特に尿の比重(1.035以下の低下)が早期発見の重要な指標となります。
猫の慢性腎臓病を予防するには、良質なタンパク質を適量与え、水分を十分に補給することで腎臓への負担を軽減し、病気の進行を遅らせる助けとなります。また、寒冷や脱水などのストレス要因を避けることも、猫の健康を守るために大切です。
急性腎障害
猫の急性腎障害は、腎臓が突然機能不全に陥る重篤な疾患で、迅速な対応が必要です。主な原因として、腎臓への血液供給不足や血栓による血管の詰まり、毒物(不凍液やエチレングリコールなど)による中毒、感染症や腫瘍、尿路結石による尿路閉塞が挙げられます。
急性腎障害が進行すると、尿が出なくなり、体内に老廃物や毒素が蓄積して「尿毒症」を引き起こします。この状態では、食欲不振、嘔吐、下痢、脱水、口臭、運動失調、けいれんなどの症状が現れるほか、重症化すると低体温や発熱、頻呼吸、貧血も見られます。
急性腎障害の早期発見と治療には、日常的な健康観察が重要となるため、飲水量や排尿回数の異常、急な体調の変化に気付いた場合は、早急に動物病院で診察を受けることが猫の命を守る鍵となります。また、毒物への接触や感染症の予防にも注意を払いましょう。
尿路結石症(尿石症)
尿路結石症(尿石症)は、腎臓、尿管、膀胱、尿道といった尿路に結石ができる病気で、主に「ストルバイト結石」や「シュウ酸カルシウム結石」が見られます。ストルバイト結石は、リン酸アンモニウムマグネシウムを主成分とし、尿がアルカリ性に傾くことで形成されやすく、シュウ酸カルシウム結石は酸性尿やミネラル濃度の上昇が原因で形成されます。
症状として、排尿時の痛み、血尿、頻尿、尿が出ないといった異常が挙げられます。特に雄猫は尿道が細いため、結石が詰まりやすく、尿道閉塞による尿毒症や腎臓病を引き起こすリスクが高いため注意が必要です。一方、雌猫では尿道閉塞は稀ですが、膀胱炎などの症状を引き起こすことがあります。
治療や予防には、療法食を用いて尿のpHを調整したり、飲水量を増やして尿を希釈することで効果が期待できます。しかし、一度結石ができた猫では再発リスクが高いため、定期的な尿検査や適切なフード選びが重要です。また、日頃からトイレの様子を観察し、排尿異常が見られた場合は早めに動物病院で診察を受けましょう。
膀胱炎
膀胱炎は、膀胱内に炎症が起きた状態を指し、猫では膀胱結石や細菌感染、特発性膀胱炎が主な原因として挙げられます。膀胱結石は、尿路結石が膀胱内で形成された場合に起こり、結石が膀胱壁を傷つけることで炎症を引き起こします。また、細菌が尿道を通じて侵入し、感染を引き起こす細菌性膀胱炎もあります。
猫の膀胱炎のなかで特に見られるのは、特発性膀胱炎です。特発性膀胱炎は、明確な原因が特定できない膀胱炎で、頻尿や血尿などの症状が見られるものの、検査で細菌感染や結石が確認されません。発症要因の一つにストレスがあるとされ、環境の変化や来客、新しいペットの迎え入れ、トイレの変更などが引き金となることがあります。
猫の膀胱炎を予防するには、生活環境を安定させ、静かで落ち着けるスペースを用意することが推奨されています。また、十分な水分補給は膀胱炎のリスクを軽減するため、猫が水を飲みやすい工夫も行いましょう。総じて、頻尿や血尿などの異常を見つけた際は、早めに動物病院で相談することが重要です。
尿毒症
尿毒症は、腎臓が正常に機能しなくなり、尿として排泄されるはずの老廃物が体内に蓄積することで発症します。原因には慢性腎臓病の末期、急性腎障害、尿路閉塞や膀胱破裂などが挙げられます。
症状としては、食欲不振や体重減少、嘔吐、下痢、口からのアンモニア臭、脱水、低体温、けいれんなどが見られます。進行すると昏睡状態に陥り、治療が遅れると死に至る可能性があります。なかでも、慢性腎臓病や尿路結石症を持つ猫はリスクが高いため、注意が必要です。
尿路閉塞の場合は閉塞の解除が優先され、慢性腎臓病の末期では対症療法や血液透析が行われることがあります。尿毒症を予防するためには、日頃から排泄の様子を観察し、異常があればすぐに動物病院を受診することが重要です。また、腎毒性のある薬や植物の誤食にも注意しましょう。
腎臓病にかかりやすい猫

腎臓病にかかりやすい猫の特徴を以下で解説します。
急性腎障害にかかりやすい猫
急性腎障害は、主に尿路結石が尿道に詰まることで発症します。なかでも、ミネラル(リンやカルシウムなど)の過剰摂取をしている猫は、尿結石のリスクが高まり、尿路閉塞を引き起こしやすくなります。
また、中毒性物質も急性腎障害の原因となるため、屋外で自由に行き来する猫は、危険な物質に触れるリスクが高く注意が必要です。
急性腎障害は短期間で命に関わることもあるため、異常が見られた場合は早急な対応が求められます。
慢性腎臓病にかかりやすい猫
慢性腎臓病は、加齢に伴って発症リスクが高まる病気です。なかでも、高齢の猫がかかりやすいといわれています。
腎臓の機能は一度損なわれると回復しないため、症状が出る前の予防と早期発見が重要であるため、5歳を過ぎた猫や腎疾患の既往歴がある猫は、定期的な健康チェックや食事管理を徹底することが推奨されます。
愛猫を泌尿器疾患から守るために

最後に、愛猫を泌尿器疾患から守るためにできることを解説します。
水分摂取の工夫と食事管理
愛猫を泌尿器疾患から守るには、水分摂取を増やし、適切な食事管理を行うことが重要です。
水分摂取の工夫
猫はもともと水を飲む量が少ない動物ですが、好みに合った水を用意することで飲水量を増やせます。
例えば、冷えた水やぬるま湯、さらには流水を好む猫もいるため、猫の好みを見つけてあげましょう。ささみを茹でた汁を少量混ぜて風味をつけるのも効果が期待できます。
水器はトイレから離れた静かな場所に複数個設置し、猫がいつでも飲みやすい環境を整えます。また、清潔を保ちほかの猫と共有しないことも大切です。
食事管理
ウェットフードを活用するのもおすすめです。ウェットフードはドライフードよりも15倍程度の水分を含むため、自然に水分摂取量を増やせます。愛猫の嗜好に合ったフードを選び、泌尿器の健康に配慮した特別食を取り入れるのもいいでしょう。
このような工夫をすることで、泌尿器疾患の予防につながり、愛猫が快適に過ごせる環境を提供できます。
トイレ管理と尿の観察
愛猫を泌尿器疾患から守るためには、快適なトイレ環境を整え、尿の状態を観察することが大切です。
快適なトイレ環境の整備
トイレの数は「猫の頭数+1」が理想的です。例えば、2匹の猫には3個のトイレを用意しましょう。トイレは猫の体長の1.5倍以上の広さがあり、砂の深さが適切で清潔に保たれていることが重要です。
また、トイレの置き場所は静かで安心できる場所にし、食事場所や寝床から離して設置してください。猫によって砂の好みが異なるため、数種類の砂を試して適切な種類を選ぶこともおすすめです。
尿の観察と早期発見
猫の尿には健康状態が反映されるため、トイレ掃除の際に尿の量や色、匂いをチェックしましょう。血尿や尿量の減少、頻尿が見られる場合は、泌尿器疾患の兆候である可能性があります。
多頭飼いの場合は、個別に観察するために一時的に猫を隔離してトイレの様子を確認する方法も効果が期待できます。
日常的にトイレ環境と尿の状態を見守り、異常があれば早めに動物病院を受診することで、愛猫を泌尿器疾患から守れます。
身体のケア
愛猫を泌尿器疾患から守るためには、身体のケアが重要であるため、運動や適切な体重管理、日常的な観察を通じて、健康を維持しましょう。
運動不足を解消する
運動不足は膀胱内に尿が長時間とどまる原因となり、尿石ができやすくなるとされています。そのため、愛猫と積極的に遊んだり、キャットタワーやトンネルを設置して上下運動や探索を助けましょう。
肥満を防ぐ
肥満は腎臓に余分な負担をかけるだけでなく、運動不足を招き、尿石のリスクを高めます。なかでも、避妊や去勢後は太りやすくなるため、カロリー管理が重要なため、適切な食事と運動を組み合わせて、理想的な体重を維持しましょう。
日頃の観察を欠かさない
愛猫の日常の様子をよく観察することも大切です。スキンシップを通じて体調の変化や異常を早めに察知できれば、泌尿器疾患を早期に発見できます。なかでも、食欲や排尿の様子、動きに違和感を感じた場合は、早めに動物病院で相談しましょう。
これらのケアを習慣化することで、愛猫の健康を守り、泌尿器疾患の予防につながります。
異常に気付いたらすぐに動物病院へ
猫が下部尿路疾患にかかると、頻繁にトイレに行くのに尿が出にくい、排尿時に鳴き声を上げる、血尿が見られる、トイレ以外で粗相をするなどの症状が現れることがありますが、これらの症状を見逃さず、早めに対処することが重要です。
なかでも、注意が必要なのは「尿道閉塞」です。尿道閉塞は尿道が詰まり、尿が排出できなくなる状態で、主に尿道が細い雄猫に多く見られます。放置すると急性腎障害や尿毒症を引き起こし、数日で命に関わる危険性があります。
一方、雌猫では結石が膀胱内壁を傷つけ、膀胱炎を発症することが多いとされていますが。また、原因が特定できない「特発性膀胱炎」も近年増加しているため、注意が必要です。
これらの症状を発見した場合、日常的にトイレの様子を観察し、少しでも異常を感じたら迅速に動物病院へ相談しましょう。
まとめ
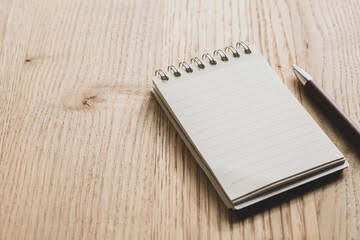
ここまで猫は泌尿器疾患になりやすいのかについてお伝えしてきました。猫は泌尿器疾患になりやすいのかの要点をまとめると以下のとおりです。
- 猫は尿を濃縮する身体の仕組みが負担となり、泌尿器疾患にかかりやすいとされている
- 急性腎障害は尿路結石や中毒、慢性腎臓病は加齢や腎疾患の既往歴がある猫が腎臓病にかかりやすいとされている
- 愛猫を泌尿器疾患から守るには、適切な水分摂取と食事管理、快適なトイレ環境の整備、運動不足の解消や肥満予防が重要で、日頃から尿や体調を観察し、異常を感じたら早めに動物病院を受診することが大切
猫は尿を濃縮する身体の仕組みから泌尿器疾患にかかりやすいとされているため、適切な水分摂取や食事管理、トイレ環境の整備、運動と体重管理を心がけ、日頃から尿や体調を観察することを心がけましょう。
これらの情報が少しでも猫は泌尿器疾患になりやすいのかについて知りたい方のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


