犬はもともと唾液量が多い動物ですが、だらだらと垂れるほどのよだれが続くと「何か病気だろうか」と心配になる飼い主さんも多いでしょう。唾液は食べ物を飲み込みやすくし、口の中を洗い流す大切な役割を果たしていますが、過剰に分泌されると脱水や皮膚炎、誤嚥の原因になることもあります。本記事では、正常なよだれの範囲と個体差を確認したうえで、よだれが増える代表的な病気や緊急サイン、動物病院で受ける検査・治療、そして飼い主さんが今日からできるケアや対策までを解説します。
犬の正常なよだれの量とは

犬は人よりよだれを分泌しやすく、通常は健康な身体の働きの一部です。食べ物のにおいを嗅いだり口に食べ物が入ると消化の準備として唾液分泌が増え、わずかなよだれは自然な反応です。また、暑さを感じてパンティング(開口呼吸)すると口が乾きやすくなり、よだれが増えることもあります。
犬種によって異なるよだれの量
犬種によってよだれの多さは大きく異なります。一般に、セント・バーナードやブラッドハウンド、マスティフ、ニューファンドランドなど巨大犬種や長い顎の犬種は構造的に唾液が垂れやすく、大量に垂らしているように見えます。一方、チワワやトイプードルなどの小型犬や口吻の細い犬種はよだれが少ない傾向があります。鼻の短いフレンチ・ブルドッグやパグなどの短頭種も、構造上よだれがたまりやすいです。
年齢別のよだれの傾向と注意点
子犬の場合、歯の生え変わり時期によだれが増えることがあります。生後数週間で乳歯が生え始め、生後4〜7ヶ月頃に永久歯へ生え替わる間、歯茎のむず痒さや痛みを和らげるため唾液が多くなり、よだれが出やすくなるのです。実際、歯の生え変わり期の子犬はおもちゃや家具を盛んに噛み、その際によだれでベタベタになるほど唾液が出るのは自然な反応といえます。
一方、シニア犬(高齢犬)はよだれの異常に特に注意が必要です。歳をとった犬は若い頃に比べ口腔内のトラブルが増え、歯肉炎や歯周病などによってよだれが増える傾向があります。また、高齢になると歯周病以外にもがんや膵炎、腎臓病、熱中症などさまざまな病気のリスクが高まるうえ、筋力の衰えなどで口がうまく閉じられず唾液が垂れやすくなることもあります。
刺激によってよだれが出るのは自然な反応
食事前の期待や食べ物の匂いへの反応として犬はよだれを垂らします。これは正常な生理現象で、食べ物を前にすると特に多く分泌されます。また暑い時や興奮時にはパンティングが増え、口の中が乾燥するため唾液が多めに出ます。これらのよだれは通常、一時的であり、犬が落ち着けば収まるので心配は不要です。ただし、通常より異常に多量・長時間続く場合は注意が必要です。
犬のよだれが多すぎるのは病気のサイン?

よだれの増加が病気のサインになることもあります。歯や口の痛み、異物、内臓疾患、中毒、熱中症など多様な原因が考えられます。以下のような要因が疑われる場合は、よだれだけでなくほかの症状にも注意しましょう。
口腔内疾患
歯周病や歯肉炎、口内炎などの口腔トラブルはよだれの増加によく見られる原因です。歯石が付着していると歯茎が腫れ、痛みで食事がしにくくなり、よだれを垂らしがちになります。また、口の中に腫瘍ができると口が閉じにくくなりよだれが多くなることがあります。口周りの異物(骨やおもちゃの破片)や外傷、舌炎などでもよだれが増える場合があり、口臭がひどい、口元を触られるのを嫌がる、出血などの症状があれば歯科疾患を疑います。
誤飲や誤食、中毒
異物を飲み込むと吐き出そうとする反応でよだれが増えます。例えば、おもちゃや骨片を飲み込んで喉につかえると、嘔吐感のある状態でよだれだけが絶え間なく出ることがあります。また、チョコレート、タマネギ、ブドウなど有毒な食べ物や殺虫剤、洗剤、植物中毒などもよだれ増加の原因です。中毒の場合はよだれに加え、痙攣や嘔吐、ふらつきなども起こるため、すぐに動物病院へ相談しましょう。
消化器系疾患
胃腸の炎症や腫瘍、膵炎、腸閉塞、胃拡張・捻転など重篤な消化器疾患でもよだれが増えます。特に大食い後や早食いで胃が膨らんだ状態のまま運動すると胃がねじれてしまい、激しい腹痛・嘔吐・腹部膨満とともによだれが大量に出ます。急なよだれ増加に腹部膨満や苦しげな様子が加われば、緊急手術が必要な可能性があります。また急性膵炎でも強い腹痛とともによだれが増え、嘔吐や下痢が見られることがあります。
代謝異常
腎不全や肝不全などの内臓機能低下でもよだれが多くなることがあります。特に、肝機能が著しく低下した場合は肝性脳症が起き、よだれ・痙攣・意識障害などが起こりやすくなります。慢性的な腎臓病(尿毒症)でも体内に老廃物がたまり吐き気や口内炎を起こし、唾液量が増えることがあります。糖尿病や副腎皮質機能低下症など代謝疾患でも二次的に唾液分泌が変化する場合があります。
熱中症
夏場や高温環境で激しくパンティングしている場合、体温調節が追いつかず熱中症になる恐れがあります。熱中症ではよだれの量も急増し、口腔粘膜の充血・嘔吐・下痢などを伴うことがあります。短頭種(フレンチブルドッグ、パグなど)は特に熱中症にかかりやすい犬種です。暑い日によだれが増え元気がない場合はすぐに涼しい場所で冷却し、動物病院を受診しましょう。
そのほかの理由
神経疾患もよだれ増加の原因になりえます。てんかん発作や脳腫瘍、水頭症では脳神経の異常で唾液分泌が制御されず、発作前後によだれが多く出ることがあります。またジステンパーや狂犬病など重篤な感染症では嚥下障害でよだれが飲み込めなくなります。さらに、ストレスや車酔いで吐き気を催しよだれが増える場合もあります。以上のような多彩な原因があるため、よだれが急激に増えたりほかの症状が現れたら慎重な観察が必要です。
よだれで動物病院を受診する目安

よだれだけで即受診ではありませんが、以下のような症状がある場合は速やかに診察を受けましょう。目安を知っておくだけで、危険なタイミングを逃さず、不要な通院ストレスも減らせます。
犬がぐったりしている
よだれの増加に加えて犬がぐったり無気力であれば、命に関わる状態の可能性があります。食欲不振や嘔吐、発熱などが伴う場合も同様です。ぐったりしていれば熱中症や胃捻転、毒物摂取など重篤な疾患を疑い、迷わず病院へ連れて行ってください。
よだれに血や泡が混ざっている
口の中や消化管から出血があると、よだれに血液が混ざります。また、泡状のよだれは嘔吐直前やてんかん発作などの前兆のことがあります。血や泡が見られたら歯肉炎・潰瘍・腫瘍や神経系の問題など重大な病気の可能性があるため、獣医師に相談しましょう。
よだれのニオイが普段と異なる
よだれ自体や口臭の異常は、口腔内感染や消化不良のサインです。いつもと量や色・においが違う場合は何らかの病気のサインかもしれません。特に膿のような臭いや腐敗臭を伴う場合は、口内や消化管で細菌感染が起きていることもあるため、早めに診てもらいましょう。
よだれが止まらない
通常、犬は落ち着けば唾液分泌も治まります。ところが何時間も垂れ続ける、止められないほどのよだれは異常です。異物や毒物摂取、口腔の重篤な痛みなどの可能性があります。よだれが止まらずほかの対応で治まらない場合は獣医師に相談し、原因を調べてもらいましょう。
よだれが多いときの応急ケア
異常なよだれに気付いたときの応急処置も知っておきましょう。例えば暑さによるよだれ増加が見られるときは、まず涼しい場所へ移動して身体を冷やし、新鮮な水を飲ませてあげます。苦い薬を飲んだ後など一時的な刺激が原因のよだれなら、水やフードを少量与えると落ち着きます。ただし、洗剤などの化学物質や危険な中毒物を舐めた際はすぐに動物病院に連絡し指示を仰いでください。絶対に自宅で無理に吐かせようとしないことも重要です。塩を飲ませて吐かせる民間療法は危険で、高ナトリウム血症(塩分の過剰摂取)による痙攣など命に関わる症状を引き起こす恐れがあります。応急ケアをしつつも、異常なよだれの原因に心当たりがない場合や症状が改善しない場合は速やかに獣医師の診察を受けるようにしましょう。
動物病院でのよだれの検査と治療

普段よりも多いよだれは、さまざまな病気が隠れていることがあります。動物病院では、その原因を調べるためにまず身体検査で口腔内を詳しく診察し、原因に応じた検査を実施します。
動物病院でのよだれの検査方法
獣医師は口腔内の視診・触診を行い、歯や歯茎・舌の状態を確認します。必要に応じて血液検査で肝腎機能や電解質を調べ、レントゲンや超音波検査で胸部・腹部を撮影します。誤飲が疑われる場合は内視鏡検査やエコー検査で異物の有無を確認することもあります。以上の検査で原因を特定し、適切な治療計画を立てます。
動物病院での治療法
原因に応じて治療が選択されます。口腔内疾患の場合、歯石除去や抜歯などで歯周病を改善し、口内炎には抗炎症薬や鎮痛剤を用います。誤飲では異物除去や催吐(吐かせる処置)を行い、中毒が疑われるときは吸着剤投与や輸液による解毒・対症療法を行います。熱中症では身体を冷却し輸液で循環を安定させ、胃拡張・捻転では緊急外科手術を行います。腎不全・肝不全の場合は点滴治療や特別食で体内環境を整えます。このように、検査で見つかった病気に対して外科処置や投薬・支持療法など複合的に治療を進めます。
日常的なよだれ対策

よだれが出てからの対処法も重要ではありますが、そもそも日頃から口腔ケアや環境整備を心がけ、よだれやニオイを予防することも重要です。本章では日常的なよだれ対策として、口腔内ケアや消臭アイテムの活用などを解説します。
口腔内ケアの徹底
定期的な歯磨きやデンタルガム、歯石除去で口腔内を清潔に保ちましょう。歯周病を予防すれば、口内の痛みや炎症によるよだれ増加を抑えられます。定期検診で歯科処置を受けたり、歯磨きガイドラインに沿ったケア用品(犬用歯磨き粉、デンタルコートスプレーなど)を活用することも効果的です。誤飲防止のため散歩中は拾い食いに注意し、危険物を室内に置かないことも大切です。
消臭アイテムの活用
床や犬具に落ちたよだれはこまめに拭き取り、専用のクリーナーやシートで清掃します。よだれやけ(皮膚の変色)対策としては、抗菌・消臭効果のある成分(カオリン・ゼオライト・ナノシルバーなど)配合の外用剤で清拭すると効果的です。散歩時にはポータブルのウェットティッシュで口まわりを拭く、脱臭マットや空気清浄機で室内の匂いを抑えるなど工夫してもよいでしょう。
季節ごとの対策
犬のよだれは気温や季節の影響も受けます。暑い夏場はパンティングによって唾液分泌が増え、よだれが垂れやすくなります。特に猛暑日には熱中症予防が最優先です。日中の暑い時間帯の散歩は避け、室内ではエアコンや扇風機で涼しい空間を作り、新鮮な水をいつでも飲めるようにしましょう。短頭種や厚い被毛を持つ犬種は特に注意が必要です。車内に愛犬を残すことは厳禁で、夏場は日陰でも短時間で車内が高温になるため絶対に避けてください。また、夏は湿度も高く、垂れたよだれが皮膚に残ると雑菌が繁殖しやすい環境になります。こまめに口元を拭き取り、皮膚炎(よだれ焼け)を防ぎましょう。
一方、寒い冬場は一見よだれとは無縁に思えますが、油断は禁物です。暖房の効いた室内で過ごす時間が長い場合、身体に熱がこもって軽い脱水や熱中症のような状態になることもありえます。冬でも室温管理を徹底し、水分補給を怠らないようにしましょう。暖房器具の近くで過ごす犬は喉が渇きやすいため、適度な湿度を保ち、水飲みをいつでも利用できるようにしておくと安心です。秋から冬にかけての季節の変わり目にも体調を崩す犬は多いので、よだれの様子に限らず元気や食欲の変化にも気を配り、必要に応じて早めに対策を講じてください。
まとめ
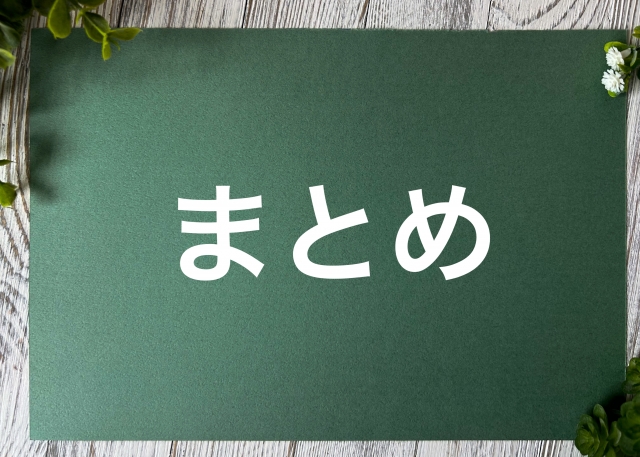
犬のよだれは生理的な現象ですが、量や状態の急激な変化は病気のサインかもしれません。歯周病や誤飲、消化器疾患、熱中症、代謝疾患など多様な原因が考えられ、ぐったりや血・泡を伴うときはすぐ受診が必要です。動物病院では口腔検査や血液・画像検査で原因を診断し、歯科処置や投薬・手術など適切な治療が行われます。日常では歯磨きなどの口腔ケアを徹底し、消臭グッズを併用してよだれ対策を行いましょう。定期的に愛犬の様子を観察し、異常を感じたら早めに獣医師に相談することが大切です。
参考文献


