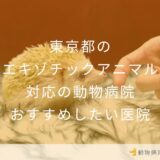「うちの犬、すぐに震えるし散歩中にほかの犬を見ると逃げ出す……」「怖がると飼い主にも噛みついてきたり吠えたりする……」このような愛犬の怖がりな性格に悩む飼い主さんは少なくありません。
怖がりな犬は環境や経験、性格によってさまざまな反応を見せますが、適切なトレーニングや接し方で徐々に症状を改善していくことが可能です。
本記事では怖がりな犬の特徴や原因を詳しく解説します。また、しつけ教室でどのような変化が期待できるのか、接し方のポイントも詳しくご紹介します。
愛犬への接し方を見直すきっかけや、しつけ教室の選び方の参考にしてみてください。
怖がりな犬の特徴

怖がりな犬は、その不安や恐怖をさまざまな行動で表現します。そのなかにはわかりやすい行動もあれば、一見すると気付きにくいものもあるため注意が必要です。ここでは、怖がりな犬に見られる代表的な特徴を4つご紹介します。
愛犬の行動と照らし合わせながら、その背景にある感情を読み解くヒントにしていただければ幸いです。
突然逃げ出す
怖がりな犬は、周囲の物音や見慣れないものに過敏に反応し、突然その場から逃げ出してしまうことがあります。散歩中であれば車の音やほかの犬、人の動きなどが引き金になる場合がほとんどで、飼い主が予想できない行動を取ることも少なくありません。
これは危険から逃れたいという本能的な反応であり、強い不安や恐怖を感じている証拠です。無理に止めたり追いかけたりせず心を落ち着かせる対応が必要になるでしょう。
攻撃的な態度を取る
一見すると怖がりと正反対に思える攻撃的な態度も、実は恐怖心から来る防衛反応の場合があります。例えば、怖いと感じた相手に対して吠えたり噛もうとしたりするのは、これ以上近づかないでほしいというサインです。
これは自己防衛の一環で、特に逃げ場がないと感じたときに出やすい行動です。
飼い主が無理に抱こうとしたり、知らない人が急に触れようとしたりする場面で起こりやすいため、注意しなくてはなりません。
身体が震える

恐怖心が高まると、犬の身体は自然に震えてしまうことがあります。震えはストレス反応のひとつで、特に音や見知らぬ環境への不安を感じたときに多く見られます。雷や花火の音、動物病院の診察台の上などでよく見られる現象です。
この震えは怖いという気持ちの現れのため叱ったり無理に止めたりしようとせず、優しく声をかけたり、リラックスできるスペースを用意してあげることが大切です。
防御行動をとる
怖がりな犬は、自分の身を守るためにさまざまな防御行動を取ります。代表的なのは以下の行動です。
- 耳を伏せる
- しっぽを巻く
- 身を低くする
- 隅に隠れる
これらは自分を目立たせず、危険を避けたいという心理が働いている証拠です。飼い主が無理に近づけることや、怖がる対象に慣れさせようとしてしまうと、逆効果になる場合もあります。
まずは犬の気持ちに寄り添い、少しずつリラックスできる環境を整えていくことが大切です。
犬が怖がりになる原因

犬が怖がりになる背景には、いくつかの原因が考えられます。なかには生まれつきの性質もありますが、多くは環境や過去の経験、人との関わり方に起因するものです。
原因を知ることで、飼い主として適切に対応し、愛犬の不安を少しずつ取り除くことが可能です。ここでは主な3つの原因を解説します。
過去のトラウマが影響している
保護犬や、過去に虐待・放置などの経験がある犬は、強い恐怖心を抱えやすい傾向にあります。例えば、以前に叩かれたことのある犬が手を上げるしぐさに敏感に反応するように、過去の体験が現在の行動に影響しているのです。
こうしたトラウマはすぐには消えませんが、焦らず根気強く接することで徐々に心を開いていくこともあります。信頼関係を築くことが、第一歩となるでしょう。
遺伝的要因がある
犬の性格には、ある程度の遺伝的な傾向が影響すると考えられています。もともと警戒心が強い犬種や、慎重な性格を持つ血統の場合、環境に大きな問題がなくても怖がりな傾向が見られることがあります。
また、同じ犬種でも個体差があるため、生まれつき繊細な性格の犬も少なくありません。遺伝的要因が関係している場合は、その特性を受け入れたうえで、無理のない範囲でサポートを行うことが重要です。
人やほかの犬との関わりに不安を感じている
幼少期に十分な社会化がされていないと、人やほかの犬と接する際に強い不安を感じやすくなります。例えば子犬の時期にほかの犬と遊ぶ機会が少なかったり、人との接触が極端に限られていたりすると、新しい刺激にうまく適応できません。
その結果、吠えたり隠れたりといった行動につながります。社会化不足は時間をかけて克服することが可能です。段階的に関係性を築けるようサポートしていきましょう。
しつけ教室で犬の怖がりは改善する?

怖がりな犬でも、適切なしつけ教室に通うことで少しずつ不安を克服し、自信をつけていくことが可能です。犬の性格や不安の原因に寄り添い、無理のないトレーニング環境を選びましょう。
少人数制や出張型、専門トレーナーによる指導など、刺激をできるだけ抑えた教室であれば犬もリラックスして学ぶことができます。トレーニングを通して怖くない経験を積み重ねていくことで、犬の行動は大きく変わっていきます。
焦らず、犬のペースに合わせて進めることが成功のカギです。
怖がりな犬に向いているしつけ教室

怖がりな犬は、一般的なしつけ教室ではかえってストレスを感じてしまう場合があります。そのため、犬の性格や不安のレベルに即した教室選びが必要です。
しつけ教室は少人数制や出張型、オンライン型や怖がりな犬専門のトレーナーによる教室など、多様な選択肢があります。それぞれの特徴を理解し、愛犬に合った環境を選びましょう。
少頭数に制限しているしつけ教室
ほかの犬や人が多い環境に不安を感じる怖がりな犬には、1回の参加頭数を少なく制限しているしつけ教室が向いています。参加頭数が少なければ、その分騒がしさや刺激も抑えられ、落ち着いた雰囲気のなかでトレーニングに集中しやすいようです。
犬自身のペースに合わせて指導が進められるので、無理なくステップアップができるでしょう。少人数ならトレーナーの目も届きやすく、細やかなサポートも期待できます。
出張型のしつけ教室
自宅というリラックスできる環境でレッスンが受けられる出張型のしつけ教室は、特に怖がりな犬に適しておすすめです。
知らない場所に行くだけで強いストレスを感じる犬にとって、自宅でのトレーニングは心の負担を大幅に軽減できます。
また、普段の生活環境で問題行動の原因を把握しやすく、より実践的なアドバイスが受けられるのも大きなメリットです。
オンラインのしつけ教室

外出が苦手な犬や、まだ対面トレーニングに不安がある飼い主さんには、オンラインのしつけ教室も選択肢となるでしょう。トレーナーからビデオ通話を通じてアドバイスを受けて自宅で実践できるスタイルなので、犬に余計な緊張を与えにくいようです。
リアルタイムでの質疑応答も可能なため、個別の悩みにも柔軟に対応できます。初期段階のトレーニングとして取り入れるのにもおすすめです。
怖がりな犬専門のドッグトレーナーが指導するしつけ教室
犬の性格や過去の背景に深く理解のある、怖がりな犬専門のドッグトレーナーによる教室に通うのもよいでしょう。無理に慣れさせるのではなく、犬の気持ちを尊重しながら少しずつ自信を育てていくアプローチが特徴です。
経験豊富なトレーナーなら繊細な反応にも気付き、適切なタイミングでサポートしてくれるため、飼い主にとっても学びの多い場になるでしょう。慎重な性格の犬にこそおすすめの方法です。
犬の怖がりを改善する方法

怖がりな犬を少しでもリラックスさせ、自信をつけさせていくためには、日常生活のなかでの働きかけがとても大切です。無理に慣れさせるのではなく、少しずつ段階を踏んで怖くない体験を積み重ねていく必要があります。
ここからは音や人、ほかの犬との接し方を通してできる、実践的な怖がりの改善方法を紹介します。
音に慣れさせる
犬が怖がるもののなかでも特に多いのが、大きな音や不意な物音です。雷や花火・掃除機・工事の音など、敏感な犬にとっては強いストレスとなります。
このような音にいきなり慣れさせようとするのではなく、小さな音から徐々に慣らしていく音慣れトレーニングが有効です。
音量をコントロールできる音源を使い、ごほうびを与えつつ、無理のない範囲で音は怖くないものという印象をつけていきましょう。
頻繁に会う人や犬に慣れさせる

怖がりな犬は、人やほかの犬との接触に強い不安を感じることがあります。特に、急に近づいてくる人や騒がしい犬には過敏に反応する場合がほとんどです。
まずは、いつもお顔を合わせる家族や散歩中に会う犬など、特定の相手と繰り返し穏やかに接する機会を設けましょう。
相手が落ち着いていること、そして犬がリラックスできる距離を保つことが大切です。少しずつ慣れさせることで、自信を育てていくことができるでしょう。
子犬の場合は社会勉強をさせる
子犬の時期は社会化期と呼ばれ、さまざまな刺激に対して順応しやすい時期です。この時期に多くの人や犬・音・場所などに触れさせておくことで、将来の怖がりの予防ができます。
無理に押し付けるのではなく、楽しい経験として学ばせることが大切です。公園で優しい犬と触れ合ったり、落ち着いた環境で新しい音を聞かせることで、前向きな社会性を身につけていくことができるでしょう。
怖がりな犬との接し方
怖がりな犬にとって、日々の飼い主との関わり方が心の安定や成長に大きな影響を与えます。ちょっとした言動が犬の不安を強めてしまうこともあれば、逆に安心感を与えることも可能です。
愛犬の性格や反応をよく観察しながら、心を開いてもらえるような接し方を心がけましょう。ここからは怖がりな犬との接し方のポイントを6つ紹介します。
一貫した態度で接する
怖がりな犬は、周囲の変化や不安定な対応に敏感に反応します。そのため、飼い主が日々一貫した態度で接することがとても大切です。
ある日は怒鳴る、別の日には甘やかすといったように対応がバラバラだと、犬は何が正しいのかわからず不安になります。指示や褒め方、叱り方を家族全員で統一することも効果的です。安定した関係性が、犬にとってリラックスできる基盤となります。
成功体験を積ませて自信をつける
怖がりな犬には小さな成功体験を積ませることで、少しずつ自信を育てていくことが重要です。
例として苦手だったおもちゃに触れられた、知らない人の前で落ち着いていられたなど、些細なことでも褒めてあげましょう。成功に対してごほうびや言葉でしっかりと褒めてあげることで、犬のやってみようという気持ちを引き出せます。
焦らず、少しずつハードルを上げていくことがポイントです。
大きな声や急な動きは避ける
怖がりな犬にとって、大きな声や突然の動きは恐怖の対象となりやすく、警戒心や防御反応を引き起こしてしまうことがあります。特に、驚かせるような行動や、感情的に叱ることは逆効果になりがちです。
なるべく落ち着いた声のトーンとゆっくりとした動作を意識し、安心感を与える接し方を心がけましょう。犬が不安を感じないような環境づくりが、信頼関係の構築にもつながります。
無理強いは避ける

怖がりな犬に対して、苦手な相手や場所に無理やり近づけることは逆効果です。恐怖心が強まるだけでなく、信頼関係が損なわれるリスクもあります。
大切なのは、犬自身が大丈夫かもしれないと思えるまで待つことです。そのためには犬の様子をよく観察し、不安そうなときは距離をとり、少しずつ環境に慣れるよう配慮をしましょう。
無理させないことは、怖がりを克服するための基本です。
定期的に愛情表現をして信頼を築く
怖がりな犬ほど、人からの愛情表現が心の支えになります。ただし、過剰に構いすぎるのはよくありません。日常のなかで優しく声をかける、落ち着いたスキンシップを取るといった関わり方が効果的です。
犬が自ら寄ってきたときには、しっかりと応えてあげることで信頼関係が深まります。定期的なコミュニケーションを通して、この人は信頼できる存在だと感じてもらうことが何より大切です。
安心できる場所を作ってあげる
家のなかに犬がリラックスして過ごせる逃げ場を用意してあげることも効果的です。
静かで落ち着ける空間にベッドやクレートを置き、誰にも邪魔されない安全地帯を作ってあげましょう。怖がりな犬にとって、ここにいれば大丈夫と思える場所があるだけで、心の余裕が生まれます。
音や人の出入りが少ない場所を選び、普段からそこをリラックスできる場所として定着させましょう。
まとめ

怖がりな犬には、性格や背景に配慮したしつけ教室の活用が効果的です。突然逃げ出す、震える、吠えるといった行動は不安や恐怖のサインです。
少頭数制や出張型、専門トレーナーのいる教室であれば、怖がりな犬でも無理なく少しずつ環境に慣れさせることができます。
さらに、家庭での一貫した接し方や成功体験の積み重ねも重要なポイントです。怖がりな犬にとって、頼れる存在がそばにいることが心の支えになります。
しつけ教室と家庭での接し方を組み合わせながら、ゆっくりと愛犬の自信を育てていきましょう。
参考文献