犬との暮らしは、たくさんの喜びをもたらしてくれます。しかし、指示した内容を聞いてくれない、落ち着きがないなど、愛犬の行動に悩む飼い主も少なくありません。こうした問題の多くは、犬が人との暮らし方を学ぶ機会がなかったことに原因があるため、適切な関わり方を実践することで改善できます。
このような悩みを解決する方法の1つが、しつけ教室で行われる服従訓練です。服従訓練では、お座り、待てなどの基本動作から始め、段階的にほかの犬や人との関わり方を身につけることができます。
この記事では、服従訓練の目的や種類、訓練が必要なケース、具体的な内容、費用や期間の目安、教室の選び方、通う際の注意点について解説します。
しつけ教室の服従訓練とは

服従訓練とは、犬が飼い主さんの指示を理解し、適切に行動できるようにするためのトレーニングです。しつけ教室では、専門のトレーナーが愛犬と飼い主の関係を深めるための効果的な方法を指導しています。
ここでは、服従訓練の概要や目的、種類について詳しく解説します。
服従訓練の概要
服従訓練とは、犬が人の指示に従い、落ち着いて行動できるようにするための基本的なトレーニングです。例えば、お座り、待て、伏せなどの指示に従うことを教えることで、愛犬との生活がより快適になります。
服従訓練は、人と暮らす犬にとって重要な学びの1つです。特に初めて犬を飼う方にとっては、トレーナーによる正しい知識のもとで訓練を行うことで、犬との信頼関係を築く大きな助けになります。
服従訓練の目的
服従訓練の目的は、犬と人が快適に社会のなかで暮らせるようになることであり、単に命令に従わせることではありません。訓練を受けることで、以下のような効果が期待できます。
- 犬自身の安全性を高める(飛び出しや誤飲の防止など)
- ほかの犬とのトラブルを避ける(過剰な吠えや飛びつきの防止)
- 飼い主との信頼関係を深める(病院での診察や治療をスムーズに受けられる)
このように、服従訓練は犬と人が互いに快適に暮らすための関係性を築くうえで重要な訓練です。
服従訓練の種類
服従訓練は、難易度や目的に応じて以下のような段階に分けられます。
| クラス | 内容 |
|---|---|
| 初級 | お座り、待て、伏せなどの基本動作を習得し、飼い主の指示に従う習慣を身に付ける。 |
| 中級 | リードをつけた状態での歩行練習や、複数の指示を連続して実行するトレーニングを行う。また、ほかの犬や人がいる環境でも落ち着いて行動できるよう、社会化を強化する。 |
| 上級 | リードなしでのコントロールを習得し、遠くからの指示にも反応できるよう訓練し、状況に応じた適切な行動を学ぶ。 |
各段階を犬の性格や習熟度に合わせて進めることで、より服従訓練の効果を引き出すことができます。ただし、詳細な訓練内容は教室によって異なるため、通う前に事前に問い合わせて確認しましょう。
しつけ教室で服従訓練が必要なケース

すべての犬に服従訓練が必ず必要というわけではありません。しかし、以下のような状況では、専門家の助けをかりながら計画的に訓練を進めることが推奨されます。
初めて犬を飼った場合
犬を初めて飼う飼い主は、正しいしつけの手順やタイミングがわからず、不安や戸惑いを抱くことが少なくありません。しつけ教室では、専門のトレーナーが犬の行動だけでなく、飼い主に対しても指導を行うため、基礎から学びたい場合に有効です。
社会化期のタイミングを逃した場合
生後3週〜12週は社会化期と呼ばれ、この時期の経験が犬の将来の行動に大きな影響を与えます。人やほかの犬、音、環境など、さまざまな刺激を受けて慣れることが重要です。
しかし、この時期に十分な刺激を受けずに成長した犬は、環境変化に過敏になりやすく、警戒心や恐怖反応が強く出ることがあります。服従訓練は、このような犬に対し、新しい環境に適応するための学習を促す手助けになります。
落ち着きがなく、衝動的な行動がみられる犬
散歩中に突然走り出す、チャイムの音で吠え続けるなど、衝動的な行動が多いような感情のコントロールが難しい犬は、服従訓練を受けることでそのような刺激のなかでも落ち着いて行動する力を養うことができます。
しつけ教室で行われる服従訓練の具体的な内容

しつけ教室での服従訓練は、単に指示に従うことを教えるだけではなく、犬が人と協調して行動し、家庭や社会で快適に過ごせる力を育むことを目的としています。
そのため、訓練内容は犬の年齢、性格、家庭環境などに応じて調整されます。
服従訓練の内容
代表的な訓練項目には以下のようなものがあります。
- 基本的な指示の習得:お座り、伏せ、待て、おいでなど
- アイコンタクトの習慣化:指示の入りやすさや信頼関係を向上させる
- 脚側行進(きゃくそくこうしん):リードがたるんだ状態で人の左側を歩くこと
- 脱感作:人、音、物など犬が苦手な刺激や状況に少しずつ慣れさせ、恐怖や不安を軽減させる
- 障害物跳躍(しょうがいぶつちょうやく):飼い主の指示で障害物を飛び越える訓練
これら以外にも、しつけ教室によって異なる訓練内容があり、犬の特性に応じた指導が行われます。
一般的な服従訓練の流れ
服従訓練は1回で大きな変化が見られるものではなく、段階的に成長していく学習方法です。一般的な流れは以下のとおりです。
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | カウンセリング、性格評価 | トレーナーが犬の性格や行動傾向、飼い主との関係性などを観察して、どのような訓練が必要かを判断する。 |
| 2 | 基本行動の導入 | お座り、待て、伏せなどの基本的な指示を理解させることから開始する。これによって、犬が飼い主の指示に従う習慣を習得させる。 |
| 3 | 訓練の目的を決める | 基本行動が安定したら、多くの刺激のなかでも落ち着いて行動するための応用練習へ移行する。具体的には、屋外の環境や、家族以外の人、ほかの犬がいる状況で練習を行う。 |
| 4 | 日常生活へ応用する | トレーニングで得た内容を家庭内で活かす方法を学ぶ。(食事前に伏せ、来客時は静かに待機するなど) |
| 5 | 飼い主への指導 | 犬だけでなく、飼い主にも日々の生活のなかで訓練中と同じような接し方ができるように指導を行う。 |
しつけ教室の服従訓練にかかる費用相場と期間の目安

服従訓練を受ける際に、飼い主が気になる点の1つが費用と期間です。しつけ教室の料金体系は、教室の規模や地域、トレーナーの資格、提供スタイル(個別指導やグループ指導)などによって大きく異なります。ここでは、一般的な費用相場と期間の目安を紹介します。
服従訓練の費用相場
服従訓練の費用は、トレーニングの種類や教室の形式によって異なりますが、一般的な相場は以下のとおりです。
| 訓練形式 | 費用 |
| グループレッスン | 約4,000~6,000円/回 |
| 出張レッスン | 約5,000~10,000円/回(別途交通費が必要な場合あり) |
| ショートステイ(合宿型) | 約50,000~70,000円 |
| 長期預かり訓練 | 約60,000円~200,000円 |
また、教室によっては入会金が必要な場合もあり、その子の年齢や性格、体格によって料金が変わることもあります。そのため、詳細な料金は事前に各教室へ確認しましょう。
服従訓練にかかる期間の目安
服従訓練の期間は、その子の学習の進み具合やトレーニングの目的によって異なりますが、短期間で習得できるものではなく、継続的な取り組みが必要です。一般的な目安は以下のとおりです。
- 初級レベル:約1〜3ヶ月
- 中級レベル:約3~6ヶ月
- 上級レベル:6ヶ月以上
服従訓練の効果はしつけ教室での訓練だけでなく、家庭での継続的な実践によっても大きく左右されるため、家庭でも復習することが重要です。
服従訓練コースの選び方

しつけ教室の服従訓練は、どこで誰に教わるかによって成果や犬のストレスが大きく変わります。そのため、教室選びは慎重に行う必要があります。特に初めてであれば、以下の内容を重視して選びましょう。
トレーナーの資格と経験を確認する
犬のしつけを指導するには、科学的な知見に基づいた方法で行うことが重要です。必須ではありませんが、以下の資格を持つトレーナーは、専門的な教育を受けた証として教室選びの参考になります。
- 日本ドッグトレーナー協会(JDTA)
- JKC公認訓練士(ジャパンケネルクラブ)
- 日本警察犬協会 指導手
ただし、資格を持っていることがトレーナーの実力を保証するわけではありません。そのため、資格の有無だけでなく、指導経験や専門性(愛玩動物看護師の資格を持っているかどうかなど)を総合的に判断することが重要です。
褒めて伸ばす指導方法を行っている
トレーニング方針は教室によって異なりますが、犬にストレスや恐怖を与える方法(首を強く引く、押さえつけるなど)を採用している教室は避けましょう。近年の研究では、恐怖を与えるよりも、褒めて伸ばす方が効果的であることが報告されています。
初回のカウンセリング時に、どのような方法で教えるのか、注意する際の対応方法などを事前に確認することが重要です。
個別指導とグループ指導の違いを理解する
服従訓練には、個別指導とグループ指導の2種類があり、それぞれの特性を理解して選びましょう。
| 指導形式 | 特徴 |
| 個人指導 | 犬の個性や特徴に合わせた細やかな指導が可能だが、費用が高くなる傾向。 |
| グループ指導 | 費用を抑えられるが、ほかの犬の影響で集中しにくく、効果が低くなる場合がある |
個別指導とグループ指導を併用できる教室もあるため、必要に応じて切り替え可能できるかも事前に確認しておきましょう。
通いやすくて継続できる
服従訓練は短期的なものではなく、継続的な取り組みによって成果が現れます。そのため、以下の点を考慮すると無理なく続けやすくなります。
- 教室の立地:生活圏内にあって、通いやすいか
- 時間帯:仕事や日常生活のスケジュールに合わせやすいか
- 予約の取りやすさ:柔軟に訓練の予定を組めるか
特に生活範囲内で通いやすい環境を選ぶことで、日常的なトレーニングを行う際もスムーズに行えます。
しつけ教室に服従訓練に通う際の注意点

しつけ教室に通う際には、いくつかの注意点を理解しておくことで、無理なく継続でき、訓練効果を高められる可能性があります。
訓練の進行度には個人差がある
服従訓練を受けても、すべての犬が同じペースで成長するわけではありません。犬の性格や背景はさまざまで、例えば以下のような違いがあります。
- 臆病な犬:環境の変化に慎重で、慣れるまで時間がかかる
- 活発すぎる犬:注意が逸れやすく、集中力を持続させる工夫が必要
- トラウマを持っている犬:過去の経験が行動に影響を与えるため、慎重な対応が必要
このように、それぞれの犬によって進行度は異なるため、焦ったり、ほかの犬と比較したりせず、愛犬のペースに合わせた進め方を心がけましょう。
飼い主も参加する姿勢を持つ
服従訓練は、犬だけでなく飼い主さんも学ぶことが必要です。トレーニング中はトレーナーに犬を任せきりにせず、飼い主さん自身も積極的に関わりましょう。家庭での練習でも、教室と一貫した対応を取ることで学習の定着が促されます。しつけ教室の指導をただ受けるのではなく、飼い主さん自身が学び、実践する姿勢を持つことが重要です。
トレーニング後も家庭内で練習を行う
教室で学んだ内容は、日常生活で繰り返すことにより定着します。1回習っただけでは身に付かず、家庭での対応が教室と異なると、犬が混乱しやすくなるため、以下の内容を意識しましょう。
- 家庭での対応を教室と統一する
- 家族全員で学んだ内容を共有する
- 日常の場面で教室で習った内容を積極的に実践する(食事前の待て、来客時に落ち着いて過ごすなど)
トレーニングは教室だけで終わるものではなく、家庭で継続することが重要です。
まとめ
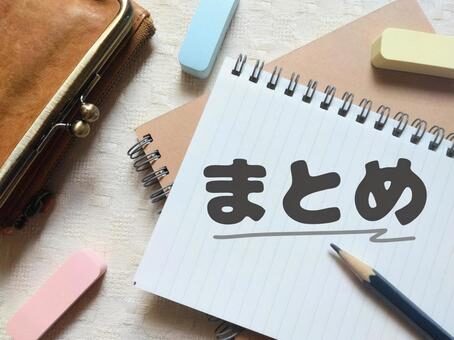
愛犬との暮らしをより快適にするために、しつけ教室で行われる服従訓練は大きな助けになります。服従訓練を受けることで、お座りなどの基本的な指示に従えるようになるだけでなく、ほかの犬や人との関わりも深められます。
訓練は段階的に進められ、一般的に初級・中級・上級のレベルに分かれています。特に、初めて犬を飼う方や、落ち着きのない子、問題行動のある子には、専門家のサポートによる訓練が有効です。費用や期間、トレーニングの形式はさまざまで、それぞれの子に適した内容を選ぶことが重要です。
ただし、どの子も一度の訓練ですべてが変わるわけではありません。トレーニングを積み重ねることで、犬は自信を持ち、飼い主さんとの絆も深まっていきます。まずは愛犬の現在の様子を振り返り、少しでも気になる点があれば、しつけ教室や動物病院への相談から始めてみましょう。
本記事が、しつけ教室の服従訓練を選ぶ際の参考になれば幸いです。
参考文献


