愛犬や愛猫の口元に黄色や茶色の汚れが見られたら、それは歯石かもしれません。放置すると口臭や食欲低下を引き起こす原因になります。
本記事では動物病院での歯石取り処置の流れや料金相場、注意点を解説します。正確な知識でペットの健康をサポートしましょう。
ペットの歯石取りを行う理由
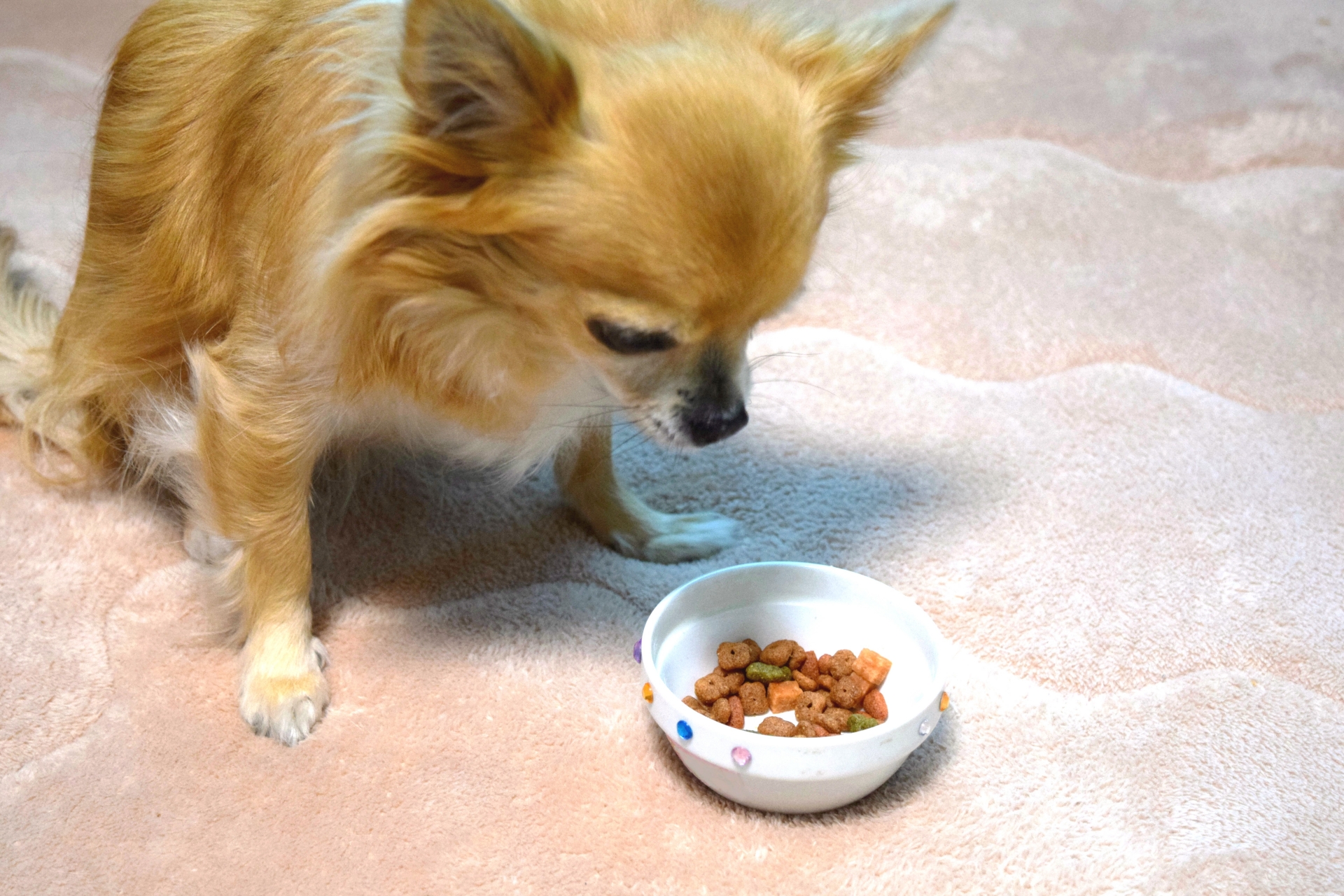
ペットの口臭が強いのは、歯石が蓄積している可能性があります。歯垢や歯石に繁殖した細菌は、口内環境を悪化させ、歯周病や歯肉炎を引き起こします。
これらの症状は初期段階では見た目の変化が少ないため見逃されがちです。しかし進行すると歯茎の腫れや出血など明らかな症状が現れます。
さらに口内細菌は血流を通じて全身へ広がり心臓や腎臓にも影響するので注意が必要です。特に小型犬や猫は歯石が付きやすく、7歳以上の犬の約80%が歯周病を抱えているとされます。
歯周病による慢性炎症は、全身の免疫力低下を招き、さまざまな健康問題の原因になります。若いペットでも早期からのケアが大切です。
歯のトラブルは痛みを伴い生活の質を下げるため、適切な歯石取りと予防が推奨されています。歯痛によって食欲が減退すると、栄養不足により全身状態が悪化する悪循環に陥ることがあります。
動物病院での犬や猫の歯石取りの流れ

動物病院での歯石除去処置は、一般的に以下のような手順で実施されます。初めて経験する飼い主にとっても理解しやすいよう各ステップを詳しく解説します。
視診や打診による診察
初めのステップは獣医師による口腔内検査です。歯石の付着状況や歯肉の炎症、歯のぐらつきなどを確認します。この初期評価により、歯周病の進行程度や口腔全体の健康状態を把握可能です。
獣医師は専門的な知識と経験に基づき視診と触診を組み合わせて評価します。この段階では飼い主も立ち会うことができるため疑問点があれば質問するとよいでしょう。
診察時にはペットの普段の食事内容や歯磨きの頻度など生活習慣についても情報提供すると診断の参考になります。
施術前の検査

歯石除去処置は通常全身麻酔下で実施されるため、麻酔リスクを調べる術前検査が必須となります。リスクを見極めるため、全身の健康状態を詳しく調べることが重要です。
術前検査には、血液検査や心電図検査などが含まれます。高齢動物や基礎疾患を持つペットではより包括的な検査が実施されることもあります。
これらの検査結果は飼い主にも説明されるので不明点は遠慮なく質問しましょう。麻酔について不安がある場合は、事前に相談しておきましょう。
歯石取り
術前検査で麻酔に問題がないと判断されれば歯石除去処置が行われます。全身麻酔導入後、専門的な超音波スケーラーを使用して歯石を除去していきます。
専用の器具を使うことで歯を傷つけることなく効果的に歯石を取り除くことが可能です。処置では表面的な歯石除去だけでなく、歯茎の下にある歯周ポケット内の清掃も行われます。
歯周ポケット内は目視できないため、麻酔下での処置が必要です。処置後には歯面研磨が行われ歯の表面を滑らかにします。
施術時間は歯石の量や歯の状態によって異なりますが、一般的には30分から1時間程度かかります。重度の歯周病が認められる場合は、同時に抜歯処置が必要です。
抜歯は痛みや感染源を取り除き、口腔環境を改善するための重要な治療法です。処置中は常にバイタルサインがモニタリングされ、麻酔深度や全身状態が管理されています。
動物病院での歯石取りの料金

歯石除去処置の費用は、麻酔の有無や動物の大きさ、そして動物病院の立地や設備も料金に影響します。以下では一般的な料金相場を解説します。
麻酔ありの場合の料金
全身麻酔下での歯石除去処置の一般的な料金相場は以下のとおりです。
- 小型犬・猫:15,000円〜30,000円(税込)
- 中型犬:20,000円〜40,000円(税込)
- 大型犬:30,000円〜50,000円(税込)以上
この料金には基本的な血液検査や麻酔管理費が含まれている場合があります。なお、動物病院によっては検査費用が別途加算されることもあります。
また、歯周病が進行しており抜歯処置が必要な場合は、1歯あたり3,000円〜10,000円程度の追加費用が発生することが一般的です。抜歯の難易度や本数によって総額は変動します。
歯石除去の費用は予防医療の観点から見ても、将来的な疾患を防ぐための投資です。口腔内細菌による全身性疾患のリスク低減や、定期的なケアによる大規模な治療の回避という点で、長期的な健康管理コストの削減にもつながります。
無麻酔の場合の料金
一部の動物病院では無麻酔での歯石除去を提供しており、その料金は5,000円〜15,000円程度と、より低価格に設定されています。初期費用だけを見ると経済的に魅力的に感じるかもしれません。
しかし無麻酔での処置には重要な制限があります。歯茎の上の眼に見える歯石のみしか除去できず、歯周病予防に重要な歯茎の下の清掃が十分に行えません。
また動物にとって拘束によるストレスが大きく、適切な処置が困難になる場合もあります。獣医歯科学の観点からも無麻酔での歯石除去の有効性については専門家間で見解が分かれるところです。
麻酔に対する不安から、無麻酔処置を選択するケースも見られます。しかし口腔内健康の包括的な管理と処置の完全性を考慮すると全身麻酔が望ましいでしょう。
適切な術前検査と麻酔管理を伴う処置が専門家からも推奨されています。次項では、麻酔下での処置の具体的なメリットについて詳しく解説します。
ペットの歯石取りで麻酔をするメリット

全身麻酔下での歯石除去処置には多数の医学的メリットがあります。初期費用は高くなりますが、処置の質に加え、以下のような具体的な利点があります。
痛みを軽減できる
歯石除去処置中、特に歯肉炎や歯周炎を発症している場合、歯茎は炎症を起こしています。炎症があると、わずかな処置でも強い痛みを伴うことがあります。
全身麻酔の使用により、処置中の痛覚が遮断され、動物のストレスや不快感を極力抑えることが可能です。適切な鎮痛管理は獣医療における重要な倫理的配慮であり、動物の福祉向上に不可欠な要素です。
処置中に痛みを感じないことで、術後の回復も円滑になるという利点もあります。麻酔中は獣医師が適切な鎮痛薬を併用することで、処置後の痛みも効果的に管理できます。
歯石取りの安全性を高められる
無麻酔状態では動物が突然動いたり、処置に抵抗することがあります。これにより鋭利な歯科器具による口腔内組織の損傷リスクが高まります。
麻酔に関連するリスクへの懸念は無視できません。しかし現代の獣医学ではさまざまな対策が取られています。術前スクリーニング検査や麻酔中の細やかなモニタリング技術が発達しました。
さらに個体に適した麻酔プロトコルの選択により麻酔リスクを大幅に低減できることが示されています。適切な麻酔管理は、処置の質を向上させる重要な要素です。
歯周ポケットまで清掃できる

歯周病原性細菌は、主に歯茎の下の歯周ポケット内に生息しており、目視できる歯石の下に隠れています。全身麻酔下でのみ、これらの領域への適切なアクセスと徹底的な清掃が可能です。
表面的な清掃だけでは根本的な問題解決にならず、歯石は短期間で再形成される傾向があります。歯周ポケット内の細菌バイオフィルムを除去することで、真の治療効果が得られ、再発率が低下します。
専門的な歯科器具と技術を用いた歯肉縁下清掃は、口腔衛生の維持に不可欠です。
すでに治療が難しい歯は抜歯できる
重度の歯周病により保存不可能と判断された歯がある場合、同一処置中に抜歯を行うことが可能です。抜歯は侵襲性の高い処置であり、適切な麻酔と鎮痛管理が絶対に必要です。
罹患歯の抜歯により、慢性的な痛みや感染源が除去され、周囲の健康な歯組織への病変の拡大を防止できます。
獣医歯科学の研究によれば、適切な時期に行われた抜歯処置は動物の食欲回復や活動性の向上など、生活の質を著しく改善することが示されています。抜歯後の環境は、残った歯の健康維持にもよい影響を与えます。
歯石が付着するのを予防する方法

日常的な予防ケアで歯石形成を抑え、動物病院でのクリーニング頻度を減らすことができます。予防は治療よりも経済的で飼い主とペットの負担も軽減できるメリットがあります。
定期的な歯磨きが特に効果的です。獣医歯科学研究では、適切な歯ブラシと専用歯磨き剤による毎日のケアで、歯垢をおよそ8割も減少させることができるとされています。
毎日行うのが理想ですが、週2〜3回のケアでも十分な効果が期待できます。子犬や子猫の頃からあらかじめ慣らしておくとよいでしょう。歯磨きの際は無理にお口を開かせるのではなく徐々に慣れさせる方法が効果的です。
ペット用の指サックブラシから始め、徐々に通常の歯ブラシへ移行するのがスムーズです。歯磨きが難しい場合は以下の代替製品が有効です。
- 特殊設計ドライフード:咀嚼による歯面清掃
- 酵素配合デンタルトリーツ:唾液中で活性化し歯垢分解
- 口腔ケア用水添加剤:細菌繁殖抑制
- デンタルジェル・スプレー:歯垢形成抑制
- デンタルワイプ:物理的歯垢除去
これらを獣医師の指導のもとで併用することで歯石の蓄積を抑えられますが、専門的な処置の完全な代替にはなりません。
定期的な獣医師の検査と処置は長期的な口腔健康に必要です。予防と定期健診を併用することでペットの口腔健康を守りましょう。
動物病院で歯石取りをしてもらう場合の注意点

歯石除去処置を受ける際には、その効果を十分に得るために注意すべき重要なポイントがあります。以下のチェックリストを参考に、事前準備と情報共有を行うことをおすすめします。
歯周病などほかの症状がないか診てもらう
歯石除去処置を依頼する際は、単に歯石除去のみを目的とするのではなく、包括的な口腔内健康評価を受けることが重要です。
歯周病や口内炎、腫瘍性病変など、ほかの口腔内疾患が併発している可能性があります。初期に疾患を発見することで、治療の難易度や予後が大きく変わります。
早期発見・早期治療により、より侵襲性の低い処置で対応可能なケースが多く、結果としてペットと飼い主の負担を軽減することが可能です。歯石除去と同時に総合的な口腔内検査を受けることは予防医療の重要な一環です。
ペットに持病がある場合は事前に医師に相談

心臓疾患や腎疾患を持つペットでは麻酔リスクが上昇する可能性があります。肝疾患や糖尿病なども麻酔に影響するため、事前に獣医師へ既往歴と現在の治療内容を詳細に伝えることが必須です。
基礎疾患があるからといって必ずしも麻酔処置ができないわけではありません。多くの場合、疾患の状態に応じた麻酔プロトコルの調整や追加モニタリングにより、丁寧に処置を行うことが可能です。
場合によっては持病の管理状態を整えてから歯科処置を行う必要があるため、タイミングの調整が重要になることもあります。
以前麻酔によるアレルギー症状が出たことがないか
過去の麻酔経験における有害事象やアレルギー反応の情報は、丁寧な麻酔管理に不可欠です。麻酔からの覚醒遅延や血圧低下、不整脈のほかアナフィラキシー反応など、以前に発生した問題があれば、必ずあらかじめ獣医師に伝えましょう。
これらの情報により、獣医師は代替の麻酔薬選択や追加のモニタリング措置を講じることができます。
初回麻酔の場合でも、ほかの薬物アレルギーの既往や特定の薬に対する反応性などの情報提供が重要です。適切な情報共有により、個体に合った麻酔計画が立案されます。
院内の設備が整っているか
歯石除去処置を行う動物病院の設備や専門性は、処置の質と以下の点に直結します。理想的には、以下の設備および体制が整っている医療機関を選択することが望ましいでしょう。
- 麻酔モニタリング機器:心電図、血圧計など
- 歯科用レントゲン設備:歯根部評価用
- 歯科用超音波スケーラー:専門的歯石除去
- 術中保温・輸液管理システム:麻酔管理用
- 歯科処置に精通した獣医師:専門的技術提供
これらの設備や体制をあらかじめ確認することで、より質の高い歯科処置を受けることができます。必要に応じて複数の病院を比較検討し、設備と専門性のバランスが取れた医療機関を選択することも一つの方法です。
まとめ

ペットの歯石除去は美容だけでなく健康維持に不可欠な予防医療です。全身麻酔下での処置により、歯周ポケットの清掃や必要な抜歯を含む包括的なケアが行えます。
費用は小型犬・猫で15,000円〜30,000円、中大型犬で20,000円〜50,000円が相場です。将来的な疾患の予防を考えれば、費用は合理的な投資といえるでしょう。
日常の歯磨きやデンタルケア製品で歯石蓄積を遅らせられますが、専門的処置の代わりにはなりません。口臭悪化や歯の変色に気付いたら早めに動物病院へ相談しましょう。
愛犬や愛猫の健康と生活の質を守るために、口腔ケアを日常管理の一環として継続し、獣医師と連携して適切なケアプランを立てましょう。
参考文献


