元気いっぱいに走り回る愛犬が、突然足をかばうように歩き始めたら、飼い主としては心配でたまりませんよね。もしかしたら、それは骨折のサインかもしれません。犬の骨折は、日常生活の些細な事故から、思いがけないアクシデントまで、さまざまな原因で起こります。
本記事では犬の骨折について以下の点を中心にご紹介します。
- 犬の骨折の原因や症状
- 骨折しやすい犬の特徴
- 犬の骨折の予防法
犬の骨折について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
犬の骨折について

犬の骨折とはどのような特徴や原因などがあるのでしょうか。以下で解説します。
犬の骨折の特徴
犬の骨折は、人間と同じく骨に急な衝撃が加わることで起こりますが、発生するシチュエーションはよりさまざまです。例えば、ソファから飛び降りたり、フローリングで滑ったりといった、ありふれた行動のなかでも骨折する可能性があります。
なかでも小型犬や骨の細い犬種は、前足を中心に骨折のリスクが高い傾向があります。前足には橈骨と尺骨があり、両方同時に折れることも珍しくありません。骨折はヒビや欠けも含まれ、重症度には幅があります。
犬が骨折する原因
犬が骨折する原因はさまざまです。
例えば、高所からの落下が骨折の原因となるケースがあります。なかでも、好奇心旺盛で動きが活発な1歳未満の子犬は、抱っこ中の落下やソファやベッドなどからの飛び降りによって、骨に強い負荷がかかりやすくなります。
ほかにも、滑りやすいフローリングでの転倒、階段昇降中の落下、飼い主さんが誤って踏んでしまう事故なども原因になります。さらに、散歩中の交通事故や、ほかの犬との接触でも骨折が起こることがあります。
まれに、骨腫瘍やホルモン異常、カルシウム不足による内部要因で、軽い衝撃でも折れてしまう病的骨折が発生することもあります。骨折は激しい衝撃などの外部要因だけで起こるわけではないことを理解しておきましょう。
犬の骨折の症状
犬が骨折した際には、患部が腫れて熱を持ち、触れると強く痛がる反応を示します。足をかばうように地面につけずに歩く、歩行を拒む、ふらつくといった症状が見られます。顎の骨折では食事が困難になります。神経を巻き込むような骨折をすると排尿や排便がしづらくなることもあります。
また、犬は痛みを我慢する傾向があり、じっとして動かなくなる、隅でうずくまるなどの行動にも注意が必要です。さらに、折れている部分を頻繁になめたり、抱っこを嫌がったりする異変も見逃さないようにしましょう。歩き方や生活行動に違和感が見られた場合は、すぐに動物病院を受診することが大切です。
犬の骨折の主な種類

ここでは、犬の骨折の種類を詳しく解説します
横骨折
横骨折とは、骨が横方向にまっすぐ折れてしまうタイプの骨折です。骨の断面に対して水平に近い形で骨折線が入るため、整復後の安定性が高いとされています。
ギプスなどで適切に外固定すれば治癒することが期待でき、ほかのタイプの骨折よりも治療の難易度は低い傾向にあります。
斜骨折
斜骨折とは、骨が斜め方向に割れてしまうタイプの骨折です。行動を抑制できない犬では骨片同士の位置がずれやすく、ギブスのみでの回復は難しい場合があります。
このため、多くの場合、プレートやピンを用いた外科的な整復手術が必要です。放置すると骨が正しい位置に癒合せず、変形や後遺症を引き起こすリスクがあるため、早期の外科的処置が推奨されます。
らせん骨折
らせん骨折とは、骨に強いねじれの力が加わった際に発生する骨折です。
斜骨折同様ワイヤーやピンを使用した内固定が主流で、多くの場合で手術が必要です。走ったり飛び跳ねたりした際の転倒など、激しい動きに伴う事故で起こりやすい骨折とされています。
粉砕骨折
粉砕骨折とは、骨が複数の細かい破片に分かれてしまう重度の骨折です。交通事故や高い場所からの落下など、大きな外力が加わった際に発生します。
骨の破片が不規則に散らばるため、骨を元の形に整えることが困難です。外見上も変形が見られることが多く、外科手術による整復が必要ですが、治療の難易度は高いといえます。元の骨同士が癒着せず癒合不全となり、骨折の治癒が遅く再手術を繰り返す小型犬も少なくありません。
開放骨折
開放骨折とは、骨折によって皮膚が破れ、折れた骨が外に露出した状態を指します。骨と外部が直接接触するため、細菌感染のリスクがとても高く、速やかな処置と緊急手術が求められます。
いわゆる複雑骨折に分類され、治療には傷口の清潔保持、抗生剤の投与、骨の整復など、総合的かつ迅速な対応が必要です。
骨折しやすい犬種・年齢

ここまで犬の骨折について特徴や種類などをみてきましたが、骨折しやすい犬はいるのでしょうか。以下で解説します。
骨折しやすい犬種
犬の骨折リスクは犬種によって異なり、なかでも注意が必要なのがトイ・プードル、ポメラニアン、イタリアン・グレーハウンドなどの小型犬です。これらの犬種は骨が細く、脚の骨も鉛筆程の太さしかないため、わずかな衝撃でも骨折しやすい傾向があります。
加えて、抱っこされる機会が多い傾向にあることから、落下事故による骨折リスクも高まります。
また、アイリッシュ・セターやボルゾイ、サルーキといったスリムな中型や大型犬も、骨が細長く筋肉量が少ないため、骨折しやすいとされています。どの犬種でも、交通事故など大きな衝撃による骨折の可能性はあり、日頃から注意が必要です。
骨折しやすい年齢
犬の骨折リスクは年齢によっても大きく変わります。まず、1歳未満の仔犬は骨が未成熟でとてももろいため、少しの衝撃でも骨折しやすい傾向があります。活発に動き回る時期でもあり、落下や転倒による骨折が目立ちます。
一方、シニア期の犬も注意が必要です。加齢に伴う骨粗しょう症や筋力や関節機能の低下により転倒しやすくなり、思わぬ骨折を引き起こすリスクが高まります。見た目では内部のリスクがわかりにくいため、定期的な健康診断を受けさせること、異変があればすぐに対処できるよう日頃から観察することが大切です
犬の骨折の治療法

犬の骨折には、以下のような治療法が用いられます。
外固定(ギプス)
外固定は、骨折した部位を外側からギプスで巻き、安定させる治療法です。ヒビのみの不全骨折、ズレが少ない単純骨折によく適用されます。手術を行わずに済むため、犬の身体への負担を抑えられるのがメリットです。また、シーネを用いた外固定などは手術前の一時的な固定処置として使われることもあります。
犬がギプスを嫌がって外そうとしたり、装着したまま激しく動くと、皮膚炎や擦り傷を引き起こすリスクがあります。皮膚や性格などの個体差によってギプス固定が適さない場合もあるため、治療方法は獣医師と相談して慎重に選びましょう。
内固定(プレート/髄内釘/ワイヤー)
内固定は、プレート、髄内釘やワイヤーなど医療用デバイスを、損傷した骨同士を固定するために体内に入れる観血的な治療法です。内固定よりも骨の形状をより正確に整復できるのがメリットです。
例えば、プレート固定の場合は、骨折部位を金属製のプレートとネジで強固に固定します。大型犬や活動量の多い犬など、しっかりとした固定が求められるケースでよく選択される治療法です。使用されるプレートには、様々なタイプがあり、症例に応じて選択されます。外科手術による犬への身体的負担が大きく、プレートの費用も高額なため、内固定よりも治療費が高くなります。
創外固定法
創外固定法は、体の外側からピンを骨に挿入したのち、ピン同士を体外で固定して骨折部位を固定する治療法です。複雑な骨折や、プレート等による内固定が難しいときの治療に用いられます。
骨が細くてプレートや髄内釘も難しい小型犬に適応があります。一方で、ピンが体外に露出しているため、感染リスクが高く、治療期間中を通して高いレベルでの清潔管理が求められます。
犬の骨折の治療期間・費用
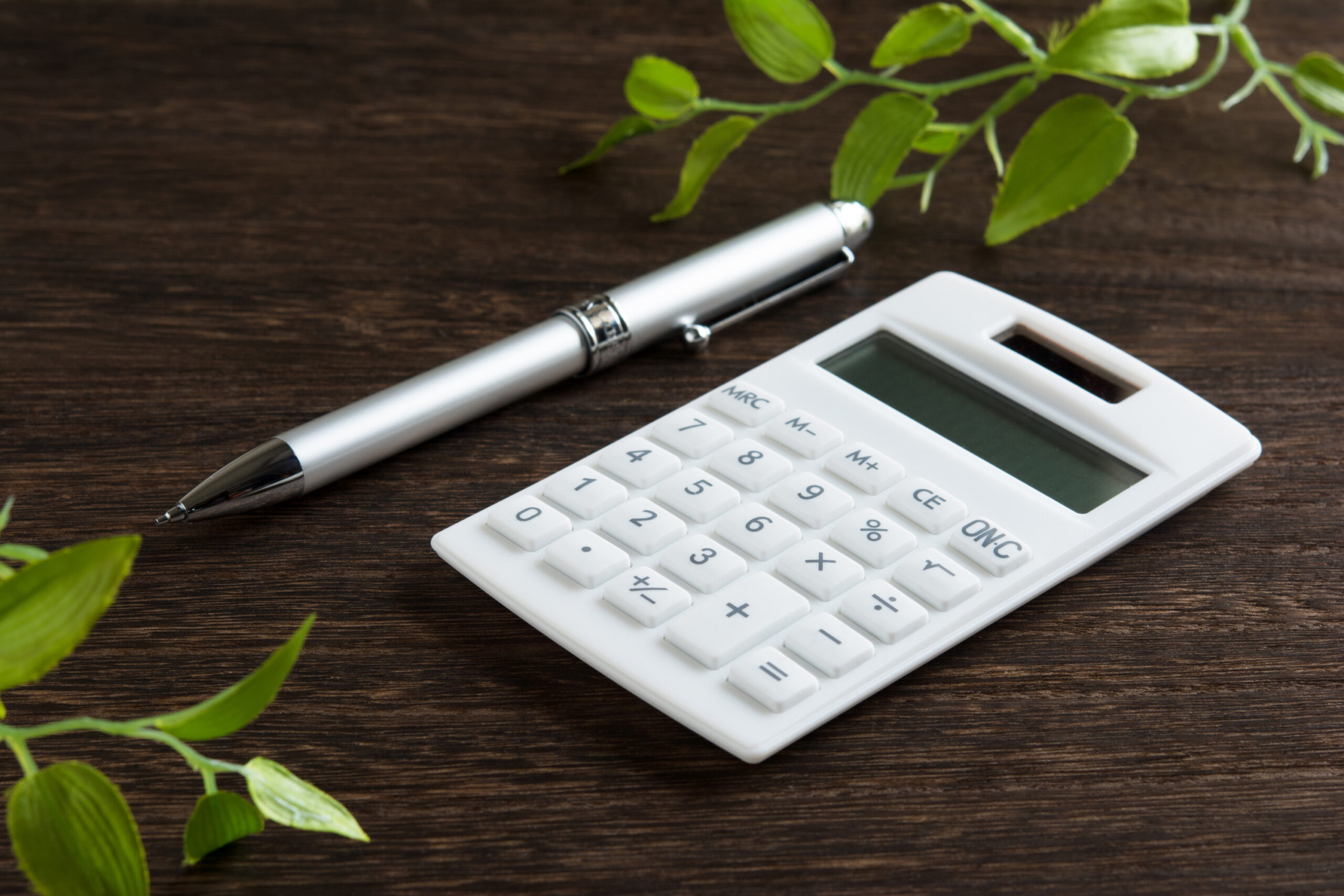
犬の骨折の治療期間や費用の目安を紹介します。
治療期間
犬の骨折治療にかかる期間は、骨の損傷具合や治療法、年齢などによって異なります。軽度な骨折であれば、2週間程で骨が修復されるケースもありますが、手術を必要とする重度の骨折は、治癒までに2〜3ヶ月程度かかるとされています。特に治癒力の低下した老犬や、残念ながら癒合不全に至った場合は、回復に半年程かかることもあります。
手術後は入院や通院が必要になる場合が多く、犬のストレスだけでなく、飼い主の時間や経済的な負担も大きくなる傾向があります。
治療中は安静に過ごさせることが重要で、日常生活の調整や自宅でのケアも必要です。正確な期間は獣医師の診断をもとに確認するようにしましょう。
治療費用
人間のような公的保険がなく、また治療は定額ではありません。そのため、犬の骨折治療にかかる費用は、病院ごと、骨折の場所や重症度、そして選択する治療方法によって大きく異なります。
ギプスやシーネなどの外固定で対応できる軽度の骨折であれば、5〜10万円程度が相場です。金属プレートやピンなどの医療デバイスを用いる骨折手術の場合は、麻酔や入院、手術材料費を含めて20〜40万円程かかる傾向にあります。骨折部位や使用材料によってはさらに高額となり、創外固定などでは50万円近くになるケースもあります。
さらに、術後の通院やリハビリ、定期検査といった追加費用も考慮が必要です。突然の出費に備えるためにも、ペット保険への加入や事前の貯蓄をしておくと、万が一のときに安心して対応できるでしょう。
犬の骨折を予防する方法
犬の骨折を防ぐためにも、以下のような方法を試してみましょう。

犬の骨折を防ぐためにも、以下のような方法を試してみましょう。
食事と運動の改善
犬の骨を丈夫に保つには、バランスのとれた食事と適度な運動が欠かせません。カルシウムやビタミンDを含む食事を意識し、日光浴も取り入れることで、骨の健康維持に役立ちます。
また、運動によって筋肉を鍛えることで骨への負担を軽減でき、骨折リスクの低下につながります。ただし、過度な運動は関節や骨にかえって負担をかける恐れがあるため、成長期の子犬や高齢犬は特に注意が必要です。
生活環境を整える
家庭内の環境整備は、犬の骨折を防ぐうえで重要です。
フローリングは滑りやすく、転倒による骨折の原因になりやすいため、滑り止めマットやカーペットを敷いて対策しましょう。ソファやベッドなど高い場所からの飛び降りを防ぐため、専用のステップやスロープの設置もおすすめです。
階段にはゲートを設置し、ドアにはストッパーを取り付けるなど、行動範囲を適切にコントロールしましょう。屋外移動時の事故防止にも配慮しましょう。こうした小さな工夫が、愛犬の安全な生活につながります。
しつけを行う
犬の骨折を防ぐためには、日常のしつけも欠かせません。子犬の頃から「ハウス」や「まて」といった基本的なコマンドを教えることで、屋内外での予測不能な動きを抑え、事故のリスクを減らせます。
「ハウス」を覚えると、飼い主の目が届かないときでも安全な場所で落ち着いて過ごす習慣が身に付きます。また、「まて」ができれば、興奮して飛び出すなどの危険な行動を防ぐことが可能となるでしょう。
しつけは、犬の行動を管理するためだけでなく、愛犬の命を守るための大切な備えでもあります。
抱っこに慣れさせる
小型犬が骨折してしまう原因のひとつは、抱っこに慣れておらず暴れて転落してしまうことです。安全な場所で普段から練習して、抱っこの姿勢や動きに慣れさせることが大切です。
無理をせず、安心できる環境で少しずつ慣らしていきましょう。なかでも、子どもが犬を抱く際には、落下のリスクが高まるため、大人が見守るなか座った状態で練習するのが望ましいでしょう。
日常から正しい抱っこを習慣づけることが、骨折などの重大な事故を未然に防ぐポイントになります。
まとめ

ここまで犬の骨折についてお伝えしてきました。犬の骨折の要点をまとめると以下のとおりです。
- 犬の骨折は、高所からの落下や自宅での転倒、散歩中の交通事故のほか、まれに骨腫瘍やホルモン異常、カルシウム不足などの内部要因などで起こる
- 患部が腫れて熱を持ち、触ると痛がる、かばって歩くなどの反応を示す
- トイ・プードル、ポメラニアン、イタリアン・グレーハウンドなどの小型犬は、四肢の骨が細いため特に前肢を骨折しやすい。子犬やシニア犬も注意すべき特徴として挙げられる
- 犬の骨折を予防するには、バランスのとれた食事と適度な運動のほか、フローリングにカーペットを敷くなど生活環境を整えたり、大人しく抱っこができるようしつけたりなどが推奨される
犬は人間よりも弱い衝撃で骨折しかねません。愛犬との生活に注意を払い、何か異変を感じたときは、速やかに動物病院を受診しましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


