突然のお別れは、誰にとっても受け入れがたいものです。
それが大切な家族の一員のペットであれば、なおさら心の整理がつかず、深い悲しみに包まれることでしょう。特に動物病院に入院している間に亡くなってしまった場合、心の準備ができていないなかで、お別れを迎えることになり、戸惑いや混乱を感じる方も少なくありません。
この記事では、そのような状況に直面した飼い主さんに向けて、いざというときに知っておきたい対応の流れや、心のケアのヒントをお伝えします。
大切なペットが動物病院で亡くなったときの悲しみとの向き合い方

大切なペットを動物病院で亡くしたとき、飼い主さんの悲しみは計り知れません。「そばにいられなかった」と自分を責めてしまうこともあるでしょう。しかし、悲しみは深い愛情の証です。無理に元気を出そうとせず、涙を流すことも自然な心の反応として受け入れてください。焦らず、自分のペースで少しずつ心の整理をしていくことが大切です。
動物病院に入院中のペットが死亡したときに獣医師に確認したいこと

入院治療中にペットが亡くなった場合、獣医師にいくつか確認しておきたい点があります。ペットの最期の状況を知ることは、悲しみを和らげ今後の心の整理をするうえでも大切です。不明点を残さないためにも、遠慮せずしっかり説明を受けましょう。
入院中に亡くなった理由
ペットが入院中に亡くなった場合、入院経過や死亡の原因について確認します。病気の進行によるものなのか、治療中に急変したのか、あるいは予期せぬ合併症や事故があったのか、獣医師に確認しましょう。
確認すべき内容は、以下のような点が挙げられます。
- 入院中の治療経過と病状の変化
- 死因となった具体的な要因
- 治療内容と効果
- 亡くなる前の症状や兆候
最期の様子
次に、ペットの最期の様子について確認しましょう。最期の瞬間に苦しみはなかったか、安らかに眠るように息を引き取ったのか、どのような状況だったのかを知ることは、飼い主さんの心の整理につながることがあります。
獣医師に聞いておきたい内容は以下のようなものです。
- 亡くなる直前の状態(苦しんでいなかったか)
- 最期まで意識があったか
- スタッフからのケアは十分だったか
大切なペットが亡くなった直後は、気が動転していたり、気持ちの整理がつかなかったりして、獣医師に質問する余裕がないこともあるでしょう。ですが、後になって「あのとき、もっと聞いておけばよかった」と思うことがあるかもしれません。
獣医師からの説明を受けるときに大切なのは、疑問を残さないこと、そして納得できる形で話を聞くことです。そうすることが、ペットの死を少しずつ受け入れていくための大切な一歩になります。
疑問や後悔を少しでも減らせるよう、遠慮なく質問し、獣医師から必要な情報を得ておきましょう。
入院していた病院でのエンゼルケア

エンゼルケアとは、ペットが亡くなった後に身体を清め、安らかな姿で送り出してあげるための処置のことです。具体的には目や口を閉じて表情を整え、身体をきれいにして汚れを落とし、毛並みをブラッシングしてきれいにするなどのケアを行います。必要に応じて、排泄物が出てくる部位にガーゼを当て、硬直が始まる前に手足を自然な体勢に整えることも含まれます。
亡くなった子との最後の時間の過ごし方

ペットが亡くなった直後から火葬や埋葬までの間、亡くなったペットとの最後の時間が訪れます。この時間をどう過ごすかは飼い主さん次第ですが、後悔のないように十分にお別れをすることが大切です。ここでは、自宅でペットと過ごす際の具体的な準備を紹介します。
自宅で過ごす場所を整える
ペットの遺体をご自宅に連れて帰ったら、安置する場所を整えましょう。できれば直射日光の当たらない涼しく静かな部屋の一角を確保し、清潔な布やペットシーツの上にペットを寝かせてあげます。使い慣れたベッドや毛布の上に寝かせてあげるのもよいでしょう。身体の下には漏れ防止のためペットシーツを敷き、身体を優しく拭いて清潔にします。
安置場所を選ぶポイントは以下のようなものです。
- 涼しく風通しのよい場所
- 直射日光の当たらない場所
- 清潔で静かな環境
- 家族が集まりやすい場所
好きだったおもちゃやフードを用意する
ペットとの最後の時間を過ごす際、そばに置きたいものは生前に好きだったおもちゃや食べ物です。例えば、いつも遊んでいたボールやぬいぐるみ、毎晩抱えて寝ていたクッションなどがあれば、一緒に寝かせてあげるとよいかもしれません。フードボウルに好物のおやつやご飯を少し入れてそばに置いたり、水を一杯供えてあげたりするのもよいでしょう。
動物病院で亡くなったペットの火葬

ペットが亡くなった後の火葬方法には、大きく分けて、自治体による火葬と専門のペット葬儀業者による火葬があります。それぞれサービス内容に違いがあるため、飼い主さんの希望に合わせて選択します。また、自宅の庭などに土葬(埋葬)する方法もあります。
自治体での火葬
自治体で火葬をする場合、ほかのペットと一緒にまとめて火葬を行う合同火葬が基本になります。そのため、立ち会いや遺骨の返却(返骨)はできません。しかし、自治体によっては、ペットごとに火葬する個別火葬や返骨に対応している自治体もあります。自治体での火葬は、お住まいの自治体公式Webサイトで確認可能です。
申し込みは、市役所のごみ収集課や清掃事務所などの担当窓口に、飼い主さんが連絡して行います。申込み後は、指定された日時に遺体を引き渡します。引き渡し方法には、飼い主さんが遺体を指定の施設へ持ち込む方法と、自治体に収集(引き取り)を依頼する方法があります。自治体によっては持ち込みのみ対応している場合もあるため、申し込み時に確認しておきましょう。
専門事業者による火葬
ペット葬儀社やペット霊園などでは、飼い主さんの希望に応じたさまざまなプランが用意されています。例えば個別火葬や、火葬に飼い主さんが立ち会いお骨上げまで行う立会火葬など、人の葬儀に近い形で見送ることも可能です。また火葬炉のある霊園に飼い主さん自身がペットを連れて行く方法だけでなく、自宅まで移動火葬車で来てもらい自宅前で火葬を行うサービス、遺体を業者に引き渡して後日遺骨を返送してもらうプランなど、多様な供養方法が選べます。
自宅での埋葬
自治体での合同火葬や専門業者に依頼するのではなく、自宅での埋葬を検討されている飼い主さんもいらっしゃると思います。法律上、日本には人間の遺体について定めた墓地埋葬法がありますが、ペットの遺体に関する全国一律の法律は存在しません。そのため、自宅の庭など私有地であれば、法的には埋葬することに問題はありません。しかし、自宅での埋葬にはいくつかの注意点があります。特に気を付けたいのは、遺体の腐敗によって発生する臭いや害虫の発生です。また、ほかの動物に掘り返されるリスクもあるため、十分な深さに埋めるなどの配慮が必要です。
動物病院で亡くなったペットの供養について

ペットを火葬した後、遺骨や思い出をどう供養するかも大切なステップです。供養の方法には、ペット霊園など専門施設で供養する方法と、飼い主さん自身が自宅で供養する方法があります。
霊園での供養
ペット霊園や動物供養寺院で供養する方法です。火葬後、ペット霊園に遺骨を納め、僧侶にお経をあげてもらうことで手厚い弔いができます。霊園によって屋内に遺骨を安置する納骨堂やほかのペット達を一緒に埋葬する合同墓地があり、飼い主さんの希望に応じて選択できます。個別のお墓を建てられる霊園も存在します。
自宅での供養
遺骨を自宅に置いて供養する方法です。自宅供養の場合、まず自宅のなかでペットの遺骨を安置する場所を決めましょう。和室の一角や棚の上などに写真やお花を飾り、小さなペット用仏壇を設ける方もいます。
ペットが亡くなったときに必要な手続き
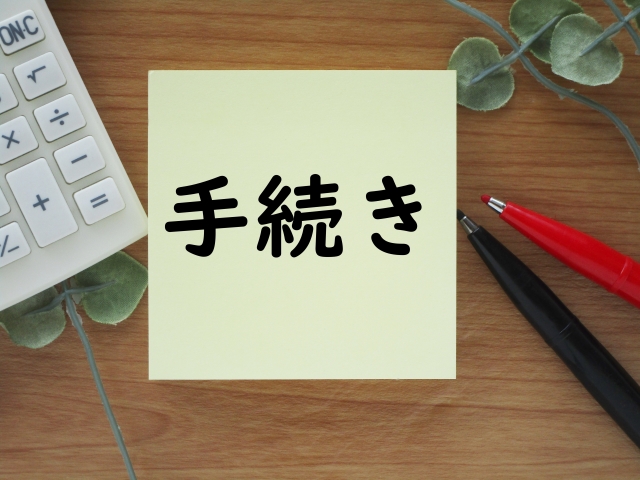
ペットが亡くなった際、公的な手続きが必要となる場合があります。特に犬の場合は法律で届け出義務が定められており、忘れずに対応しなければなりません。ペット保険に加入していた場合の解約などの手続きが必要です。
犬が亡くなったときの手続き
飼い犬が亡くなった場合、市区町村役場への死亡届の提出(畜犬登録の抹消届)が法律で義務付けられています。これは狂犬病予防法による規定で、生後91日以上の犬が死亡したときは30日以内に市区町村に届け出なければならないと定められています。
猫が亡くなったときの手続き
猫の場合、犬のような公的登録制度が基本的にはないため、役所へ届け出る必要はありません。マイクロチップを装着、登録している猫は、環境省のデータベースで情報更新の手続きを行うことが推奨されています。環境省データベース犬と猫のマイクロチップ情報登録には、所有者情報の変更やペットの死亡時の届出項目があります。もし飼い猫がマイクロチップ登録されていたら、データベース上で死亡の届出をしてください。
うさぎ、ハムスターや鳥類が亡くなったときの手続き
うさぎやフェレット、ハムスターやモルモットなどの小動物や小鳥類は、犬のような登録制度もなく、公的な届出義務もありません。そのため、小動物や小鳥類が亡くなった場合に、行政での手続きは必要ありません。
ペットが亡くなったときの保険金請求に関する手続き
ペット保険に加入していた場合、ペットの死亡時には保険会社への連絡と契約の解約手続きが必要です。解約時に必要な書類は保険会社により異なりますが、一般的には死亡日を確認できるもの(動物病院の死亡診断書や診療明細書など)が求められることがあります。また、解約返戻金の振込先口座の届出が必要になることもありますので、加入している保険会社の案内にしたがい、コールセンターなどに電話して指示を仰ぐとよいでしょう。
心のケアと受けられるサポート

ペットを亡くした悲しみから立ち直るには時間がかかります。無理に日常に戻ろうとしても、ふとした瞬間に涙があふれたり、気力が湧かなかったりするのはごく自然なことです。心のケアにはさまざまな方法や支援があるため、孤独に耐えようとせず上手に頼ってください。ここでは、飼い主さん自身の心を癒やすためのポイントと利用できるサポートについて解説します。
無理に立ち直ろうとしない
まず何よりも、悲しみから早く抜け出さなければ、と焦らないことが重要です。ペットを失った悲嘆は、簡単に消し去ることはできません。無理に元気な自分を演じても、後から大きな悲しみに襲われてしまうものです。
悲しみのプロセスには個人差があります。早い方もいれば遅い方もいます。数週間で前向きになれる方もいれば、何ヶ月も気力が戻らない方もいます。自分のペースでゆっくりと心を癒すことが、結果的に確かな立ち直りにつながります。
周囲の理解と助けを求める
悲しみが深いときこそ、周囲の支えが必要です。一人で抱え込んでしまうと、悲嘆が深まるばかりか精神的に不安定になってしまうおそれもあります。できれば家族や友人に今の気持ちを打ち明け、理解と協力を求めましょう。ペットロスは決して恥ずかしいことではなく、身近な方に話すことで心の整理がついていくものです。「実はペットが死んで辛い」「元気が出ない」と正直に話してみてください。きっと相手は親身になって耳を傾け、寄り添ってくれると思います。
グリーフケアを利用する
どうしても自分や身近な方たちだけでは悲しみを乗り越えられないと感じる場合、専門的なグリーフケアの利用を検討しましょう。グリーフケアとは、死別の悲嘆に対するケア全般を指し、カウンセリングやサポートグループ活動などが含まれます。ペットロスに特化したカウンセラーやセラピストも存在しており、飼い主さんの心に寄り添った支援を提供しています。ペットロスのカウンセリングでは、飼い主さんの話に耳を傾け、感じている罪悪感や後悔、悲しみの感情を受け止め、一緒に整理していく作業を行います。専門家に思いの丈を話すことで、自分では気付かなかった心の傷に気付けたり、感情の整理がついたりする効果が期待できます。
まとめ

動物病院で大切なペットを亡くすことは、飼い主にとって想像を絶する辛い体験です。しかし、適切な知識と準備があれば、その後の手続きや心のケアを少しでもスムーズに進めることができます。重要なことは、ペットへの深い愛情から生まれる悲しみは自然で正常な反応であり、悲しみを受け入れながら、自分のペースで癒しのプロセスを進めることです。
参考文献
- https://jvma-vet.jp/about/pdf/3-2.pdf
- https://jvma-vet.jp/about/projects/chikai_pdf/2-1.pdf
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/veterinarynursing/26/2/26_E1/_pdf
- https://petreien-a.tokyo/
- https://www.pref.saitama.lg.jp/a0706/doubutu/petsougi.html
- https://www.city.ichikawa.lg.jp/env07/1111000014.html
- https://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/page000447.html#:~:text=%E7%8A%AC%E3%81%AE%E6%AD%BB%E4%BA%A1
- https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/saijo/saijo/petto.html#1560C
- https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kankyo/gomi/gominowakekata/news/ippan06.html
- https://www.city.minato.tokyo.jp/unei/kurashi/gomi/kate/konnan/pethikitori.html
- https://reg.mc.env.go.jp/owner/owner_general_menu/init
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/tjp/17/0/17_1/_pdf/-char/ja


