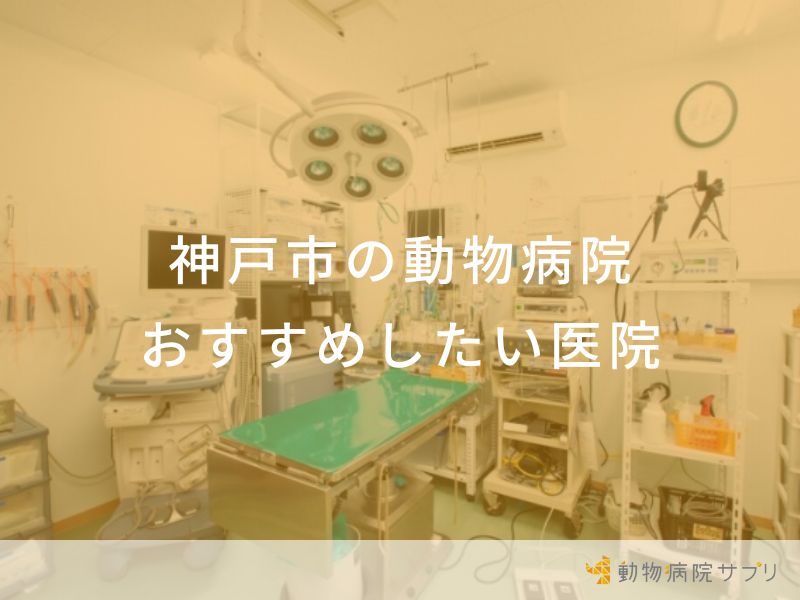犬の腎臓病とは、腎臓になんらかの異常や病気がある病態の総称です。腎臓病は初期段階では無症状であることも多いですが、進行すると、体に老廃物が蓄積してさまざまな症状を引き起こします。初期の腎臓病の場合、進行を食い止めるためのひとつの方法に食事療法があります。本記事では、腎臓病そのものの解説をしたうえで、食事療法のポイントなどをお伝えします。
犬の腎臓病とは

腎臓病という言葉はよく聞くものの、どういった症状が出るのか、治療にはどのような方法があるのか、寿命にどの程度影響するのかなどはわからない飼い主さんも多いでしょう。この章では、症状や治療法、予後について解説します。
腎臓病の症状
腎臓病は、急性腎障害と慢性腎臓病に分けられ、症状の現われ方に違いがあります。
急性腎障害の症状は、突然の元気や食欲の消失です。数時間から数日のうちに急激に腎機能が悪化し尿量が減少したり、まったく尿が出なくなったりします。嘔吐や、下痢が続くこともあります。
慢性腎臓病の場合、初期では無症状であることも多いです。進行すると、多量の水を飲み、多量の尿を排泄する多飲多尿が現われます。さらに悪化すると、食欲不振、元気消失、体重減少、嘔吐、下痢、便秘などさまざまな症状が現われます。皮膚や被毛の状態が悪くなったり、高血圧から眼底出血がでたりすることもあります。
さらに老廃物が体に蓄積されると、尿毒症をひきおこし、けいれんや昏睡などの神経症状が現われることもあります。
腎臓病の治療法
一度、慢性腎臓病にかかると、腎臓病自体の根本治療は難しいといえます。慢性腎臓病の治療は、進行を食い止めながら、症状に対する対症療法を行い、犬の生活の質を保つのが目的です。
慢性腎臓病の治療の中心は食事療法です。進行するにつれてさまざまな症状が出る傾向にあるため、症状に応じた対症療法も行います。
例えば脱水に対して点滴、嘔吐に対して制吐薬や胃酸分泌抑制剤、高血圧に対して降圧剤、貧血に対して造血剤などが挙げられます。場合によっては獣医師の指示、指導のもとで飼い主さんが自宅で定期的に皮下点滴をすることもあります。
一方で急性腎障害の治療法の基本は、腎障害を起こしている原因を解消することです。その原因も細菌感染や尿路閉塞、心不全などさまざまあり、まずは原因の特定が大切です。
また、腎臓への毒性がある薬物や中毒物質の誤飲など、原因がはっきりしていることもあるため、胃洗浄や吐かせる処置、活性炭などの吸着剤の投与なども行います。
原因が速やかに取り除かれれば腎機能が回復する可能性もありますが、腎障害が残ってしまうと慢性腎臓病に移行することもあります。
腎臓病の予後
慢性腎臓病は、国際獣医腎臓学研究グループ(IRIS)の分類を用いて、ステージ1~4に分けられ、ステージ1が初期でステージ4が末期です。
一般的に、ステージが早い段階で治療を開始できるほど予後がよい一方、ステージ4に進行した犬の生存中央値が約1.98ヶ月という報告があります。
参照:『犬と猫の慢性腎臓病の治療 治療に関するIRIS(国際獣医腎臓病研究グループ)からの提言〈2016年度版〉』(日本獣医腎泌尿器学会)
参照:『Factors associated with survival in dogs with chronic kidney diseas』(Journal of Veterinary Internal Medicine)
【犬の腎臓病】食事療法と効果

犬の腎臓病の場合、ステージ1~2の初期の段階では、食事療法が効果的です。この章では、食事療法とその効果をお伝えします。
食事療法とは
食事療法とは、病気の治療、進行防止、予防などのための、食事の内容の調整です。腎臓病のほかに、犬では食物に対するアレルギーや、肝臓病、尿路結石などで取り入れられることが多い自宅療法のひとつです。
腎臓病における食事療法において、頭に入れておくべきポイントは以下です。
- 低タンパク高エネルギー(カロリー)
- 低ナトリウム(塩分)
- 低リン
タンパク質が分解され発生する老廃物は、腎臓で代謝され、体外に排出されます。腎臓病になると、腎臓での老廃物の処理が衰えて、老廃物が体に蓄積しやすくなります。これをできるだけ避けるために、摂取するタンパク質を制限します。
一方、タンパク質を制限すると、摂取できるエネルギーも減ります。体内のエネルギーが不足すると、体は筋肉などを分解してエネルギーを補おうとするため、病態が悪化します。そのため、低タンパクでありながら、高エネルギーが得られる食事が基本です。
また、腎臓は、余分なナトリウムやリンなどのミネラルを濾過する機能も持ちます。これらが多量に摂取されると、腎臓に負荷がかかるため必要以上のナトリウムやリンの摂取は控える必要があります。
食事療法の効果
食事療法の具体的な効果を示す文献としては、2002年の研究があります。38頭のステージ2~3の慢性腎臓病の犬に対して、一般的なフードを与えた群と腎臓病用に設計されたフードを与えた群に分けて検証を行ったところ、後者の群の方が死亡までの期間が有意に長かったと報告されています。
食事療法の効果は、長期に渡って行うことで、腎臓病の進行を遅らせて、生活の質を保つことです。薬とは異なり、短期間ではっきりとした効果を実感する療法ではない点は頭に入れておく必要があります。
【犬の腎臓病】栄養バランスと食材の選び方

腎臓病の犬に実際どのような食事を与えればよいのかを考えるのは難しいですね。この章では、具体的な食材を挙げて与えたい食材と避けるべき食べ物を解説します。
積極的に摂りたい栄養素・食材
積極的に摂りたい栄養素はEPA、DHAなどのオメガ-3脂肪酸です。これらは、腎臓の炎症や高血圧を抑制する可能性が報告されているため、積極的に取り入れたい栄養素です。
これらの栄養素を食材から選択的に取り入れることは難しいのでサプリメントで補う方法が一般的です。
サプリメントにもさまざまなものがあるのでかかりつけの先生に相談してみましょう。
避けたほうがよい食材
上でもお伝えしたように、高ナトリウム、高リン食材は避けるべきです。これらを多く含む食品は以下となります。
- 人用加工食品
- 乳製品
- 肉、魚
ハムやソーセージなど、人用の加工食品は、一般的に高ナトリウムです。ナトリウムだけでなく、人用加工食品には、犬にとっては多量の糖分などが含まれる可能性があるため、控えましょう。
また、プロセスチーズ、ヨーグルトなどの乳製品、肉、魚といったタンパク質にはリンが多く含まれます。腎臓病の犬にとっては多量の摂取を避ける必要がある食材です。
ほかにも、ぶどうは犬にとって急性腎不全を発症させるリスクがあるため、絶対に与えないように気をつけましょう。生のぶどうだけでなく、レーズンなどの加工したぶどうも与えてはいけません。
フードを選ぶときのポイント
フードの裏面には、栄養成分が表記されています。栄養成分を確認して、低タンパクで高エネルギーなものを選ぶ必要がありますが、多種のフードのすべての栄養成分を見て選ぶのは難しいでしょう。
数あるフードのなかでも裏面に「療法食」と記載のあるものは病気の治療のために特別に栄養バランスが調整されたフードなので腎臓病療法食と記載のあるものがよいでしょう。
療法食もさまざまなメーカーから発売されているので、こうしたフードのなかから、より嗜好性のよいものなどを選ぶと効率的です。
また、療法食は獣医師の指示のもと開始する食事療法ですので飼い主さん自身での判断で与えないようにしましょう。
食欲が落ちている犬の場合、ドライフードよりも、ウェットタイプのフードの方が食いつきがよい可能性があります。ウェットタイプのフードの場合、水分補給の面でもメリットがあるため、選択肢に入れましょう。
【犬の腎臓病】食事療法のポイント

腎臓病の犬のなかには、病気の進行とともに食欲が落ちたり、腎臓によいフードに変えたのに食べてくれなかったりする子も少なくありません。この章では、食事の与え方のポイントをお伝えします。
食事の頻度
少量を複数回に分ける少量頻回の与え方を心がけましょう。たくさんの食事を一度に与えると、代謝による老廃物も一度に多量に出て腎臓に負担をかけます。
さらに、食欲が落ちている犬の場合、一度にたくさんの食事を与えるより、少しずつ与える方が食が進むこともあります。
食事のタイミング
食べない時間が長いと、体内で筋肉の分解がはじまる可能性があるため、食事間隔は短めに設定するのが大切です。
犬の食事は、朝晩の1日2回にしている飼い主さんも多いですが、可能であれば朝昼夜の1日3回にするのがおすすめです。
また、腎臓病で薬を処方されている場合は、薬と食事のタイミングにも気をつけましょう。リン吸着剤は、食事と同時に与えることで効果が発揮されます。反対に、吐き気を抑える薬は効果が出るまで1時間ほどかかるので空腹のタイミングでの投与が推奨されます。
食事を食べてくれないときの対処法
食欲が落ちて食事を食べてくれないときは下記のような対処を試してみましょう。
フードを温める
フードを温めると、香りがたち、食欲がそそられるため、効果的なことがあります。特に、高齢の犬の場合、嗅覚が衰えてきている可能性もあり、いつもの与え方では刺激が少ないこともあります。
フードを温めるのには電子レンジが便利です。ドライフードの場合、水を少量かけて電子レンジで10秒間隔程度のこまめなチェックをしながら温めるとよいでしょう。
フードにお湯や出汁を加える
食欲が落ちたときは、水分を加えると嗜好性があがることがあります。腎臓病の犬のなかには高齢の子も少なくないため、お湯でふやかすことで物理的に食べやすくなることもあります。お湯で食べてくれないときは、鶏肉や鰹節を茹でた出汁なども試してみましょう。
出し汁を作る時間がないときは、市販の犬用スープを利用するのもよいでしょう。このときも、少し温めるとより食欲を刺激します。
普段のフードに混ぜながら療養食の割合を増やす
普段のフードから低タンパク食のフードに切り替えると、犬が今までのフードよりもおいしくないと感じることも少なくありません。いきなりフードすべてを新しいフードに変えるのではなく、普段のフードに少量ずつ新しいフードを混ぜて慣れてもらいましょう。
まとめ

本記事では、腎臓病の犬に対する食事療法について、腎臓病そのものの解説を行い、食事療法における栄養のポイントや、食べてくれないときの対処法などもお伝えしました。腎臓病は、一度かかってしまうと、完治させることは難しい病気です。しかし、初期の段階で適切にコントロールすれば、生涯にわたり、上手につきあうことが可能です。フード選びや食事の与え方に迷ったときは、獣医師に相談しながら取り入れてみましょう。
参考文献