動物病院で行われる緩和ケアとは、ペットの穏やかな生活を守るために欠かせない処置の1つです。医療行為の一種であり、ペットのクオリティー・オブ・ライフ(生活の質)の維持・向上を目指す医療です。
この記事では、緩和ケアとはなにかについて解説します。
動物病院での緩和ケアの基礎知識
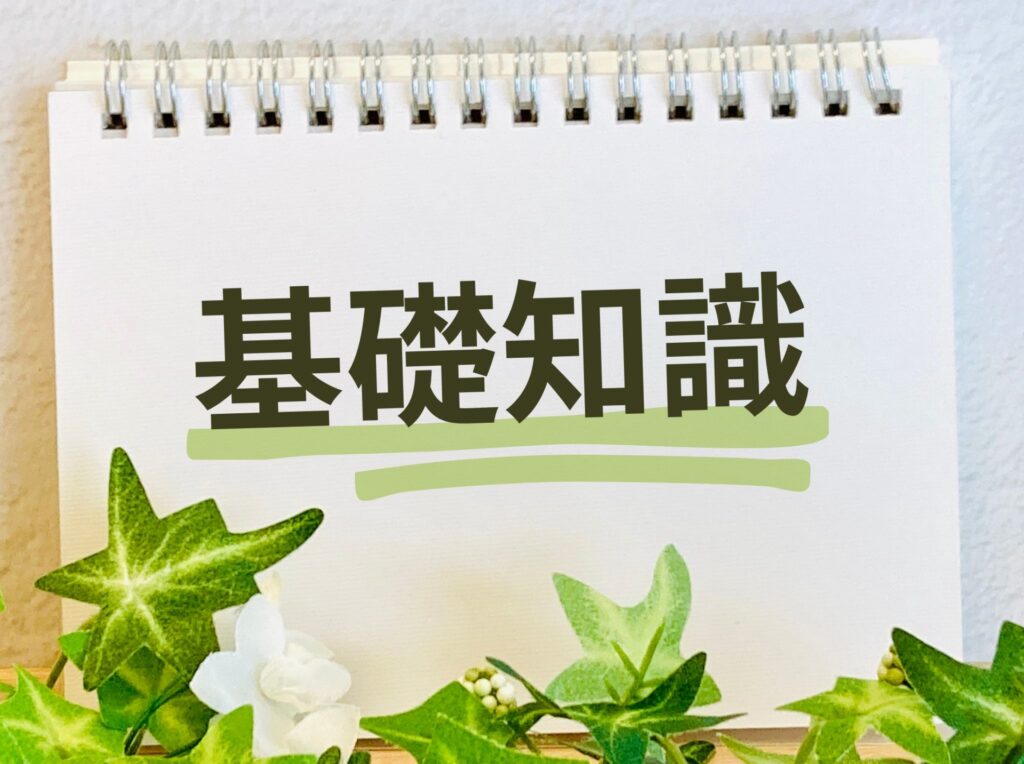
動物病院で行われる緩和ケアには定義があり、病気や怪我を治そうとする根治治療とは目的が異なります。
緩和ケアにおける基礎知識として、緩和ケアの定義と目的、根治治療との違いをみていきましょう。
緩和ケアの定義と目的
緩和ケアの定義は、生命を脅かす疾患に罹患し、根治が困難と判断されたペットに対して、痛みや苦しみから解放するための医療行為を意味します。
例えば、ペットが疾患による痛みで苦しんでおり、日常生活を送るのにも支障が出ていたとしましょう。通常の医療行為では疾患を食い止めたり、治すための治療を行いますが、緩和ケアは疾患に付随して起こる痛みや苦しみを改善、緩和するために行われます。
そして、痛みや苦しみにとらわれずに生活を送れるように支援するため、生活の質を向上させる働きがあるとされているのです。
なお、近年は根治治療と並行して早期から緩和ケアを導入し、治療中の疼痛・悪心を抑えることで治療完遂率を高めるアプローチも推奨されています。
根治治療との違い
根治治療とは、病気や怪我を治して元どおりの身体に戻すための治療方法です。緩和ケアとの大きな違いは、治療のゴールにあります。
緩和ケアはいわゆる対処療法であり、変わりゆくペットの体調に応じて苦しみや痛みに対処するのが目的です。
動物病院で緩和ケアが優先される理由
緩和ケアは、病気を治すことよりも痛みを抑え、残された時間をできる限り穏やかに過ごさせることを目的にした医療です。根治治療が効果を発揮しない、あるいは治療自体がかえって身体的・精神的負担になる場合には、無理に延命を図るよりも QOL(生活の質)を守ることが優先されます。
例えば、全身転移が進んだがんや重度の臓器不全では、追加の手術や強い抗がん剤が期待した効果を得られず、副作用だけが大きくなるケースが少なくありません。こうした状況で無理な治療を続ければ、食欲低下や嘔吐、倦怠感などが強まり、かえって苦痛が増す恐れがあります。
そこで獣医師は、治療で得られる可能性のある延命効果と治療に伴う苦痛やストレスを天秤にかけ、ペットにとって最善の選択肢を検討します。その結果、体力を温存しながら痛みをコントロールし、呼吸や排泄、食事といった基本的な活動を支える緩和ケアが推奨されるのです。
緩和ケアは、治療を諦めることではなく、残された時間を前向きに過ごすための積極的な医療であるため、動物病院で緩和ケアが重視される最大の理由です。
動物病院の緩和ケアが必要になるタイミングと対象疾患

動物病院において、緩和ケアが必要であるとされるタイミングと対象となる疾患を見ていきましょう。
ここでは、緩和ケアに移行するかの判断はいつすべきなのか解説します。
がん終末期の症状
がんの末期症状が、現れているケースでは、根治治療を目指す医療から緩和ケアに移行する場合があります。全身に転移がみられる、手術を繰り返しても再発するような状態であれば、ペットが痛みを感じないよう、苦しまずに日々を過ごせるよう、サポートする医療に切り替えることも検討されます。
進行性腎不全や肝不全などの臓器疾患
進行性の腎不全や、肝不全などといった内臓にまつわる疾患についても、治療の手立てがなくなれば緩和ケアに移行するケースがあります。
病気によっては、病気が発覚したときにはかなり症状が進行してしまっているケースも少なくありません。高齢のペットの場合、手術に耐えうる体力がないという観点から、緩和ケアが第一の選択肢となることも考えられます。
心不全や呼吸器疾患による慢性苦痛
心不全や呼吸器疾患による慢性的な苦痛を抱えるペットに対しても、緩和ケアに移行する場合があります。
特に腎不全や呼吸器系の疾患は、日常生活において息をするだけでも、ペットは苦しみを感じる場合も少なくありません。
散歩程度の運動でも難しい場合は、緩和ケアに移行して様子を見る場合があります。
高齢による衰弱・認知症の進行
歩行がふらつく、寝ている時間が極端に長い、夜間に徘徊したり鳴き続けたりする、こうした変化が見え始めたら、早めに獣医師へ相談してください。
・身体機能のサポート
足腰を守るために滑りにくい床材を敷く、段差にスロープを設置するなど住環境を工夫し、転倒や関節への負担を減らします。
・認知症ケア
規則正しい生活リズムと軽い刺激が進行を緩やかにすると報告されています。専用サプリや処方食が役立つ場合もあるため、適切な栄養プランを獣医師と検討しましょう。
こうした総合的なケアにより、高齢ペットが“その子らしく穏やかな晩年を過ごせる可能性が高まります。
動物病院で受けられる主な緩和ケア

動物病院で受けられる、主要な5つの緩和ケアについて解説します。言葉で自分の気持ちを表現できないペットたちだからこそ、飼い主さんによる緩和ケアは過不足がないよう配慮しなければなりません。
- 痛みや苦しみを取り除いてあげられているか
- 自由が制限されるペットでも過ごしやすい生活空間が確保できているか
- 食べ物や飲み物に困らないで済むか
- 自分のタイミングで自由にトイレにアクセスできるか
病院で受けられる緩和ケアについて、具体的な事例をみていきましょう。
疾患で生じる痛みの管理
動物病院で受けられる代表的な緩和ケアには、疾患で生じる痛みを和らげるものがあります。ペットが罹患する疾患のなかには、身体に痛みを覚えるものもあり、そうした症状を抱えたままでは、ペットは常に痛みによって苦しまなければなりません。
また痛みがあると、活発に動き回っていたペットも動きが鈍くなります。
歩かなくなると足腰が弱って寝たきりになる、このような状態を防ぐためにも、緩和ケアは重要な役割を果たすでしょう。
栄養管理や食事のサポート
緩和ケアでは、ペットの栄養管理や食事のサポートも行われます。
例えば、同じフードを食べさせていても温められるのであれば、温めて香りをよくして食いつきをよくさせるように、ちょっとした工夫も緩和ケアの一種です。
また、摂取カロリーが不足してしまっているときは、少量でもカロリーがきっちり摂取できるようなフードに切り替えるといった、食事のマネジメントも一つの方法です。
呼吸を楽にするケア
緩和ケアには、呼吸を楽にしてあげるケアも含まれます。呼吸困難の症状では胸や腹に水が溜まってしまうケースもあり、ペットは言葉にできないものの常に不快感を感じているでしょう。
こういった症状が原因となる場合は、薬剤を投与して溜まった水を抜く処置を行います。また、呼吸困難の原因を取り除けない場合は、呼吸そのものを楽にするための処置を行うのも緩和ケアの役割の1つです。
適宜、酸素を吸わせて低酸素状態を脱却し、息苦しさそのものの解消に努める場合もあるでしょう。
皮膚の床ずれのケア
寝たきり状態に陥っているペットは、自力では動けないため、長時間同じ姿勢をとってしまう時間が増え、床ずれのリスクが上がります。いつもよりも入念なグルーミングを行うのも緩和ケアの1つです。
また、床ずれのケアに付随して、ペットのいる場所や寝床を整えてあげられるよう配慮するのも、重要な緩和ケアだといえるでしょう。
飼い主さんへの精神的なサポート
緩和ケアでは、ペットだけでなく飼い主さんの心のサポートも不可欠です。治療が困難と告げられると悲しみや不安が重なり、食事や睡眠が乱れることも少なくありません。
そのため、獣医師は病状と在宅ケアの選択肢を整理して説明し、カウンセラー紹介やセルフケア指導、定期的な声かけで負担を軽減します。
さらに、写真や足形を残す思い出作りやペットロスを見据えたグリーフケアの情報提供も行い、飼い主さんが後悔なく最期を見守れるようサポートも行ってくれます。
動物病院で緩和ケアを受けるメリット

動物病院で緩和ケアを受けるメリットは大きく3つあります。緩和ケアはシンプルな対処療法ではなく、ペットの生活の質を向上するための施術です。
実施すべき理由を理解してペットの最期のために尽くしてあげましょう。
痛みや不安の軽減により穏やかに過ごせる
緩和ケアの目的は、痛み・不安のコントロールです。鎮痛薬(NSAIDs・オピオイド)や抗不安薬、漢方、温熱、マッサージ、低出力レーザーなどを症状に合わせて組み合わせ、動作時の鋭い痛みや持続する鈍痛を多角的に緩和します。
呼吸が苦しい子には酸素室や利尿薬を追加し、夜間の不安鳴きにはメラトニンやフェロモン製剤で睡眠サイクルを整えます。
苦痛が減ると食欲と睡眠が安定し、表情に柔らかさが戻り、ストレス由来の攻撃行動や無気力も大幅に減少するため、ペットは安心して好きな場所で横になり、穏やかな時間を取り戻せます。
ペットが飼い主と一緒に過ごす時間を増やせる
緩和ケアは、自宅中心で行うため、ペットが家族と過ごせる時間を大幅に確保できます。自宅では、飼い主さんと一緒に食事をとったり、陽当たりのよい場所でまどろむなど、従来の日常に近い生活リズムを維持できます。
短時間でも抱っこやブラッシングを行うことでオキシトシンが分泌され、痛みの知覚も和らぐという報告があり、精神・身体の両面でメリットがあります。
尊厳ある看取りがしやすい
痛みや不快感を適切に抑えたうえで日常生活を整えると、ペットは自分らしさを失わず穏やかに最期を迎えられます。
呼吸困難や嘔吐を伴う処置を減らし、清潔な寝具や体位変換で床ずれを防ぐことで、終末期特有のストレスを少なくすることもできます。
また、飼い主さんは医学的な選択に追われる時間が減り、ペットとの対話やスキンシップ、思い出づくりに集中できるのもメリットの1つでしょう。
ペットロスを和らげられるよう、足形スタンプや写真撮影、好きだったおやつの最後のご褒美などをあげ、後悔の少ない看取りにつなげましょう。
動物病院で緩和ケアを受ける際の注意点

緩和ケアは、治す医療ではなく苦痛を抑えて生活の質を守る医療です。目標をはっきり共有し、ペットが快適に過ごせる工夫と飼い主さん自身の心身ケアを両立させることが大切です。
ケアで何ができるか・できないかを整理し、状態変化に気づける仕組みを作りましょう。ここでは、緩和ケアを受ける際の注意点について解説します。
症状悪化を見逃さないようよく観察する
緩和ケア中でも病状は進行する可能性があります。呼吸数・食欲・排泄・睡眠パターンを毎日記録し、痛みスコアや咳の頻度など客観的指標で変化を把握しましょう。
「ぐったりして動かない」「舌の色が紫がかる」「鳴き声が強くなる」など小さなサインでも獣医師へ速やかに報告し、薬量調整や酸素投与の追加など早期対応につなげることが肝心です。
根本治療ではないことを理解する
緩和ケアは原因疾患を治癒させる治療ではありません。鎮痛や栄養補給で苦痛を減らし、残された時間を穏やかに過ごすことが目的です。「続ければ治るのでは」と期待し過ぎると判断を誤りやすいため、根治治療との違いを家族全員で確認し、治療目標を定期的に見直すことが望まれます。
飼い主さん本人の負担や精神的なケアが必要だと自覚する
介護疲れやペットロスへの不安は誰にでも起こります。睡眠と食事を確保し、週に一度は短時間でもリフレッシュの時間を設けましょう。
感情が追いつかないときは獣医師やカウンセラーに気持ちを打ち明け、グリーフサポート団体の力を借りるのも有効です。
前向きな心の準備が、ペットとの残された時間をより温かいものにします。
まとめ

ペットに施す緩和ケアは、クオリティーオブライフといって生活の質を向上するために行われるケアです。ペットの残り僅かな寿命を延ばすものではありませんが、毎日を穏やかに、快適に過ごすために欠かせない医療行為です。治療する手立てがないから仕方なくやるものではなく、寿命を全うするための前向きな処置であるとらえてください。
緩和ケアを実施すれば、ペットが日々感じている痛みや苦しみが軽減されます。飼い主さんも、緩和ケアを通じてペットとの時間を大切にしながら、残された時間を有意義に使ってください。
【参考文献】


