大切な愛猫がご飯を吐いてしまうと、「どうしたのだろう」と不安になりますよね。猫は元気そうに見えても吐くことがあり、毛玉や早食いといった一時的な理由で済む場合もあれば、病気が隠れていることもあります。様子見でよいのか、それとも早めに受診が必要なのかを見極めることが大切です。この記事では、猫がご飯を吐く主な原因や病院へ行く目安、予防の工夫について、飼い主さんにわかりやすく解説します。
猫が食事後にご飯を吐く原因

猫が食事の後にご飯を吐いてしまうと、飼い主さんは心配になりますよね。原因として、軽いものから病気が関係する場合までさまざまなので、ここでは代表的な理由を解説していきます。
- 猫が食べた直後にご飯を吐いてしまうのはなぜですか?
- 多くの場合、早食いや食べ過ぎが原因です。
猫は急いで食べると、食べ物と一緒に空気を飲み込んでしまい、胃が急にふくらんで吐き戻してしまいます。特に多頭飼いで競争心がある場合や、一度に大量に食べた場合に見られやすいです。
- ご飯の早食いや食べ過ぎ以外で嘔吐する原因はありますか?
- はい。毛玉が胃にたまって吐き出そうとする場合や、フードが体に合っていない場合、異物を飲み込んでしまった場合の他、胃腸炎、感染症、腫瘍、腎臓病や甲状腺の病気などが考えられます。
長毛種や換毛期には毛玉による嘔吐が増えやすく、また急なフードの切り替えや成分が合わないときにも吐くことがあります。
さらに、おもちゃや紐などを誤飲した際には胃や腸に負担がかかり、繰り返し吐くこともあるため注意が必要です。
ストレスや季節の変わり目などの変化により胃腸炎を起こしてしまうことがあります。
また高齢の場合には、腫瘍や腎臓病や甲状腺機能亢進症などが原因で嘔吐が見られること多くあります。
- ご飯の種類や食事環境が嘔吐に影響することがあるのか教えてください
- あります。粒の大きさや形状によっては丸飲みしやすく、吐きやすくなります。また、急にフードを変えると消化が追いつかず嘔吐を招くこともあります。
食器の形も影響し、深い器よりも浅い平皿の方が落ち着いて食べやすく、吐き戻しを防ぎやすいです。
さらに、多頭飼いの環境や周囲の騒音によるストレスで早食いになることもあるため、食事環境を整えることも大切です。
- 単純な早食いと病気による嘔吐の見分け方を教えてください
- 早食いや食べ過ぎによる吐き戻しは、吐いた後も元気や食欲が普段どおりであることが多く、頻度もそれほど高くありません。
これに対して病気による嘔吐では、吐く回数が増えるだけでなく、元気がなくなったり、食欲が落ちたり、体重が減ってきたりすることがよく見られます。
何度も吐いたり、吐いた後に回復せずぐったりする場合は、病気の可能性が高いため注意が必要です。
- 緊急性の高い嘔吐の症状とはどのようなものですか?
- 緊急性が高い嘔吐の特徴としては、吐いたものに血が混じっている場合や、何度も立て続けに吐いてしまう場合が挙げられます。また、吐こうとしても何も出ず苦しそうにしていたり、同時に元気や食欲が極端に落ちているようなときも危険なサインです。
こうした場合は自然に治ることは少なく、命に関わることもあるため、すぐに動物病院を受診することをおすすめします。
- 消化器疾患による嘔吐の特徴を教えてください
- 消化器疾患が原因で嘔吐が起きている場合、軽度の急性胃腸炎の場合には症状が2、3日で落ち着くこともありますが、原因によっては数日から数週間にわたり繰り返し吐く場合や、下痢や便秘といった排便の異常が一緒に見られることがあります。
さらに、元気がなくなる、体重が減るといった全身の変化を伴う際には注意が必要です。
動物病院を受診すべきタイミング
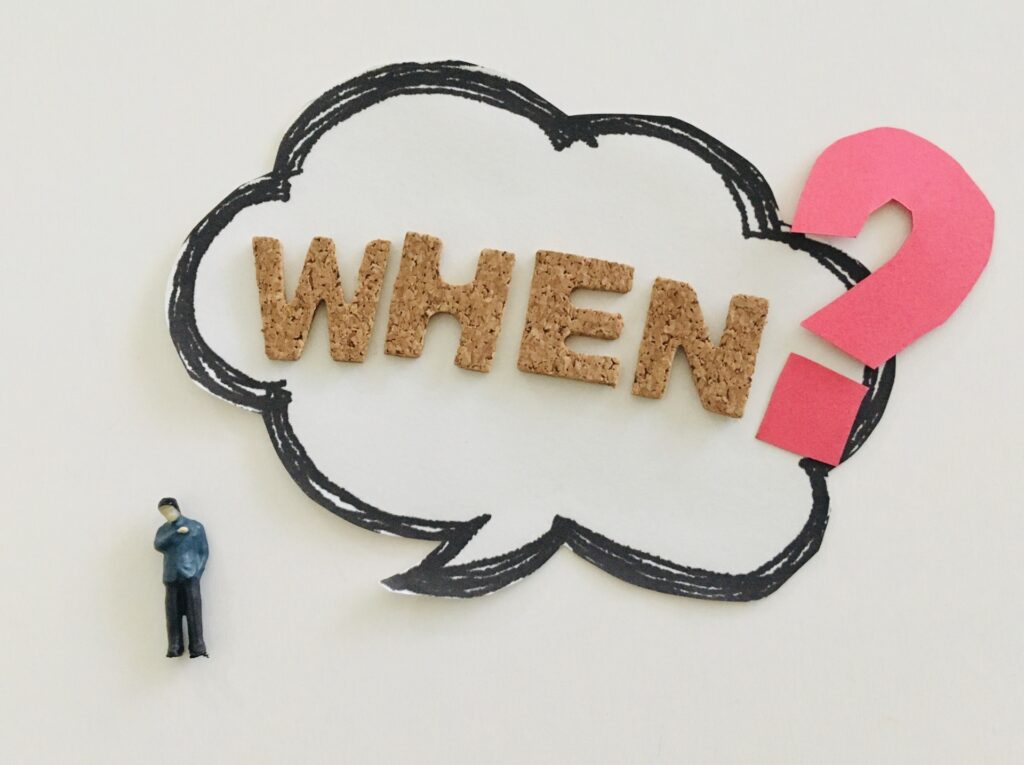
どのような症状、もしくは併発症状があれば動物病院を受診すべきなのか、そのタイミングについて解説します。
- どのような嘔吐の症状があれば動物病院を受診すべきですか?
- 猫が嘔吐したとき、吐いたものに血が混じっていたり、色が茶色や黒っぽい場合は緊急性が高く、できるだけ早く受診することをおすすめします。
吐いた後に元気がなく、ぐったりしている、呼吸が荒いなどの症状が見られる、また何度も繰り返し吐くようであれば、病気の可能性が高いでしょう。
反対に、吐いた後も普段と変わらず元気であったり、一度きりの嘔吐で吐く頻度が低い場合は、自宅で様子を見てもよいでしょう。ただし、改善がない、元気がなくなっていくなどの変化が見られれば、受診をおすすめします。
- 嘔吐以外にどのような症状が併発していたら緊急受診が必要ですか?
- 嘔吐と同時に下痢が続く、食欲が落ちて水もあまり飲まないようなときには脱水や重症化のリスクが高まります。さらに、元気がなく寝てばかりの状態やお腹が張って苦しそうな場合には、消化器疾患や感染症など深刻な原因が隠れている可能性があります。
- 子猫や高齢猫の嘔吐で特に注意すべき点があれば教えてください
- 子猫や高齢猫は体力や免疫力が弱いため、たとえ軽く吐いた程度でも脱水や体調悪化につながりやすく、注意が必要です。
子猫の場合、嘔吐が1回でもぐったりしていたり、下痢や発熱を伴っていたりすれば、低血糖を起こすことや感染症や誤飲など重篤な病気の可能性を疑う必要があります。
高齢猫では腎臓病や肝臓病など慢性疾患や腫瘍、甲状腺機能亢進症などの症状として嘔吐が出ることもあるため、少しでも普段と様子が違えば、診てもらうようにしましょう。
嘔吐を予防するためのご飯のあげ方
ここでは、ご飯の種類や食器の選び方、与え方、そしてストレス対策を中心に、猫の嘔吐を防ぐ工夫について解説します。
- ご飯の選び方や食器の工夫で嘔吐を改善できますか?
- はい、改善できます。毛玉対策になるように食物繊維を含んだフードを選ぶと、毛玉が胃に溜まりにくくなります。
また、食器の形状も工夫が可能です。表面にでこぼこがあるものや中央が盛り上がっているスローフィーダータイプの器は、自然と食べるペースが落ちて早食いを防げるため、吐き戻しを減らす効果が期待できます。
さらに、傾斜のある器や高さのあるスタンドを利用することで食事姿勢が安定し、吐きにくくなることもあります。
- 嘔吐を予防するご飯の与え方を教えてください
- 空腹や食べ過ぎが原因で吐いてしまう猫には、一度に与える量を減らして回数を増やす方法が有効です。例えば一日2回の食事を3回や4回に分けるだけでも、胃への負担を軽くできます。また、夜中や朝方に空腹で吐いてしまう猫には、寝る前にドライフードを数粒与えると予防効果が期待できます。
さらに、早食いの癖がある場合は早食い防止の食器を使ったり、粒の大きなキャットフードに変えたりするのも効果的です。粒が大きいと自然に噛んで食べるようになり、食事のスピードが落ちる猫もいます。
- ストレスが原因の嘔吐にできる対策はありますか?
- 猫は模様替えや引っ越し、来客といった小さな変化でも強いストレスを感じ、それが嘔吐のきっかけになることがあります。もし思い当たることがある場合は、できるだけ模様替えを避けて猫が安心できる環境を維持し、落ち着いて過ごせるスペースを設けてあげましょう。来客があるときには隠れられる場所を確保しておくことも大切です。
また、上下運動ができるキャットタワーを置く、飼い主と遊ぶ時間を増やすといったことも有効です。さらに、猫のペースに合わせたスキンシップを心がけるだけでも、ストレスを軽減して嘔吐の頻度を減らすことにつながります。
編集部まとめ
猫が吐くこと自体は珍しいことではなく、ちょっとした食べ方の癖や環境の影響で起こることもあります。ただし、何度も繰り返したり元気がなくなったりする場合は、体からのサインかもしれません。子猫や高齢猫は特に体調を崩しやすいため、早めの受診をおすすめします。特に子猫や高齢猫は体調を崩しやすいため注意が必要です。
日頃から食事や環境を整え、少しでも不安を感じたときにはすぐに獣医師へ相談できるようにしておくことが、愛猫の健康を守る一番の近道になります。


