愛犬の健康を守ることは、飼い主の大切な役割です。すべての病気や怪我を防ぐことはできませんが、適切な対策を講じることでリスクを下げられる病気があります。対策のなかでも欠かすことができないものが予防接種です。予防接種が求められている疾患は、罹患すると愛犬にとって特にリスクの高い疾患です。
子犬を飼い始めたときに、最初に接種するワクチンが混合ワクチンです。混合ワクチンにも種類はありますが一般的な種類は6種混合ワクチンです。本記事では、犬の6種混合ワクチンの必要性、予防できる病気、接種スケジュール、副反応や接種後の過ごし方などをわかりやすく解説します。
犬の6種混合ワクチンとは?必要な理由と概要

犬の6種混合ワクチンは、複数のワクチンが組み合わせられたワクチンです。すべての子犬が打つべき4種の疾患を予防するコアワクチンと、生活環境により感染リスクがあるため予防目的に接種するノンコアワクチンの2種で構成されています。
コアワクチンには狂犬病も含まれますが、狂犬病ワクチンは単独で接種するため混合ワクチンには含まれません。また、狂犬病ワクチンは法律で接種が義務付けられていますが、6種混合ワクチンは任意接種になっています。
コアワクチンとは、世界中で感染がみられ、罹患すると重篤になるウイルス感染症を予防するためのワクチンです。2024年に改定されたWSAVAのガイドラインでは、従来の4種に犬レプトスピラ感染症が追加され、現在コアワクチンは5種となっています。
ノンコアワクチンとは、地域や生活環境によっては罹患リスクがあり接種がすすめられるワクチンです。6種混合ワクチンは、コアワクチンのうちレプトスピラ感染症を除いた4種に、ノンコアワクチンの2種を加えた、計6種のウイルス感染症を予防するワクチンです。
犬の6種混合ワクチンで予防できる感染症
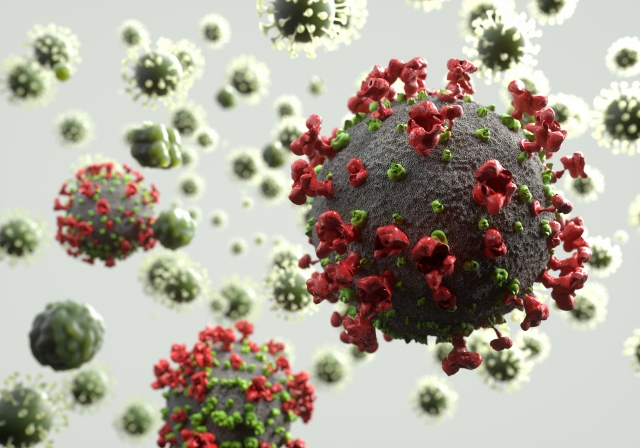
コアワクチンに含まれる4種のウイルス感染症と、ノンコアワクチンに含まれる2種の感染症は以下のとおりです。
コアワクチン
- 犬ジステンパーウイルス感染症(CDV)
- 犬パルボウイルス感染症(CPV−2)
- 犬アデノウイルス1型感染症(CAVー1)
- 犬アデノウイルス2型感染症(CAVー2)
ノンコアワクチン
- 犬パラインフルエンザウイルス感染症(CPiV)
- 犬コロナウイルス感染症(CCoV)
本章では、これらのウイルス感染症を1つずつ解説します。
犬ジステンパーウイルス
犬ジステンパーウイルスは、ヒトの麻疹ウイルスに似た構造をしていることが特徴です。過去にヒトに感染したという報告はありません。理由はいまだ解明されていませんが、一部の研究では、多くのヒトが保有する麻疹ウイルスに対する抗体が犬ジステンバーウイルスに対しても働いていると考えられています。
感染すると、発熱や食欲不振、活気がなくなる、目やに、鼻水などの症状が現れ、これらの症状は麻疹に類似しています。特に子犬は免疫力が発達段階にあり、重症化しやすいとされています。
感染力はとても強く、主に飛沫感染、接触感染で広がります。ヒトへの感染例はないものの、キツネ、フェレット、アライグマなど、犬以外の動物にも感染します。
犬パルボウイルス感染症
病原ウイルスは、1978年に最初に発見された犬パルボウイルスです。ウイルスは熱に弱い傾向にあるなか、パルボウイルスは60度に熱しても1時間は死滅しないという特徴があります。また、アルコールや石けんも無効であり、次亜塩素酸ナトリウム、ホルマリンなどを使用することで死滅します。
感染すると、約2日の潜伏期間を経て、激しい下痢、嘔吐、脱水、活気低下がみられるようになり、食欲が廃絶していきます。一般的には、感染数日で体内に免疫が構築され症状は改善に向かう傾向にあります。しかし、幼犬においては、発症後1日程度で命を落とすことがある恐ろしい感染症です。
感染経路は、感染している犬の糞便に含まれるウイルスが口や鼻から入ることです。上述したとおり、なかなか死滅せず、人間の靴や持ち物に付着し移動することもあります。また、感染したすべての犬が発症するわけではなく、約20%以下とされています。
犬アデノウイルス1型
病原ウイルスは、犬アデノウイルス1型です。血清型の異なる2型のウイルスも存在します。イヌ科動物やクマ科動物に感染し、肝臓や血管内皮細胞を標的とします。そのため、犬アデノウイルス1型感染症は、犬伝染性肝炎とも呼ばれます。
感染すると、最初は発熱や鼻水のような風邪の症状が出現します。一般的には重症化せず軽快しますが、ときに肝炎を引き起こし重症化します。肝炎を発症すると、嘔吐や高熱、腹水の貯留、全身性の出血性病変など深刻な症状を引き起こし、死に至ることがあります。また、回復期にはブルーアイと呼ばれ、角膜浮腫を原因とし、目の角膜が青白く変化する特徴的な症状がみられることがあります。
感染経路は、感染した犬の口や鼻からの分泌物との接触や飛沫感染に加え、糞便などの排泄物を介しても広がります。
犬アデノウイルス2型
病原ウイルスは、上述の犬アデノウイルス1型と血清型が異なる犬アデノウイルス2型です。このウイルスと犬パラインフルエンザウイルスは、ケンネルコフ(伝染性の呼吸器疾患の総称)という、呼吸器感染症を引き起こす代表的な原因ウイルスです。
感染すると、乾いた咳(ケンネルコフの特徴)、くしゃみ、鼻水、発熱といった風邪症状が、みられます。一般的には軽症で済む傾向にありますが、二次的な細菌感染を引き起こすと重症化する可能性があります。
感染経路は、主に感染した犬の口や鼻からの分泌物との接触や飛沫による感染です。
犬アデノウイルス2型(CAV-2)予防のワクチンは犬アデノウイルス1型(CAV-1)にも効果があるため、現在はCAVー2のワクチン接種により1型2型ともに予防するのが一般的です。
犬パラインフルエンザウイルス
犬パラインフルエンザ感染症は、上述したように、ケンネルコフという、犬の伝染性の呼吸器疾患を引き起こす感染症です。病原ウイルスは、犬パラインフルエンザウイルスで、ヒトのインフルエンザウイルスとは別の種類のウイルスです。犬アデノウイルス2型感染症と同様、二次的な細菌感染症を引き起こすと重症化する可能性があります。
症状としては、乾いた咳が続くことが特徴です。
感染経路は、主に感染した犬の口や鼻からの分泌物との接触は飛沫による感染です。
犬コロナウイルス
病原ウイルスは、犬コロナウイルスであり、ヒトの間で大流行した新型コロナウイルスとは別の種類のウイルスです。多くの場合は軽症で自然回復する傾向にあり重症化せずか軽快します。しかし、犬パルボウイルス感染症との混合感染や細菌感染症と合併すると重篤化することがあります。
感染すると、下痢、嘔吐、脱水といった消化器症状が出現します。
感染経路としては、主に感染した犬の糞便を口にすることによる経口感染です。
犬の6種混合ワクチン|接種スケジュール

ワクチン接種のスケジュールは、幼犬と成犬で異なります。特に幼犬のときの接種スケジュールは特殊ですから、しっかりと把握しておきましょう。子犬の場合は、免疫力に乏しく、3〜4回の接種が必要になります。
1回目の6種混合ワクチンを接種するタイミング
生まれたばかりの子犬は、母乳を通して抗体を受け継ぎます。これを移行抗体といいます。移行抗体は生後6〜8週頃から消失し始めます。消失の遅い生体でも生後約90日〜120日の間で消失していくと考えられています。この期間にワクチン接種を終えることが推奨されています。しかし、移行抗体が体内に豊富に存在している期間は、ワクチンを接種してもワクチン抗原が移行抗体に邪魔をされ十分な免疫がつかない、ワクチンブレイクという現象が起こります。
そのため、1回目の6種混合ワクチン接種は、母親からの移行抗体が減少し始める生後6〜8週間以降が推奨されています。
免疫系は個体差も大きく、十分な免疫を確立するために合計で3〜4回のワクチン接種を行います。
2回目以降の接種間隔
2回目以降は初回接種後約3〜4週間ごとに接種します。また、最終接種が生後16週以降になることが推奨されているため、初回接種のタイミングによっては、4回目の接種を行うことがあります。
成犬の場合のワクチン接種の間隔に関しては、WSAVA(世界小動物獣医師会)が2024年に更新したガイドラインによると、以下のように推奨されています。
- コアワクチン:成犬の場合は長期間効果が持続するため、約3年に1度の接種間隔でよい
- ノンコアワクチン:必要に応じて1年に1回の接種が推奨される
なお、WSAVAのガイドラインでは1年に1回の健康診断を推奨しており、そのタイミングで獣医師と相談し、愛犬の生活環境や健康状態に応じた適切なワクチン接種スケジュールを決めることが大切です。
ほかのワクチン接種との兼ね合い
ほかのワクチンとの同時接種を禁止する法律はありませんが、推奨はされていません。
理由としては、下記が挙げられます。
- 同時投与により副反応が強くなる可能性がある
- 副反応が出た場合、原因の特定が困難
接種間隔としては一般的には2週間から1ヶ月程度あけることが推奨されます。
犬の6種混合ワクチンで確認されている副反応

ワクチン接種とは、弱毒化もしくは不活化した病原体を体内に注入することで免疫を賦活化させるため、副反応が起きることがあります。本章では副反応を軽度な症状と重度な症状に分けて解説します。
軽度な副反応
軽度な副反応では以下のような変化がみられます。
- 一過性の元気・食欲減退
- 疼痛・腫脹
- 発熱
- 嘔吐・下痢など
これらは、一過性であり、通常数日以内に改善します。
重度な副反応
まれではありますが、過敏な体質の犬ではときに、アレルギー反応(顔面腫脹、掻痒、じんま疹)またはアナフィラキシーショック(血圧低下、呼吸速拍、呼吸困難、体温低下、けいれん)がみられるとされています。特に命に関わるアナフィラキシーショックは、即時型アレルギー反応といい、接種後数分〜1時間程度で発症します。そのため、動物病院では、接種後はしばらく様子を見てから帰宅となります。アナフィラキシーショック以外のアレルギー反応は接種後数時間を経過してみられることがあるため、事前に獣医師に副反応について相談しておくとよいでしょう。
犬の6種混合ワクチンを受けた後の自宅での過ごし方

ワクチンを接種すると、体力が低下し、疲れやすくなります。人間は、ワクチン接種後の激しい運動や飲酒を控えるのと同じように愛犬にも配慮が必要です。本章では、6種混合ワクチンを受けた後の過ごし方について解説します。
安静にさせる
まずは、愛犬がゆっくりと静かに過ごせる環境を整え、身体に余計な負担をかけないようにしましょう。ワクチン接種後は、体力を温存し、ストレスや疲労を避けることが、免疫の働きを助けるうえでとても重要です。
犬はワクチンを打ったから安静にしよう、と自分で考えるわけではありません。そのため、普段以上に飼い主さんが意識してあげる必要があります。具体的には、散歩は接種後2〜3日は控えるか短時間で済ませたり、興奮して遊びすぎないようにおもちゃを減らしたりするなどです。
シャンプーや激しい運動を避ける
ワクチン接種後にシャンプーや激しい運動を避けるべきと考えられています。激しい運動や血流がよくなり、副反応が強く出てしまうリスクがあります。また、実はシャンプーをすることは、愛犬にとっては体力を消耗する行為です。そのため、接種後2〜3日は避けることが望ましいです。具体的な日数は愛犬の体調や年齢にもよります。ワクチン接種時に獣医師に相談するようにしましょう。
体調の変化に注意する
上述したとおり、ワクチン接種では、副反応が生じることがあります。特に接種直後の数時間〜1日は、副反応が出やすいとされているため、いつも以上に愛犬の体調の変化に気付くように観察してあげましょう。
犬の6種混合ワクチンか8種混合ワクチンで迷ったときの選び方

犬の混合ワクチンには、2種〜11種までのバリエーションが存在します。一般的には、上述した6種混合ワクチンもしくは、6種混合ワクチンに2種の犬レストスピラを追加した8種混合ワクチンです。ワクチンの種類は、生活環境により選択します。具体的には、6種で十分なケースは以下のような環境です。
- 室内飼いが中心
- 都市部に住んでいて、自然や野生動物と触れ合う機会がない
次に、8種が望ましいケースは以下のような環境です。
- キャンプや川遊びなど、自然やほかの野生動物と触れ合う可能性がある
- 多頭飼育で、ほかの犬からの感染が心配な環境
6種と8種のどちらのワクチンを選択するか悩む場合は、獣医師と相談し、地域や生活環境に合わせて選択しましょう。
まとめ

犬の6種混合ワクチンは、愛犬を重篤な感染症から守るために大切です。特に子犬のワクチン接種はスケジュールが特殊なため、接種を忘れないように飼い主さんが理解をしておくことが重要になります。混合ワクチンには種類があります。地域や生活環境によって接種すべき種類が異なります。獣医師に相談し、適切なワクチンを接種し、愛犬を守りましょう。
参考文献


