一般に健康な猫はほとんど体臭がありません。ただし、ほとんど臭わないはずの猫から、いつもと違う強いニオイがした場合は注意が必要です。それは何らかの異常や病気のサインかもしれません。本記事では、そんな猫が臭いと感じるときの理由や対処法について解説します。
猫の正常なニオイと異常なニオイの見分け方

正常な体臭と異常なニオイはどのように見分ければよいでしょうか。ポイントはニオイの種類や強さ、発生源を観察することです。口を開けたときの息が臭ければ口腔内の問題、耳を近づけて鼻をひそめたくなるなら耳の異常、身体や被毛全体から強い臭いを感じる場合は皮膚・被毛のトラブルやグルーミング不足などが考えられます。このように猫のニオイの変化に気付いたら、その種類と発生源を見極めることが大切です。
【原因別】猫が臭いと感じるのはどのようなとき?
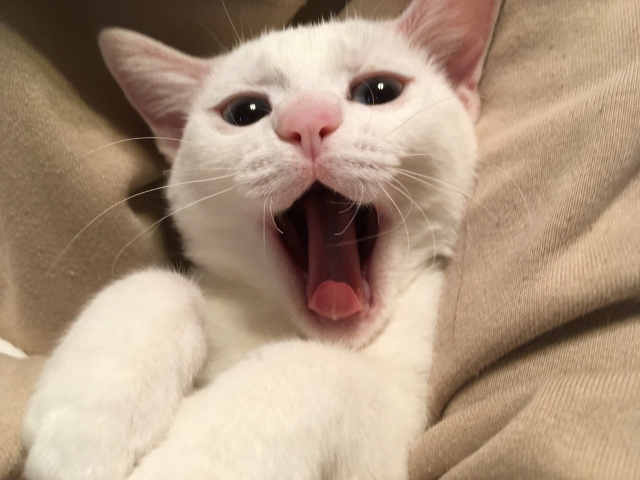
猫から発せられる異常な臭いには、さまざまな原因が考えられます。ここでは、飼い主さんが「なんだか臭う」と感じる代表的なケースを原因別に解説します。それぞれの原因に応じて、どのような臭いがするのか、どのような病気が潜んでいる可能性があるのかを見ていきましょう。
歯周病や口内炎などのニオイ
口臭(息の臭い)が強い場合、主な原因は口の中の病気だといわれています。特に多いのは歯周病で、歯石の蓄積や歯肉の炎症によって口腔内に細菌が繁殖し、揮発性硫黄化合物などの臭気物質を出すため口臭がきつくなります。歯周病が進行すると歯茎からの出血や痛み、歯のぐらつきも起こり、さらに口臭が悪化します。また、口内炎も口臭の原因になります。口臭のほかにヨダレが増えたり、口を気にして食欲が落ちるといった症状があれば口腔内トラブルの可能性が高いでしょう。さらに、内臓の病気によって口が臭くなるケースもあります。腎臓病が進行すると体内に尿素や老廃物が蓄積し、息がアンモニア臭(おしっこのような刺激臭)になります。糖尿病の場合は、代謝産物のケトン体により熟れた果物のような甘酸っぱい口臭になることがあります。
耳の汚れや病気などのニオイ
耳が臭う場合、外耳炎など耳の病気が考えられます。普段は無臭な猫の耳から悪臭がするなら要注意です。細菌性の外耳炎では、耳の中がジメジメ湿って膿のような分泌物や茶色い耳垢が出て、強い臭いを放ちます。耳ダニ(ミミヒゼンダニ)が寄生している場合も、コーヒー粉のような黒い耳垢が大量に出て耳が臭くなります。真菌(カビ)の感染による外耳炎では、独特の蒸れたような臭いとともに痒みから頭を振る仕草や皮膚のフケ・脱毛が見られることがあります。
肛門腺の分泌液によるニオイ
強烈な臭いの代表が肛門腺のニオイです。猫の肛門の左右には、肛門嚢(肛門腺)と呼ばれる臭い袋があり、中に強烈な臭いの分泌液(肛門腺液)が溜まっています。この臭いは例えるならスカンクがお尻から発射する液と同じようなもので、一度嗅いだら鼻にこびりつく刺激臭です。通常はウンチと一緒に少量ずつ排出されますが、肥満や運動不足、高齢などで肛門腺液がうまく出せないと袋に溜まり続け、猫のお尻周りが異様に臭くなります。
猫がお尻を床にこすりつけて歩くおしり歩きをしたり、しきりに尻尾の付け根を舐めて気にする仕草は、肛門腺に分泌物が溜まっているサインです。放っておくと中の液がさらに濃く粘り、肛門嚢炎(感染)を起こして膿や血が混じることもあります。そうなると通常の生臭い匂いから、より一層ひどい悪臭へ変化し、肛門周囲に腫れや痛みも生じます。最悪の場合、袋が破れて皮膚から膿が漏れ出す肛門腺破裂に至り、激しい臭気を放ちながら患部がただれる重症状態になります。
体毛の汚れによるニオイ
本来、猫は頻繁な毛づくろいにより清潔を保っているため体毛や皮膚から強い臭いはしません。しかし、何らかの理由でグルーミングが行き届かないと、被毛に皮脂や汚れが蓄積して臭いの原因になります。例えば、ケガや病気、肥満、老化によって身づくろいの頻度が落ちると、毛がベタついてフケや汚れが増え、獣臭い匂いがしてくることがあります。猫は汗腺が少なく体臭が弱い動物ですが、皮脂は常に分泌されており、舐めて除去されないまま溜まると酸化してイヤな臭いを発しがちです。
また、好奇心旺盛な猫は狭い所に潜り込んだり物にスリスリする習性があるため、身体に外部の臭いが付着することもあります。一時的な汚れであればブラッシングや部分洗いで落とせますが、いつも毛が脂っぽく汚れて臭う場合は皮膚疾患の有無も疑いましょう。
皮膚の病気によるニオイ
皮膚疾患が原因で体臭が強くなることもあります。代表的なのは皮脂の分泌異常による脂漏症(しろうしょう)や、それに伴う二次感染です。脂漏症になると皮膚の新陳代謝が乱れ、皮脂が過剰分泌されて被毛がベタベタになり、独特のきつい油臭を放つようになります。特に、油性脂漏症では皮膚にフケと皮脂が混じった塊がこびり付き、触るとギトギトして臭気が強まります。一方、細菌感染で膿が出ている膿皮症や、ケガが化膿して膿んでいる場合も注意が必要です。膿には腐敗臭に似た強烈な悪臭があり、猫の体表にできた傷や腫れものから膿が漏れていれば周囲に悪臭が漂います。
また、真菌(カビ)や酵母菌による皮膚炎も臭いの原因になります。マラセチア菌という酵母菌が増殖する皮膚炎では、古い油のような独特の匂いとベタつき、かゆみを伴うことがあります。皮膚糸状菌症では強い臭いはありませんが、免疫力低下で二次的に細菌感染を起こすと臭気を帯びます。
トイレのニオイ
猫を飼っているお部屋で気になりやすいのはトイレ周りの臭いです。猫自体は体臭が少なくても、排泄物は放っておけば強烈な悪臭を放ちます。特に、尿にはアンモニアが含まれるため時間経過で臭いがきつくなります。猫は排泄後に砂をかけて隠す習性がありますが、トイレの砂や周辺に汚れが残っていると部屋全体が尿臭・便臭で臭くなってしまいます。猫の足裏に尿や便がついて、それを家中に踏み散らしてしまうことも少なくありません。また、トイレ以外での排泄や、オス猫のスプレー行為(縄張りマーキングのための尿スプレー)も部屋の悪臭の原因になります。
そのほかのニオイ
上記以外にも、以下のような場合に猫が臭いと感じることがあります。
おなら(ガス臭)
猫も人と同じくオナラをします。通常のオナラでも多少臭いますが、腸内環境の悪化や消化不良でガスがたまると異常に臭いおならが出ることがあります。
発情期のニオイ
未去勢のオス猫は発情期に独特の強い体臭を発することがあります。
病気特有のニオイ
重度の肝臓病では腐敗したような生臭い体臭を放つことがあります。また、猫白血病ウイルスや猫エイズウイルスなどで免疫が落ちた猫は口や皮膚の感染を併発し悪臭を放つこともあります。
猫が臭いときは動物病院に行くべき?

猫の体臭や口臭が普段と比べて明らかにおかしいと感じたら、基本的には動物病院に相談するのが安心です。特に、以下のような場合は受診を検討してください。
- 悪臭が長引く・何度も繰り返す場合
- 臭いとともに、ほかの症状が見られる場合
- 強烈な異臭や出血・膿を伴う場合
- 原因がわからない場合
以上のように、普段と違う臭いが続いたり、体調面で気になったりすることがあれば受診を検討してください。軽度のうちに治療すれば短期間で治る皮膚炎や歯周病も、放置すれば慢性化して治療が長引くことがあります。病院に行くべきか迷う場合は、臭いや症状について電話で相談に乗ってくれる動物病院もあります。大切な愛猫の健康のため、臭いのサインを見逃さずに対処しましょう。
猫が臭いときに動物病院で行われる検査と治療法

異常な臭いの原因によって、動物病院での検査内容や治療法は異なります。ここでは、動物病院で実際にどのような診察・検査・治療が行われるかを説明します。愛猫を病院に連れて行く際の参考にしてください。
動物病院での診察内容
動物病院ではまず獣医師が問診と身体検査(視診・触診)を行います。問診では、いつ頃から臭うか・臭いの種類(どのような臭いか)・ほかに症状はあるか・食欲や飲水の変化などを詳しく確認されるでしょう。身体検査では、猫の口、耳、皮膚、肛門など臭いの発生源と思われる部位を中心に観察します。
動物病院での検査方法
口臭の原因が歯周病だと疑われれば、歯や顎のレントゲン検査で歯根や顎骨の状態を確認することがあります。口内の腫瘍が見つかった場合は、腫瘍の種類(良性か悪性か)を確かめるため細胞検査や生検を実施します。
耳の臭いの場合、耳垢を綿棒で採取して顕微鏡で調べる耳垢検査(耳鏡検査・細胞診)により、細菌や酵母菌、ダニの有無を確認します。皮膚の臭いでは、被毛や皮膚スワブを採取して寄生虫や真菌を調べる皮膚検査や、膿が出ている場合はその膿を培養して細菌の種類と有効な抗生剤を調べる細菌培養検査を行うこともあります。
また、臭いの背後に内臓疾患が潜んでいないか確認するため、血液検査や尿検査も行われます。血液検査では、腎臓や肝臓の数値、血糖値、炎症の有無などを確認し、尿検査では尿中の糖やケトン体、潜血、細菌などを調べます。必要に応じてウイルス検査)やホルモン検査、腹部エコー検査、全身のレントゲン検査など、より専門的な検査に進む場合もあります。
こうした検査結果を総合して、最終的な診断が下されたら治療方針が決まります。臭いの原因を特定するために必要な検査は猫それぞれで異なりますが、獣医師は猫への負担も考慮しつつ優先度の高い検査から行います。
動物病院での治療法
原因に応じた治療によって、異常な臭いは改善していきます。主なケースごとに治療法の一例を挙げます。治療後は臭いの改善が期待できますが、再発予防のため飼い主さんによるケアや生活環境の改善も重要です。
口腔内の病気に対する治療
歯周病が原因の場合、基本的には全身麻酔下でのスケーリング(歯石除去)と口腔内の徹底洗浄を行います。
耳の病気に対する治療
外耳炎の場合、まず耳道内の汚れや膿を可能な範囲で除去し、点耳薬(耳の薬)を用いて治療します。
肛門腺の病気に対する治療
肛門嚢炎(肛門腺の感染)であれば、まず肛門腺を絞って中の膿を排出します。そのうえで抗生剤や消炎剤の投与など内科的治療を行うのが一般的です。
皮膚病に対する治療
皮膚の感染症や脂漏症が原因の場合、状態に応じて薬用シャンプー療法を行います。抗菌シャンプー・抗真菌シャンプーで皮膚を洗浄しつつ、内服の抗菌薬や抗真菌薬で感染を治療します。
内臓疾患に対する治療
腎臓病や糖尿病などが見つかった場合は、それぞれ慢性疾患に対する継続的な管理治療となります。
猫のニオイ対策

愛猫の臭いトラブルを防ぎ、常に清潔で快適に過ごしてもらうために、日頃からのケアと環境づくりが大切です。ここでは飼い主さんが家庭で実践できるニオイ対策を紹介します。いずれも難しいことではなく、少しの工夫で効果が上がりますのでぜひ取り入れてみてください。
歯磨きや耳掃除などのケアを実施する
猫の口臭予防には歯磨きが特に有効です。猫は人より歯石が付きやすく、食べかす由来の歯垢がわずか3日ほどで歯石に変わってしまいます。歯石はザラザラしてさらに歯垢がつきやすくなり悪循環となるため、歯垢の段階で毎日取り除くことが肝心です。やわらかい猫用歯ブラシや指サック型ブラシに猫用歯磨きペーストを付け、嫌がらない範囲で少しずつ磨いてあげましょう。
定期的にブラッシングをする
猫のブラッシングは臭い対策に効果的です。ブラッシングをすることで抜け毛やフケ、ホコリなどを取り除き、被毛の通気性を良くして匂いの元を減らせます。また、皮膚に適度な刺激を与えて血行を促し、皮脂の分泌を整える効果もあります。先述のように、猫は自分で毛づくろいをして身体を清潔にしますが、病気やケガ、高齢などでグルーミングが十分にできない場合は飼い主さんが手伝ってあげる必要があります。丁寧にブラッシングするだけで、被毛にこもった臭いが緩和されることもあります。
トイレを清潔に保つ
猫のニオイ対策でもっとも基本となるのがトイレ環境の管理です。部屋の猫臭の原因はトイレの場合も多いので、ここをしっかり清潔に保てば臭いが防げることがあります。特に4つの点に注意しましょう。
- 毎日の掃除
- 定期的な全替えと洗浄:少なくとも月に1回は全部の砂を新品と交換
- トイレ周りのケア: トイレマットを敷いて散らばった砂をキャッチし、床や壁に飛んだ場合は消臭スプレーや除菌シートで拭き掃除します
- 住環境の工夫: 猫トイレはできれば換気しやすい場所に置きましょう
消臭グッズを活用する
どうしても生活空間に残るペット臭には、市販の消臭グッズもうまく活用してみましょう。ただし、使用にあたっては猫に有害な成分が含まれていないか注意が必要です。
- ペット用消臭剤を選ぶ
- 強い香りは避ける
- 空気清浄機・脱臭機の利用
このように、安全に配慮しつつ消臭グッズを使えば、猫との暮らしの嫌な臭いをかなりコントロールできます。消臭剤を使った後に換気も行うなど、基本的な対策と組み合わせて効果を高めてください。
まとめ

「猫が臭い」と感じるとき、その背後にはさまざまな原因が潜んでいます。健康な猫は自分のニオイを抑える習性があるため普段はほとんど体臭を感じませんが、それだけにニオイの変化は重要なサインです。口臭がきつければ歯周病や内臓病、耳が臭ければ外耳炎、体全体の悪臭は皮膚病やグルーミング不足、強烈なお尻の臭いは肛門腺トラブルといったように、臭いの種類や発生源からある程度の推測ができます。本記事で解説した原因別の特徴を参考に、まずは愛猫の臭いの原因を探ってみてください。
参考文献


