うさぎは不調があっても元気そうにふるまうため、病気に気付きにくいのが特徴です。野生では捕獲される側のため、敵に襲われにくいよう本能から弱みを見せない傾向があります。
うさぎの皮膚は薄くてデリケートなので皮膚病にかかりやすく、日頃のケアで抱っこをしたときやお店からの指摘で発見される印象です。
一見何もないかのように元気にしているのでわかりにくいですが、よく観察していると早い段階で発見できます。
では、うさぎはどのような皮膚病にかかる可能性があるのでしょう。その原因や予防法、治療の疑問がでてきます。
ここでは、うさぎの皮膚病の疑問と、治療費の相場も併せて解説します。
うさぎの主な皮膚病と原因

うさぎは全身を美しい被毛で覆い、皮膚病になっていても表面的には見えにくく発見も遅れがちです。毛の密度が濃い代わりに薄くて繊細な皮膚をしているため傷つきやすく感染しやすいことも覚えておきましょう。
また、肛門や鼠径部、首の下にある臭腺は皮膚病の好発部位ですが、見えにくい場所であり発見が遅れる原因でもあります。
飼い主が、うさぎの異常に気付いてあげることで早期発見や早期治療が可能です。
抱っこを嫌ううさぎでも、次のような姿を発見すれば早い段階で皮膚病に気付けるかもしれません。
- いつもと様子が違う
- 同じ場所を舐めている
- いつもより身体を搔いている
- 異臭がする
では、代表的な皮膚病にはどのようなものがあるのでしょう。疾患別に原因と併せて解説します。
湿性皮膚炎
湿性皮膚炎は皮膚が湿っている状態が続くことで細菌に感染してしまう皮膚病です。皮膚が薄く傷つきやすいため小さな傷からでも感染を起こします。
高温多湿が特に炎症を助長するため湿度の調整が必要で、特に運動不足による肥満のうさぎが発症しやすい傾向です。被毛が濡れ湿ってしまうと乾きにくいため皮膚病になるリスクが上がってしまいます。
眼の周りやお口周り、陰部、お尻周りで起こりやすく、ケージの床が濡れて下痢や尿漏れなどの汚染で発症につながります。
次のような場面は皮膚病の原因の一つです。特に足の裏は濡れると乾きにくいので気を付けましょう。
- 尿で汚染したままになっている
- 涙や臭腺が湿ったままになることからの感染
- 給水ボトルの水で顎に水がたれ被毛が濡れる
- 肥満による皮膚のたるみで湿っている
飼育環境を整え、コミュニケーションをとりながらよく観察してあげましょう。
緑膿菌感染
うさぎに感染する病原菌に緑膿菌があります。不衛生な環境や抵抗力が弱いうさぎに感染しやすい傾向です。
皮膚にできものとなって現れ湿疹や脱毛、目やになどを起こし、ひどくなると感染部位は潰瘍になることもあります。また、感染が広がることで、鼻汁やくしゃみから肺炎と移行し亡くなってしまうこともあります。
原因は、抵抗力の衰えと不衛生な飼育環境が考えたられるため、ストレスのない環境づくりと衛生的な環境を見直すことが必要です。
足底皮膚炎

足底皮膚炎はソアホックとも呼ばれ、足の裏が炎症を起こし壊死していく疾患です。床が硬いと足の裏に圧力がかかるため血流を阻害して発症します。
初期の段階では足底の脱毛や皮膚の炎症、硬く厚くなる、かさぶたができるなど、ややわかりにくい症状です。
足の裏は厚い被毛で保護されていますが、肉球がないため強くありません。
特に床材が金網などの圧力がかかりやすいものでは、発症率が高い傾向です。
金網の床材は掃除が簡単で扱いやすいですが足への負荷が大きく、体重が増えるとさらにリスクが増強します。
また爪の伸びすぎも、かかとに負荷がかかりやすく足底皮膚炎を起こす原因になります。
皮膚糸状菌症
皮膚糸状菌症とは、真菌とも呼ばれるカビの感染です。
抵抗力がある元気なときは感染しても無症状の場合がありますが免疫力の低下により、フケや脱毛、かさぶたなどの症状が現れます。高齢うさぎや免疫力の弱いうさぎに発症しやすい傾向です。
カビのある環境での遊びや、水虫の足でなでるなどでも感染します。
また、給水ボトルの下で寝るのが好きなうさぎもいます。垂れた水で被毛が長時間濡れると菌が繁殖しやすい状況を作ってしまうのも原因です。ほかにも、カビだらけの家具の隙間に入って遊んでしまったなど、生活のなかにはさまざまな原因が隠れているので気を付けましょう。
心因性脱毛症
心因性脱毛症はストレスなどで自分の被毛や、ほかのうさぎの被毛を抜いてしまう病気です。身体を舐めることで気を紛らせているうち、行動がエスカレートして被毛をむしってしまいます。
皮膚感染による痒みでも舐めているうちに脱毛はおこるので、検査をして感染性の脱毛が除外されて心因性の要因が考えられます。
うさぎはストレスに弱いことで知られており、小さなストレスにも敏感です。以下はストレス要因となるものの例です。
- 暑さや寒さ
- 季節の変わり目
- 痛みや痒み
- 不衛生などの不快感
- 受診時の恐怖
- 飼い主による過干渉
- ホルモンの影響による発情のイライラ
- 引っ越しや外出で縄張りにいる安心感がなくなったとき
しかしながら、上記は一部の事例にすぎず本当の原因はうさぎにしかわかりません。
ホルモンによるストレスは、避妊手術をすると改善がみられることがあります。
治療中は身体を舐めないようエリザベスカラーやスタイを使用し予防する方法もありますが、エリザベスカラーやスタイがストレスとなるため極力避ける獣医師もいます。
皮下膿瘍
皮下膿瘍は喧嘩や自分の爪でひっかいてしまい、傷から細菌が入ることで皮下に膿がたまる病気です。
しこりのようなできものや皮膚の腫れをみつけて発見できることが多く、ひどくなると増大し被毛が抜けて壊死してしまいます。切開すると白くチーズのようなどろどろした物が出てくるので、洗浄と消毒、抗生物質を投与します。しかし、残念ながら治癒は難しい傾向です。
歯のトラブルから発症した場合は顎の下や眼の下にできやすく、特に顎下は発見しにくいため大きくなってしまうことがあります。
喧嘩による怪我が原因のことがあるので、爪をケアして仲が悪いうさぎ同志を同じ空間にいさせないようにしましょう。
うさぎの皮膚病で生じる主な症状

喧嘩による外傷や生活のなかで作った小さな傷から、飼育環境の汚染などで繁殖した細菌などが感染します。
皮膚病の好発部位は眼やお口(顎)、陰部、お尻、足があり、濡れやすい部位と考えるとわかりやすいかもしれません。
眼の周囲に起こる皮膚病の症状や原因となる兆候は、長時間皮膚を湿らせてしまうため感染の原因になります。例えば、目やにや涙、まぶたの腫れ、目の白濁や充血などで目の周りが湿った状態が続くなどです。
お口周りは噛み合わせが悪いとよだれが出るため、顎に水が停滞し炎症を起こします。原因となる疾患(不正咬合など)の治療が先決かもしれません。
特に陰部・お尻周りは臭腺があり排泄物でも濡れやすく汚れやすいため感染しやすい部位で皮膚炎になると次のような症状が現れます。
- 臭い
- 皮膚が赤くなる
- 皮膚が腫れる
- ただれる
- 被毛がからまる
- 潰瘍になる
- 脱毛する
- 下腹部や肛門付近で尿がかたまる
早期発見を目指しケアの時間に観察をしましょう。
耳は中耳炎、外耳炎を起こすことがあります。皮膚が赤くなっていたり、耳を掻いたりする場面が増えたときは、耳の中を観察してみましょう。耳垢や汚れ、異臭がするなどの異変がある場合は、動物病院に相談するとよいかもしれません
好発部位の足裏(足底皮膚炎)は脱毛や腫れ、皮膚が硬い、出血、爪が折れるなどで異常を発見できます。
また、被毛の艶がいつもより悪いと思ったらよく観察してみましょう。フケや皮膚の赤み、ただれなどが悪化すると被毛が絡まり脱毛して潰瘍になることもあります。いつもと違う異変を感じたら動物病院に相談しましょう。
うさぎの皮膚病の診断方法

「皮膚病の診断は何をするのか」なにも情報がないまま動物病院に行っては、うさぎの負担にならないかと心配になるでしょう。そこで、動物病院ではどのような検査をするのかを解説します。
スタンプ検査
スタンプ検査は、皮膚にスライドガラスやセロハンテープを押し当てて、皮膚表面の細胞を付着させる採取法です。色を付けて顕微鏡でのぞくと細菌や真菌の感染なども確認できます。
顕微鏡検査

スタンプ法で採取した皮膚表面のフケや皮膚から、ブドウ球菌やマラセチア、細菌、腫瘍細胞などが確認できます。
健康な身体にも存在している常在菌が、免疫力の低下などから増えてしまい悪さをすると皮膚病になるため、原因の解明に役立つのが顕微鏡検査です。爪ダニや卵など肉眼では見えないものも発見でき、効果的な治療につながります。
被毛検査
被毛の異常を調べる検査です。被毛を数本抜いて顕微鏡で寄生虫や真菌がいないかどうかを確認します。また、毛根の状態から噛みちぎって抜けたのか、毛周期の異常からなのかなどの脱毛の原因もわかります。
うさぎの皮膚病の治療法

皮膚病の基本的な治療法は、洗浄後に消毒をして必要があれば抗生物質や抗菌剤の投与をします。
うさぎはストレスを嫌い処置をしても舐めて包帯を外してしまうことがあるため、処置の方法も慎重に選びます。また、治療中の管理も飼い主の重要な役割です。
抗生物質の投与
感染性の皮膚病には抗生物質の投与を行います。皮膚炎や皮下膿瘍でも使用されます。
抗生物質の塗り薬も治療には有効ですが舐めてしまう可能性があり、場合によっては悪化の可能性があるので注意が必要です。
使用できる抗生物質は限られており、種類によって致命的な下痢などの消化器系の副作用を起こします。抗生物質を飲み始めたら下痢をするようになったなどの、異変に気付いたらすぐに獣医師に相談しましょう。
消毒薬による治療
炎症している傷口はまず、洗浄と消毒で炎症の拡大を阻止します。
消毒後に軟膏処置などを行うと保護のための包帯を巻く必要がありますが、包帯を嫌がるうさぎもいるため、かえって傷を悪化させてしまうことも考えられます。
必要があればエリザベスカーラーやスタイなどを使用し舐めないように保護する手段もありますが、うさぎにとってストレスが強いとかえって免疫力が低下するので簡単にはいきません。
そのため、感染源となる飼育環境を見直し消毒して乾燥させることが大切です。
抗真菌薬の投与
皮膚糸状菌症の治療には、カビ菌と戦う抗真菌薬を使用します。自然治癒することもありますが、通常内服の使用で1〜2ヶ月かかります。
ただし再発しないよう生活環境にいるカビを退治する必要があるので、うさぎを別室に移動して掃除機や洗濯などに加え、薄めた塩素系漂白剤を使用した消毒も行いましょう。
塩素系漂白剤を使用するときは、換気と消毒後の洗浄も行いよく乾燥させる必要があります。
うさぎの皮膚病の治療費用の目安

うさぎの治療費は獣医師団体などで基準となる料金は決まっていないため、動物病院によって差があります。
およその相場は、3000円未満が50%以上を占めており、腫瘍の摘出手術や検査を行った場合などは別途費用がかかります。
年齢が若いうちは、安価におさまりますが高齢になると免疫も落ちて皮膚病にかかる確率が増えるため、治療費も増える傾向です。
うさぎの皮膚病の予防法

皮膚病の予防は、湿度が高くならないよう50〜60%に調整し、被毛が常に濡れる環境を作らないことが大切です。また、病原菌を寄せ付けない清潔な飼育環境と床材をやわらかいものの使用で、うさぎのストレスの緩和につながりリスクが激減するでしょう。
やわらかい床材を使用する
ケージの床が金網の場合、限局して圧がかかってしまうため、やわらかい素材の床を敷いてあげるとよいでしょう。
木製のものや、コルクなどは自然の素材なのでかじって食べても問題ありません。また、フローリングの床を走り回って部屋んぽをする場合は、爪がひかっからない毛足の短いカーペットを敷いてあげると走りやすく運動不足解消にも役立ちます。
毛先がリング状になっているループパイルカーペットは、ホリホリして爪が折れたり引っかかったりするので避けた方が賢明です。また、タイルカーペットは隙間からかじって食べてしまううさぎもいるため気を付けましょう。
運動習慣をつけることで肥満解消につながります。おもいっきり走らせてあげたいですが足底が毛でおおわれているので、フローリングは滑りやすく走りにくいです。毛足の短いカーペットはうさぎにとって走るためにもくつろぐ場所にも快適な環境になるでしょう。
こまめに掃除する

トイレは毎日交換し週に1度は水洗いをしましょう。尿石がついていたら水200mlにクエン酸小さじ1杯を溶かしスプレーすれば、トイレにこびりついた尿石を溶かすことができます。
食器はペレットの粉や唾液が付着しているかもしれないので、毎日洗って乾かしてから使用します。ケージ全体も月に1度は大掃除をしてあげるとよいでしょう。
給水ボトルも本体から取り外し丸洗いします。ボトルの中や手の届きにくい場所は水垢がたまるので、細長いブラシで中までしっかり洗浄してあげると衛生的です。
足の裏は毛で覆われているので濡れてしまうとなかなか乾きません。洗ったものはしっかり乾かしてからケージに戻し使用しましょう。
まとめ
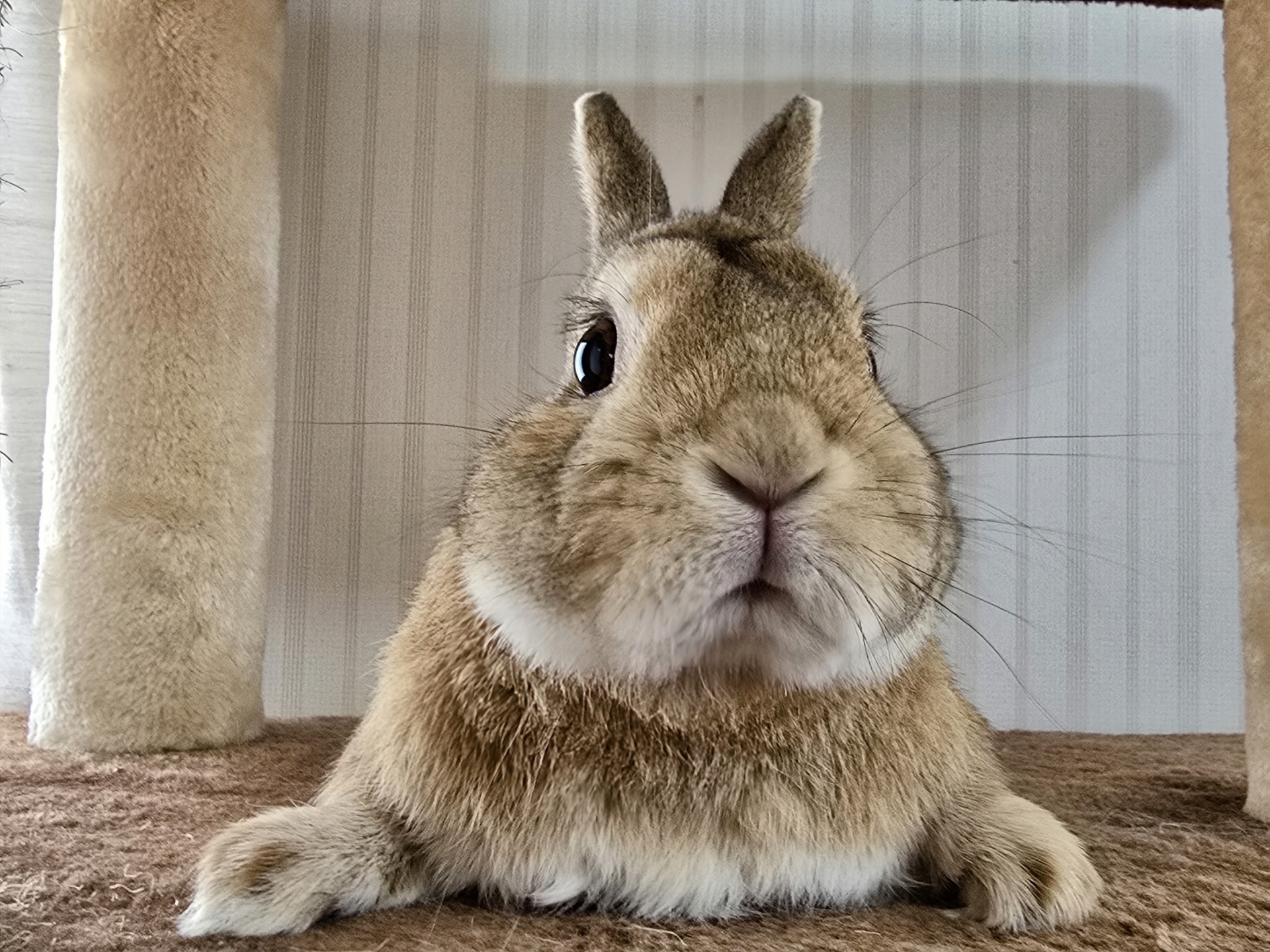
うさぎは高温多湿とストレスに弱くデリケートな皮膚の持ち主です。皮膚病にかかるリスクは高く、抵抗力の弱まる高齢になるほど罹患しやすくなります。
動物病院では皮膚や被毛を採取し原因を調べて適切な診療を行うものの、傷が悪化し手遅れになると治療が困難になることがあるため早期発見が重要です。
早めに動物病院で診療を受ければ悪化を防ぐことができますが、飼い主さんが予防と早期発見のためにできることはたくさんあります。
いつもと違う行動や臭い、毛並み、皮膚の観察などです。また、高温多湿を避け、清潔な飼育環境を整えると皮膚疾患の原因を避けられます。
うさぎにとってストレスのない環境は、皮膚病のリスクを減らし早期発見につながります。そして、うさぎさんとの幸せな暮らしがいつまでも続くことでしょう。
参考文献


