人の医療に欠かすことのできないMRI検査ですが、近年は動物病院でも導入が進み、従来の検査では難しかった病気の診断が可能になりつつあります。しかし、いざペットがMRI検査を受けるとなると、リスクや費用についての不安が大きいのではないでしょうか。今回はペットのMRI検査を検討している方に向けて、検査を受けるべき症状や押さえておきたい注意点などの情報をまとめました。正しい知識を持って検査に臨み、ペットの健康をサポートしてあげましょう。
動物病院で行うペットのMRI検査の特徴
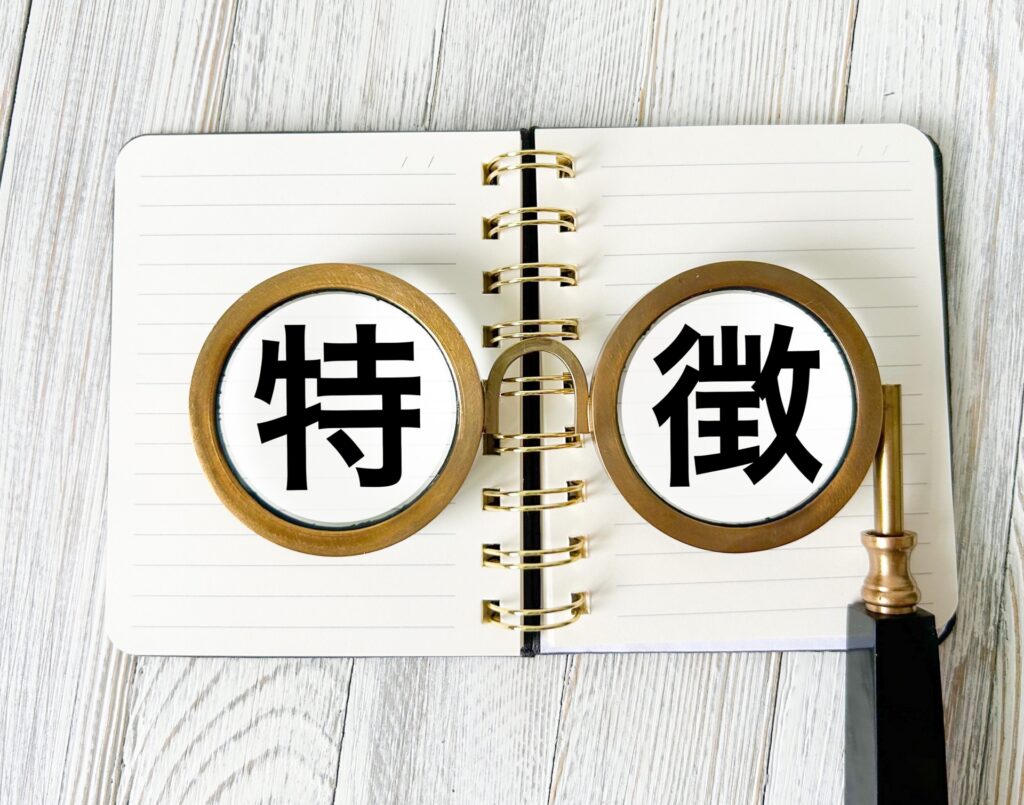
そもそも動物病院で実施されるMRI検査とは、どのようなものなのでしょうか。MRI検査の基本情報を確認したうえで、検査を受けるメリットとデメリットを掘り下げていきましょう。
- 動物病院で実施されるMRI検査は、どのようなものですか?
- MRIとは、磁気共鳴画像法Magnetic Resonance Imagingの略であり、X線ではなく磁気を使った検査方法になります。身体を強い磁場のなかに入れてある周波数の電磁波(ラジオ波)を流すと、体内の水素原子と磁気共鳴し、原子核の向きを特定の方向へ変化します。そして電磁波を止めると、細胞によって異なる信号を出しながら元の向きに戻ろうとします。このときに発生する信号を受信しコンピューターによって画像化するというメカニズムです。MRI検査の画像は横断面のみならず、縦・横・斜めといったあらゆる断面から撮影することができます。造影剤なしで痛みもなく、簡単に検査できるというのも特徴です。
- CT検査やレントゲン検査と何が違うのですか?
- MRI検査とCT検査、レントゲン検査はいずれも高度な画像診断技術ですが、それぞれの強みは異なります。具体的に解説すると、レントゲン検査は骨の状態を迅速かつ低コストに確認できますが、詳細な内部構造の評価には適していません。CT検査はX線を利用して身体の断層画像を取得するため、骨といった硬組織の異常を高精度で診断できます。一方のMRI検査は磁気と電磁波を用いて軟部組織の詳細な画像を取得することから、脳や脊髄、関節などの診断に適しています。神経系や筋肉、靱帯などの評価においては、MRI検査が強みを発揮するといえるでしょう。各検査の特性を理解して適切に選択すれば、より正確な診断と効果的な治療が可能となります。
- MRI検査のメリットとデメリットを教えてください
- MRI検査は放射線を使うことなく磁気と電磁波によって詳細な画像を取得する、安全性が高く効果的な診断方法です。放射線被曝がない点は、MRI検査の大きなメリットといえるでしょう。一方で検査にあたってはペットが長時間動かないようにするため、全身麻酔が必要となります。全身麻酔はペットの内臓などに負担をかけることから、MRI検査を受ける際のデメリットとして留意しなければなりません。
- MRI検査によって診断できる疾患を教えてください
- MRI検査を受けると、脳腫瘍や椎間板ヘルニア、関節の損傷、内臓の詳細な状態などについて高精度で診断することができます
ペットのMRI検査を希望する場合の確認事項
MRI検査はとても効果的な診断方法ですが、やみくもに取り入れてよいわけではありません。このパートでは、ペットのMRI検査を希望するときに確認しておくべき事項について、具体的に解説を加えます。
- どのような症状が見られたら、MRI検査を検討しますか?
- けいれん発作や手足の麻痺、身体の動きとは関係なく目が動く眼振の症状、頭の傾きや急に後ろ足が立たなくなるなどの様子が見られたら、神経系の異常が疑われるためMRI検査を検討するとよいでしょう。また、性格や行動の変化が目に付く場合にも、獣医師に相談してみてください。
- MRI検査ができないケースもありますか?
- MRI検査では強力な磁場が使用されるため、ペースメーカーなどの金属製インプラントを持つペットは検査を受けることができません。インプラントが移動したり、加熱したりするリスクがあります。発作を持つペットについても、検査中の安全性確保が難しいことから、MRI検査に適しているとはいえません。加えて、MRI装置には体重制限があり、それを超える大型犬などは検査できないことも留意しておきましょう。ただし、てんかん発作を持つペットについては検査中の安全確保が難しいですが、診断をするために、状態が安定しているならMRI検査を実施することもあります。
- 検査前に必要な準備があれば教えてください
- MIR検査の前日にはペットの食事を控え、指定された時間から絶食を開始します。水分は通常接種可能ですが、獣医師の指示に従いましょう。薬の服用などについても、事前に対応を確認しておきます。ペットがリラックスして過ごせるよう、飼い主がサポートすることも重要です。
- MRI検査にかかる費用の目安を教えてください
- 10〜20kgのペットであれば10万円前後が目安です。術前検査代など、別途費用が必要となるケースもあります。いずれにしても、決して安い費用ではないため、具体的な金額については動物病院に問い合わせておきましょう。なお、MIR検査は動物専用医療保険の保険対象になることも少なくないので、併せて詳細をチェックしてみてください。
ペットがMRI検査を受けるときの注意事項

終わりに、ペットがMRI検査を受けるときの注意点をまとめます。飼い主としてあらかじめ必要な情報を押さえておくことで、ペットが問題なく検査に臨める環境を整えてあげましょう。
- MRI検査を受ける前に、どのような情報を伝えるとよいですか?
- 検査当日は動物病院の受付にて必要な書類の提出や問診票の記入を行うため、ペットの健康状態や既往歴について、詳しく共有しましょう。その他にも気になることがあれば、担当のスタッフに伝えてください。検査直前になって焦ることがないよう、重要な情報はメモしておくというのも一案です。
- MRI検査は全身麻酔が必要か教えてください
- MRI検査を受けるにあたっては、全身麻酔が必要になります。そのため、事前に身体検査や血液検査を行うことで、麻酔を問題なく使用できるかどうかのチェックが実施されます。全身麻酔はペットの負担になりますが、検査中は長時間動かずにいる必要があり、ペットに不快感を与えるような大きな音も鳴るので、不可欠な対応であると理解しましょう。そのぶん検査の前後にはペットが落ち着いて過ごせるよう気を配り、ストレスの軽減に努めることがポイントです。
- MRI検査を受けたら当日中に帰宅できますか?
- MRI検査は通常30分から1時間程度で終了します。検査を受けた後は当日中に帰宅することが可能です。なお、検査終了後には獣医師がMRI画像を解析のうえ、診断結果の報告を行います。飼い主は結果についての詳細な説明を受けるとともに、今後の治療方針などに関して相談できるため、疑問に思うことがあれば、その場で質問しましょう。日帰りできるとはいえ、MRI検査を受けると、飼い主にもペットにも一定の負担がかかります。検査の費用も安くはありません。せっかく検査を受けたのであれば、その結果と丁寧に向き合い、大切なペットの健康維持に役立てていきましょう。
編集部まとめ
軟部組織の異常を高精度で診断できるMRI検査をうまく活用すれば、特に神経系や筋肉、靱帯などについて、早期に異常を発見することが可能です。放射線を使用しないことから安全性が高く、ペットへの負担を可能な限り抑えられるというメリットもあります。一方で全身麻酔を必要とするため、内臓ダメージリスクを避けることはできません。MRI検査のメリットとデメリットを理解したうえで、検査を受けるか否か慎重に判断しましょう。


