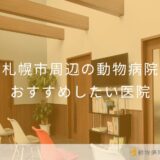猫は、年齢を重ねると人間と同じように白内障を発症することがあります。白内障は、目のなかの水晶体が白濁色に変色し、視力の低下を引き起こす目の病気です。小さな変化を見落として放置すると、失明するリスクもあるので注意が必要です。ここでは、猫が白内障になる原因をお伝えしたうえで、発症するタイミング、症状、治療法などを解説します。家族の一員である愛猫が、長く健康な目を維持するためにも、飼い主さんとして正しい知識を身につけておきましょう。
猫が白内障になる主な原因

猫が白内障になる原因として、加齢や先天的な体質のほかにも疾患や外傷による二次的要因が絡むことがあります。原因を特定することで効果的な治療や対策が可能です。ここでは、猫が白内障になる主な原因について解説します。
加齢による水晶体タンパク質の変化
猫の白内障は、高齢になるにつれて増加するため加齢が一つの要因として考えられるでしょう。水晶体は主にタンパク質で構成されていますが、加齢とともに白く濁り始めて視力に影響がでます。12歳を過ぎたあたりから徐々に白内障を患う猫の数が増加します。初期症状として部分的な濁りはみられますが、明らかな視力の低下には気付きにくいため、毎日一緒に暮らしている飼い主さんでも気付きにくい点が特徴的です。遺伝体質や基礎疾患がないにも関わらず、目の色が白く濁り始めたら、早めに動物病院を受診しましょう。
遺伝性・先天性の体質
ごく稀なケースではあるものの、猫の白内障は遺伝性や先天性の体質が関係していると報告されています。白内障にかかりやすいとされる猫の種類は次のとおりです。
- ロシアンブルー
- ヒマラヤン
- ペルシャ
- ベンガル
- ブリティッシュ
- バーマン
- シャム
猫の白内障は年を重ねてから発症するケースが一般的であり、若い猫で白内障が確認されたときは、遺伝性や先天性の要因をまず疑います。長毛種の猫で報告されている事例があるため、目の色の変化や視力の低下が疑われる場合、すぐに動物病院を受診しましょう。
糖尿病などの全身疾患に伴う代謝異常
猫が糖尿病になると、合併症により高確率で白内障を発症します。まず、一般的に猫は犬と比べて白内障になりにくいといわれています。犬の場合、水晶体が糖分を代謝するための酵素を使い切ると、別の物質を分泌するため、その物質が水晶体の変性を起こすことがあります。一方で猫は、糖分を代謝するための酵素が不足しても、犬のように代わりの物質を分泌する構造になっておらず、水晶体の変性が起こるリスクが高くありません。
この背景により、一般的に猫は白内障になりにくいといわれていますが、糖尿病になると眼球内の糖分も高くなるので、白内障を引き起こします。糖尿病による白内障は、進行スピードが早く、症状が悪化しやすいので早期治療が欠かせません。
外傷や炎症による二次的要因
目をどこかにぶつけた、目のなかに異物が混入した、自分で目を引っ掻いた……など何かしら外部の刺激が加わり外傷や炎症が起きた場合、二次的に白内障を発症するケースがあります。ウイルスや細菌による感染が原因になる場合もあるので、外傷や炎症で出血している際には注意が必要です。
軽症にみえても、愛猫が自分で掻いたり舐めたりして傷口を広げてしまうと、侵入経路の拡大や免疫力の低下を引き起こし危険です。外を散歩する猫は、ほかの動物との接触や細菌、植物の成分などから病気をもらうリスクがあるため、一時的に室内で生活させて様子をみるなどの対応が必要です。
発症しやすいタイミング

猫の白内障は、12歳を過ぎたあたりからリスクが高くなるとされています。一方で糖尿病など全身疾患を持つ猫は、若年期でも白内障を発症する可能性があるため、一概に年齢だけで判断することはできません。ここでは、猫が白内障を発症しやすいタイミングについて解説します。
シニア期
猫は、中高年期が7〜10歳、高齢期が11〜14歳、老齢期が15歳以上と分類されており、大体7歳を過ぎたあたりから加齢が原因の疾患が目立つようになります。加齢による白内障は老年性白内障と呼ばれ、12歳以降に急増すると報告されています。ただし、年齢とともに免疫力が低下するので、12歳未満でも老年性白内障になる可能性があります。初期症状で気付かずに放置してしまうと、急速に進行するおそれがあるので注意が必要です。
目の色の変化だけではなく、光の反射に敏感になったり、壁や物にぶつかることが増えたりした場合、視力の低下が疑われます。自宅での観察や動物病院での定期検診を徹底して、早期発見と進行抑制に努めましょう。
全身疾患がある場合は若年期でも
加齢による老年性白内障とは別に、糖尿病や感染症などの全身疾患によって患う白内障を若年性白内障と呼びます。とくに糖尿病になると、眼球内を含む全身の糖分が高くなるので、合併症として白内障になります。糖尿病の初期段階で適切な治療をしてコントロールできていれば、白内障を併病するリスクを軽減したり、進行を遅らせたりすることが可能です。ただし、一度目の色が変色してしまうと白内障で濁った水晶体は元に戻せません。そのため自宅での安静管理が重要です。変化に気付いたら、すぐに動物病院を受診しましょう。
白内障で見られる主な症状

白内障の症状は目の変色と視力の低下が典型的です。ただし、初期段階では飼い主さんが見落としてしまう可能性があるため、見た目の変化と一緒に行動や生活態度にも注力することが重要です。ここでは、猫の白内障でみられる主な症状を解説します。
瞳孔部分が白く濁って見える
猫の白内障の典型的な症状として、瞳孔が白もしくは青白く濁ってみえる状態が挙げられます。これは、水晶体のタンパク質が変性することで、光を通さなくなることが原因です。初期段階では無症状で、見た目の変化には気付かないことがあります。しかし、白内障の症状が進行するにつれて、白濁とした変色が目立ち始めるので、一緒に生活している飼い主さんや定期検診で診療する獣医師でも気付きやすいです。写真で撮ると、フラッシュに白く反射することがあるので、記録として保存しておくと比較しやすくなります。少しでも目の色に変化があれば、早めに動物病院を受診して状態を確認してもらいましょう。
家具や壁に頻繁にぶつかる
猫の白内障が進行すると、目の色の変化だけではなく視力の低下が始まります。視力が下がると、住みなれた家でも家具や壁との距離感をつかみにくくなるので、何気ない生活をしているなかでもぶつかる回数が増えるでしょう。また、飼い主さんと目があわなくなったり、物音に対して過敏な反応を見せるようになったら、白内障の進行が疑われます。片目のみ白内障になった場合、視力の残っているほうの目で生活できるので、行動の変化に気付けずに発見が遅れる可能性があるので注意が必要です。目の色の変化と一緒に愛猫の行動をよく観察する習慣をつけることで、視力低下を見落とさずに済みます。
暗い場所を怖がる、歩きたがらない
もともと猫は人間よりも暗闇での視力がよいことで知られていますが、そんな猫が暗い場所を怖がるようになったり、歩くことを躊躇うようになったら、視力の低下が疑われます。白内障は、光を調整する水晶体が不透明になることで、明暗の差を感じ取りにくくなります。よって、光の調整ができなくなった猫は、自分を守るために行動範囲を制限し始めるのです。今までは電気を消した部屋でも、自由に移動していた愛猫が、じっとして動かなくなったら要注意です。移動できないことがストレスになる可能性があるので、寝床まで移動してから電気を消したり、部屋を完全に暗くしないなど工夫しましょう。
充血・涙やけなどの合併症が現れることも
猫の白内障は、目の色が少し変化するだけで生涯を終えるケースがあれば、水晶体脱臼やぶどう膜炎などの合併症で眼の痛みや充血などを引き起こします。
- 水晶体脱臼:水晶体をつなぐチン小帯が切れて、本来の位置から前方もしくは後方に大きく外れる状態
- ぶどう膜炎:眼のなかに血液や栄養を運ぶ膜に炎症が起きる状態
水晶体が前方にズレて前眼房内に水晶体が侵入すると、激しい痛みが生じます。ぶどう膜炎になると、白目の部分が充血したり瞳が小さくなったりします。症状が悪化すると、緑内障を併発する恐れがあり危険です。白内障は、軽度のまま終わることもありますが、合併症などを引き起こすと失明につながるので早期発見と治療が必要です。眼の白い部分が充血していたり、眼の周りを気にしている素振りをみせている際には、まずは獣医師に診断してもらいましょう。
猫の白内障に対する治療方法

猫の白内障治療は、進行度合いや原因によって対応が異なります。初期段階で軽度であれば、経過観察でも問題ありませんが、進行したら外科手術を提案されることもあります。ここでは、白内障に対する治療方法について解説するので参考にしてください。
軽度の場合は経過観察
猫の白内障の初期段階では、目の色の変化や視力の低下がほとんどみられない無症状の場合があります。進行スピードも緩やかであれば、内服治療や外科手術をせずに、基本的には経過観察となります。ただし、放置すると緑内障などの合併症を併発するリスクがあるため、定期的に眼科検診を受けて、水晶体の濁りの進行具合、眼圧や炎症の有無をチェックしてもらいましょう。
動物病院での眼科検診の頻度は、基本的に1年に1回が目安ですが、白内障の状態を確認するために適した頻度を獣医師に判断してもらうことを推奨します。点眼薬とサプリメントで進行を遅らせる方法もありますが、進行した白内障を完治させることはできません。
進行した場合は、外科手術の選択も
猫の白内障が進んで、視力の低下や合併症の併発が確認された場合、外科手術を提案されることがあります。濁った水晶体を取り除いて、代わりに人工レンズを入れることで視力を取り戻せる手術です。大まかな手術の流れは、次のとおりです。
- 角膜切開
- 水晶体前嚢切開
- 水晶体乳化吸引
- 人工眼内レンズ
- 角膜縫合
- アフターフォロー
外科手術をする場合、術前から術後の数ヶ月〜数年間は点眼治療が必要です。そのため、愛猫が点眼に対して強い拒否反応をみせるのであれば、手術は推奨できません。また、安静に過ごせる環境やエリザベスカラーの装着など、一部の猫にとってはストレスになりやすいので、リスクを理解したうえで、愛猫のためになる選択を選びましょう。
猫の白内障を予防する方法

猫の白内障を完全に予防することは困難ですが、生活環境を見直して、定期的な健康チェックを受けることで発症リスクを軽減できます。さらに、小さな変化を見落とさないことで早期回復や進行抑制に効果的です。ここでは、猫の白内障を予防する方法について解説します。
直射日光や紫外線を避ける工夫をする
猫の目は人間よりも紫外線の影響を受けやすい特徴を持っており、冬よりも夏に強くなる紫外線は目の老化を促進させるおそれがあります。日向ぼっこが好きで、室内飼いでも窓際でリラックスする猫もいますが、UVカットガラスやカーテンレースなどを活用して、紫外線による負担を軽減できる工夫をしましょう。
年1回は健康診断を受ける
猫の白内障に対して早期治療をするためには、定期的な健康診断が重要です。言葉を話さない猫は、自分で痛みや視力の低下を訴えることができません。毎日一緒に暮らしている飼い主さんが、愛猫の小さな変化に気付いてあげるべきですが、専門知識がなければ見落としてしまうケースも少なくありません。
そこで、定期的に健康診断を受けることで、白内障の有無、進行状況を正確に把握できます。また、眼科検査と並行して検便や血液検査などを受ければ、感染症や糖尿病などの全身疾患の兆候にも気付けるでしょう。
まとめ

猫の白内障は、加齢や遺伝、全身疾患などさまざまな要因で発症するため、原因を特定したうえで適した治療法を選択する必要があります。進行状況によって、内科治療で経過観察するか、水晶体を取り替える外科手術など使い分けます。完全な予防策はありませんが、日常生活を見直したり定期検診を受けることで早期発見につながるため、愛猫の目の健康を守るためにできることを知っておきましょう。