猫のフィラリア症は、蚊によって媒介される犬糸状虫(Dirofilaria immitis)という寄生虫が猫の体内に寄生することで起こる病気です。フィラリア症は一般的に犬の病気と思われがちですが、猫にも感染しうる疾患であり、放置すれば致命的な肺や心臓の障害を引き起こすことがあります。本記事では、猫のフィラリア症について、その感染経路と発症メカニズム、症状と行動の変化、検査方法と治療法、感染してしまった場合のケアのポイント、そして予防方法まで詳しく解説します。
猫のフィラリア症とは?

猫のフィラリア症は、寄生虫である犬糸状虫が猫の心臓や肺の血管に寄生することで発症する病気です。犬糸状虫症とも呼ばれ、本来は犬を終宿主とする寄生虫ですが、猫も蚊を介して感染することがあります。しかし、この幼虫が死滅する過程で猫の肺に重度の炎症が起こることがあります。フィラリア幼虫による肺の炎症は犬糸状虫随伴呼吸器疾患(HARD)と呼ばれ、猫のフィラリア症に特徴的な病態です。HARDにより気管支や肺血管が障害され、猫では主に肺の病気として症状が現れます。さらに、猫では、犬のフィラリア症治療に用いられる成虫駆除薬(メラルソミン)が副作用で使用できないため、根本的な駆虫治療が行えないという問題があります。
猫のフィラリア症の感染経路と発症のメカニズム
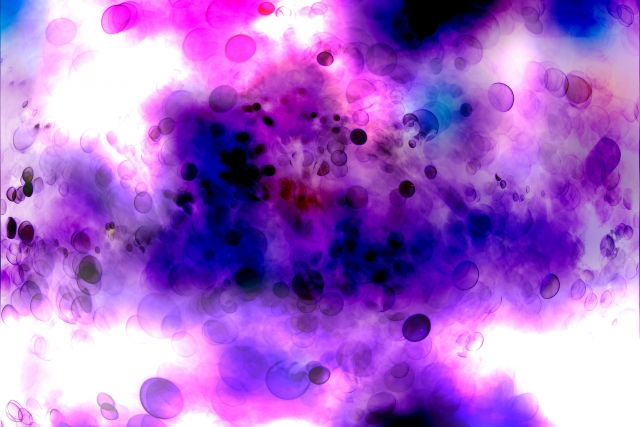
猫では侵入した幼虫の多くが免疫によって駆逐されてしまい、成虫まで育つ例はほとんどありません。そのため猫の体内のフィラリア成虫数はごく少数に限られますが、それでも猫に深刻な病気を引き起こすことがあります。
フィラリア症の感染には蚊が不可欠な媒介者となります。まず、フィラリアに感染した犬の血を蚊が吸うと、その血中にいるミクロフィラリア(フィラリアの幼虫)が蚊の体内に取り込まれます。蚊の体内で幼虫は約10~14日かけて発育し、感染可能な幼虫(感染幼虫)となります。次に、その蚊が吸血する際に、蚊の口器を通じて皮下に感染幼虫が侵入し、猫へと移行します。侵入した幼虫は猫の体内を移動しながら成長し、約6ヶ月かけて肺動脈や心臓付近で成虫へと成熟します。フィラリア成虫は猫では2~3年ほど生存するとされ、その間に宿主の肺や心臓に損傷を与え続けます。
猫のフィラリア症|症状と行動の変化

猫のフィラリア症は、症状が多彩です。初期には目立った症状が出ないことも多く、病気が進行してから突然重篤な症状が現れるケースもあります。本章では、初期症状、進行した場合の症状、そして飼い主が気付きうる猫の行動の異変について段階的に説明します。
猫のフィラリア症の初期症状
フィラリアに感染した直後から成虫になるまでの初期段階では、ほとんど症状が現れないか、ごく軽微な症状しか示さないことが珍しくありません。しかし、フィラリア幼虫が肺へ達し始める感染後2~3ヶ月頃から、徐々に以下のような症状が見られる場合があります。
- 咳
- 嘔吐
- 元気消失・嗜眠
- 下痢
以上の初期症状はいずれも特異的ではなく、ほかの病気と区別が付きにくいものです。そのため、この段階でフィラリア症だと断定するのは困難です。ほぼ無症状のまま経過する猫もいるため、飼い主が初期に異変を察知することは難しいですが、少しでも気になる症状があれば早めに動物病院で相談するとよいでしょう。
進行した猫のフィラリア症の症状
フィラリア症が進行し、猫の体内に成虫が存在する段階やHARDによる肺障害が重くなってくると、症状はより明確で深刻になります。具体的には、呼吸器症状の悪化と全身状態の悪化が顕著になります。
- 重度の咳
- 呼吸困難
- 少し動いただけでぐったりと座り込む、歩行がよろける
- けいれん発作
- 腹水や胸水
フィラリア症が重度になると、ごく短期間で容体が急変することもあります。突然の虚脱や呼吸不全、そしてそのまま突然死に至ることもあります。
猫にみられる行動の異変
猫のフィラリア症では上記のような症状が現れますが、それに伴い日常の行動にも変化が現れることがあります。飼い主さんが異変に気付くきっかけとして、次のような行動上のサインにも注意してください。
- 活動性の低下
- 食欲や好みの変化
- 呼吸姿勢や寝方の変化
- 隠れ場所に籠る
以上のような変化から普段の様子との違いにいち早く気付くことが、フィラリア症に限らずあらゆる病気の早期発見につながります。日頃から猫の行動をよく観察し、気になる変化があれば獣医師に相談するようにしましょう。
猫のフィラリア症の検査と治療

猫のフィラリア症は症状だけで診断を下すことが難しいため、いくつかの検査を組み合わせて総合的に判断する必要があります。また前述のとおり、猫には犬のような確立された治療法がありません。そのため治療においては対症療法(症状を和らげる治療)が中心となり、場合によっては外科的に成虫を摘出する処置が検討されます。以下では、フィラリア症の主な検査法と、治療法について解説します。
フィラリア症の検査法
フィラリア感染が疑われる猫には、まずフィラリア抗原検査とフィラリア抗体検査の両方を実施することが推奨されます。また、血液検査以外では、画像検査も行われます。胸部X線検査では、肺動脈の肥大や肺野の炎症像などフィラリア感染に特徴的な所見が確認できる場合があります。また、心臓超音波検査(心エコー)は、心臓や肺動脈内にいる成虫そのものを映し出せることがあります。
フィラリア症の治療法
猫のフィラリア症に対する治療は、対症療法(薬物療法)と、必要に応じた外科的治療(成虫摘出手術)に大別されます。以下では薬物療法と手術療法それぞれの内容について説明します。
薬物療法では、前述のとおり、フィラリア成虫そのものを殺す薬剤(駆虫薬)を猫に使うことはできません。以上を踏まえ、薬物療法では以下のようなことが行われます。
- 抗炎症剤(ステロイド)の投与
- 気管支拡張薬・利尿剤・強心剤
- 酸素吸入・安静管理
- 抗生物質の投与
これらの支持療法によって多くの猫は一時的に症状が改善し生活の質が向上することがあります。しかし、成虫が生存している限り、突然死のリスクは残存します。
内科的治療ではフィラリア成虫そのものを除去できないため、状況によっては外科手術による成虫摘出が検討されることがあります。具体的には、麻酔下で静脈(頸静脈など)から特殊な器具を挿入し、心臓や肺動脈内のフィラリア成虫を物理的に取り出します。ただし、猫への負担がとても大きく、術中・術後のリスクも高いため、手術が選択されるケースはまれなのが現状です。
フィラリア症にかかった猫のケアと注意点

もし愛猫がフィラリア症に罹ってしまったら、飼い主さんとしてどのようにお世話をすればよいのでしょうか。治療はもちろん獣医師に委ねることになりますが、日常のケアも猫の回復を支えるために大切です。ここでは、フィラリア症と診断された猫をお世話する際のポイントをまとめました。
獣医師の指示に従い安静を保つ
フィラリア症の治療期間中、そして治療後もしばらくは、猫をできるだけ安静に保つことが重要です。過度な運動やストレスは猫の心肺に負担をかけ、症状を悪化させたり突然死の引き金となったりする可能性があります。激しい遊びや運動は避け、静かでリラックスできる環境を用意してあげましょう。
特に、呼吸が荒くなりやすい子は、涼しく空調の効いた場所で休ませ、興奮させないように配慮します。必要に応じて獣医師からケージレスト(狭いケージ内で安静に過ごさせる)の指示が出ることもありますので、その場合は指示にしたがってください。猫自身も身体がだるいため大人しくしていることが多いですが、少し元気になってくると動きたがる場合もあります。「もう平気そうだから」と油断せず、獣医師から運動再開の許可が出るまでは安静第一で過ごさせましょう。
また、ストレスがかかる環境も避けるべきです。来客や大きな物音、新しいペットの導入など猫の心拍数が上がるような出来事は極力控えてください。愛猫が落ち着いて休めるよう、静かな寝床や隠れ家を用意し、こまめに様子を観察しましょう。万一呼吸が苦しそうだったり咳込んだりした場合は、すぐに病院に連絡し指示を仰いでください。
投薬の管理を徹底する
フィラリア症の治療中は、獣医師から処方された薬を指示どおりに投与することが何より大切です。ステロイド剤や気管支拡張薬、利尿剤など、与えられた薬は決められた時間・量を守ってください。特にステロイドは途中で勝手に中止するとリバウンドで症状が悪化するおそれがあるため、獣医師の指示なしに減薬・中止しないよう注意しましょう。投薬スケジュールをカレンダーに記入したり、ピルケースを活用したりなどして飲み忘れを防ぐ工夫をしてください。
猫は投薬自体が難しいケースもあります。嫌がって吐き出してしまう場合は、投薬補助のおやつを使ったり粉薬に替えてもらったりなど、獣医師に相談してみましょう。投薬ストレスを減らすことも大事なケアの一環です。
さらに、フィラリア予防薬の継続投与も忘れずに行います。フィラリア症に感染した猫は再び感染するリスクも高いため、指定された期間中は予防薬を定期的に与え続けます。通常、月1回のペースでスポットオン(首筋に垂らす薬)や経口薬を使いますが、投薬日にムラがあると幼虫を取り逃がす可能性があるため、毎月きっちり投与してください。予防薬を併用することで、体内のミクロフィラリアを駆除し、新たな寄生を防ぐ効果が期待できます。なお、治療中に体調が優れない日があって投薬を迷う場合は、自己判断せず獣医師に相談しましょう。
定期的に検査を受ける
フィラリア症に罹患した猫は、治療開始後も定期的な検査・チェックが欠かせません。治療によって症状が落ち着いているように見えても、体内ではフィラリアが生存していたり、治療の副次的影響が出たりしている可能性があります。特に、胸部X線検査は経過観察に有用で、6~12ヶ月ごとに肺や心臓の状態を評価することが推奨されています。レントゲンで肺炎症の改善・悪化を追跡することで、ステロイド投与量の調整など治療方針の見直しが行われます。
また、必要に応じて超音波検査や血液検査も行い、成虫の動向や全身状態をチェックします。超音波検査では前回見えていた虫体が消えているか確認し、逆に新たな異常所見がないかを調べます。血液検査では腎臓や肝臓など、長期の薬物治療で負担のかかる臓器の数値も確認します。これらの定期検査によって、合併症の早期発見や治療終了の判断が適切に行えるのです。
飼い主としては通院や検査は負担に思われるかもしれませんが、愛猫のためにスケジュールどおり受診しましょう。特に治療開始から6ヶ月~1年の間は状態が不安定になりやすいため、獣医師の指示する頻度で検査を受けることが大切です。「元気になったしもういいかな」と自己判断せず、最後まで油断しないようにしましょう。
猫のフィラリア症を予防する方法

一度感染してしまうと根本的な治療法がなく大変厄介なフィラリア症ですが、幸い予防薬を適切に使えば多くが防ぐことができる寄生虫症です。本章では、愛猫をフィラリア症から守るために飼い主ができる2つの予防策、蚊を避ける工夫と予防薬の投与について解説します。
蚊を避ける
フィラリア症は蚊に刺されない限り感染しません。したがって、日頃から猫が蚊に接触しないよう環境を整えることが予防の第一歩です。具体的には以下のような対策が有効です。
- 室内への蚊の侵入を防ぐ
網戸や玄関の目張りをしっかりと行い、家の中に蚊を入れないようにします。 - 屋外での散歩や遊びを控える
猫をお散歩させている方は、蚊の活動が活発な暖かい季節(特に夕方~夜間)の外出を控えましょう。 - 蚊の発生源を減らす
家の周囲に古いバケツや植木鉢の受け皿など水のたまり場があれば、蚊の発生源になります。定期的に水を捨ててボウフラ(蚊の幼虫)が湧かないようにしましょう。 - 虫除けグッズの活用
ペット用の蚊取り線香や超音波式の虫除け器など、安全な虫除けグッズを使用するのもよいでしょう。
以上のように蚊を避ける努力をしても、完全に刺されるリスクをゼロにすることは困難です。蚊はマンションの高層階にも飛んでくるほど行動範囲が広く、家の中でもエアコンの排水口や人の出入りの隙に侵入してきます。そのため、蚊を避ける対策だけでなく、次に述べる予防薬の併用が不可欠となります。
予防薬を投与する
現在、猫のフィラリア症を防ぐ最も重要な方法はフィラリア予防薬の定期投与です。フィラリア予防薬は蚊に刺されて体内に入り込んだフィラリア幼虫を早期のうちに駆除し、成虫へ成長するのを阻止するお薬です。形態としては、月に1回投与するスポットオン(首筋に垂らす液体)やチュアブル錠(おやつタイプの経口薬)が主流で、動物病院で入手できます。近年ではフィラリアとノミ・ダニ予防が一体化した便利な総合薬もありますので、かかりつけ医と相談するとよいでしょう。フィラリア予防薬は適切に使えば猫のフィラリア症をほぼ100%防ぐことができる大変効果的な手段です。薬剤自体の安全性も高く、副作用はまれですが、万一異常が見られた場合はすぐ医師に連絡しましょう。
まとめ

猫のフィラリア症は、一見犬ほどは感染しにくいように思われますが、いったん感染すれば重篤化し突然死を招くこともある恐ろしい病気です。猫では診断も治療も難しく、発症してからでは手の施しようがないことも少なくありません。しかし、飼い主さんの努力でこの病気は多くが予防できます。日頃から蚊を避ける環境作りに努め、適切な時期に予防薬を投与することで、愛猫をフィラリア症の脅威から守ることが可能です。猫のフィラリア症は予防こそ最大の治療です。毎月の予防は手間に感じるかもしれませんが、それによって愛猫の命と健康を守れるなら安いものです。ぜひかかりつけの獣医師と相談のうえ、最善の対策を取るようにしてください。大切な家族である猫が、フィラリア症に悩まされることなく健やかに過ごせるよう願っています。
参考文献


