猫の心臓肥大は、初期段階ではほとんど症状が現れないことが一般的で、違和感に気づいたときには末期の状態もしくは突然死に至る場合があります。現時点では根本治療が見つかっていませんが、早期発見による治療で進行を遅らすことのできる可能性があります。こちらの記事では、猫の心臓肥大とはどういったものか、その症状、合併症、診断法などを解説します。
猫の心臓肥大とは

猫の心臓肥大とは、心臓の様々な部位が通常より大きくなったり肥厚したりする状態の総称です。
猫の心臓肥大には主に以下のパターンがあります
- 心筋肥大:心臓の筋肉が分厚くなる状態で、特に左心室の壁が厚くなる肥大型心筋症が猫では一般的です。
- 心筋肥大:心臓の筋肉が分厚くなる状態で、特に左心室の壁が厚くなる肥大型心筋症が猫では一般的です。
- 心房拡張:心房(特に左心房)が拡大する状態で、多くの場合、心筋肥大などのほかの心臓疾患の二次的な結果として発生します。
- 心室拡張:心室(特に左心室)が拡大する状態で、心筋が薄くなって心室が拡張する拡張型心筋症が代表的です。
- 右心系拡大:右心房や右心室が拡大する状態で、肺高血圧症などが原因で起こることがあります。
心筋肥大は、甲状腺機能亢進症や全身性の高血圧、リンパ腫、成長ホルモン過剰症などの病気に関連して二次的に発生することもあります。最も一般的な心筋肥大の原因は肥大型心筋症です。
肥大型心筋症は、猫に多く見られます。以下の純血種で遺伝的要因が特定されています。
- メイン・クーン
- ラグドール
その他の猫種にも家族性素因が知られていますが、肥大型心筋症に限定すると、決して遺伝的な要因だけではありません。すべての7歳以上の猫のうち3割が罹患しているといわれています。若くても罹患していることもあるため、超音波検査などで心臓の状態の確認をすることで診断していきます。
一方、拡張型心筋症は、猫では比較的まれな疾患です。心臓のポンプ機能が低下し、重篤な心不全を引き起こすことがあります。超音波検査が重要で、心室収縮力低下と左室の拡大を確認することで診断されます。
心臓肥大でみられる症状

猫の心臓肥大は、初期段階でほとんど症状が見られず、ゆっくりと進行するケースにおいては飼い主さんでも変化に気づけないことがあります。ここでは、心臓肥大の猫にみられる症状について解説します。
呼吸の回数が多い
一般的に猫は1分間に20~30回程度の呼吸をするといわれていますが、とくに心不全に進行した状態の心臓肥大になると呼吸回数が増加します。1回あたりの呼吸が浅く速くなったり、口を開けて呼吸をしている状態は、努力呼吸と呼ばれる異常な呼吸です。
努力呼吸は、水分が胸腔に溜まったり、血液が肺にうっ滞することが原因で起こります。左心系の肥大や拡張が進行すると左心不全を、右心系の問題が進行すると右心不全を引き起こして、それぞれ異なる病態ながら呼吸困難を生じさせることがあります。特に睡眠時に呼吸回数が多いようなことがあれば動物病院を受診しましょう。
動きたがらない
進行した状態の心臓肥大になると、通常の生活を送っていても疲労感が増して、軽く動いただけで息切れを起こすこともあるでしょう。結果的に活動量は徐々に減っていきます。遊ぶことが大好きだった猫に以下のような状態が見受けられたら、進行した心臓肥大や他の病気による倦怠感を感じているかもしれません。
- 飼い主さんの呼びかけやおもちゃに興味を示さなくなった
- 以前と比べて静かに寝ている時間が増えた
- 高いところへの移動を極端に避けるようになった
加齢によって静かに過ごすことが増えたなどのパターンもありますが、その可能性も踏まえて注意深く観察しましょう。
失神
心臓から全身へいく血液の量が低下して正常に脳まで血液が届かなくなると、失神することがあります。心臓のリズムや血液循環を理由に失神することを心原性失神と呼びます。失神をするようなことがあれば原因精査や治療を始めた方がいいでしょう。前触れのない失神は
失神のあと数秒から30秒程度で意識が戻りますが、失神する回数が増えたり、失神した後にぐったりと動かなくなったりするようになれば、より緊急性が高いです。
食欲不振・体重減少
進行した状態の心臓肥大になると、通常の生活を送っていても疲労感が増して、猫の食欲が落ちることがあります。正常に活動できなくなったり食事量が減ったりすれば体重が減ることもあります。「最近あまり食べなくなった」「痩せてきた気がする」といった変化も、心臓の病気のサインの可能性があります。
お腹が膨らむ
心臓肥大が進行して右心系機能が低下すると、お腹に水が溜まることがあります。猫のお腹が以前よりも膨らんで見える、触ると張っているような感じがする場合は注意が必要です。腹水が溜まると、猫は苦しそうにしたり、横になるのを嫌がったりすることもあります。
心臓肥大に起こる合併症
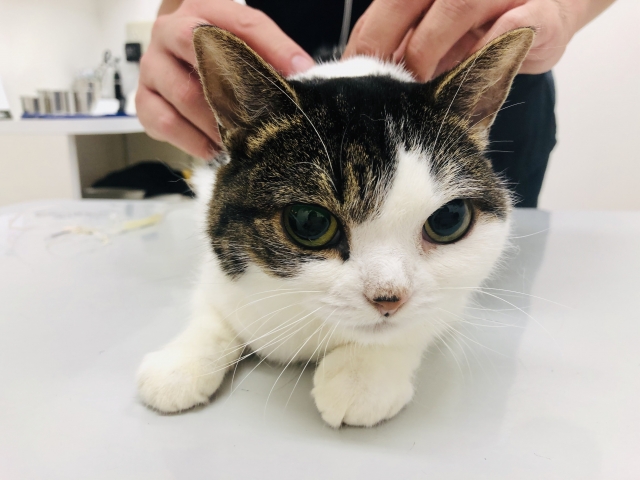
猫の心臓肥大は、命に関わる合併症のリスクがある深刻な病気です。ここでは、心臓肥大の猫に起こりうる合併症について解説します。
心室頻拍
心室頻拍とは、心室内で異常な電気信号が過剰発生する不整脈です。心室の筋肉が異常な速度で収縮を繰り返す結果、血液を送るポンプ機能が低下して、脳に届く血液量が不足してめまい・失神を引き起こします。
心不全
心不全とは、心臓の異常が進行して全身の血行動態にまで異常をきたした状態です。呼吸・活動性・食欲に異常が起こり、進行すると咳が出るなどの症状が目立ち始めます。治療が遅れると致死的になりえます。
動脈血栓塞栓症
心臓肥大が進行して左心房が拡大すると内部の血流が滞って血栓ができやすくなります。血栓が左心室から全身に流れ出て、大きな動脈の端に詰まります。例えば後ろ肢に血液が流れなくなると、以下のような症状が現れることがあります。
- 後ろ肢が急に動かなくなる
- 後ろ肢が冷たくなる
- 激しい痛みで鳴き続ける
- 肢の指や爪の色が青白くなる
この症状が万が一見られた場合は、すぐに動物病院を受診しましょう。麻痺のために、痛みを感じなくなって途中で訴えなくなることもありますが、肢は動かない状態のままです。他にも、腸管の血管や腎臓の血管に詰まり、それぞれの臓器に致命的な障害を引き起こす事があります。
心臓肥大の診断方法

猫の心臓肥大は、症状や検査結果に応じて、さまざまな検査方法を組み合わせて原因や状態を特定します。ここでは、診断方法について解説します。
超音波検査
超音波検査では、心臓の形状や動きをリアルタイムで観察できるため、心臓の筋肉が分厚くなっているかどうかを瞬時に判断できる診断方法です。心臓のどの部分(心室、心房)がどのような状態(収縮、拡張、弁の動き)になっているかを画像で評価できます。
正常のサイズ以上に左心室の壁の肥厚がみられると、肥大型心筋症の可能性が考えられます。一方、拡張型心筋症では心筋の収縮力が低下しているのが特徴です。重篤な合併症の原因となる血栓があるかどうかも確認できます。精度が高く猫への負担が少ないため、心臓の病気を疑った場合は必ず行う検査です。
X線検査
X線検査では、心臓の大きさや形状、肺の状態を評価します。
左心房が拡大したり左心室が肥大したり、心臓全体が大きく見えたりするなどで心臓肥大の補助的な診断に役立ちますが、進行しないとはっきりした所見がでないこともあります。また、心不全によって胸に水が溜まった状態である肺水腫かどうかも確認することが出来ます。
心電図
心電図は、心拍数や心臓の動きを記録します。心臓のリズムが乱れる不整脈の有無を特に診断できます。
猫が心臓肥大になると、心臓の筋肉に大きな負担がかかりやすく、その結果、心拍数が増えたり心臓のリズムが乱れたりします。猫の身体に電極を装着するだけで簡単に検査ができるため、治療の経過や副作用の有無を判断するためにも活用されます。
血液検査・尿検査
血液検査は、心臓肥大に関連した病気がないかを確認するために用いられます。甲状腺機能亢進症や腎疾患などの病気が進行すると心臓肥大につながることがあります。拡張型心筋症では、タウリン欠乏で起こることもあるため、血液中のタウリン濃度を測定することもあります。
尿検査は、腎臓機能の状態や体内の電解質バランスを把握でき、腎臓の病気の診断のほか、心臓肥大や心不全に効果的な治療を行うために助けになります。
血圧測定
血圧測定では高血圧の有無を診断します。高血圧になると、心臓に過度な負担がかかってしまいます。早期発見により適切な管理を行って、心臓肥大の進行を防ぎます。
心筋肥大の治療方法

猫の心臓肥大は早期による治療をすることで、症状の進行を遅らせたり、合併症の予防につながったりします。ここでは、心臓肥大を起こしやすい肥大型心筋症・拡張型心筋症のステージ別の治療方法について解説します。
ステージA
ステージAとは、治療が必要ないとされる段階です。心臓肥大になりやすい要因を持ち合わせているとしてもわかっていても、心エコーに異常がない場合はこのステージです。経過観察しましょう。
ステージB1
ステージB1とは、心エコーで所見が少なく身体症状もないため、治療は必要ないとされる段階です。無症候性心筋症とも呼ばれます。生涯にわたって無症状のままの猫も多いです。
今後進行する恐れがあるため、1年に1回以上の心臓超音波検査をするように推奨されています。
ステージB2
ステージB2とは、身体症状はないが心エコーで重大な所見があり、動脈血栓塞栓症の発症リスクが上昇しているため、状況によって抗血栓療法などが推奨される段階です。治療薬としてβブロッカー、ACE阻害剤、抗血栓薬などを投与します。
ステージC
ステージCとは、心臓肥大が進行して身体症状も出ているため、症状に応じた適切な治療が必要な段階です。症状は、心臓肥大による明らかな症状がでている急性期と、症状が落ち着き始める慢性期があります。
急性期で、胸水・肺水腫などの合併症がある場合、すぐに利尿剤の投与や胸水の抜去をして対処します。心不全の場合は、すぐに入院治療が必要です。動脈血栓塞栓症になった場合、治療をすれば改善する見込みがあると判断されて治療が選択されることもありますが、長い苦しみを与えないよう安楽死を選択されることもあります。
慢性期は、急性期治療が落ち着いたら、内服で利尿剤や抗血小板薬の投与を継続します。2〜4ヶ月に1回のペースで心臓の再検査、安静時や睡眠中の呼吸数などを記録、動脈血栓塞栓症の予防やなりやすさを継続して評価していきます。
ステージD
ステージDとは、ステージCの治療で効果が発揮されず、予後数日から数ヶ月とされる段階です。苦痛が出にくいような内服や食事管理が続けられます。
h2:拡張型心筋症の治療方法
猫の拡張型心筋症は心臓のポンプ機能が低下する病気で、心不全になりやすいため治療が必要です。猫ではこの病気はまれです。また、タウリン欠乏型かどうかで治療方針は大きく異なります。
初期段階
素因はあるが心エコーで異常が少ない段階です。タウリン欠乏が疑われる食事を与えていたり、品種的なリスクがある場合などが該当します。この段階では血液検査によるタウリン濃度の測定と、適切なキャットフードへの変更が推奨されます。この段階で見つかることは多くないです。
中等度段階
心エコーで心機能の低下が確認されているものの、まだ明らかな症状が現れていない段階です。タウリン不足の場合は補充療法を行い、特発性拡張型心筋症には治療薬として強心剤、必要に応じて抗血栓薬などを使用することが検討されます。タウリン欠乏型の場合は数週かけて治療が奏功すると、その後は回復していきます。
中等度のうち症状のある段階
積極的な治療が必要です。呼吸困難や食欲不振、活動性の低下などの症状が見られることもあります。急性期の場合、入院で、利尿剤と強心剤の持続投与による集中治療を行います。胸水や腹水が溜まっている場合は、水を抜く処置を実施することもあります。しかし、タウリン欠乏型でない限り治療が著効することは少なく、数ヶ月の経過で重篤な段階へ至ることも少なくありません。
重篤な段階
治療に反応せず心不全が進行して、治療内容の変更や終末期ケアが必要な段階です。予後は数週間から数ヵ月程度と厳しく、猫の生活の質を考えた治療を行うことも検討されます。
心臓肥大は早期発見が大事

心臓肥大は、薬などで進行を遅らせるしかないため、早期発見が重要です。以下の4つに特に留意しましょう。
- 定期的な健康診断
- 呼吸数の観察
- 活動量や食欲
- 適切な食事と運動管理
定期的な健康診断は、7歳を超えたら年に1〜2回は獣医師に見てもらいましょう。必要に応じて呼吸数の観察を寝ているときに行い、1分間に30回以上の呼吸が見られないか確認をしてください。そして、元気があるか、食欲があるかなど猫の状態がいつもと違わないか確認をします。肥満は心臓に負担をかけるため、普段から適切な食事量と適度な運動をうながしましょう。
まとめ

猫の心臓肥大は気づきにくく、未治療で過ごした結果、重篤な合併症や突然死につながる事例もあるので注意が必要です。現時点で、心臓肥大を完治するための治療方法は見つかっていませんが、心不全の進行や重篤な合併症の予防につながる治療は可能です。一緒に暮らすペットの健康を守るためにも、定期健診のほか、呼吸回数の増加など必要なタイミングで動物病院を受診して検査結果に応じた治療を受けましょう。


