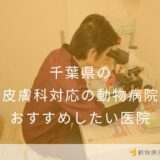愛猫が自分の身体を傷つけてしまうような行動を見せると、飼い主さんはとても心配になります。自傷行動はなぜ起こるのか、放っておいて大丈夫なのか、と不安に思われる方も多いでしょう。本記事ではQ&A形式で、考えられる原因や対策、受診の目安などを質問形式で解説します。
目次 非表示
猫の自傷行動の基礎知識

- 猫の自傷行動とはどのような行動のことを指しますか?
- 猫の自傷行動とは、文字どおり猫が自分で自分の身体を傷つけてしまうような異常な行動のことです。具体的には、必要以上に自分の身体を舐め続けて皮膚が赤くただれてしまう、あるいは自分の尻尾を追いかけて噛みつき、傷になるまで繰り返すといった行動が挙げられます。本来、グルーミング(毛づくろい)や身体を掻く行為自体は猫にとって正常な習慣ですが、自傷行動ではその頻度や強さが明らかに行き過ぎており、結果として毛が抜けたり出血するほどのケガにつながってしまいます。こうした自傷行為は、常同障害や強迫行動とも呼ばれ、ストレスなどに起因する心の不調の表れである場合が多いとされています。いずれにせよ、猫が自分で自分を傷つけてしまう状態は正常ではなく、注意が必要なサインだといえるでしょう。
- 猫の自傷行動で生じる問題を教えてください
- 自傷行動によってまず心配されるのは、猫自身の身体に起こるトラブルです。過剰なグルーミングや噛みつきによって脱毛や皮膚の傷が生じ、それが悪化すると傷口から細菌が侵入して感染症や皮膚炎を引き起こす可能性があります。実際、毛を舐めすぎて皮膚が赤くただれたり、出血するほど噛んでしまった場合、そのまま放置すると化膿したり慢性的な皮膚病に発展することもあります。
また、自傷行動が続くことで猫の心にも負担がかかります。常に強いストレスや不安を感じている状態ですので、猫の生活の質(QOL)は低下してしまいます。自傷行動は一度クセになると繰り返し起こりやすく、行動が習慣化すると治りにくくなることも少なくありません。さらに、愛猫が自分を傷つける姿を見守ることになる飼い主さんにとっても大きな精神的ストレスとなりえます。そのため、自傷行動による皮膚の異変に気付いたら、早めに対処してあげることが大切です。
猫が自傷行為をする理由

- 猫はどのようなときに自傷行動をしますか?
- 猫が自傷行動を起こす大きな理由の一つはストレスや不安など精神的な要因です。例えば、環境の変化は猫にとって大きなストレスになります。引っ越しで住環境が変わった、新しい家族が増えた、近所で工事が始まって大きな音がするようになったなど、猫にとって日常ではない出来事が起こると、強い不安を感じてしまいます。その心の不安を紛らわすために、猫は過剰な毛づくろいをしたり自分の尻尾を噛んだりしてしまうことがあるのです。
- 自傷行動と間違えやすい猫の病気や症状を教えてください
- 猫が身体をしきりに舐めたり噛んだりしていると、「ストレスで自傷しているのかな?」と思いがちですが、実は何らかの病気による症状を自傷行為と見間違えてしまうこともあります。
代表的なのは皮膚の痒みを伴う病気です。例えばノミの寄生があると、猫は痒みで体中を掻きむしったり舐めたりします。同様にダニなどの寄生虫、細菌や真菌(カビ)による皮膚感染症、アレルギー性の皮膚炎がある場合も、皮膚の痒みから舐め壊しや引っ掻き傷ができてしまいます。一見すると猫が自分で自分を傷つけているように見えますが、原因はストレスではなく皮膚の病気による痒みなのです。
また、体内の痛みや違和感によって二次的に自傷行動に至る場合もあります。典型的なのは肛門嚢炎です。お尻にある匂い袋(肛門腺)の炎症で痛みや不快感があると、猫はしきりに尻尾の付け根を舐めたり噛んだりします。
- 自傷行動をしやすい猫の特徴はありますか?
- 個体差はありますが、いくつかの要因によって自傷行動を起こしやすい猫がいると考えられています。
まずは性格や生活環境です。特に飼い主さんへの依存心が強い猫は、自傷行動を起こしやすいタイプといえます。常に飼い主さんと一緒にいたいタイプの猫は、留守番で長時間一人になると強い孤独や不安を感じ、ストレスから毛をむしるなどの行動に走りがちです。
また、神経質で繊細な猫も注意が必要です。ちょっとした物音や環境の変化でストレスを感じやすい猫は、そのストレス反応として常同行動を取りやすく、結果的に自傷行為に至る可能性があります。逆に遊び好きな猫も、発散の機会が足りないと退屈から身体を舐め壊すような癖がつくことがあります。特に若い猫や室内飼いで刺激の少ない環境にいる猫は、運動不足や退屈を紛らわすために自分の毛をむしったり尾を噛んだりしてしまうことがあるのです。
以上のように、性格的な傾向や生活環境によって、自傷行動をしやすい猫の特徴があります。愛猫がこれらに当てはまる場合は、特にストレス管理に気を配るとよいでしょう。
猫の自傷行動への対策

- 猫の自傷行動の対策として飼い主ができることを教えてください
- 飼い主がまず取り組むべきは、猫のストレスを減らし生活環境を整えてあげることです。自傷行動の背景にストレスがある場合、その原因を探って可能な限り取り除いてあげましょう。次に、十分な遊びと運動の機会を与えることも大切です。飼い主が一緒に遊んであげられる時間を毎日作り、猫じゃらしやおもちゃで存分に身体を動かしましょう。お留守番が多いご家庭では、時間設定で自動で動くおもちゃやおやつ入りパズルなどを活用して、一人の時間でも退屈しのぎができる工夫をするとよいでしょう。
- 猫の自傷行動をやめさせるために用意するものはありますか?
- 自傷行動への対策として用意しておくと役立つものはいくつかあります。まず、緊急時に備えてエリザベスカラーがあると安心です。エリザベスカラーとはプラスチックや布製の円錐状のカラーで、装着することで猫が自分の身体を舐めたり噛んだりできないよう物理的に防ぐ道具です。患部を保護する必要があるとき、一時的にこれを付ければ舐め壊しや噛み壊しの悪化を防ぐ効果が期待できます。
- 猫に自傷行動がみられる場合は動物病院を受診すべきですか?
- はい、早めに動物病院で相談することをおすすめします。自傷行動が見られる場合、前述したようにその原因が身体の病気にある可能性が少なくありません。獣医師に診てもらうことで、痒みや痛みの原因となる疾患がないか調べ、適切な治療につなげることができます。病気が見つかればその治療をすることで、結果的に自傷行動が治まることも少なくありません。
- 猫の自傷行動に対して、病院ではどのような治療が行われますか?
- 動物病院での治療は、原因に応じて大きく二つの方法に分かれます。まず、身体的な原因が見つかった場合はその治療が優先されます。診察のなかでノミの寄生や皮膚炎などが確認されれば、駆虫薬の投与や消毒・抗生物質の投薬などで皮膚の治療を行います。あるいは、アレルギーが疑われる場合は原因となりそうなアレルゲン(食べ物や環境中の物質)を特定し、食事療法やアレルギー症状を和らげる薬を用いることもあります。
このように検査を行ったうえで、該当する疾患の治療を進めていきます。
一方、明らかな身体の病気がなく心理的な問題と考えられる場合は、生活環境の改善や行動療法、必要に応じて薬による治療が行われます。具体的には、飼い主に対してストレス原因を問診し、それを減らす工夫を一緒に考えてくれます。また、症状が重い場合には抗不安薬や抗うつ薬など、猫の不安を和らげるお薬を使う選択肢もあります。
編集部まとめ

猫の自傷行動には、何らかの原因や背景があります。大切なのは、飼い主がいち早くそのサインに気付き、対処してあげることです。自傷行動を放置すれば、傷が悪化して皮膚病や感染症のリスクが高まるだけでなく、猫自身が長く苦しい思いをすることになります。なかなか改善しない場合は動物病院を受診して、原因を調べ、適切な治療を行うことが重要です。本記事がその一助になれば幸いです。
参考文献