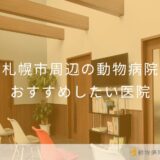犬と暮らしていると、心不全という言葉を耳にすることがあるかもしれません。よく聞く言葉ですが、実際にどのような状態なのか、どのような症状が出るのかはわからない飼い主さんも多いでしょう。本記事では、犬の心不全をわかりやすく解説し、受診のタイミングを逃さないための兆候や初期症状などをご紹介します。
犬の心不全の基礎知識

多くの飼い主さんが、心不全を心臓病の一種だととらえているようです。しかし、心不全は病名ではありません。本章では、その点についても整理しながら、心不全そのものについて解説し、原因やかかりやすい犬種についてもお伝えします。
犬の心不全の概要
心臓は、右心房、右心室、左心房、左心室という4つの部屋から構成され、ポンプのように絶えず動き、全身に血液を送り出すことで命を維持します。なんらかの原因で、心臓のポンプ機能が低下すると、心臓から全身へ送られる血液量が減り、酸素や栄養も身体に行き届かなくなります。
その結果、身体にさまざまな不調が現れます。心不全とは、心臓の働きの低下によっておこる不調の総称です。
心不全は、初期の段階ではほとんど症状が出ないため、飼い主さんが気付かないことも少なくありません。しかし、早い段階で治療を開始すれば、生活の質を落とさずに長期間コントロールすることが可能なので、早期発見早期治療が大切です。
心不全の原因
心不全の主な原因は、さまざまな心臓の疾患です。犬の心臓の病気には、先天性心疾患と呼ばれる生まれつきの病気と、後天性心疾患と呼ばれる成長後に発症するものとがあります。
犬の心不全の原因となる代表的な心臓疾患について、先天性心疾患と後天性心疾患に分けてご紹介します。
心不全の原因となる代表的な先天性心疾患
動脈管開存症
犬の先天性心疾患のなかでも一般的な病気です。本来は、出生後に閉じるはずの、母犬の体内にいる間のみ存在する動脈管という血管が、出生後も残ることにより異常な血流が生じます。
心室中隔欠損症
心室中隔欠損症は、左右の心室を分ける心室中隔という壁に、生まれつき穴が開いていて、左右の心室の血液が混ざり合う病気です。穴の大きさや位置によって症状はさまざまです。
肺動脈狭窄症
犬の先天性心疾患のなかで、2番目に多い病気です。肺動脈とは、心臓の右心室から肺に血液を送る血管です。右心室と肺動脈の間には、肺動脈弁という仕切りがありますが、この仕切りが生まれつき狭いことで右心に負担がかかり、心不全をおこします。
大動脈弁狭窄症
大動脈は、心臓の左心室から全身に血液を送る血管です。左心室と大動脈の間にある弁が、大動脈弁で、この弁が生まれつき狭いことで、血液を大動脈に送り出しにくくなる病気です。
心不全の原因となる代表的な後天性心疾患
僧帽弁閉鎖不全症
犬においては、最も一般的な心臓の病気で、先天性、後天性すべてを含んだ心臓病の75%を占めます。僧帽弁は、左心房と左心室の間にある弁のことで、この弁に異常が出て、左心室と右心室の間で血液の逆流が起こることで心不全をおこす病気です。
拡張型心筋症
心臓を構成する筋肉である心筋が薄くなり、心臓のポンプ機能が弱くなって心不全をおこす病気です。心筋症は犬ではそれほど一般的ではありませんが、一部の大型犬で特異的に発生頻度が高いことが知られています。
心不全にかかりやすい犬種
心不全は、どのような犬種でもかかることがあります。しかし、心不全の原因となる心疾患のなかには、一部の犬種で発生頻度が高いことがわかっている病気もあります。
動脈管開存症になりやすい犬種
- シェットランド・シープドッグ
- ポメラニアン
- ミニチュア・ダックスフント
- コーギー
- コリー
- ミニチュア・プードル
- チワワ
心室中隔欠損症になりやすい犬種
- イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル
- 柴犬
- ミニチュア・ダックスフント
大動脈弁狭窄症になりやすい犬種
- ゴールデン・レトリーバー
- ジャーマン・シェパード
- ボクサー
- ロットワイラー
僧帽弁閉鎖不全症になりやすい犬種
- キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル
- マルチーズ
- 老齢の小型犬
拡張型心筋症になりやすい犬種
- ドーベルマン・ピンシャー
- ボクサー
- グレート・デーン
- イングリッシュ・コッカー・スパニエル
犬の心不全の前兆と初期症状

犬の心不全は、できるだけ早く気付いて治療を始めることが大切です。しかし、発症初期ではほとんど症状が出ないことも多く、飼い主さんが異常に気付くことは容易ではありません。本章では、早期に異変を感じ取れるよう、心不全のサインとなるような前兆や初期症状についてお伝えします。
犬の心不全の前兆
犬の心不全の前兆は、なんとなく普段と様子が違うというわずかな変化です。散歩や遊びなどの行動や、食欲、睡眠時の様子に下記のような変化があらわれます。
行動の変化
- 散歩の途中で座り込む
- 散歩に前ほど行きたがらない
- 階段や坂道を嫌がる
- 前ほど夢中で遊ばない
- 運動した後、前よりも呼吸が荒いようにみえる
食欲の変化
- まったく食べないわけではないが、前ほど食欲がない
- 食欲にむらが出てきた
睡眠の変化
- 寝ている時間が長い
- 寝るときの姿勢が変わった
- 寝ている間、何度も体勢を変える
- 寝ていても呼吸が荒いようにみえる
犬の心不全の初期症状
犬の心不全の初期症状で、わかりやすいのは咳です。「心臓の病気で咳が出るのか?」と疑問に思うかもしれませんが、心臓疾患では心臓自体が大きくなることが多く、心臓によって気管支が圧迫されて咳が出やすいのです。
特に、初期では運動直後や興奮時に咳が出やすいです。咳以外にも、呼吸が浅く速くなる、元気がなくなる、痩せるなども心不全の初期症状のひとつです。
犬の心不全の進行速度と症状

犬に心不全の症状があらわれたとき、急激に悪化するのか、ゆっくり進行するのかによって、飼い主さんの心構えも変わるでしょう。病状が進んだ際の症状も気になるポイントです。この章では、心不全の進行速度と、進行した際の症状についてご紹介します。
犬の心不全の進行速度
心不全の進行速度は、原因となる心臓の疾患や、生活環境などによって異なるため一概にはいえません。しかし、一般的に、先天性の心疾患が原因の場合、進行は早くなることが多く、後天性の心疾患が原因の場合はゆっくり進む傾向があります。
犬の心不全の原因として、最も多い僧帽弁閉鎖不全症においては、いくつかの犬種では、進行速度についての研究が行われています。
例えば、ヨークシャー・テリアとミニチュア・シュナウザーにおける僧帽弁閉鎖不全症の進行速度についての研究では、ヨークシャー・テリアはミニチュア・シュナウザーに比べて急激な重症化は少ないという結果でした。
マルチーズにおいても、進行が穏やかだという疫学調査の結果があります。
一方で、キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルは、若年でも発症しやすく、進行速度も速いことがわかっています。
進行した心不全の症状
心不全が進行すると、身体に十分な酸素が行き渡らなくなり、犬は呼吸が苦しくなります。そのため、口を開けてハアハアと浅く速い呼吸をするようになります。
少しでも呼吸を楽にしようとして、前足を突っ張り、首を伸ばして胸を開く独特な犬座姿勢という姿勢をとることもあります。
進行に伴って、食欲が低下し、吐いたり下痢をすることもあるため、栄養状態が悪化して痩せ、毛並みも悪くなるという全身状態の変化もみられます。
チアノーゼと呼ばれる、本来はピンクのはずの歯茎や舌などの粘膜が青白くなる状態になることもあります。
腹水が溜まり、お腹がぽっこり膨らんで見えたり、お腹を触ると水風船を触るような感触になることもあります。心臓よりも下に位置する四肢や胸の前のあたりがむくむこともあります。
心不全が進行して、このような症状がみられるようになった段階では、犬の命に関わる重篤な状態である可能性が高いといえます。
犬の心不全の受診サイン

犬の心不全の場合、犬座姿勢やチアノーゼがみられるなど、重篤な状態に進行してから受診するのでは手遅れなことも少なくありません。犬の命を守るためには、上の章でお伝えしたような、前兆や初期の段階で受診することが大切です。
特にわかりやすい受診のサインはこれらとなります。
- 運動後や遊びの際に咳がでる
- 散歩や遊びの途中で座り込む、行きたがらない
- 運動後などに呼吸が荒い
- なんとなく食欲がない
- 寝ている時間が長く、元気がないようにみえる
- 寝るときに落ち着かない様子
動物病院での心不全の治療

心不全の治療は、心臓の機能を補い、症状を緩和し、できる限り快適な生活を送れるようにすることが目的です。治療法には大きく分けて手術療法と薬物療法があります。心不全の原因となる心疾患、心不全の進行程度、年齢、ほかの基礎疾患の有無などによって、どちらかを選択したり、両方を組み合わせることもあります。
手術療法
手術は、心不全の原因となる心疾患そのものを根本的に治療する方法です。一般的に、動脈管開存症では、手術療法を視野に入れることも多い傾向があります。僧帽弁閉鎖不全症も、診断時の年齢や状態に応じて手術が適用となることもあります。
手術療法のメリットは、機能を根本的に修復できるため、症状が劇的に改善する可能性が高いことです。
一方で、犬の心臓の手術は難易度が高く、限られた病院でしか受けることができません。全身麻酔が必要で、身体への負担も大きいことが多く、費用も高額なケースがほとんどです。
薬物療法
どのような心臓の疾患が原因の心不全でも、選択されることが多いのが、薬物療法です。薬によって心臓の働きやその他の臓器もサポートし、症状の進行を遅らせることを目的とします。主に使われる薬として、下記が挙げられます。
- ACE(エース)阻害薬:血圧を下げ、心臓の負担を軽減する働きがあります
- 強心薬:心臓の収縮力をサポートし、ポンプ機能を強めて、全身への血流を改善させます
- 利尿薬:肺や腹部にたまった水分を排出し、呼吸を楽にする効果があり、同時に、全身の血液量を軽減させて、心臓の負担を減らします
- β遮断薬やカルシウム拮抗薬:一部の不整脈や心筋症に対して使用する薬です
薬を組み合わせることによって、ほとんどのケースで長期間、安定した生活を送れます。手術療法と比較すると、費用も抑えることが可能です。
ただし、あまりに進行した心不全では、薬によるコントロールが難しい場合もあります。薬は生涯続ける必要があり、有害な副作用のリスクもあるため、定期的な受診も欠かせません。
飼い主さんが気を付けたいポイント

犬の心不全を早期に発見したい、もしも犬が心不全と診断されたらできるだけ進行を遅らせたい、という飼い主さんが多いでしょう。ここでは、犬の心不全の兆候にできるだけ早く気付くため、また、心不全の進行を遅らせるために飼い主さんが日常で気を付けるべきポイントをお伝えします。
散歩中の注意点
散歩中は常に犬の様子を観察し、呼吸の様子や立ち止まる回数など、普段と異なる点がないか気を配りましょう。
心不全の犬の場合、散歩は短時間で、犬のペースに合わせて行いましょう。気温の変化によって、症状が急に悪化することもあるため、特に暑い日や寒い日は散歩を控えるか時間帯を配慮する必要があります。
ペットホテルや知人に預ける際の注意点
ペットホテルなどに預けなくてはならない場合、心不全であることを必ず伝え、緊急時の対応についても共有しましょう。
ペットホテルでは、投薬などの対応ができない施設もあります。事前に十分なコミュニケーションを心がけることが大切です。
知人などに預ける場合も、薬の時間や症状の変化に気をつけてもらい、なにかあればすぐにかかりつけの動物病院を受診してもらうようにお願いしておきましょう。
日頃のケアでの注意点
歯磨きなどいつものケアで、息切れしたり、咳をしないかを確認したり、皮膚の状態やお口の中の色を確認しましょう。
心不全の犬との生活では、薬の投与をきちんと管理することが重要です。決められた時間と量を守り、定期的に検査を受けることも忘れてはなりません。
まとめ

本記事は、犬の心不全に対する理解を深め、心不全を早期に発見し、治療につなげることを目指しました。日常のなかの些細な変化が心不全のサインかもしれません。少しでも「いつもと違う」と感じたら、早めに動物病院を受診しましょう。
参考文献
- 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 心不全|病気について|循環器病について知る|患者の皆様へ|国立循環器病研究センター 病院
- 厚生労働省:心疾患の治療と仕事の両立 お役立ちノート
- 日本獣医生命科学大学 心臓血管外科手術 | 動物医療センター | 日本獣医生命科学大学
- 公益財団法人 埼玉県獣医師会 犬の僧帽弁閉鎖不全症
- Updates on Treating Congestive Heart Failure, Part 2: Guidelines for Diagnosing Congestive Heart Failure in Dogs with Chronic Degenerative Valvular Disease
- Degenerative Valvular Disease in the Cavalier King Charles Spaniel: Results of the UK Breed Scheme 1991-2010
- Myxomatous mitral valve disease in Miniature Schnauzers and Yorkshire Terriers: 134 cases (2007-2016)
- 獣医内科学 小動物編 改訂版 日本獣医内科学アカデミー編 文永堂出版
- イヌネコ家庭動物の医学大百科 改訂版 公益財団法人 動物臨床医学研究所編